労災事故で腕切断の金額と障害等級は?痛みと入院期間は?

腕切断事故では労災被害者の落ち度を指摘されることも!
適正な賠償金を獲得するなら弁護士に相談を!
労災で腕を切断した場合に請求できる金額には、労災保険から支払われる療養補償給付(治療費)、休業補償給付のほか、障害補償給付のほか、会社が労災事故について責任を負っている場合に請求できる慰謝料や損害賠償金があります。
金額の大部分を占める障害補償給付や損害賠償金は、労災保険が認定する後遺障害等級によって大きく異なりますが、腕の切断の場合には後遺障害5級以上となる可能性が高いので、金額も高額になります。
このページでは、法律事務所リンクスの労災に強い弁護士が、労災事故で腕を切断した場合に受け取れる金額と後遺障害等級について、わかりやすく解説します。
電話での依頼で解決される方多数!お気軽にご相談ください!
- お電話で
無料相談【全国対応】 - 0120-917-740
受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)
労災保険から受け取れる金額は?
仕事で腕を切断した場合、労災保険からもらえる主な金額には次のものがあります。
| 療養補償給付 | 腕切断の治療費の補償 |
|---|---|
| 休業補償給付 | 腕切断で仕事を休み減った給料の補償 |
| 障害補償給付 | 腕切断による後遺障害に対する補償 |
療養補償給付の金額と請求の流れ
 療養補償給付は、労災で負ったけがを治療するのにかかる費用を補償するものです。
療養補償給付は、労災で負ったけがを治療するのにかかる費用を補償するものです。
労災認定されれば、治療費は労災保険から支払われ、原則として自己負担はありません。
労災指定病院で治療をした場合、窓口で「労災保険を使いたい」と伝えれば、自己負担なく治療を受けることができます。
労災指定外の医療機関で治療を受けた場合は、治療費はいったん自己負担することになりますが、労基署に申請すれば返金してもらうことができます。
療養補償給付の支給の申請は会社が代行してくれることが多いですが、小さな会社で申請をしてくれる人がいない場合には、ご自身で労基署に療養補償給付の支給を申請することになります。
休業補償給付
 労災によって仕事を休んで給料が減ってしまった場合、労災保険から休業補償給付が支払われます。
労災によって仕事を休んで給料が減ってしまった場合、労災保険から休業補償給付が支払われます。
具体的には、会社を3日以上休んだ場合、4日目の休業分から、給料の60%が支払われます。
また、別途「社会復帰促進等事業」より、「休業特別支給金」として、追加で給料の20%が支払われます。
休業補償給付の支給の申請も会社が代行してくれることが多いですが、小さな会社で申請をしてくれる人がいない場合には、ご自身で労基署に休業補償給付の支給を申請することになります。
休業補償給付の計算は、「給付基礎日額」を基に計算します。
「給付基礎日額」とは、原則として、事故発生日直前の3か月間に支払われた賃金総額を、その期間の暦日数で割った1日あたりの賃金額です 。これは、労災保険給付の最も基本的な算定基礎となります。
計算式:
例えば、事故発生前の3か月間の給与が毎月30万円(合計90万円)、その期間の暦日数が90日だったとすると、
障害補償給付
後遺障害等級が認定されると、労災保険から障害補償給付が支払われます。では、腕の切断の場合に、障害補償給付はどうなるのでしょうか。
労災被害者のための無料電話相談実施中
 法律事務所リンクスの無料電話相談では、労災に強い弁護士が、労災被害でお困りの被害者の方やご家族のための電話での無料相談を実施しています。
法律事務所リンクスの無料電話相談では、労災に強い弁護士が、労災被害でお困りの被害者の方やご家族のための電話での無料相談を実施しています。
労災で大怪我をした場合、仕事に復帰できるのか、今後の生活はどうなるのか、後遺障害が残ったらどうすればよいのかといった不安が大きいこといます。
弁護士に依頼すれば、どのように対応すればよいかのアドバイスを受けたり、着手金0円で窓口を任せたりすることができますので、治療や仕事復帰に集中することが可能です。
労災で怪我をしてお困りの被害者の方は、0120-917-740にお電話を頂くか、LINEで労災の無料相談をお申し込みください。
腕切断後の痛み、入院期間と義手装着までの治療経過
腕の切断手術及び断端(切断箇所)の形成術の後は、断端の治療をして回復に努めます。ほとんどのケースにおいて、切断による傷は3~4週間で塞がり、傷跡になっていきますが、傷の完治までには未だかなり時間がかかります。
腕切断後は幻肢痛を感じすことがあります。これは現実の痛みではなく、切断された腕に痛みを感じるものです。幻肢痛は、切断後数日以内に始まりますが、遅れて現れることもあります。幻肢痛によってリハビリが遅れると、機能回復に時間がかかったり制限が残ったりする可能性があるので、精神面のケアを受けながら、早期に義手の装着訓練をして心身を回復させることが望ましいです。実際、幻肢痛は義肢を装着していないときによくみられるようです。
切断による傷が回復し、一定のリハビリを経て退院できるだけの生活機能を回復したら、退院を検討することになります。退院後もリハビリテーションを続けますが、切断した腕が元通りになることは残念ながらありませんので、後遺障害として補償を受けることが必要になります。
腕切断の障害等級と保険金、慰謝料、逸失利益
労災事故で腕を切断した場合、上肢の「欠損障害」となります。。
上肢の欠損障害は、切断した部位や、片腕か両腕かによって、1級から5級までの等級が定められています 。
特に重要なのが、「ひじ関節以上で失った」か「手関節以上で失った」かという基準です。
「上肢をひじ関節以上で失ったもの」とは
肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断したもの
肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの
ひじ関節において、上腕骨と橈骨及び尺骨(前腕の骨)が離断したもの
「上肢を手関節以上で失ったもの」とは
ひじ関節と手関節の間において上肢を切断したもの
手関節において、橈骨及び尺骨(前腕の骨)と手根骨(手の骨)が離断したもの
上肢の欠損障害に関する後遺障害等級表
これらの基準に基づき、具体的な後遺障害等級は以下の表のように定められています。
このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
全国の労働災害の被害者の救済のため無料電話相談に取り組む。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2015年に法律事務所リンクスを設立し、2016年に弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)として法人化。現在、東京と京都にオフィスがある。
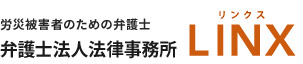
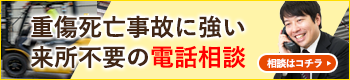
 後遺障害等級が認定されると、労災保険から給付金が支払われます。
後遺障害等級が認定されると、労災保険から給付金が支払われます。 労災被害者は、事故があった年の4月に入社した新規採用の従業員であったが、造粒機のラインにより造粒加工作業に従事中、造粒機に組み合わされて設置されたロータリーバルブに右腕を巻き込まれ、右上肢肘下10センチメートルの部分で切断を余儀なくされ、一上肢を手関節以上で失ったものとして、後遺障害等級の5級に該当する後遺障害を負いました。
労災被害者は、事故があった年の4月に入社した新規採用の従業員であったが、造粒機のラインにより造粒加工作業に従事中、造粒機に組み合わされて設置されたロータリーバルブに右腕を巻き込まれ、右上肢肘下10センチメートルの部分で切断を余儀なくされ、一上肢を手関節以上で失ったものとして、後遺障害等級の5級に該当する後遺障害を負いました。 これまでご説明してきたとおり、労災は労基署と会社という2つの組織を相手にしなければならない上に、手続きも複雑であるため、労災で怪我をした本人やそのご家族だけで進めていくことには限界があります。
これまでご説明してきたとおり、労災は労基署と会社という2つの組織を相手にしなければならない上に、手続きも複雑であるため、労災で怪我をした本人やそのご家族だけで進めていくことには限界があります。


