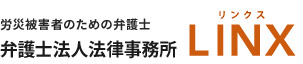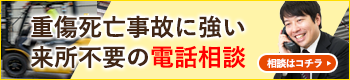転落事故で労災!慰謝料は請求できる?墜落転落・崩壊倒壊災害事例

転落事故は死亡事故や重篤な後遺障害が起きやすい!
適正な賠償金を獲得するなら弁護士に相談を!
 転落・倒壊事故は、次のような高所作業や不安定な場所での作業中に起こりやすく、死亡や重大な後遺障害につながる可能性が高い事故類型です。
転落・倒壊事故は、次のような高所作業や不安定な場所での作業中に起こりやすく、死亡や重大な後遺障害につながる可能性が高い事故類型です。
・高所作業中に足場から落下する
・屋根の上での作業中に落下する
・脚立の上での作業中に脚立が倒れて転落する
・重いものを運びながら階段を下りていたところ、バランスを崩し、転げ落ちる
・トラックの積み荷が崩れるのに巻き込まれて転落する
・手すりの不備によって階段から落下する
厚生労働省の統計によると、2023年における「墜落・転落」を原因とする労働災害の発生件数は20758件、「崩壊・倒壊」を原因とする労働災害の発生件数は1995件であり、「墜落・転落」「崩壊・倒壊」による労働災害を合わせると、2023年の全労働災害135371件のうち、「転倒」(36058件)に続いて多い事故類型となっています。また死亡災害は合計242件発生しており最多となっています(参照:厚生労働省HP「労働災害統計」))。
このページでは、法律事務所リンクスの労災に強い弁護士が、転落・倒壊事故の事例を紹介しながら、「適正な慰謝料をもらうための3つのポイント」「会社に損害賠償責任が認められる場合」「労災被害者に落ち度が認められて損害賠償金が減額される場合」「弁護士に依頼した方がよい理由」について、説明します。
電話での依頼で解決される方多数!お気軽にご相談ください!
- お電話で
無料相談【全国対応】 - 0120-917-740
受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)
転落・倒壊事故で死傷した被害者・遺族が適正な慰謝料をもらうための3つのポイント
転落・倒壊事故では、会社から適正な慰謝料をもらうためにはクリアしないといけない3つのポイントがあります。
- きちんと労災申請をする
- 元請業者・下請業者・孫請業者など複数の会社が関与している場合にどの会社に損害賠償請求するか
- 労災被害者の落ち度による減額幅を小さくする
①きちんと労災申請をする
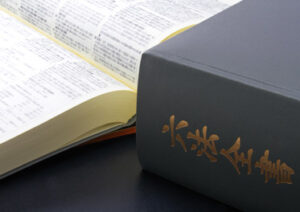 転落・倒壊事故で労災被害者が死亡した場合、「死人に口なし」になってしまいかねませんので、どのような事故であったかを把握するため、きちんと労災申請をして、労働基準監督署に調査してもらわなければ、会社の責任を問えず、適正な慰謝料を受け取れなくなる可能性があります。
転落・倒壊事故で労災被害者が死亡した場合、「死人に口なし」になってしまいかねませんので、どのような事故であったかを把握するため、きちんと労災申請をして、労働基準監督署に調査してもらわなければ、会社の責任を問えず、適正な慰謝料を受け取れなくなる可能性があります。
労災の死亡事故の注意点や金額について詳しく知りたい方は、「労災で死亡事故の金額は?保険金はいくら?遺族補償年金の計算は?」をご覧ください。
また、大怪我を負い、治療を続けたにもかかわらず後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定を受けないと、適切な慰謝料の支払いを受けることができません。
労災で適正な後遺障害等級の認定を受けるには、労災に強い弁護士に相談することが必要です。詳しくは「労災で後遺障害!後遺症認定率が高い診断書とは?申請の流れは?」をご覧ください。
②元請業者・下請業者・孫請業者など複数の会社が関与している場合にどの会社に損害賠償請求するか
 転落・倒壊事故が起きるような現場は、元請業者・下請業者・孫請業者など複数の会社が関与していることが多いので、どの会社に損害賠償請求するかが大事になります。
転落・倒壊事故が起きるような現場は、元請業者・下請業者・孫請業者など複数の会社が関与していることが多いので、どの会社に損害賠償請求するかが大事になります。
基本的には、その現場を実質的に指揮監督していた業者には安全配慮義務違反があると認められやすいですが、形式的に関与していた業者には安全配慮義務違反は認められないことが多いです。
これから説明する2つの事例でも、現場責任者として自社の従業員を選任していた元請業者には安全配慮義務違反が認められていますが、下請業者が設備や機材を準備し、元請業者は直接的な指揮をしていないという場合には元請業者には安全配慮義務違反は認められていません。
③労災被害者の落ち度による減額幅を小さくする
 転落・倒壊事故が起きる場合、会社に安全配慮義務違反が認められることが多いですが、転落するきっかけであったり、倒壊事故が起きた場合に落下しないように安全帯を設置していなかったことについては、労災被害者にも落ち度があると認められることが多いです。
転落・倒壊事故が起きる場合、会社に安全配慮義務違反が認められることが多いですが、転落するきっかけであったり、倒壊事故が起きた場合に落下しないように安全帯を設置していなかったことについては、労災被害者にも落ち度があると認められることが多いです。
労災被害者側としては、安全教育やマニュアルの不備、施設管理や人員配置の不備、危険な労務環境が日常的であったこと、労災被害者の経験の少なさなどを主張して、落ち度が低いことを主張立証していくことが必要となります。
労災被害者のための無料電話相談実施中
 法律事務所リンクスの無料電話相談では、労災に強い弁護士が、労災被害でお困りの被害者の方やご家族のための電話での無料相談を実施しています。
法律事務所リンクスの無料電話相談では、労災に強い弁護士が、労災被害でお困りの被害者の方やご家族のための電話での無料相談を実施しています。
労災で大怪我をした場合、仕事に復帰できるのか、今後の生活はどうなるのか、後遺障害が残ったらどうすればよいのかといった不安が大きいこといます。
弁護士に依頼すれば、どのように対応すればよいかのアドバイスを受けたり、着手金0円で窓口を任せたりすることができますので、治療や仕事復帰に集中することが可能です。
労災で怪我をしてお困りの被害者の方は、0120-917-740にお電話を頂くか、LINEで労災の無料相談をお申し込みください。
墜落転落の労災事例
高架橋工事の吊り足場が落下して転落死して3400万円余りの損害賠償が認められた事例
東京地裁平成22年12月14日判例秘書搭載
 労災被害者は、高架橋工事の孫請業者の従業員でしたが、高架橋の橋桁架設現場において、桁から吊り下げる足場を架設している作業中、作業のために乗っていた吊り足場が約29mの高さから落下したため、転落して亡くなりました。
労災被害者は、高架橋工事の孫請業者の従業員でしたが、高架橋の橋桁架設現場において、桁から吊り下げる足場を架設している作業中、作業のために乗っていた吊り足場が約29mの高さから落下したため、転落して亡くなりました。
労災被害者のご遺族は、元請業者に対し、安全配慮義務違反があるとして、損害賠償を請求しました。
これに対し、元請業者は、孫請業者の労働者との間に直接の雇用契約関係がなく安全配慮義務を負わないと主張しました。
裁判所は、元請業者の損害賠償責任を認め、3400万円の損害賠償を命じました(労災被害者の落ち度は3割)。
元請業者は孫請会社の従業員(労災被害者)に対する安全配慮義務に違反し損害賠償責任を負うと判断
裁判所は、労災被害者側の安全配慮義務違反の主張を認め、高架橋工事の現場責任者として自社の従業員を選任していたことを重視し、信義則上、労災被害者に対して安全配慮義務を負うと判断しました。
その上で、裁判所は、次の理由から、元請業者は安全配慮義務に違反しているとして、損害賠償責任を負うと判断しました。
- クランプ(締付・固定工具)の種類ないしその変更にも注意を払わなかったため、落下した吊り足場の北側のクランプの締め付けが不十分であったこと
- 安全帯の使用について,親綱の設置を具体的に指示し,足場工事の従事中,現に労働者が安全帯を使用しているか否かの確認(パトロール)をしなかったこと
労災被害者の落ち度は3割にとどまると判断
裁判所は、労災被害者に①吊り足場が落下する直前に単管の端を蹴るようにして踏み込んだ点、②橋桁の上段の吊りピースに親綱を設置することは可能であり安全帯の使用も不可能ではなかった点に落ち度が認められるものの、労災被害者は末端の労働者であり、吊り足場に共に乗っていた者の地位がその上司的立場(職長)にあったことを考慮すると、労災被害者の落ち度が5割を超える重いものであるとはいえず、せいぜいその過失割合は3割程度であると認めるのが相当と判断し、3400万円の支払を命じました。
塗装工事中に2階屋根から落下して負傷し1000万円余りの損害賠償が認められた事例
大阪地裁平成31年2月6日判例秘書登載
 孫請業者(労災被害者)は、下請業者の指示によって2階屋根の塗装を行うこととなり,安全帯を付けることなく作業を行っていたところ,同屋根から地面に落下して右肩を負傷し、労基署から後遺障害第10級9号「一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」に該当すると判断されました。
孫請業者(労災被害者)は、下請業者の指示によって2階屋根の塗装を行うこととなり,安全帯を付けることなく作業を行っていたところ,同屋根から地面に落下して右肩を負傷し、労基署から後遺障害第10級9号「一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」に該当すると判断されました。
労災被害者は、元請業者と下請業者に対し、安全配慮義務違反があるとして損害賠償を請求しましたが、元請業者の責任は認められず、下請業者の責任のみが認められ、1000万円余りの損害賠償金の支払いが命じられました(労災被害者の過失2割)。
元請業者は労災被害者に対して安全配慮義務を負わないと判断
裁判所は、次の理由から、元請業者は労災被害者に対して安全配慮義務を負わないと判断しました。
- 元請業者は、下請業者に対し、必要な安全管理体制の構築を義務付けていた
- 元請業者は、本件現場を視察していたものの、本件工事において使用するローラー等の資材やヘルメットを準備し、足場を設置したのは全て下請業者であって、元請業者が下請業者や労災被害者を含め下請業者の下で作業に従事していた者に対し、具体的な作業内容やその方法について直接的な指導監督を行っていたとはいえない
下請業者は労災被害者に対して安全配慮義務を負うと判断
裁判所は、下請業者と労災被害者との間には労働契約が成立しているとしたが、その点を措くとしても、次の理由から、信義則上、下請業者は労災被害者に対して安全配慮義務を負うと判断しました。
- 本件事故日において、労災被害者に対し、2階屋根の塗装作業を指示していたこと
- 本件工事の下請業者として、労働安全衛生法等の関連法令で定める足場等からの墜落防止対策、ヘルメットの着用及び安全帯の使用等について厳守することを誓約していたこと
- 実際にも、本件工事で使用する塗装用のローラーやペンキ等の資材やヘルメットを準備し、足場の設置を行っていたこと
下請会社が労災被害者に対する安全配慮義務を怠ったため損害賠償責任を負うと判断
裁判所は、次の理由から、下請業者は安全配慮義務に違反しているとして、損害賠償責任を負うと判断しました。
- 本件工事については、屋根の上での下地塗り等を行う際、落下事故の発生するおそれがあることは明らかであること
- 墜落を防止するためには、作業者に対し、安全帯を装着させた上、足場と安全帯をロープで結びつける等の措置が必要であると認められるところ、下請業者は、労災被害者について、安全帯を装着するよう指示したり、安全帯を装着せずに屋根に上ってはならない旨注意したりすることはなかったこと(本件事故当時,足袋靴やヘルメットも装着していなかった。)
- 実際、労災被害者は、本件事故当時、安全帯を装着することなく、屋根の上で下地塗りの作業に従事していたこと
労災被害者にも2割の過失があったと認定
その上で、労災被害者にも次のような落ち度があり2割の過失があるとして、損害賠償金を2割減額して1000万円余りの支払を命じました。
- 労災被害者は、本件工事までの間、防水工事に従事することはあったものの、塗装工としての経験は比較的乏しかったこと
- 戸建て2階の屋根に上がって下地塗り作業を行うに当たっては、2階から落下する危険性があることは明白であり、本件現場の客観的状況等も踏まえると、同危険性に関しては、労災被害者自身にも十分に予見することが可能であったと認められること
- 労災被害者は、本件現場に安全帯を持参していたにもかかわらず、下請業者との間で、安全帯装着の必要性等を十分に議論することなく、安全帯を装着せずに2階の屋根へ上がったこと
転落・倒壊事故で会社に損害賠償請求できる場合
これらの事例ように、転落・倒壊事故について会社に責任がある場合には、会社に対して損害賠償請求をすることが可能です。
では、どのような場合に、会社に責任がある場合といえるのでしょうか。
会社が損害賠償責任を負う場合のうち代表的な3つの場合をご紹介します。
①安全配慮義務違反
1つ目は「安全配慮義務」です。会社には、従業員の心身と健康と安全を守るべき義務があります。
労災においては、「労働災害の危険を発見し、その危険を事前に排除する義務」ともいえます。
転落・倒壊事故の場合に問題となる義務については、
・従業員が使用する機材を定期的に点検し、安全に使えるようにする
・従業員に機材の使い方や指導、マニュアルの配布などを行う
・従業員に必要な保護具などを機材を提供する(ヘルメットなど)
・機材に安全装置などを設置する(ハーネスなど)
などのほか、労働安全衛生規則518条以下に
・作業床の設置等
・悪天候時の作業禁止
・照度の保持
・移動はしごの基準
・脚立の基準
などの具体的な義務が定められています。
②使用者責任
2つ目は、「使用者責任」です。こちらは、従業員が、他の従業員や第三者に対して損害を与えてしまった場合に、会社も連帯して責任を負うことを指します。
従業員(A)のミスで他の従業員(B)が労災にあった場合、Bに対する損害賠償責任は従業員(A)と会社が連帯して負わなければなりません。
会社は、従業員に仕事をさせることで利益を得たり、危険を拡散していたりします。ですので、安全に配慮した対策を講じていても、連帯責任を負うことになります。
③工作物責任
3つ目は、「工作物責任」です。労災が会社の設備や建物の欠陥によって引き起こされた場合、「工作物責任」が適用されます。その名の通り、設備の欠陥で労災が発生した場合、設備の管理者が責任を負うというものです。
工作物責任を負うのは、労災に遭った従業員を雇っている会社だけではありません。他社や第三者が設置した工作物が原因で労災が発生した場合は、該当者が損害賠償責任を負うことになります。
転落・倒壊事故の労災被害を弁護士に依頼した方がいい理由
会社に対して損害賠償請求をするには、弁護士に依頼することが不可欠です。その理由は次のとおりです。
①自分で示談交渉をしても、法的責任を否定されるなど相手にしてもらえない可能性があるが、弁護士相手だとそうはいかない
②会社との金銭交渉を自分で行うのは精神的ストレスが大きいため、弁護士に任せてしまった方がいい
③慰謝料をはじめとした損害賠償金が高くなる可能性がある
労災被害にあったら労災に強い弁護士に無料相談・電話相談を!
 これまでご説明してきたとおり、労災は労基署と会社という2つの組織を相手にしなければならない上に、手続きも複雑であるため、労災で怪我をした本人やそのご家族だけで進めていくことには限界があります。
これまでご説明してきたとおり、労災は労基署と会社という2つの組織を相手にしなければならない上に、手続きも複雑であるため、労災で怪我をした本人やそのご家族だけで進めていくことには限界があります。
法律事務所リンクスの労災に強い弁護士の無料相談・電話相談では、手続きの進め方や後遺障害等級、慰謝料の見込みについて丁寧にご説明させて頂いております。
法律事務所リンクスでは着手金を0円とさせて頂いており、ご依頼頂ける場合にも経済的負担を心配される必要はございません。
まずはお気軽に法律事務所リンクスの無料相談・電話相談をご利用ください。
このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
全国の労働災害の被害者の救済のため無料電話相談に取り組む。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2015年に法律事務所リンクスを設立し、2016年に弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)として法人化。現在、東京と京都にオフィスがある。