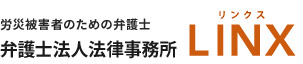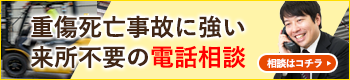落下物下敷きで労災!慰謝料は請求できる?飛来落下災害事例

落下物下敷き事故は死亡や重篤な後遺障害が起きやすい!
適正な賠償金を獲得するなら弁護士に相談を!
 落下物・下敷き事故は、次のように高所での作業中や重機で運んでいる途中に物を落とし下にいる人に直撃させてしまう事故類型で、死亡や重大な後遺障害につながる可能性が高いです。
落下物・下敷き事故は、次のように高所での作業中や重機で運んでいる途中に物を落とし下にいる人に直撃させてしまう事故類型で、死亡や重大な後遺障害につながる可能性が高いです。
・クレーンで持ち上げた重い資材が落下して下にいる人を下敷きにする
・足場から工具が落下して下にいる人にぶつかる
・ビルの高層階から窓ガラスや看板が落下し、下にいる人にぶつかる
厚生労働省の統計によると、2023年における「飛来物・落下物」を原因とする労働災害の発生件数は5859件で、2023年の全労働災害135,371件のうち、相当数を占める事故類型となっています(厚生労働省「労働者死傷病報告」による死傷災害発生状況(令和5年確定値))。
このページでは、法律事務所リンクスの労災に強い弁護士が、落下物・下敷き事故の事例を紹介しながら、「適正な慰謝料をもらうための3つのポイント」「会社に損害賠償責任が認められる場合」「労災被害者に落ち度が認められて損害賠償金が減額される場合」「弁護士に依頼した方がよい理由」について、説明します。
電話での依頼で解決される方多数!お気軽にご相談ください!
- お電話で
無料相談【全国対応】 - 0120-917-740
受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)
落下物・下敷き事故の被害者・遺族が適正な慰謝料をもらうための3つのポイント
落下物・下敷き事故で会社から適正な慰謝料をもらうためにクリアしないといけない3つのポイントは次のとおりです。
- きちんと労災申請をする
- 誰にどのような根拠で損害賠償請求するかを検討する
- 労災被害者にも落ち度があると主張された場合に適切な反論をする
①きちんと労災申請をする
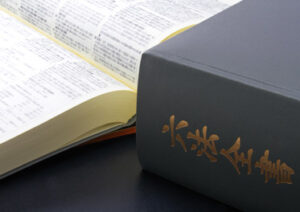 落下物・下敷き事故で労災被害者が死亡した場合、「死人に口なし」になってしまいかねませんので、どのような事故であったかを把握するため、きちんと労災申請をして、労働基準監督署に調査してもらわなければ、会社の責任を問えず、適正な慰謝料を受け取れなくなる可能性があります。
落下物・下敷き事故で労災被害者が死亡した場合、「死人に口なし」になってしまいかねませんので、どのような事故であったかを把握するため、きちんと労災申請をして、労働基準監督署に調査してもらわなければ、会社の責任を問えず、適正な慰謝料を受け取れなくなる可能性があります。
労災の死亡事故の注意点や金額について詳しく知りたい方は、「労災で死亡事故の金額は?保険金はいくら?遺族補償年金の計算は?」をご覧ください。
また、大怪我を負い、治療を続けたにもかかわらず後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定を受けないと、適切な慰謝料の支払いを受けることができません。
労災で適正な後遺障害等級の認定を受けるには、労災に強い弁護士に相談することが必要です。詳しくは「労災で後遺障害!後遺症認定率が高い診断書とは?申請の流れは?」をご覧ください。
②誰にどのような根拠で損害賠償請求するかを検討する
 落下物・下敷き事故では、労災被害者の勤務する会社に加えて、その元請会社、物を落下させたり倒した者、その雇用主、工作物が倒れて下敷きになった場合にはこれを占有管理している会社を特定し、誰にどのような法的根拠で損害賠償請求をするかを検討する必要があります。
落下物・下敷き事故では、労災被害者の勤務する会社に加えて、その元請会社、物を落下させたり倒した者、その雇用主、工作物が倒れて下敷きになった場合にはこれを占有管理している会社を特定し、誰にどのような法的根拠で損害賠償請求をするかを検討する必要があります。
労災被害者の勤務する会社は労災被害者に対して安全配慮義務(民法415条)を負っていますが、元請会社は労災被害者に対して安全配慮義務を負っているとは限りません。
他方で、物を落下させたり倒した者は不法行為責任(民法709条)、その雇用主は使用者責任(民法715条1項)、工作物が倒れて下敷きになった場合の占有管理者は工作物責任(民法717条1項)を負っています。
このように誰にどのような法的根拠で損害賠償請求をするかを検討する必要があります。
③労災被害者にも落ち度があると主張された場合に適切な反論をする
 落下物・下敷き事故が起きる場合、会社に安全配慮義務違反が認められることが多いですが、労災被害者にも落ち度があると主張してくる可能性があります。
落下物・下敷き事故が起きる場合、会社に安全配慮義務違反が認められることが多いですが、労災被害者にも落ち度があると主張してくる可能性があります。
例えば、これから紹介する事案のように、落下させたのが労災被害者自身である自損事故の場合、会社側は損害賠償責任を否定してきたり、労災被害者に多大な過失があると主張してきます。
また、労災被害者にはそのような危険な業務を指示していないなどと主張して、同じく損害賠償責任を否定してきたり、労災被害者に多大な過失があると主張してきたりすることもあります。
労災被害者側としては、安全教育やマニュアルの不備、施設管理や人員配置の不備、危険な労務環境が日常的であったこと、労災被害者の経験の少なさなどを主張して、落ち度が低いことを主張立証していくことが必要となります。
労災被害者のための無料電話相談実施中
 法律事務所リンクスの無料電話相談では、労災に強い弁護士が、労災被害でお困りの被害者の方やご家族のための電話での無料相談を実施しています。
法律事務所リンクスの無料電話相談では、労災に強い弁護士が、労災被害でお困りの被害者の方やご家族のための電話での無料相談を実施しています。
労災で大怪我をした場合、仕事に復帰できるのか、今後の生活はどうなるのか、後遺障害が残ったらどうすればよいのかといった不安が大きいこといます。
弁護士に依頼すれば、どのように対応すればよいかのアドバイスを受けたり、着手金0円で窓口を任せたりすることができますので、治療や仕事復帰に集中することが可能です。
労災で怪我をしてお困りの被害者の方は、0120-917-740にお電話を頂くか、LINEで労災の無料相談をお申し込みください。
運転資格のない労災被害者がクレーン操作中吊り下げていた物が落下して右足を挟まれて負傷した事故で会社の損害賠償責任が認められ1200万円余りが支払われた事例
千葉地裁平成元年3月24日判タ712号179頁
 労災被害者は、下請業者の従業員でしたが、運転資格がないのに製鉄所内でクレーンを操作していたところ、吊り下げていた物が落下して右足を挟まれ、右膝蓋骨脱臼、右下腿骨開放性骨折の傷害を負いました。
労災被害者は、下請業者の従業員でしたが、運転資格がないのに製鉄所内でクレーンを操作していたところ、吊り下げていた物が落下して右足を挟まれ、右膝蓋骨脱臼、右下腿骨開放性骨折の傷害を負いました。
労災被害者は、勤務先の下請業者及びその元請業者に対し、安全配慮義務違反があるとして、損害賠償を請求しました。
本件では、会社側に安全配慮義務違反が認められ、労災被害者の過失は3割認められたものの、1200万円余りの損害賠償金が認められました。
会社側が労災被害者に対する安全配慮義務を怠っため損害賠償責任を負うと判断
会社側は、次の理由から、会社には損害賠償責任はないと主張しました。
- 労災被害者はクレーンの操作には従事しておらず、クレーンを運転する資格を有していなかった。
- クレーンの運転資格を有していた作業責任者が現場を離れていたので、クレーンを操作してはならない状況にあった。
- 労災被害者は無資格で職務外のクレーン操作を行い、必要のない作業を行って、事故を引き起こした。
これに対し、裁判所は、事故の発生原因としては、労災被害者がクレーンの操作を誤ったことを指摘することができるのであるが、会社側は「本件クレーンを操作して走行中のものを停止させるには、それなりの習熟度を必要としたのに、これを運転する資格を有していない者がクレーンを操作していたのを黙認していた」ことなどを指摘して、安全配慮義務を尽くさなかったと認めるのが相当と判断しました。
労災被害者にも3割の過失があったと認定
その上で、裁判所は、労災被害者は、「危険を伴う作業を行おうとしたのであるから、補助者の手を借りるとか、走行用スイッチの操作に気を配るとかして、安全に作業を進めるべきであったのに、これを怠り、そのために事故を引き起こした」として、労災被害者の過失の程度は三割と判断し、損害賠償金を3割減額して1200万円余りの支払を命じました。
鏡の搬出作業をしていたところ倒れてきた鏡によって負傷し約1800万円の損害賠償が認められた事例
東京地判平成27年7月10日D1-Law.com判例体系
 労災被害者(中国籍)は、会社の指示監督下で鏡の搬出作業をしていたところ、倒れてきた複数枚の鏡とトラック荷台との間に挟まれ、右総頸動脈損傷、右総頸動脈閉塞症、脳梗塞、頸部挫創、外傷性気胸などの傷害を負い、労基署から後遺障害第9級7号の2「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」に該当すると判断されました。
労災被害者(中国籍)は、会社の指示監督下で鏡の搬出作業をしていたところ、倒れてきた複数枚の鏡とトラック荷台との間に挟まれ、右総頸動脈損傷、右総頸動脈閉塞症、脳梗塞、頸部挫創、外傷性気胸などの傷害を負い、労基署から後遺障害第9級7号の2「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」に該当すると判断されました。
労災被害者は、会社に対し、安全配慮義務違反があるとして損害賠償を請求しました。
これに対し、会社側は、次のように主張して、本件事故は予見し得ない事情により発生したものであり、安全配慮義務違反があるとは言えないと主張しました。
- 労災被害者は、雇用される際、在留資格を明らかにしなかったところ、これが明らかにされていれば、労災被害者を雇用することはなく、本件事故に遭遇することもなかった。
- 労災被害者は、鏡の運搬作業に従事することが予定されていなかったにもかかわらず、会社側の指示を無視して勝手に、鏡を積んだトラック荷台に上がり、本件事故に遭遇した。
会社は労災被害者に対して安全配慮義務違反があったと判断
裁判所は、次の理由から、会社側の主張を否定し、安全配慮義務があったと判断しました。
- 鏡は一枚でも重量が重く、成人一人では容易に動かしたり運搬したりすることができないものであって、その運搬作業は相当程度危険な作業であったのだから、会社は、そのような作業をさせるに際し、安全を図るために設計された具体的な作業手順を指導すべきところ、事前に具体的な安全確認作業の手順などを決めておかなかった。
- 会社側は、作業員以外にその安全を図るための監督者を配置するなど作業の安全に配慮すべき義務があったところ、監督者は作業途中で現場から離れてその後の作業を作業員に委ね、別の作業に従事していて、本件事故発生当時、現場を監督すべき被告側の担当者はいなかった。
- 労災被害者が携わってもよい作業とそうではない作業とを具体的に指示するなどしていたわけでもなく、日本語を理解できない労災被害者に正確に伝わっていたのかそもそも疑問である。
労災被害者にも落ち度はなかったと判断
会社側は、「労災被害者が在留資格を明らかにしなかったこと、会社側の指示を無視して勝手にトラック荷台に上がり労災事故が発生したことなどを考慮すると、労災被害者の過失割合は8割を下らない」と主張しましたが、裁判所は、労災被害者側の「在留資格を偽ったことなどないし、指示に従って作業をしていたにすぎないから、過失はない。」との主張を認め、労災被害者の過失を認めませんでした。
落下物・下敷き事故で会社に損害賠償請求できる場合
落下物・下敷き事故について、会社に責任がある場合には、会社に対して損害賠償請求をすることが可能です。
会社に責任がある場合のうち、代表的なものを3つをご紹介します。
①安全配慮義務
1つ目は「安全配慮義務」です。会社には、従業員の心身と健康と安全を守るべき義務があります。
労災においては、「労働災害の危険を発見し、その危険を事前に排除する義務」ともいえます。
落下物・下敷き事故の場合に問題となる義務については、
・従業員が使用する機材を定期的に点検し、安全に使えるようにする
・従業員に機材の使い方や指導、マニュアルの配布などを行う
などのほか、労働安全衛生法20条以下に
・機械による危険を防止するため必要な措置を講じる義務(労働安全衛生法第20条)
・荷役等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するために必要な措置を講じる義務(労働安全衛生法第21条)
・労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じる義務(労働安全衛生法第24条)
・労働者への安全教育を行う義務(労働安全衛生規則第35条)
などの義務が定められています。
②使用者責任
2つ目は、「使用者責任」です。こちらは、従業員が、他の従業員や第三者に対して損害を与えてしまった場合に、会社も連帯して責任を負うことを指します。
例えば、従業員(A)が機械の操作ミスをしたことで資材が落下し、下にいる従業員(B)がけがをした場合、会社はAが連帯してBに対して損害賠償を行うことになります。
会社は、従業員に仕事をさせることで利益を得たり、危険を拡散していたりします。ですので、安全に配慮した対策を講じていても、連帯責任を負うことになります。
③工作物責任
3つ目は、「工作物責任」です。労災が会社の設備や建物の欠陥によって引き起こされた場合、「工作物責任」が適用されます。その名の通り、設備の欠陥で労災が発生した場合、設備の管理者が責任を負うというものです。
例えば、工場の壁が施工不良により突然崩れ落ち、壁の近くで作業していた労働者がけがをした場合、その建物の所有者は損害賠償責任を負う可能性があります。
工作物責任を負うのは、労災に遭った従業員を雇っている会社だけではありません。他社や第三者が設置した工作物が原因で労災が発生した場合は、該当者が損害賠償責任を負うことになります。
落下物・下敷き事故の労災被害を弁護士に依頼した方がいい理由
会社に対して損害賠償請求を行う場合は、弁護士に依頼するのがおすすめです。その理由を以下にあげます。
- 労災認定を受けるための手続きを一任できる
- 弁護士に依頼することで治療に専念できる
- 適切な後遺障害認定を受けられる可能性が高まる
- 会社に対する損害賠償請求の手続きを一任できる
- 会社との示談交渉がスムーズに進みやすくなる
- 裁判に発展した場合でも弁護士が対応してくれる
- 慰謝料の金額が高くなりやすくなる など
労災被害にあったら労災に強い弁護士に無料相談・電話相談を!
 これまでご説明してきたとおり、労災は労基署と会社という2つの組織を相手にしなければならない上に、手続きも複雑であるため、労災で怪我をした本人やそのご家族だけで進めていくことには限界があります。
これまでご説明してきたとおり、労災は労基署と会社という2つの組織を相手にしなければならない上に、手続きも複雑であるため、労災で怪我をした本人やそのご家族だけで進めていくことには限界があります。
法律事務所リンクスの労災に強い弁護士の無料相談・電話相談では、手続きの進め方や後遺障害等級、慰謝料の見込みについて丁寧にご説明させて頂いております。
法律事務所リンクスでは着手金を0円とさせて頂いており、ご依頼頂ける場合にも経済的負担を心配される必要はございません。
まずはお気軽に法律事務所リンクスの無料相談・電話相談をご利用ください。
このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
全国の労働災害の被害者の救済のため無料電話相談に取り組む。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2015年に法律事務所リンクスを設立し、2016年に弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)として法人化。現在、東京と京都にオフィスがある。