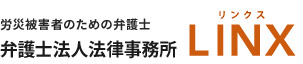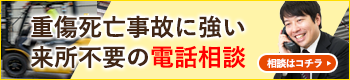フォークリフトの労災事例は?死亡事故の賠償金は?パレット事故も?

フォークリフト事故は死亡や重篤な後遺障害が起きやすい!
適正な賠償金を獲得するなら弁護士に相談を!
 フォークリフトの労災死傷事例には、次のようなものがあり、厚生労働省の2023年の統計で1989件発生しており、死亡事故や重篤な後遺障害が残ることも多いです(参照:厚生労働省HP「労働者死傷病報告」による死傷災害発生状況(令和5年確定値))。
フォークリフトの労災死傷事例には、次のようなものがあり、厚生労働省の2023年の統計で1989件発生しており、死亡事故や重篤な後遺障害が残ることも多いです(参照:厚生労働省HP「労働者死傷病報告」による死傷災害発生状況(令和5年確定値))。
- 歩行者がフォークリフトに挟まれたり轢かれたり衝突される
- フォークリフト同士やその他の乗り物が衝突して負傷する
- 運転手がフォークリフトごと転落したり転覆する
- 運転手がフォークリフトから落下する
- フォークリフトで積み重ねたパレットが崩壊して歩行者を直撃する
にもかかわらず、フォークリフト事故の労災事例では、会社が労災申請に協力しないことも多く、中には労災隠しをしようとしているのではないかと疑われるような事案もあります。
このページでは、法律事務所リンクスの労災に強い弁護士が、フォークリフトの労災事故事例を紹介しながら、「適正な慰謝料をもらうための3つのポイント」「会社に損害賠償責任が認められる場合」「労災被害者に落ち度が認められて損害賠償金が減額される場合」「弁護士に依頼した方がよい理由」について、説明します。
電話での依頼で解決される方多数!お気軽にご相談ください!
- お電話で
無料相談【全国対応】 - 0120-917-740
受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)
フォークリフト事故の労災被害者が適正な慰謝料をもらうための3つのポイント
フォークリフト事故で会社から適正な慰謝料をもらうためにはクリアしないといけない3つのポイントがあります。
- 必ず労災申請をする
- 後遺症が残った場合には適正な後遺障害等級を獲得する(お亡くなりになった事故の場合は②へ)
- 事故状況を正確に把握する
①必ず労災申請をする
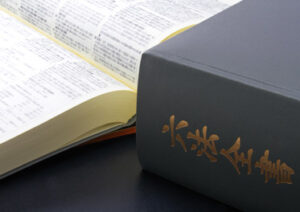 フォークリフト事故で労災被害者が死亡した場合、「死人に口なし」になってしまいかねませんので、どのような事故であったかを把握するため、きちんと労災申請をして、労働基準監督署に調査してもらわなければ、会社の責任を問えず、適正な慰謝料を受け取れなくなる可能性があります。
フォークリフト事故で労災被害者が死亡した場合、「死人に口なし」になってしまいかねませんので、どのような事故であったかを把握するため、きちんと労災申請をして、労働基準監督署に調査してもらわなければ、会社の責任を問えず、適正な慰謝料を受け取れなくなる可能性があります。
労災の死亡事故の注意点や金額について詳しく知りたい方は、「労災で死亡事故の金額は?保険金はいくら?遺族補償年金の計算は?」をご覧ください。
また、大怪我をしているにもかかわらず、会社が労災申請に協力していなかったり、業務災害であるのに通勤災害であるとか従業自身が転倒したというように申告させたりという事案がよく見られます。
会社としては、労災保険料が上がったり、指導を受けたりしたくないのでしょうが、労災申請をしないと十分な補償を受けられず、不利益を受けますので、できる限り早く申請しないといけません。
②後遺症が残った場合には適正な後遺障害等級を獲得する
 労災事故で大怪我を負い、治療を続けたにもかかわらず後遺症が残った場合、後遺障害等級認定を受けることで、適正な慰謝料の支払いを受ける前提条件が整います。
労災事故で大怪我を負い、治療を続けたにもかかわらず後遺症が残った場合、後遺障害等級認定を受けることで、適正な慰謝料の支払いを受ける前提条件が整います。
適正な後遺障害等級認定を受けるには、主治医にきちんとした後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。
労災で後遺障害認定率が高い後遺障害診断書を作成してもらう方法等について詳しく知りたい方は、「労災で後遺障害!後遺症認定率が高い診断書とは?申請の流れは?」をご覧ください。
特にフォークリフト事故の場合には、労災の後遺障害等級認定に加えて、自賠責保険の後遺障害等級認定を利用することが可能ですので、どちらの手続きを利用するのか、両方利用するのかが問題になりますが、ケースバイケースになります。詳しくは「フォークリフト事故にあった場合の流れ」でご説明させて頂きます。
③事故状況を正確に把握する
フォークリフト事故は、事故状況に応じて、誰に責任があるかや労災被害者の落ち度が変わります。
フォークリフトが歩行者に衝突して死傷させた場合の責任と被害者の落ち度
歩行者がフォークリフトに衝突されて死傷した場合、フォークリフトの運転手のほか、運転手を雇用していた会社、フォークリフトを所有していた会社や事故現場の管理をしていた会社に責任があることが考えられます。
この場合は歩行者なので、労災被害者の落ち度はさほど高くないことが多く、一般的な安全確認が不足していたという程度であれば10%程度に留まります。他方で、安全確認を著しく欠いていたり、通行が禁止されている場所を歩行していた場合には、30~40%程度が認められることもあります。
フォークリフトが転落転覆して運転手が死傷した場合の責任と被害者の落ち度
フォークリフトが転落転覆するなどして運転手が死傷した場合は、運転手を雇用していた会社、事故現場の管理をしていた会社のほか、転落転覆の原因となった設備を所有していた会社などが考えられます。
この場合は運転手の操作ミスやシートベルト不着用などが問題となり、50%を超える落ち度が認められることもあります。
どの会社に損害賠償請求するかを特定しないと示談交渉や裁判ができませんし、労災被害者の落ち度で損害賠償金の減額幅が大きく変わりますので、労災に強い弁護士に依頼して、労災被害者の落ち度が低いことを証明することをお勧めします。
労災被害者のための無料電話相談実施中
 法律事務所リンクスの無料電話相談では、労災に強い弁護士が、労災被害でお困りの被害者の方やご家族のための電話での無料相談を実施しています。
法律事務所リンクスの無料電話相談では、労災に強い弁護士が、労災被害でお困りの被害者の方やご家族のための電話での無料相談を実施しています。
労災で大怪我をした場合、仕事に復帰できるのか、今後の生活はどうなるのか、後遺障害が残ったらどうすればよいのかといった不安が大きいこといます。
弁護士に依頼すれば、どのように対応すればよいかのアドバイスを受けたり、着手金0円で窓口を任せたりすることができますので、治療や仕事復帰に集中することが可能です。
労災で怪我をしてお困りの被害者の方は、0120-917-740にお電話を頂くか、LINEで労災の無料相談をお申し込みください。
フォークリフトの労災事例(1)歩行者が衝突された事例
荷捌き作業中に後退してきたフォークリフトに右足を轢かれ1500万円余りの損害賠償が認められた事例
東京地裁平成18年4月7日労働判例918号42頁
 A社はB社から荷物の搬送を請け負っていたところ、A社に雇用されている労災被害者は、B社の支店において荷物の積み込み作業をするに際して、車輪付きのかごを後ろ向きに引いていたところ、Cが運転するフォークリフトが後進してきて労災被害者の背後に衝突を受けて倒れ、その際にフォークリフトの左後輪に右足を轢かれました。
A社はB社から荷物の搬送を請け負っていたところ、A社に雇用されている労災被害者は、B社の支店において荷物の積み込み作業をするに際して、車輪付きのかごを後ろ向きに引いていたところ、Cが運転するフォークリフトが後進してきて労災被害者の背後に衝突を受けて倒れ、その際にフォークリフトの左後輪に右足を轢かれました。
労災被害者は、右第1中足骨骨折、変形性足関節症と診断され、治療を続けましたが後遺症が残り、労基署から後遺障害併合第11級と認定されました。
労災被害者は、自身の雇用主であるA社、Cの雇用主であるB社及びフォークリフトの運転手Cなどに対し、損害賠償請求訴訟を提起しましたが、その後A社とは和解しました。
裁判所は、B社およびÇの損害賠償責任を認め、1500万円の損害賠償を命じました(労災被害者の落ち度は1割と認定)。
フォークリフトの運転手と運転手を雇用している会社は損害賠償責任を負う
フォークリフトの運転手側は、次の理由から、損害賠償責任を負わないと主張しました。
- フォークリフトが構内で動いているときには作業員はフォークリフトが動く範囲内とされている枠内(事故当時は黄色で標示されていた)に入ることが禁止されていた
- にもかかわらず、労災被害者が黄色の標示線の枠内に入り込んで事故が発生した
- 早朝の作業で後退時になるブザーを切っていたが労災被害者も十分承知していた
- 会社側は「フォークリフト安全作業マニュアル」に準拠して安全教育を実施していた
しかし、裁判所は、次の理由から、フォークリフト運転手と会社の損害賠償責任を認めました。
- 事故のあった構内でルールとしてフォークリフト稼働中は作業員の仕分けあるいは荷さばき作業が禁止されていたかどうかは定かでない
- 衝突地点が黄色の枠線内かどうかどうかも定かではない
- フォークリフトの走行警告音がならないことを原告が知っていたとしてもCの車両走行に当たっての注意義務が軽減されるものではない
- 人と荷物ボックスの混み合う場所をフォークリフトの運転手である被告Cが後方を確認せずにしかもバック・ブザーを鳴らさずに走行したのには過失が認められる
- フォークリフトのバック・ブザーについての指導・管理、構内における作業員の荷さばき作業とフォークリフトの稼働の棲み分けについての指導・管理などの点について現場管理監督者の指導の不徹底及び管理不行届があったものと評価できる
労災被害者の落ち度は大きくない
フォークリフトの運転手側は、労災被害者に大きな落ち度があるので、大幅に減額すべきと主張しましたが、裁判所は、労災被害者には、後方を確認せずに車輪付きのかごを後ろ向きに引いていた点に落ち度が認められるが、その程度は1割にとどまると判断し、1500万円の損害賠償を命じました。
フォークリフトの労災事例(2)フォークリフトの転落死亡事例
粗大ごみを受入れホッパーに投入する作業中にフォークリフトごと転落して死亡し2900万円余りの損害賠償が認められた事例
東京地裁平成25年2月18日D1-Law.com判例体系
 千葉県内の市からごみの再使用再資源化施設の運転維持管理を委託されていた会社の従業員が、粗大ごみを、フォークリフトを使って粗大ごみ受入れホッパーに投入する作業中に、ギアをニュートラルにせず、サイドブレーキも引いていない状態であったにもかかわらず、クラッチから足を離したために、フォークリフトが急発進し、フォークリフトごとホッパー内に転落しました。
千葉県内の市からごみの再使用再資源化施設の運転維持管理を委託されていた会社の従業員が、粗大ごみを、フォークリフトを使って粗大ごみ受入れホッパーに投入する作業中に、ギアをニュートラルにせず、サイドブレーキも引いていない状態であったにもかかわらず、クラッチから足を離したために、フォークリフトが急発進し、フォークリフトごとホッパー内に転落しました。
その際、従業員は、シートベルトをしておらず、身体が車外へ飛び出し、頭部をフォークリフトの車体の左後部とホッパーの壁面との間に挟まれ、脳挫傷、頭蓋骨骨折の傷害を負い、これにより、間もなく死亡しました。
従業員の遺族は、市に対しては転落防止のための設備を設置していなかったことを理由に、会社に対しては安全対策が不十分であったことを理由に、損害賠償請求訴訟を提起しましたが、裁判所は市の責任は認めず、会社については安全配慮義務違反があったとして2900万円余りの損害賠償を命じました(労働者の落ち度は4割と認定)。
市の損害賠償責任は認められない
従業員の遺族は、本件施設の完成時から、本件事故当時まで、本件ホッパーの投入口に車止め等の転落防止のための設備が設けられていなかったことから、本件施設が通常有すべき安全性を欠いており、本件施設の設置又は管理に瑕疵があると主張しました(国家賠償法2条1項)。
これに対し、裁判所は、次の点を指摘して、本件施設が通常有すべき安全性を欠き、被告市による本件施設の設置又は管理に瑕疵があると認めるには足りないと判断しました。
- 本件施設の設計・施工当時及び本件事故当時において、フォークリフトを利用して本件ホッパーへ直接投入方式によりごみを運搬・投入する者は、フォークリフトの運転に係る知識と技術を有する者に限定されることが前提とされていた
- そのような者にとっては、転落しないようにフォークリフトを操作することが特段困難なことではなかった
- 実際、本件施設において過去に転落事故はなく、車止め設置の要請もなかった
- 市は、相応の対価をもって、ごみ処理施設の運転維持管理等を専門とする業者に本件施設の運転維持管理を委託していた
会社の損害賠償責任は認められる
他方で、裁判所は、次の理由から、会社に安全配慮義務に違反したと認定し、会社の損害賠償責任を認めました。
- 会社が、責任者を通じて、従業員に対し、フォークリフトを用いてごみを本件ホッパーへ直接投入する作業についての安全な作業手順を周知徹底し、本件作業手順書に記載の作業手順が間違いなく遵守されるよう指導・教育する義務を果たしていたと認めることはできない
- 会社は、シートベルトを着用せずにフォークリフトを運転している従業員に対してシートベルトを着用するようその都度、注意・指導し、併せて、当該従業員だけでなく、他の従業員に対してもシートベルトの着用を徹底するよう指導・教育することを怠っていた
従業員の落ち度は4割と認定
会社は、シートベルト不装着とフォークリフトの操作ミスの落ち度は大きく8割の減額をすべきと主張しましたが、裁判所はシートベルトの不装着とフォークリフトの操作ミスについて会社の側にも多大な帰責性があると認め、従業員の落ち度として4割の減額をして、遺族厚生年金として受給済みの1200万円余りを差し引いた上で、2900万円余りの支払を命じました。
フォークリフト事故にあった場合の流れ
フォークリフト事故にあった場合の流れは次のとおりです。
労災の手続きや流れについて詳しく知りたい方は、「労災の手続きの流れと期限は?労災申請から示談の注意点を解説」をご覧ください。
①労災を報告してすぐに治療を開始する

労災事故が発生したらすぐに会社に報告し、労基署に労災申請をしてもらう必要があります。
またこれと並行して、すぐに治療を開始しましょう。できることなら、労災発生日に受診するのがおすすめです。
労災が発生してから、治療開始までに時間がかかってしまうと、「けがが労災によって引き起こされたものであること」を証明するのが難しくなるからです。
② 休業補償の支給
労災で仕事を4日以上休む場合、労基署が休業補償を支払ってくれますが、 労災の休業補償は申請してから支払われるまで1か月以上かかることも多いです。
労災保険が支払う休業補償には、給料の6割に当たる休業(補償)給付と2割に当たる特別支給金がありますが、会社に対して損害賠償請求をする際には、さらに4割の休業補償を請求することができます。
休業補償給付の支給の期限は2年ですので、早めに請求するようにしてください。
③ 症状固定(治療終了)

労災による怪我が完治せず、治療をしてもこれ以上よくならない状態になったら、治療効果がなくなるので、治療は終了になります。この状態のことを症状固定と呼びます。
症状固定となると、治療費や休業補償が打ち切られますので、症状固定のタイミングはとても大事になります。
症状固定の際に後遺症が残っている場合には④の後遺障害等級認定の手続きを取る必要がありますが、後遺症がない場合には⑤の会社との示談交渉に移ります。
④ 後遺障害の申請をする
後遺症が残っている場合、診断書を作成してもらわないと後遺障害の申請ができませんので、診断書を作成してもらいます。
その後、障害補償給付等の支給申請書などの必要書類と共に診断書を労働基準監督署に提出して、後遺障害の申請を行います。
フォークリフト事故の場合、労災の後遺障害等級認定に加えて、自賠責保険の後遺障害等級認定を利用することが可能ですので、どちらの手続きを利用するのか、両方利用するのかが問題になります。
自賠責保険の後遺障害等級認定を利用すると、自賠責保険金を受け取ることができるというメリットがあるのですが、自賠責保険の後遺障害等級が労災保険の後遺障害等級よりも低い等級で認定された場合、自賠責保険の後遺障害等級の方で慰謝料を計算される可能性がありますので、慎重に検つする必要があります。
⑤ 会社との間で示談交渉をする
 治療が終了して後遺障害の有無が確定したら、損害額が確定するので計算して、会社との間での示談交渉に移ります。
治療が終了して後遺障害の有無が確定したら、損害額が確定するので計算して、会社との間での示談交渉に移ります。
示談交渉で折り合えない場合には裁判に移ることになります。
会社に対する損害賠償請求の期限は、労災事故発生または症状固定日から5年になります。
労災保険の後遺障害等級認定の後で自賠責保険の後遺障害等級認定を利用した方がよいかはケースバイケースなので、労災に強い弁護士に早めに相談することをお勧めします。
フォークリフト事故の労働災害を弁護士に依頼した方がよい理由
フォークリフトの労働災害が発生した場合、労災に強い弁護士に依頼するのがおすすめです。その理由を説明します。
各種申請や請求の手間が省ける
労災が発生すると、様々な手間が発生します。
・各種保険金の請求のための書類作成や収集
・症状固定後の後遺障害認定の準備
・会社との示談交渉のやりとり など
それぞれの手続き自体は、自分の力で行うことは可能です。しかし、労災でけがの痛みに耐えながら、様々な行動を取るのは、心身共に辛いものがあるでしょう。
弁護士に依頼することで、面倒な手続きはすべて省くことができ、自分は治療に専念することができます。
適切な後遺障害等級に認定されやすくなる
後遺障害は、症状に合った適切な等級に認定されることがとても大切です。
後遺障害不認定になってしまったり、予定していた等級より低く認定されてしまったりすると、もらえる慰謝料(損害賠償金)の額が大きく変わってしまいます。
後遺障害の認定や、等級を決めるにあたって重要なのは、後遺障害診断書や、症状を証明するレントゲン写真などの証拠です。
これらを作成するのは、医師ですが、医師は、医療の専門家であり、法律や、後遺障害等級の専門家ではありません。
弁護士に依頼することで、医師に対し、後遺障害認定に必要な書類作成の指示出しをしたり、必要な検査を追加で行わせたりなど、万全の状態で申請をすることができます。
結果として、適切な等級に認定される可能性が高まります。後遺障害の審査結果に納得が行かない場合、再審査を求めることもできますが、結果が変わる可能性は20%以下だといわれています。
だからこそ、後遺障害認定は、労災に強い弁護士に依頼して、一発勝負のつもりで、挑むことが大切です。
慰謝料が増額する
慰謝料には「弁護士基準」や「裁判基準」と呼ばれる正当な金額がありますが、この金額を自分で会社に対して請求しても、うまく行かない可能性が高いです。
それは、会社が全面的に非を認めたり、大人しく支払いに応じたり、被災した労働者の交渉を聞いてくれる可能性が低いからです。
弁護士基準の最も高い金額で慰謝料を獲得するには、労災の強い弁護士に依頼して、裁判も辞さない強い姿勢で交渉をしていくことが大切です。
裁判となれば、請求する慰謝料の金額とその根拠を、裁判官に認めてもらう必要がなるので、なおさら、労災に強い弁護士の力が必要です。
フォークリフト事故の労災のまとめ
仕事中にフォークリフトで事故を起こした場合、労災認定される可能性が高いです。フォークリフト事故には、「転落・転倒・衝突」など様々な種類があります。
自分の落ち度(過失)に関わらず、業務、もしくは業務に関連する作業をしていた際に起きた事故は労災認定されます。
フォークリフト事故で負ったけがが治らず、後遺症が残る場合があります。その場合は、症状固定まで治療を続けて、後遺障害の認定を受けましょう。
後遺障害の認定を受ければ、労災保険から「障害補償給付」が支払われたり、会社に対して損害賠償請求ができます。
会社に慰謝料請求をする際、示談交渉を弁護士に依頼することで、もらえる金額がグッと高くなる可能性があります。
労災でお悩みの人は、一度弁護士に相談しましょう。法律事務所リンクスでは、無料相談を受け付けています。電話でわかりやすく説明いたしますので、お気軽にご利用ください。
労災被害にあったら労災に強い弁護士に無料相談・電話相談を!
 これまでご説明してきたとおり、労災は労基署と会社という2つの組織を相手にしなければならない上に、手続きも複雑であるため、労災で怪我をした本人やそのご家族だけで進めていくことには限界があります。
これまでご説明してきたとおり、労災は労基署と会社という2つの組織を相手にしなければならない上に、手続きも複雑であるため、労災で怪我をした本人やそのご家族だけで進めていくことには限界があります。
法律事務所リンクスの労災に強い弁護士の無料相談・電話相談では、手続きの進め方や後遺障害等級、慰謝料の見込みについて丁寧にご説明させて頂いております。
法律事務所リンクスでは着手金を0円とさせて頂いており、ご依頼頂ける場合にも経済的負担を心配される必要はございません。
まずはお気軽に法律事務所リンクスの無料相談・電話相談をご利用ください。
このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
全国の労働災害の被害者の救済のため無料電話相談に取り組む。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2015年に法律事務所リンクスを設立し、2016年に弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)として法人化。現在、東京と京都にオフィスがある。