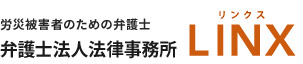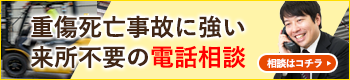労災の損害賠償請求!賠償金の計算方法と獲得までの流れを解説

労災の損害賠償は最初が肝心!
後遺症申請の前に弁護士に相談を!!
予期せぬ労災事故に見舞われた際、まず頼りになるのが労災保険です。しかし、労災保険からの給付だけでは、治療費や休業中の収入減、そして何より事故によって受けた精神的な苦痛など、被った損害のすべてをカバーできないケースが少なくありません。
「労災保険だけでは足りない…」「会社に事故の責任があるはずなのに…」
もしあなたが今、そのような状況にあるのなら、諦める必要はありません。会社に対して、労災保険では補償されない損害の賠償を請求できる可能性があります。
この記事では、法律事務所リンクスの労災に強い弁護士が、労災事故による損害賠償請求について、2025年版の最新情報に基づき、基本的な知識から具体的な請求ステップ、慰謝料などの相場、請求を成功させる秘訣、弁護士への依頼、注意すべき時効まで、網羅的に解説します。
労災事故で泣き寝入りせず、正当な補償を受けるために、ぜひ本ガイドをご活用ください。
電話での依頼で解決される方多数!お気軽にご相談ください!
- お電話で
無料相談【全国対応】 - 0120-917-740
受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)
労災の損害賠償請求とは?知っておくべき基本
労災事故に遭われた場合、労災保険から給付を受けることができますが、それだけでは十分な補償が得られないケースがあります。そのような場合に検討すべきなのが、会社に対する損害賠償請求です。ここでは、損害賠償請求の基本的な知識について解説します。
労災保険だけじゃ足りない?損害賠償請求の必要性
 労災保険は、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡に対して必要な保険給付を行う制度です。
労災保険は、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡に対して必要な保険給付を行う制度です。
しかし、労災保険から支給される金額は、あくまで法律で定められた範囲内であり、被災労働者の損害の全てを填補するものではありません。
例えば、以下のような損害については、労災保険だけでは十分な補償が得られない可能性があります。
- 精神的苦痛に対する慰謝料
- 将来の収入減(逸失利益)
- 介護費用
これらの損害は、労災保険の給付対象とならない、または十分な金額が支給されない場合があるからでます。
そのため、会社に責任がある場合には、損害賠償請求をすることで、労災保険ではカバーしきれない損害を補填する必要があるのです。
損害賠償請求できるケースとは?会社に責任がある場合
 労災事故が発生した場合、必ず会社に損害賠償責任が発生するわけではありません。
労災事故が発生した場合、必ず会社に損害賠償責任が発生するわけではありません。
損害賠償請求が認められるのは、会社に安全配慮義務違反や使用者責任などの法的責任がある場合に限られます。
具体的には、以下のようなケースが考えられます。
- 安全配慮義務違反:会社が、労働者の安全に配慮する義務を怠ったために事故が発生した場合(例:危険な機械の安全対策を怠った、過重労働を放置した)
- 使用者責任:会社の従業員(同僚など)の不法行為によって事故が発生した場合(例:フォークリフトの運転手が誤って同僚を轢いてしまった)
- 工作物責任:会社の施設や設備に欠陥があり、それが原因で事故が発生した場合
これらの責任が認められるためには、会社側の過失と事故の発生との間に因果関係があることが必要です。
因果関係の立証は難しい場合もあるため、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
労災事故解決までの流れと弁護士に依頼するメリットの解説動画
労災被害者のための無料電話相談実施中
 法律事務所リンクスの無料電話相談では、労災に強い弁護士が、労災で怪我をしてお困りの被害者のための電話での無料相談を実施しています。
法律事務所リンクスの無料電話相談では、労災に強い弁護士が、労災で怪我をしてお困りの被害者のための電話での無料相談を実施しています。
労災で大怪我をした場合、仕事に復帰できるのか、今後の生活はどうなるのか、後遺障害が残ったらどうすればよいのかといった不安が大きいこといます。
弁護士に依頼すれば、どのように対応すればよいかのアドバイスを受けたり、着手金0円で窓口を任せたりすることができますので、治療や仕事復帰に集中することが可能です。
労災で怪我をしてお困りの被害者の方は、0120-917-740にお電話を頂くか、LINEで労災の無料相談をお申し込みください。
賠償金の種類:慰謝料、休業損害、後遺障害逸失利益など
労災事故による損害賠償請求で請求できる主な項目は、以下の通りです。
| 損害項目 | 内容 |
|---|---|
| 治療費 | 労災保険でカバーされない治療費(差額ベッド代、先進医療など) |
| 休業損害 | 休業期間中の収入減(労災保険から支給される休業補償給付との差額) |
| 慰謝料 | 精神的苦痛に対する賠償金(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料) |
| 後遺障害逸失利益 | 後遺障害が残ったことによる将来の収入減 |
| 介護費用 | 後遺障害により介護が必要になった場合の費用 |
| 葬儀費用 | 死亡事故の場合の葬儀費用 |
これらの損害項目について、それぞれ金額を算出し、合計額を会社に請求することになります。
損害額の計算は複雑になる場合があるため、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。慰謝料の金額は、通院期間や家族内での立場によって異なってきます。
【簡単図解】労災の損害賠償請求、7つのステップで徹底解説
労災事故による損害賠償請求は、複雑で時間のかかるプロセスとなる場合があります。
しかし、以下の7つのステップを理解し、適切に進めることで、正当な賠償金を受け取ることが可能になります。
ステップ1:労災事故の発生を会社に報告
 まず、労災事故が発生したら、速やかに会社(上司や人事担当者など)に報告することが重要です。口頭だけでなく、書面でも報告するようにしましょう。書面で報告することで、後々の証拠となります。報告書には、以下の内容を記載すると良いでしょう。
まず、労災事故が発生したら、速やかに会社(上司や人事担当者など)に報告することが重要です。口頭だけでなく、書面でも報告するようにしましょう。書面で報告することで、後々の証拠となります。報告書には、以下の内容を記載すると良いでしょう。
- 事故発生日時
- 事故発生場所
- 事故の状況(何が起きたのか、どのようにして怪我をしたのか)
- 負傷の程度
- 目撃者の有無(目撃者がいる場合は、氏名と連絡先)
会社への報告は、労災保険の申請手続きを進める上でも必須となります。会社が労災の事実を隠蔽しようとするケースもあるため、報告した証拠を残しておくことが大切です。
ステップ2:労働基準監督署への労災申請
労災保険給付を受けるためには、労働基準監督署への申請が必要です。申請には、所定の様式に必要事項を記入し、添付書類とともに提出します。主な申請書の種類は以下の通りです。
| 給付の種類 | 申請書名 |
|---|---|
| 療養(補償)給付 | 療養(補償)給付たる療養の給付請求書 |
| 休業(補償)給付 | 休業(補償)給付支給請求書 |
| 障害(補償)給付 | 障害(補償)給付支給請求書 |
これらの申請書は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。申請書の記入方法や必要書類については、労働基準監督署に問い合わせるか、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
ステップ3:怪我の治療
 労災事故による怪我の治療は、労災指定医療機関で受けるのが原則です。労災指定医療機関であれば、治療費は原則として自己負担なしで済みます。労災指定医療機関以外で治療を受けた場合は、一旦自己負担で支払い、後日、労働基準監督署に払い戻しを請求することになります。
労災事故による怪我の治療は、労災指定医療機関で受けるのが原則です。労災指定医療機関であれば、治療費は原則として自己負担なしで済みます。労災指定医療機関以外で治療を受けた場合は、一旦自己負担で支払い、後日、労働基準監督署に払い戻しを請求することになります。
治療を受ける際には、医師に労災事故による怪我であることを伝え、適切な治療を受けるようにしましょう。また、治療の経過や内容を記録しておくことも重要です。これらの記録は、後々の損害賠償請求の際に役立ちます。
ステップ4:症状固定と診断書の作成
 治療を続けても症状の改善が見込めなくなった状態を「症状固定」といいます。症状固定の時期は、医師が判断します。症状固定と診断されたら、後遺障害等級認定の申請に向けて、医師に後遺障害診断書の作成を依頼します。
治療を続けても症状の改善が見込めなくなった状態を「症状固定」といいます。症状固定の時期は、医師が判断します。症状固定と診断されたら、後遺障害等級認定の申請に向けて、医師に後遺障害診断書の作成を依頼します。
後遺障害診断書は、後遺障害等級認定の審査において、非常に重要な資料となり、不十分な内容である場合、適正な後遺障害等級の認定を受けられない可能性がありますので、後遺障害診断書を作成する前に、労災に強い弁護士の無料相談を受けることをお勧めします。
ステップ5:後遺障害等級認定の申請
 後遺障害が残った場合、後遺障害等級認定の申請を行います。後遺障害等級認定の申請は、労働基準監督署に行います。申請には、後遺障害診断書のほか、レントゲン写真やMRI画像などの資料が必要となる場合があります。
後遺障害が残った場合、後遺障害等級認定の申請を行います。後遺障害等級認定の申請は、労働基準監督署に行います。申請には、後遺障害診断書のほか、レントゲン写真やMRI画像などの資料が必要となる場合があります。
後遺障害等級は、身体に残った障害の種類や程度によって1級から14級に区分され、等級に応じて労災保険から支払われる障害(補償)給付や会社に請求する後遺障害の損害賠償に関する金額が大きく異なります。
適切な後遺障害等級認定を受けるためには、医師の診断書や検査結果などをしっかりと準備し、申請を行う必要がありますので、 弁護士などの専門家に相談する必要があります。
後遺障害等級認定の結果に納得がいかない場合は、審査請求(異議申し立て)をすることができます。異議申し立てをする場合は、新たな証拠を提出するなどして、再度審査を求めることになります。
ステップ6:賠償金の計算
 損害賠償金の計算は、複雑で専門的な知識が必要となる場合があります。損害賠償の項目は多岐にわたり、慰謝料、休業損害、後遺障害逸失利益などが含まれます。それぞれの項目について、適切な金額を算出し、合計する必要があります。
損害賠償金の計算は、複雑で専門的な知識が必要となる場合があります。損害賠償の項目は多岐にわたり、慰謝料、休業損害、後遺障害逸失利益などが含まれます。それぞれの項目について、適切な金額を算出し、合計する必要があります。
損害賠償額の計算方法については、後述の「労災の損害賠償、いくらもらえる?相場と計算方法を徹底シミュレーション」の章で詳しく解説します。
ステップ7:会社への損害賠償請求
 損害賠償金の金額が確定したら、会社に対して損害賠償請求を行います。まずは、会社と交渉し、示談による解決を目指すのが一般的です。交渉では、損害賠償金の金額や支払い方法などについて、合意を目指します。
損害賠償金の金額が確定したら、会社に対して損害賠償請求を行います。まずは、会社と交渉し、示談による解決を目指すのが一般的です。交渉では、損害賠償金の金額や支払い方法などについて、合意を目指します。
会社との交渉がうまくいかない場合は、裁判所に訴訟を提起することも検討する必要があります。訴訟では、裁判官が双方の主張を聞き、証拠を検討した上で、判決を下します。訴訟には、時間と費用がかかるため、弁護士に相談することをおすすめします。
労災の損害賠償請求では、会社が責任を認めない、損害賠償額で合意できない、時効が迫っているなど、様々なトラブルが発生する可能性があります。これらのトラブルについては、後述の「労災の損害賠償請求でよくあるトラブルと解決策」の章で詳しく解説します。
労災の賠償金、いくらもらえる?計算方法を徹底シミュレーション
労災事故による損害賠償金は、個々の状況によって大きく異なります。「一体いくらもらえるんだろう?」と、金額の見当がつかない方もいるかもしれません。ここでは、賠償金の計算方法から、慰謝料、休業損害、後遺障害逸失利益といった賠償金の計算方法を、具体的に解説していきます。
賠償金の計算方法:項目別に解説
労災事故における損害賠償は、大きく分けて以下の項目で構成されます。
- 治療費: 労災事故による怪我や病気の治療にかかった費用(診察代、薬代、入院費、手術費など)
- 休業損害: 労災事故による休業期間中の収入減
- 慰謝料: 精神的な苦痛に対する補償
- 後遺障害逸失利益: 後遺障害が残った場合に、将来得られたはずの収入の減少分
- その他: 入院雑費、通院交通費、将来の介護費など これらの項目を一つ一つ積み上げていくことで、損害賠償額を算出します。
と増額要因
慰謝料の相場
労災事故における慰謝料は、精神的な苦痛に対する補償であり、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料と死亡慰謝料の3種類があります。
- 入通院慰謝料: 怪我の治療のために、入院や通院を余儀なくされた精神的苦痛に対する慰謝料です。通院期間や入院期間、怪我の程度によって金額が変動します。目安としては、通院1ヶ月以上で28万円~300万円程度が相場となります。
- 後遺障害慰謝料: 後遺障害が残ってしまった場合に、その精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。後遺障害等級によって金額が大きく異なり、110万円~2800万円程度が相場です。
- 死亡慰謝料:労災事故で死亡した場合に、遺族に対して支払われる慰謝料です。亡くなった方の立場に応じて、2000万円~2800万円程度が認められることが多いです。
死亡事故の損害賠償については、「労災で死亡事故の金額は?保険金はいくら?遺族補償年金の計算は?」をご覧ください。
慰謝料が増額する要因
慰謝料が増額する要因には、次のようなものがあります。
- 会社の安全配慮義務違反が重大である場合
- 事故状況が悲惨である場合
- 会社側の対応が不誠実な場合
休業損害の計算方法と注意点
休業損害とは、労災事故によって休業せざるを得なくなった期間中の収入減を補償するものです。
休業損害の計算方法
休業損害 = (事故前3ヶ月の賃金 ÷ 90日) × 休業日数
休業損害の注意点
労災保険から休業(補償)給付の支給を受けている場合、会社に請求する休業損害から差し引くのが原則です。
労災保険から支払われる休業(補償)給付の金額は、賃金の60%であり、これは差し引いて請求しますが、休業特別支給金として支払われた20%については、差し引く必要はありません。
後遺障害逸失利益の計算方法と等級認定
後遺障害逸失利益とは、労災事故によって後遺障害が残ってしまった場合に、その障害によって将来得られたはずの収入が減少してしまうことを補償するものです。
後遺障害逸失利益の計算方法
後遺障害逸失利益 = 事故前の年収 × 労働能力喪失率* × 労働能力喪失期間**に対応するライプニッツ係数***
*労働能力喪失率: 後遺障害等級に応じて定められています。例えば、1級で100%、14級で5%など。
**労働能力喪失期間: 原則として症状固定日から67歳まで。
***ライプニッツ係数: 将来受け取るはずの金額を、現在の価値に換算するための係数です。
他にも様々な損害項目がありますので、弁護士に相談してご自身のケースではどのような項目が請求できるのか、いくらくらいが相場なのかを確認することをおすすめします。 労災事故の損害賠償金額相場は、高額になると1億円を超えるケースもあります。
| 損害賠償項目 | 内容 | 計算方法・相場 |
|---|---|---|
| 治療費 | 労災事故による怪我や病気の治療にかかった費用 | 実費 |
| 休業損害 | 休業期間中の収入減 | (事故前3ヶ月の賃金 ÷ 90日) × 休業日数 |
| 慰謝料 | 精神的な苦痛に対する補償 | 入通院慰謝料:通院1ヶ月以上で28万円~300万円 後遺障害慰謝料:110万円~2800万円 |
| 後遺障害逸失利益 | 後遺障害による将来の収入減 | 事故前の年収 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
会社が賠償金を払ってくれない?労災の損害賠償請求を成功させる3つの秘訣
労災事故に遭われた方が、会社に対して損害賠償請求をすることは、決して簡単な道のりではありません。会社が責任を認めなかったり、適切な賠償額を提示してくれなかったりするケースも少なくありません。しかし、泣き寝入りする必要はありません。損害賠償請求を成功させるための秘訣を3つご紹介します。
秘訣1:労災を申請して労災認定を受ける
 まず、大前提として、労災保険の申請を行い、労災認定を受けることが重要です。労災認定は、業務または通勤が原因で負傷、疾病、障害、死亡した場合に、労働基準監督署がその事実を認めるものです。労災認定を受けることで、治療費や休業補償などの労災保険給付を受けられるようになります。
まず、大前提として、労災保険の申請を行い、労災認定を受けることが重要です。労災認定は、業務または通勤が原因で負傷、疾病、障害、死亡した場合に、労働基準監督署がその事実を認めるものです。労災認定を受けることで、治療費や休業補償などの労災保険給付を受けられるようになります。
さらに、労災認定は、会社に対する損害賠償請求においても非常に重要な証拠となります。労災認定を受けていることは、会社に安全配慮義務違反があった可能性を示す根拠の一つとなり、損害賠償請求を有利に進める上で大きな武器となります。
労災申請の手続きは煩雑で、必要な書類も多岐にわたります。しかし、諦めずにしっかりと申請を行い、労災認定を受けましょう。もし、申請方法が分からない場合は、労働基準監督署や弁護士に相談することをおすすめします。
秘訣2:早めに弁護士に相談する
 労災事故が発生したら、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。特に、以下のようなケースでは、弁護士のサポートが不可欠です。
労災事故が発生したら、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。特に、以下のようなケースでは、弁護士のサポートが不可欠です。
- 会社が労災事故の発生を認めない場合
- 会社との示談交渉が難航している場合
- 後遺障害が残ってしまった場合
- 死亡事故の場合
弁護士は、法的知識と交渉力を用いて、あなたの権利を守ってくれます。会社との交渉を代行してくれるだけでなく、適切な賠償額の算定、必要な証拠の収集、訴訟手続きなど、あらゆる面でサポートしてくれます。特に、労災問題に精通した弁護士であれば、過去の判例や類似の事例に基づいて、より有利な条件で示談交渉を進めることができます。労災に強い弁護士への相談を検討しましょう。
弁護士に相談することで、精神的な負担も軽減されます。事故後の不安や会社とのやり取りのストレスから解放され、治療に専念することができます。
秘訣3:後遺障害等級の認定を受ける
 労災事故によって後遺障害が残ってしまった場合は、後遺障害等級の認定を受けることが非常に重要です。後遺障害等級とは、労働者災害補償保険法に基づいて、後遺障害の程度を1級から14級に区分したものです。後遺障害等級が認定されると、障害(補償)給付や、後遺障害逸失利益といった損害賠償の対象となる金額が大きく変わります。
労災事故によって後遺障害が残ってしまった場合は、後遺障害等級の認定を受けることが非常に重要です。後遺障害等級とは、労働者災害補償保険法に基づいて、後遺障害の程度を1級から14級に区分したものです。後遺障害等級が認定されると、障害(補償)給付や、後遺障害逸失利益といった損害賠償の対象となる金額が大きく変わります。
後遺障害等級の認定は、専門的な知識が必要となるため、弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。適切な検査を受け、必要な書類を揃え、的確な申請を行うことで、より高い等級の認定を受けることができる可能性があります。
後遺障害等級の認定を受けることは、将来の生活を保障する上で非常に重要な意味を持ちます。諦めずに、専門家のサポートを受けながら、しっかりと手続きを進めましょう。
労災の損害賠償請求で弁護士に依頼するメリット・デメリット
労災事故による損害賠償請求は、複雑な法的知識や交渉スキルが求められるため、弁護士に依頼することを検討する方も多いでしょう。ここでは、弁護士に依頼するメリットとデメリットを具体的に解説します。
弁護士に依頼するメリット:交渉力アップ、手続き代行、精神的負担軽減
 弁護士に依頼する最大のメリットは、専門家によるサポートを受けられることです。具体的には、以下の3点が挙げられます。
弁護士に依頼する最大のメリットは、専門家によるサポートを受けられることです。具体的には、以下の3点が挙げられます。
①交渉力アップ
弁護士は、法律の専門家として、会社側との交渉を有利に進めることができます。 損害賠償請求においては、会社側が責任を認めなかったり、賠償金額で折り合いがつかなかったりするケースが少なくありません。弁護士は、法的根拠に基づき、粘り強く交渉することで、依頼者の正当な権利を実現します。
②手続き代行
労災の損害賠償請求には、煩雑な書類作成や手続きが必要です。 弁護士に依頼することで、これらの手続きを代行してもらうことができ、時間と労力を大幅に削減できます。特に、後遺障害等級認定の申請や、訴訟になった場合には、専門的な知識が必要となるため、弁護士のサポートは不可欠です。
③精神的負担軽減
労災事故に遭われた方は、心身ともに大きなダメージを受けています。 そのような状況で、会社側と直接交渉することは、精神的な負担が大きすぎます。 弁護士に依頼することで、会社とのやり取りを全て任せることができ、精神的な負担を軽減し、治療に専念することができます。
弁護士に依頼するデメリット:費用がかかる
弁護士に依頼するデメリットは、費用がかかることです。 弁護士費用は、相談料、着手金、報酬金、実費などで構成されており、事件の内容や難易度によって異なります。
もっとも、弁護士に依頼することで、賠償金が増額される可能性が高く、結果的に弁護士費用を上回るメリットを得られるケースが多いです。 また、弁護士によっては、無料相談を実施している場合や、成功報酬制を採用している場合もありますので、事前に確認しておきましょう。
弁護士費用の目安は以下の通りです。
| 費用項目 | 相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 相談料 | 無料~5,000円/30分 | 初回相談無料の弁護士も多い |
| 着手金 | 20万円~※無料の事務所もある | 事件の内容や難易度によって異なる |
| 報酬金 | 回収できた賠償金の11~22%程度 | 成功報酬制の場合 |
| 実費 | 数万円~ | 交通費、通信費、印紙代など |
法律事務所リンクスでは着手金は0円の成功報酬制を原則としています。詳しくは、「法律事務所リンクスの労災の弁護士費用」をご覧ください。
弁護士選びのポイント:労災問題に強い弁護士を選ぶ
弁護士に依頼する際には、労災問題に強い弁護士を選ぶことが重要です。 労災問題は、専門的な知識や経験が求められるため、実績のある弁護士に依頼することで、より有利に交渉を進めることができます。
労災に強い弁護士を選ぶポイントは以下の通りです。
- 労災への注力度と実績
- 後遺障害等級認定の獲得実績とサポート体制
- 相談のしやすさと説明の丁寧さ
- 手続き・解決方法の具体的説明
- 事務所の人員・労災サポート体制
- 顧問医の有無など医学的サポート体制
- 明確で納得できる弁護士費用
詳しくは「【後悔しない!】労災に強い弁護士の選び方と相談前に知るべきこと」をご覧ください。
労災の損害賠償請求でよくあるトラブルと解決策
労災事故による損害賠償請求は、会社との交渉が必要となるため、様々なトラブルが発生することがあります。ここでは、よくあるトラブルとその解決策について解説します。
トラブル1:会社が責任を認めない
 会社が労災事故に対する損害賠償責任を認めず、損害賠償請求に応じないケースは少なくありません。
会社が労災事故に対する損害賠償責任を認めず、損害賠償請求に応じないケースは少なくありません。
会社側は、次のようなことを言ってくる可能性があります。
- 事故原因は労働者自身の不注意である
- 安全配慮義務違反はない
- 労働者自身に大きな過失があるため労災保険からの支給以上に支払うものはない
このような場合、損害賠償責任が認められるのかや、労働者自身の落ち度が問題になっているので、訴訟での解決を図らないと難しいことが多く、少なくとも弁護士が入らないと交渉は前に進まないでしょう。
トラブル2:損害賠償額で合意できない
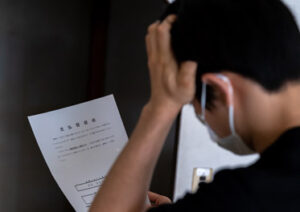 会社が損害賠償責任を認めたとしても、損害賠償額で合意できないケースがあります。
会社が損害賠償責任を認めたとしても、損害賠償額で合意できないケースがあります。
例えば、
- 慰謝料の金額が過大である
- 休業損害の計算方法に誤りがある
- 後遺障害逸失利益の算定根拠が不明確である
などと主張してくる場合です。
この場合、双方の損害額の計算が正しいのかが問題となっているので、双方が弁護士に相談するなどして損害額の計算の根拠を明らかにして、交渉を進めていく必要があるでしょう。
トラブル3:時効が迫っている
労災事故による損害賠償請求には時効があり、一定期間が経過すると請求権が消滅してしまいますので、時効が成立する前に、損害賠償を請求する必要があります。詳しくは、次の項目で解説します。
労災の損害賠償請求、時効に注意!請求期限と対策を徹底解説
労災事故による損害賠償請求には、時効があります。時効を過ぎてしまうと、会社に対して損害賠償を請求する権利を失ってしまうため、注意が必要です。ここでは、損害賠償請求の時効について、詳しく解説します。
損害賠償請求の時効:何年?
労災事故における損害賠償請求の時効は、原則として5年です。
この5年という期間は、2020年4月1日以降に発生した労災事故に適用されるものです。
それ以前の事故については、自身と労働契約を締結している会社に損害賠償請求する場合の時効は10年、他の従業員や元請など直接契約関係にない会社に損害賠償請求する場合の時効は原則3年とされていました。
起算点(いつから数え始めるか)は、損害および加害者(会社)を知った時からです。例えば、労災事故が発生し、その事故が会社の安全配慮義務違反によって発生したことを知った時点から、5年以内に請求する必要があります。
ただし、後遺障害が残った場合は、症状固定日(治療を続けても症状の改善が見込めないと診断された日)から時効が進行すると解釈されることもあります。この点については、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
また、労災保険の給付請求権にも時効があります。労災保険給付の種類によって、2年または5年の時効が定められています。
例えば、療養(補償)給付は、療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、それぞれの支出の翌日から2年で時効となります。
| 請求の種類 | 時効 | 起算点 |
|---|---|---|
| 損害賠償請求(2020年4月1日以降の事故) | 5年 | 損害および加害者(会社)を知った時 |
| 損害賠償請求(2020年3月31日以前の事故) | 3年または10年 | 損害および加害者(会社)を知った時 |
| 労災保険給付 | 2年または5年(給付の種類による) | 各給付の種類によって異なる |
時効を中断(更新)させる方法
時効が迫っている場合でも、以下の方法によって時効の進行を中断(更新)させることができます。
- 内容証明郵便による請求
内容証明郵便で会社に対して損害賠償請求を行うことで、時効の完成を6ヶ月間猶予することができます。ただし、この方法では時効の完成を一時的に猶予するだけで、根本的な解決にはなりません。6ヶ月以内に、訴訟提起などの法的手続きを行う必要があります。 - 訴訟提起
裁判所に訴訟を提起することで、時効の完成を阻止することができます。訴訟提起は、時効中断の最も確実な方法です。 - 会社による債務の承認
会社が損害賠償責任を認め、債務を承認した場合にも、時効は中断します。債務の承認は、書面で確認しておくことが重要です。
時効が迫っている場合は、速やかに弁護士に相談し、適切な対応を検討することをおすすめします。弁護士は、時効中断の手続きを代行するだけでなく、会社との交渉や訴訟手続きもサポートしてくれます。
労災の損害賠償に関するよくある質問
Q1:労災保険の給付を受けていても、会社に損害賠償請求できますか?
A1:はい、可能です。労災保険は損害の一部を補填するものですが、慰謝料や逸失利益の全額など、労災保険だけではカバーしきれない損害があります。会社に安全配慮義務違反などの責任がある場合は、別途損害賠償請求が可能です。
Q2:どのような場合に、会社に損害賠償を請求できるのですか?
A2:会社に「安全配慮義務違反」(労働者の安全を守る対策を怠った)や「使用者責任」(他の従業員の過失による事故)、「工作物責任」(会社の設備の欠陥)などが認められる場合に請求できます。会社側の過失と事故との因果関係が必要です。
Q3:損害賠償として、具体的に何を請求できますか?
A3:主に、労災保険でカバーされない治療費、休業による収入減(休業損害)、精神的苦痛に対する慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)、後遺障害による将来の収入減(後遺障害逸失利益)、将来の介護費用、死亡事故の場合の葬儀費用などが請求できます。
Q4:損害賠償請求は、どのような流れで進めればよいですか?
A4:まず会社へ事故を報告し、労働基準監督署へ労災申請を行います。治療を受け、症状固定後に後遺障害が残れば等級認定の申請をします。その後、損害額を計算し、会社と示談交渉を開始します。交渉がまとまらなければ、訴訟を検討します。
Q5:損害賠償請求に、弁護士は必要ですか?
A5:必須ではありませんが、弁護士に依頼するメリットは大きいです。法的な知識に基づき、会社との交渉を有利に進め、煩雑な手続きを代行してくれます。特に、会社が責任を認めない場合や後遺障害が残った場合、賠償額が高額になる場合は、弁護士への相談・依頼を強く推奨します。精神的な負担軽減にも繋がります。
Q6:損害賠償請求に期限(時効)はありますか?
A6:はい、あります。会社に対する損害賠償請求権は、原則として損害および加害者(会社)を知った時から5年で時効となります(2020年4月1日以降の事故の場合)。ただし、起算点や中断方法など複雑な点もあるため、早めに専門家へ相談することが重要です。
Q7:会社が「払えない」「責任はない」と言ってきた場合はどうすれば?
A7:会社が責任を否定したり、賠償額に納得しなかったりすることはよくあります。このような場合は、事故状況や会社の過失を示す証拠を集め、弁護士に相談して交渉や訴訟を進めることを検討しましょう。労災認定を受けていることは、交渉を有利に進める上で重要な要素となります。
まとめ:労災で適正な賠償金を獲得するために
労災事故による損害賠償請求は、事故によって失われたものを完全に取り戻すことはできなくとも、被災された労働者やご遺族が正当な補償を受け、今後の生活を再建するために非常に重要な手続きです。
本記事で解説したように、労災保険だけではカバーしきれない損害(特に慰謝料や逸失利益)については、会社に責任があれば別途請求が可能です。
労災事故に遭われたら、まず以下の点を強く意識してください。
- 速やかに会社へ報告し、労災申請を行うこと。(労災認定は損害賠償請求の土台となります)
- 事故状況や治療経過に関する証拠を確保すること。
- 後遺障害が残った場合は、適切な後遺障害等級認定を目指すこと。
- 損害賠償請求権の時効(原則5年)に注意すること。
- 会社との交渉や手続きに不安があれば、早期に労災問題に強い弁護士に相談すること。
会社が責任を認めない、提示額が低いといった場合でも、決して泣き寝入りする必要はありません。専門家のサポートを受けながら、適切な手順を踏むことで、正当な権利を実現できる可能性が高まります。
この記事が、労災事故でお悩みの方々にとって、損害賠償請求への一歩を踏み出すための確かなガイドとなることを願っています。
泣き寝入りしないために労災に強い弁護士に無料相談を
 労災事故による損害賠償請求は、複雑な法的問題が絡むことが多く、専門的な知識が必要となります。泣き寝入りせずに、正当な賠償金を受け取るために、まずは弁護士にご相談ください。
労災事故による損害賠償請求は、複雑な法的問題が絡むことが多く、専門的な知識が必要となります。泣き寝入りせずに、正当な賠償金を受け取るために、まずは弁護士にご相談ください。
労災事故は、労働者にとって身体的、精神的に大きな負担となるだけでなく、経済的な不安ももたらします。しかし、泣き寝入りする必要はありません。労災保険給付に加えて、会社の安全配慮義務違反が認められる場合には、損害賠償請求を行うことが可能です。
泣き寝入りせずに、まずは一歩踏み出しましょう。
法律事務所リンクスでは、労災でお悩みの方のために、無料相談を実施しています。
お電話(0120-917-740)または LINE で、労災に強い弁護士が直接あなたのお悩みをお伺いし、今後の見通しや、私たちができるサポートについて具体的にご説明します。
相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。まずはあなたの状況を整理し、専門家の意見を聞いてみるだけでも、きっと解決への道筋が見えてくるはずです。
着手金はいただいておりませんので、初期費用のご負担なくご依頼いただけます。
後遺障害の申請、会社との交渉、そしてあなたの未来のために。 まずはお気軽に、法律事務所リンクスの無料相談をご利用ください。私たちが全力でサポートいたします。
▼今すぐ無料相談▼
- お電話でのご相談(フリーダイヤル):0120-917-740
- LINEでのご相談:LINEで労災の無料相談の申込方法
ご連絡、お待ちしております。
このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
全国の労働災害の被害者の救済のため無料電話相談に取り組む。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2015年に法律事務所リンクスを設立し、2016年に弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)として法人化。現在、東京と京都にオフィスがある。