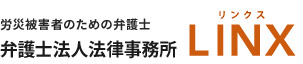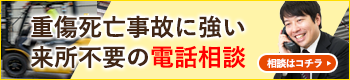労災で骨折したら休業補償期間はいつまで?リハビリ自宅療養に医師の証明は?

労災で骨折し仕事復帰を急ぐと休業補償は打ち切りに!
適正な賠償金の支払いを受けるため弁護士に相談を!
労災で骨折した場合の休業補償の期間は、仕事に復帰するまでが原則であり、仕事に復帰できない場合には治療が終了するまで支払われることも多いですが、治療が終了した場合には打ち切りになります。
労災で骨折した場合の休業補償の金額は、休業(補償)給付として賃金の6割、休業特別支給金として賃金の2割ですが、労災の発生について会社に責任がある場合には、賃金の4割を会社に請求することができる場合があります。
また、同様に、会社に対して、骨折による入通院慰謝料、後遺症が残った場合には後遺障害慰謝料や逸失利益(後遺障害で労働能力が制限されることへの補償)などの損害賠償請求をすることができます。
このページでは、法律事務所リンクスの労災に強い弁護士が、「労災で休業補償を受け取るための条件」や「労災で骨折した場合の休業補償の期間がいつまでか」「労災の休業補償の金額とその請求方法」について解説します。
労災で骨折した場合の慰謝料について詳しく知りたい方は、「労災で骨折!見舞金はいくらもらえる?慰謝料や後遺症は?」をご覧ください。
電話での依頼で解決される方多数!お気軽にご相談ください!
- お電話で
無料相談【全国対応】 - 0120-917-740
受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)
労災の骨折で休業補償を受け取れる条件は?パートでももらえる?
労災の骨折で休業補償を受け取れる条件を確認しましょう。
①通勤中もしくは仕事中に骨折
 労災保険の適用範囲は、「労働者が仕事中や通勤中に負ったけが・病気」に限られます。
労災保険の適用範囲は、「労働者が仕事中や通勤中に負ったけが・病気」に限られます。
仕事中の事故の例としては、誤って足場から転落して骨折したり、機械に手足を挟まれて骨折したりした場合などです。
通勤中の事故の例は交通事故で骨折した場合などが挙げられます。
②休業が必要であることの医師の証明
 労災で休業補償をもらうには、療養のため労働ができないことに関する医師の証明が必要です。
労災で休業補償をもらうには、療養のため労働ができないことに関する医師の証明が必要です。
その際、休業が必要な期間を証明してもらう必要があります。
③賃金をもらっていない
休業補償は、労働者が実際に賃金を受け取っていない期間に支給されます。
例えばですが、「今までの仕事はできなくなったが、けがをしている間は別の仕事をして給料をもらっている」などの状況では休業補償は給付されません。
給料と休業補償給付は二重取りできないのです。
労災で骨折したらパートでもアルバイトでも休業補償はもらえる
上記の条件を満たしていれば、パートでもアルバイトでも休業補償をもらうことができます。
労災で骨折したのにパートやアルバイトが労災保険の対象外だから休業補償は支払えないと言われても鵜呑みにする必要はありません。
労災で骨折した場合の休業補償期間はいつまで?自宅療養・リハビリ・ボルト除去の取扱いは?
労災で骨折した際、休業補償が支払われ続ける期間はいつまでなのでしょうか。
仕事に復帰するまでが原則で自宅療養中も支給される
 休業補償給付の支給期間は、原則として医師に仕事復帰が可能と診断されるまでです。
休業補償給付の支給期間は、原則として医師に仕事復帰が可能と診断されるまでです。
したがって、医師が退院後に自宅療養が必要と診断している場合には、休業補償の支給は継続します。
もっとも、医師が休業が必要と考えているにもかかわらず無理して仕事に復帰した場合、その後仕事が難しくなって休業するとなっても休業補償給付が支給されるとは限りませんので、ご注意ください。
他方で、医師に仕事復帰が可能と診断された時点で、休業補償給付は終了しますので、ボルトやプレートが入ったままの状態でも、仕事復帰が可能と診断されれば、休業補償の支給は終了となります。
ただし、骨折箇所にボルトやプレートが入っている場合、ボルトやプレートを抜く手術で休業する場合には、症状の再発として、休業補償給付が再支給されます。
仕事に復帰できない場合の休業補償の打ち切りのタイミング
骨折が完治したら打ち切り
仕事に復帰できない場合でも、骨折が完治したら、労災保険からの休業補償給付は打ち切られます。
骨折が完治しなくても症状固定で打ち切り
骨折の治療を続けても、これ以上の回復が見込めず、症状が残ってしまった場合、医師と被災者の相談により「症状固定」を行います。
症状固定は、その後の後遺障害認定や、障害補償給付の受け取りのために必要なステップですが、症状固定をした時点で休業補償給付は打ち切られます。
受給開始から1年6か月後も症状が残ったとき
休業補償給付を受給開始してから、1年6か月を経過しても病気やけがが治らない場合、休業補償給付を継続して受給するケースと、傷病補償年金に移行するケースに分かれます。
労働基準監督署の判断により、「傷病等級1~3級に該当する」と認定した場合は、傷病補償年金に移行し、休業補償給付の支払いが打ち切られることがあります。
仕事しながらリハビリ通院する場合はどうなる?
 仕事に復帰はしたものの、リハビリ通院のために会社を休んだり、早退などをすることもあるでしょう。
仕事に復帰はしたものの、リハビリ通院のために会社を休んだり、早退などをすることもあるでしょう。
このような「所定時間労働の一部だけを休業する場合」、休業補償給付が支払われるか、支払われないかについて説明します。
例えば、午前中にリハビリ通院をするために会社を休み、午後から出社するとします。
この場合、「その日会社から支払われる賃金の額が、給付基礎日額の60%未満」である場合、休業補償給付が支払われます。
具体例をあげてもう少し簡単に説明します。
1日あたりの給料(給付基礎日額)が10,000円の人の場合、会社から支払われる賃金が6,000円未満であれば、休業補償給付が支給されます。
丸半日休んだ場合、休んだ時間分の賃金は5,000円(給付基礎日額の60%未満)になりますので、休業補償給付が支払われます。
逆に5時間労働した場合、会社から支払われる給料は6,250円となり、給付基礎日額の60%を超えてしまうため、休業補償給付は支払われません。
労災の骨折で労災保険から給付される休業補償の金額
労災で骨折し、会社を休業した際に支払われる金額について説明します。
休業補償給付で賃金の60%
 労災で休業した際に、まず支払われるのは、労災保険の休業補償給付です。労災で3日以上休業した場合、「4日目以降の休業に対して、給付基礎日額の60%」が支払われます。
労災で休業した際に、まず支払われるのは、労災保険の休業補償給付です。労災で3日以上休業した場合、「4日目以降の休業に対して、給付基礎日額の60%」が支払われます。
休業補償給付の額を決定するのに、給付基礎日額について説明します。ざっくりいえば「1日あたりの自分の給料」のことですが、以下のような計算で求められます。
「給付基礎日額=労災発生前の3ヶ月にもらった給料÷労災発生前3ヶ月の日数」
例えば、月給が30万円の人の場合、3ヶ月の日数が90日だった場合、給付基礎日額は1万円となります。
給付基礎額が1万円の人が103日休業した場合、4~103日目の100日分(100万円)の60%となるため、60万円が支払われます。
給付基礎日額が1万円の人が103日休業した場合、実際に減少する給料は103万円です。休業補償給付から支払われるのは60万円ですから、「金額が足りない」のが正直なところでしょう。
休業特別支給金で賃金の20%
休業補償給付とは別に「休業特別支給金」が支払われます。
支払いの条件は休業補償給付と一緒です。4日目以降の休業に対して、給付基礎日額の20%が支払われます。
つまり、休業補償給付と合わせると、給付基礎日額の80%を受け取ることができます。
労災で休業しても賞与分は支払われない
賞与は労災保険の休業補償としては支払われません。会社に労災発生の責任がある場合には、会社に賞与減額分を請求することになります。
労災の骨折で会社に請求できる休業補償の金額
 休業補償給付と休業特別支給金を合わせても、休業分の給料を全額埋めることはできません。
休業補償給付と休業特別支給金を合わせても、休業分の給料を全額埋めることはできません。
この場合、会社が労災について損害賠償責任を負っている場合には、休業補償の不足額を会社に対して請求することができます。
会社に休業補償の不足額を請求する際、労災保険から受け取った休業補償給付を差し引く必要はありますが、休業特別支給金を差し引く必要はありません。
というのは、休業補償給付の支給目的が、「労災で休業した分の賃金を補償すること」であるのに対し、休業特別支給金の支給目的は、「労災で休業分した分の賃金を補償すること」というよりも、「被災者の生活を支えるための福祉」という位置づけなので、休業特別支給金については二重取りが認められているからです。
労災の骨折で請求できる休業補償以外の損害
治療費と療養補償給付
治療関係費は、労災保険から療養補償給付として支払われます。
労災保険から支払いがない治療関係費については、会社が労災の発生について損害賠償責任を負う場合には、会社に対して請求することができます。
慰謝料
慰謝料は労災保険からは支払われません。
会社が労災の発生について損害賠償責任を負う場合には、会社に対して請求することができます。
労災で骨折した場合の慰謝料について詳しく知りたい方は、「労災で骨折!見舞金はいくらもらえる?慰謝料や後遺症は?」をご覧ください。
障害補償給付と後遺障害逸失利益
労災で骨折して後遺症が残った場合、主治医に診断書を作成してもらって労基署に提出し、労基署が後遺障害等級を認定すれば、後遺障害に対する補償として障害補償給付が支払われます。
後遺障害逸失利益とは、労災で後遺障害を負わなければ得られた将来の所得に対する補償のことで、後遺障害等級に応じて計算しますので、障害補償給付と同じ趣旨のお金になりますが、こちらは会社が労災の発生について損害賠償責任を負う場合に限り、会社に対して請求することができます。
労災で後遺障害等級を獲得した場合にもらえる金額について詳しく知りたい方は、「労災の後遺障害等級の金額は?障害補償給付を等級表でわかりやすく!」をご覧ください。
労災で骨折した場合の休業補償期間に関するよくある質問
労災で骨折して退職した後でも休業補償は支払われますか
労災で骨折が治ることのないまま退職したとしても、休業補償給付は支払われ続けます。労災保険の適用は退職後も続くからです。完治もしくは症状固定などの区切りのタイミングで給付が終了します。
労災で骨折して有給を取得した場合に休業補償は支払われますか
有給休暇を取得している日は、会社から給料が出ているため、休業補償給付の対象外となります。有給休暇終了後に支給が開始します。
労災で骨折した場合に土日は休業補償の期間の対象ですか
休業補償給付は、治療のために休業して賃金の支払いを受けていない期間すべてが支払いの対象となります。
よって、土日祝日など、会社の定められた休日も支払いの対象になります。
労災で骨折した場合の休業補償期間に関するまとめ
労災で骨折した際の休業補償の期間について説明しました。仕事中や通勤中に骨折した場合、労災保険から補償があります。骨折で休業した分の給料は、「休業補償給付」として支払われます。
金額は、4日目以降の休業を対象に、「1日の賃金(給付基礎日額)の60%」です。労災保険とは別で、国から休業特別支給金が、「給付基礎日額の20%」支払われます。つまり、休業した際に受け取れるのは、「休業4日目以降の給料の80%」になります。
休業補償給付が支払われるのは、基本的に骨折が完治し、仕事に復帰できるまでです。骨折が完治せず、症状が残ってしまった場合には、「症状固定」をするか「傷病補償年金」に移行するタイミングで打ち切りになります。
被害者が負った損害の中で、「労災保険では金額が足りないもの」や「そもそも労災保険から支払いがないもの」に関しては、会社に対して損害賠償請求を求めることもできます。
損害賠償金については、骨折が重度で後遺障害が残るケースなどでは、金額が数千万円以上になることもよくあります。大事なことなので、自己判断せず、必ず労災に強い弁護士に相談するようにしましょう。
法律事務所リンクスでは、労災に強い弁護士が無料相談を受け付けています。わかりやすく説明いたしますので、是非ともご利用ください。
労災被害にあったら労災に強い弁護士に無料相談・電話相談を!
 これまでご説明してきたとおり、労災は労基署と会社という2つの組織を相手にしなければならない上に、手続きも複雑であるため、労災で怪我をした本人やそのご家族だけで進めていくことには限界があります。
これまでご説明してきたとおり、労災は労基署と会社という2つの組織を相手にしなければならない上に、手続きも複雑であるため、労災で怪我をした本人やそのご家族だけで進めていくことには限界があります。
法律事務所リンクスの労災に強い弁護士の無料相談・電話相談では、手続きの進め方や後遺障害等級、慰謝料の見込みについて丁寧にご説明させて頂いております。
法律事務所リンクスでは着手金を0円とさせて頂いており、ご依頼頂ける場合にも経済的負担を心配される必要はございません。
まずはお気軽に法律事務所リンクスの無料相談・電話相談をご利用ください。
このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
全国の労働災害の被害者の救済のため無料電話相談に取り組む。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2015年に法律事務所リンクスを設立し、2016年に弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)として法人化。現在、東京と京都にオフィスがある。