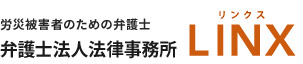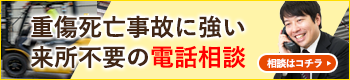労災の後遺障害等級の金額は?障害補償給付を等級表でわかりやすく!

労災の後遺障害等級は一発勝負!
適切な等級と正しい金額を知るため弁護士に相談を!!
労災の後遺障害等級の金額は、後遺障害によって労働能力が制限されることに対する補償である障害補償給付と後遺障害によって介護が必要となったことに対する補償である介護補償給付があります。このうち障害補償給付の金額は次のとおりです。
| 等級 | 障害補償給付 (給付基礎日額) |
障害特別年金・一時金 (算定基礎日額) |
障害特別支給金 |
|---|---|---|---|
| 1級 | 年313日分(年金) | 年313日分(年金) | 342万円 |
| 2級 | 年277日分(年金) | 年277日分(年金) | 320万円 |
| 3級 | 年245日分(年金) | 年245日分(年金) | 300万円 |
| 4級 | 年213日分(年金) | 年213日分(年金) | 264万円 |
| 5級 | 年184日分(年金) | 年184日分(年金) | 225万円 |
| 6級 | 年156日分(年金) | 年156日分(年金) | 192万円 |
| 7級 | 年131日分(年金) | 年131日分(年金) | 159万円 |
| 8級 | 503日分(一時金) | 503日分(一時金) | 65万円 |
| 9級 | 391日分(一時金) | 391日分(一時金) | 50万円 |
| 10級 | 302日分(一時金) | 302日分(一時金) | 39万円 |
| 11級 | 223日分(一時金) | 223日分(一時金) | 29万円 |
| 12級 | 156日分(一時金) | 156日分(一時金) | 20万円 |
| 13級 | 101日分(一時金) | 101日分(一時金) | 14万円 |
| 14級 | 56日分(一時金) | 56日分(一時金) | 8万円 |
また後遺障害1級または2級となり、介護が必要な後遺障害等級であると認定された場合の介護補償給付の金額は次のとおりです。
| 等級 | 最高額 | 最低額 |
| 後遺障害1級 | 171650円 | 73090円 |
| 後遺障害2級 | 85780円 | 36500円 |
その上、労災の発生について会社に責任がある場合には、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益(障害補償給付同様に後遺障害で労働能力が制限されたことへの損害賠償)、将来介護費(介護補償給付同様に介護が必要となったことへの損害賠償)を請求することもできます。こちらも、後遺障害等級によって金額が変わります。
このページでは、法律事務所リンクスの労災に強い弁護士が「労災の後遺障害等級とは」「労災で後遺障害等級に見合う金額をもらうためのポイント」「労災保険の後遺障害等級表と障害補償給付の金額」「介護補償給付の金額」「労災で会社に請求できる後遺障害慰謝料・逸失利益・将来介護費」などについて説明します。
電話での依頼で解決される方多数!お気軽にご相談ください!
- お電話で
無料相談【全国対応】 - 0120-917-740
受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)
労災の後遺障害等級とは
労災の後遺障害等級は、労災で負った怪我について治療をしても回復が見込めない状態(症状固定)になった場合に、その時点で残っている症状の内容及び程度に応じて、労働基準監督署(労基署)によって認定されます。
具体的には、労災被害者(被災者)が、主治医に診断書を作成してもらい、労基署に障害補償給付等の支給申請書とともに提出し、労基署が調査した上で、認定されます。
労基署は、労災保険の後遺障害等級表及び後遺障害等級認定基準に則って、後遺障害等級を認定します。
適切な後遺障害等級認定を受けて十分な金額を受け取るには、主治医に正しい後遺障害診断書を作成してもらう必要がありますが、医師は怪我を治すことに関心はあるものの、怪我が残ったことを証明する診断書の作成にはさほど関心がないため、後遺障害認定率が高い診断書を作成してくれるとは限りません。
労災に強い弁護士の無料相談を利用することで、適切な後遺障害等級を獲得し、十分な金額を受け取る可能性が高まるので、是非無料相談をご利用ください。
労災被害者のための無料電話相談実施中
 法律事務所リンクスの無料電話相談では、労災に強い弁護士が、労災で怪我をしてお困りの被害者のための電話での無料相談を実施しています。
法律事務所リンクスの無料電話相談では、労災に強い弁護士が、労災で怪我をしてお困りの被害者のための電話での無料相談を実施しています。
労災で大怪我をした場合、仕事に復帰できるのか、今後の生活はどうなるのか、後遺障害が残ったらどうすればよいのかといった不安が大きいこといます。
弁護士に依頼すれば、どのように対応すればよいかのアドバイスを受けたり、着手金0円で窓口を任せたりすることができますので、治療や仕事復帰に集中することが可能です。
労災で怪我をしてお困りの被害者の方は、0120-917-740にお電話を頂くか、LINEで労災の無料相談をお申し込みください。
労災で後遺障害等級に見合う金額をもらうためのポイント
労災で後遺障害等級に見合う金額をもらうためのポイントは次の3つです。
- できる限り早く労災に強い弁護士に相談する
- 労災の後遺障害等級認定のコツを把握する
- 労災の後遺障害等級ごとの金額の計算方法を理解する
①できる限り早く労災に強い弁護士に相談する
 労災で適切な後遺障害認定を受けるには、早い段階で労災に強い弁護士に相談しておくことが大事です。
労災で適切な後遺障害認定を受けるには、早い段階で労災に強い弁護士に相談しておくことが大事です。
労災に強い弁護士にあらかじめアドバイスを受けておくことで、適切な後遺障害等級を獲得するために必要な検査を受け、正しい後遺障害診断書を作成してもらえる可能性が高まります。
労基署の後遺障害認定の結果を覆せる可能性は20%以下とされていますので、「労災の後遺障害認定は基本的に一発勝負」と考え、労災に強い弁護士に依頼することが大切です。
また、会社と示談交渉して、十分な損害賠償金額を引き出すには、弁護士への依頼が不可欠です。
②労災の後遺障害等級認定基準を把握する
 労災で適切な後遺障害等級を獲得するにはそのためのコツを把握しておくことが大事です。
労災で適切な後遺障害等級を獲得するにはそのためのコツを把握しておくことが大事です。
労災にあったばかりの方やこれから後遺障害診断書を作成するという方は、「労災で後遺障害!後遺症認定率が高い診断書とは?申請の流れは?」を見て、労災で後遺障害を獲得するためのコツを勉強しておくことをお勧めします。
③労災の後遺障害等級ごとの金額の計算方法を理解する
 適切な後遺障害等級を獲得しても、何が正しい金額かが分からなければ、適正な補償を受けることができません。
適切な後遺障害等級を獲得しても、何が正しい金額かが分からなければ、適正な補償を受けることができません。
このページでは、後遺障害等級ごとの金額の計算方法をご説明しますので、是非ご覧ください。
労災保険の後遺障害等級表と障害補償給付の金額
労災保険は、後遺障害等級ごとに、後遺障害によって労働能力が制限されることに対する補償として、障害補償給付を支払います。
労災保険の後遺障害等級は、次の表の身体障害欄に記載された障害がある場合にこれに対応する等級が認定されるという仕組みになっています(参照:厚生労働省HP「障害等級表」)。
後遺障害1級~7級の場合、労災保険から「障害補償年金」「障害特別年金」「障害特別支給金」が支払われます。
具体的には、下記の表のとおりで、「障害補償年金」は「給付基礎日額」の何日分の年金、「障害特別年金」は「算定基礎日額」の何日分の年金、「障害特別支給金」は一定の金額が支払われます。
これに対し、後遺症が8級~14級の場合には、労災保険から「障害補償一時金」「障害特別一時金」「障害特別支給金」が支払われます。
具体的には、下記の表のとおりで、「障害補償一時金」は「給付基礎日額」の何日分の一時金、「障害特別一時金」は「算定基礎日額」の何日分の一時金、「障害特別支給金」は一定の金額が支払われます。
「給付基礎日額」とは給料の1日分、「算定基礎日額」とは賞与の1日分ですが、詳しい計算方法は次の項目で説明します。
| 障害 等級 |
身体障害 | 障害(補償)年金・一時金 | 障害特別年金・一時金 | 障害特別 支給金 |
|---|---|---|---|---|
| 1級 |
|
給付基礎日額313日分 | 算定基礎日額313日分 | 342万円 |
| 2級 |
|
同277日分 | 同277日分 | 320万円 |
| 3級 |
|
同245日分 | 同245日分 | 300万円 |
| 4級 |
|
同213日分 | 同213日分 | 264万円 |
| 5級 |
|
同184日分 | 同184日分 | 225万円 |
| 6級 |
|
同156日分 | 同156日分 | 192万円 |
| 7級 |
|
同131日分 | 同131日分 | 159万円 |
| 8級 |
|
給付基礎日額503日分 | 給付基礎日額503日分 | 65万円 |
| 9級 |
|
同391日分 | 同391日分 | 50万円 |
| 10級 |
|
同302日分 | 同302日分 | 39万円 |
| 11級 |
|
同223日分 | 同223日分 | 29万円 |
| 12級 |
|
同156日分 | 同156日分 | 20万円 |
| 13級 |
|
同101日分 | 同101日分 | 14万円 |
| 14級 |
|
同56日分 | 同56日分 | 8万円 |
- 1. 視力の測定は、万国式視力表による。屈折異常のあるものについてはきよう正視力について測定する。
- 2. 手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
- 3. 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
- 4. 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
- 5. 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。後遺障害1~7級に認定された場合は年金の形で毎年支払いが行われます。
障害補償給付はいくら?いつまでもらえる?申請方法や流れは?
障害補償給付はいくら?障害特別年金・一時金は?
 障害補償給付は給付基礎日額の何日分の年金または一時金として支払われます。
障害補償給付は給付基礎日額の何日分の年金または一時金として支払われます。
例えば、月給30万円、直近3カ月が90日の場合の給付基礎日額は、30万円×3ヶ月÷90日=1万円となります。
障害特別年金・一時金は算定基礎額の何日分の年金または一時金として支払われます。
算定基礎日額とは「1年でもらった賞与を365で割ったもの」になります。
例えば、年間73万円のボーナスがあった場合の算定基礎日額は、73万円÷365日=2,000円となります。
では、給付基礎日額1万円、算定基礎日額2000円の場合に、後遺障害等級ごとの障害補償給付の金額表を基に、後遺障害7級の場合と12級の場合にどうなるかを計算してみましょう。
| 等級 | 障害補償給付 (給付基礎日額) |
障害特別年金・一時金 (算定基礎日額) |
障害特別支給金 |
|---|---|---|---|
| 1級 | 年313日分(年金) | 年313日分(年金) | 342万円 |
| 2級 | 年277日分(年金) | 年277日分(年金) | 320万円 |
| 3級 | 年245日分(年金) | 年245日分(年金) | 300万円 |
| 4級 | 年213日分(年金) | 年213日分(年金) | 264万円 |
| 5級 | 年184日分(年金) | 年184日分(年金) | 225万円 |
| 6級 | 年156日分(年金) | 年156日分(年金) | 192万円 |
| 7級 | 年131日分(年金) | 年131日分(年金) | 159万円 |
| 8級 | 503日分(一時金) | 503日分(一時金) | 65万円 |
| 9級 | 391日分(一時金) | 391日分(一時金) | 50万円 |
| 10級 | 302日分(一時金) | 302日分(一時金) | 39万円 |
| 11級 | 223日分(一時金) | 223日分(一時金) | 29万円 |
| 12級 | 156日分(一時金) | 156日分(一時金) | 20万円 |
| 13級 | 101日分(一時金) | 101日分(一時金) | 14万円 |
| 14級 | 56日分(一時金) | 56日分(一時金) | 8万円 |
後遺障害7級の場合、障害補償年金は給付基礎日額1万円の131日分なので年131万円、障害特別年金は算定基礎日額2000円の131日分なので年26万2000円、障害特別支給金として159万円が支給されます。障害特別支給金は1回限りですが、障害補償年金・障害特別年金は毎年支払われます。
これに対し、後遺障害12級の場合、障害補償一時金は給付基礎日額1万円の156日分の156万円、障害特別一時金は算定基礎日額2000円の156日分の31万2000円、障害特別支給金として20万円が支給されますが、すべて1回限りとなります。
障害補償年金はいつまでもらえる?
障害補償年金は原則として一生もらうことができます。
障害補償年金の申請方法や流れは?
障害補償年金の申請方法や流れについては、「労災で後遺障害!後遺症認定率が高い診断書とは?申請の流れは?」をご覧ください。
労災保険の後遺障害等級ごとの介護補償給付の金額
後遺障害で介護が必要となり、後遺障害1級または2級に認定された場合には、介護補償給付が給付されます。
介護補償給付の対象となる後遺障害の症状は次のとおりです。
| 等級 | 該当する症状 |
| 後遺障害1級 | ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ・両眼を失明する など |
| 後遺障害2級 | ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ・後遺障害第1級に該当するが、常時介護が必要なわけではない など |
常に介護が必要かそうでないかや現状誰が介護をしているかなどによって支給される金額が変わります。
支払いは毎月ありますが、以下が金額の目安になります。
| 最高額 | 最低額 | |
| 常時介護を要する者 | 171,650円 | 73,090円 |
| 随時介護を要する者 | 85,780円 | 36,500円 |
労災で会社に請求できる後遺障害慰謝料・逸失利益・将来介護費
 労災が発生したことについて会社に「安全配慮義務違反」や「使用者責任」などの法的責任がある場合、労災被害者(被災者)は会社に損害賠償請求することができます。
労災が発生したことについて会社に「安全配慮義務違反」や「使用者責任」などの法的責任がある場合、労災被害者(被災者)は会社に損害賠償請求することができます。
労災保険から後遺障害等級ごとにもらえる金額には慰謝料は含まれていないので、会社が労災に対して責任を負っている場合には、慰謝料を請求することができます。
また、労災保険の障害補償給付は後遺障害によって労働能力が制限されることに対する補償ですが、障害補償給付がその全額を埋めるのに不足している場合には、労災に責任を負っている会社に対して、後遺障害逸失利益を請求することができます。
同様に、労災保険の介護補償給付は、後遺障害によって介護が必要となったことに対する補償ですが、介護補償給付がその全額を埋めるのに不足している場合には、労災に責任を負っている会社に対して、将来介護費を請求することができます。
次に、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益、将来介護費の計算方法について、簡単にご説明します。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級ごとの相場は次のとおりです。
| 後遺障害等級 | 金額 |
|---|---|
| 1級 | 2800万円 |
| 2級 | 2370万円 |
| 3級 | 1990万円 |
| 4級 | 1670万円 |
| 5級 | 1400万円 |
| 6級 | 1180万円 |
| 7級 | 1000万円 |
| 8級 | 830万円 |
| 9級 | 690万円 |
| 10級 | 550万円 |
| 11級 | 420万円 |
| 12級 | 290万円 |
| 13級 | 180万円 |
| 14級 | 110万円 |
後遺障害逸失利益
 後遺障害逸失利益とは、労災による後遺障害がなければ将来労働によって得られたであろう所得のことをいいます。
後遺障害逸失利益とは、労災による後遺障害がなければ将来労働によって得られたであろう所得のことをいいます。
その計算式は次のとおりです。
基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
基礎収入とは労災の発生前に支払を受けていた年収です。
労働能力喪失率とは後遺障害等級ごとに定められた「その後遺障害等級に応じて失われる労働能力の割合」です。
労働能力喪失期間とは労働能力の制限が続く年数のことで、後遺障害逸失利益を計算するにあたってはライプニッツ係数を乗じます。
多くの場合、67歳まで働けるものとして逸失利益を計算します。
各等級ごとの労働能力喪失率は、下記の表をご覧ください。
| 後遺障害の等級 | 労働能力喪失率 |
| 1級 | 100% |
| 2級 | 100% |
| 3級 | 100% |
| 4級 | 92% |
| 5級 | 79% |
| 6級 | 67% |
| 7級 | 56% |
| 8級 | 45% |
| 9級 | 35% |
| 10級 | 27% |
| 11級 | 20% |
| 12級 | 14% |
| 13級 | 9% |
| 14級 | 5% |
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数とは、労働能力喪失期間の年数から「中間利息」を控除した係数のことです。
本来、逸失利益は「被害者が労働をすることで得るはずだった収入」を補償するものですから、事故がなければ、毎月の給料日などで少しづつ得ていくはずだったものです。
ですが、逸失利益は一括で支払われます。例えば逸失利益の金額が4500万円だったとしましょう。
- 毎年150万円ずつ30年かけて受け取る
- 一括で4500万円を受け取る
上記を比較すると、定期預金などに預けた際の利息は、後者の方が多くなりますので、一括で受け取る方が得になります。
これを損得の内容に調整するのに必要な係数がライプニッツ係数で次の表のとおりです。
2020年4月1日以降に発生した労災事故のライプニッツ係数表(3%)
| 期間 | ライプニッツ係数 | 期間 | ライプニッツ係数 |
| 1年 | 0.9709 | 35年 | 21.4872 |
| 2年 | 1.9135 | 36年 | 21.8323 |
| 3年 | 2.8262 | 37年 | 22.1672 |
| 4年 | 3.7171 | 38年 | 22.4925 |
| 5年 | 4.5797 | 39年 | 22.8082 |
| 6年 | 5.4172 | 40年 | 23.1148 |
| 7年 | 6.2303 | 41年 | 23.4124 |
| 8年 | 7.0197 | 42年 | 23.7014 |
| 9年 | 7.7861 | 43年 | 23.9819 |
| 10年 | 8.5302 | 44年 | 24.2543 |
| 11年 | 9.2526 | 45年 | 24.5187 |
| 12年 | 9.9540 | 46年 | 24.7754 |
| 13年 | 10.6350 | 47年 | 25.0247 |
| 14年 | 11.2961 | 48年 | 25.2667 |
| 15年 | 11.9379 | 49年 | 25.5017 |
| 16年 | 12.5611 | 50年 | 25.7298 |
| 17年 | 13.1661 | 51年 | 25.9512 |
| 18年 | 13.7535 | 52年 | 26.1662 |
| 19年 | 14.3238 | 53年 | 26.3750 |
| 20年 | 14.8775 | 54年 | 26.5777 |
| 21年 | 15.4150 | 55年 | 26.7744 |
| 22年 | 15.9369 | 56年 | 26.9655 |
| 23年 | 16.4436 | 57年 | 27.1509 |
| 24年 | 16.9355 | 58年 | 27.3310 |
| 25年 | 17.4131 | 59年 | 27.5058 |
| 26年 | 17.8768 | 60年 | 27.6756 |
| 27年 | 18.3270 | 61年 | 27.8404 |
| 28年 | 18.7641 | 62年 | 28.0003 |
| 29年 | 19.1885 | 63年 | 28.1557 |
| 30年 | 19.6004 | 64年 | 28.3065 |
| 31年 | 20.0004 | 65年 | 28.4529 |
| 32年 | 20.3888 | 66年 | 28.5950 |
| 33年 | 20.7658 | 67年 | 28.7330 |
| 34年 | 21.1318 | 68年 | 28.8670 |
例えば、「年収500万円、後遺障害11級、年齢40歳」で逸失利益を計算してみますと、次のとおりです。
年収500万円×労働能力喪失率20%×18.327(27年のライプニッツ係数)=約1832万円
なお、労災保険から障害補償給付を受け取っている場合には、会社が支払うべき後遺障害逸失利益は、障害補償給付として支払われた金額(障害特別年金、障害特別一時金、障害特別支給金以外の金額)との差額ということになります。
将来介護費
 職業付添人による介護を受ける場合には実費全額、家族や親族などの介護を受ける場合には1日につき8000円とされていますが、具体的看護の状況により増減することになります。
職業付添人による介護を受ける場合には実費全額、家族や親族などの介護を受ける場合には1日につき8000円とされていますが、具体的看護の状況により増減することになります。
例えば、年齢40歳の男性が日額8000円の介護を受けるようになった場合、平均余命である82歳までの42年間の将来介護費を計算すると、次のようになります。
8000円×365日×23.7014(42年間のライプニッツ係数)=約6736万円
労災の後遺障害等級の金額に関するよくある質問
後遺障害の金額に関するよくある質問を紹介します。
労災の後遺障害14級・12級でもらえる金額は?
後遺障害14級・12級に認定された際、労災保険からもらえる金額は以下の通りです。
| 等級 | 金額と内訳 |
| 14級 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の56日分(一度だけ)
・障害特別一時金:算定基礎日額の56日分(一度だけ) ・障害特別支給金:8万円 |
| 12級 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の156日分(一度だけ)
・障害特別一時金:算定基礎日額の156日分(一度だけ) ・障害特別支給金:20万円 |
ごく簡単に説明しますと、給付基礎日額1日分とは「労災発生前にもらっていた1日あたりの給料」、算定基礎日額1日分とは「1年間でもらえるボーナスを365等分したもの」と考えましょう。
例えば月給30万円の人の給付基礎日額は1日1万円、ボーナスが年間73万円の人の算定基礎日額1日分は2000円になります。
労災でしびれが残ったら後遺障害認定される?
労災で後遺障害が残った場合、後遺障害の14級や12級などに認定される可能性があります。具体的には以下をご覧ください。
第14級9号…局部に神経症状を残すもの
第12級12号…局部にがん固な神経症状を残すもの
症状が重く、日常生活や労働に影響を及ぼすようであれば、さらに重い等級に認定される可能性もあります。
労災の後遺障害一時金がもらえるのはいつ?
労災で後遺障害認定されたあと、一時金がもらえるまでには、数週間~1カ月程度かかります。
具体的には、後遺障害認定を受けたあと、労災保険の給付請求書を提出してから、数週間~1カ月程度です。
後遺障害の審査そのものは、別で1~3ヶ月程度かかります。
労災の後遺障害等級の金額に関するまとめ
労災で後遺障害認定されると、労災保険から支払いがあります。内訳は主に「障害補償給付」「介護補償給付」「特別支給金」などです。金額は、認定された後遺障害の等級や、労災発生前の収入によって決まります。
労災保険だけではまかないきれない「逸失利益」や、労災保険から支払いがない「慰謝料」については会社や、労災の加害者に対して請求を行います。
後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益は、合わせると数百万円~数千万円にも上ることがあります。
何にせよ、これらのお金は、後遺障害に認定されないことには受け取れません。労災による損害を適切に埋めるためにも、確実に後遺障害認定を受けましょう。
適切な等級で後遺障害認定を受けるためには、労災に強い弁護士に相談することが大切です。
法律事務所リンクスでは、労災に強い弁護士が無料電話相談を受け付けています、分かりやすく説明いたしますので、お気軽にご相談ください。
労災被害にあったら労災に強い弁護士に無料相談・電話相談を!
 これまでご説明してきたとおり、労災は労基署と会社という2つの組織を相手にしなければならない上に、手続きも複雑であるため、労災で怪我をした本人やそのご家族だけで進めていくことには限界があります。
これまでご説明してきたとおり、労災は労基署と会社という2つの組織を相手にしなければならない上に、手続きも複雑であるため、労災で怪我をした本人やそのご家族だけで進めていくことには限界があります。
法律事務所リンクスの労災に強い弁護士の無料相談・電話相談では、手続きの進め方や後遺障害等級、慰謝料の見込みについて丁寧にご説明させて頂いております。
法律事務所リンクスでは着手金を0円とさせて頂いており、ご依頼頂ける場合にも経済的負担を心配される必要はございません。
まずはお気軽に法律事務所リンクスの無料相談・電話相談をご利用ください。
このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
全国の労働災害の被害者の救済のため無料電話相談に取り組む。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2015年に法律事務所リンクスを設立し、2016年に弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)として法人化。現在、東京と京都にオフィスがある。