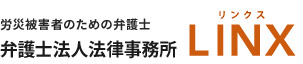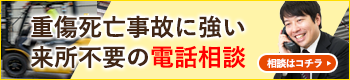労災の休業補償期間は?打ち切りは?いつまで休めるもらえる?

労災の休業補償は打ち切りになる前の対応が大事!
適正な賠償金の支払いを受けるため弁護士に相談を!
労災の休業補償期間は、労基署が労災で休業が必要なため休業補償を支給すると決定した期間のことです。休業補償の支給開始日は休業4日目で、支給終了日は労基署が休業補償の支給が必要なくなったとして休業補償の打ち切りをした日であり、最も遅くても完治または症状固定(症状の改善が見込めないと診断された時)した日に休業補償の支給は終了するのが原則です。
休業補償をいつまでもらえるかは労基署が休業補償の打ち切りをした日までですが、仕事をいつまで休めるかは労基署が休業補償の打ち切りをしたとしても仕事に復帰できない場合には休めます。
労基署が休業補償の打ち切りをした場合、労基署に審査請求という不服申立ての手続きをしたり、会社に労災事故について責任がある場合には休業損害を請求することが考えられますが、労基署は休業補償の打ち切りをする際に、主治医に復職可能かどうかについて医療照会をすることが通常なので、その判断を覆すことは容易ではありません。
休業の必要がある場合には、労基署に休業補償の打ち切りをさせないよう、日頃から主治医に仕事の内容や休業の必要性について説明しておき、主治医が労基署の医療照会に復職可能と回答するという事態が生じないようにしておくことが大事です。
このページでは、労災保険による休業補償給付の期間について、「いつから支給されていつまで続くのか」をわかりやすく解説します。また、仕事を休業できる期間(解雇されずに休める期間)や、休業補償が打ち切られるケース、注意点についても詳しく説明します。最後に、労災対応でお困りのときに弁護士に相談すべきケースも紹介します。
老成で骨折した場合の休業補償期間については、「労災で骨折したら休業補償期間はいつまで?リハビリ自宅療養に医師の証明は?」をご覧ください。
電話での依頼で解決される方多数!お気軽にご相談ください!
- お電話で
無料相談【全国対応】 - 0120-917-740
受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)
そもそも労災の休業補償給付とは?
休業(補償)給付の目的と種類
 休業(補償)給付は、労働者が仕事中や通勤中の出来事が原因でケガや病気を負い、働くことができなくなったために得られなくなった収入を補てんし、安心して療養に専念できるようにするための公的な保険給付制度です 。
休業(補償)給付は、労働者が仕事中や通勤中の出来事が原因でケガや病気を負い、働くことができなくなったために得られなくなった収入を補てんし、安心して療養に専念できるようにするための公的な保険給付制度です 。
この給付には、原因によって2つの名称があります 。
- 休業補償給付:業務災害(仕事が原因のケガ・病気)の場合
- 休業給付:通勤災害(通勤途中のケガ・病気)の場合
名称は異なりますが、待期期間中の会社の補償義務の有無などを除き、給付の内容や金額の計算方法は基本的に同じです 。
支給される金額の計算方法(給与の約8割が補償)
 休業(補償)給付として支給される金額は、被災前の賃金の約8割に相当します。これは、2種類の給付の合計額です 。
休業(補償)給付として支給される金額は、被災前の賃金の約8割に相当します。これは、2種類の給付の合計額です 。
- 休業(補償)給付:給付基礎日額の60%
- 休業特別支給金:給付基礎日額の20%
これらを合計して、給付基礎日額の80%が、休業1日あたりの補償額となります。
ここでいう「給付基礎日額」とは、原則として、労災事故が発生した日(または病気の診断が確定した日)の直前3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った1日あたりの平均賃金額のことです 。
休業補償給付の支給条件
労災で仕事を4日以上休業すると、条件を満たす限りその休業期間中の所得の一部が労災保険から支給されます。
休業補償給付の支給条件は次の4つです。
- 業務または通勤が原因のケガ・病気であること
- 療養のため労働できないこと
- 休業中に賃金をもらっていないこと
- 休業日数が4日以上であること
これらを満たす場合に、休業4日目以降について休業補償給付を受け取ることができます(最初の3日間は「待期期間」といって労災保険からの給付対象外となりますが、業務上災害の場合その最初の3日分は会社から平均賃金の60%が補償されます)。
例えば給付基礎日額が1万円の人が10日間休業した場合、労災保険から支払われるのは4日目以降の7日分の補償で、休業(補償)給付として60%の金額=4万2000円と休業特別支給金として20%の金額=1万4000円が支給されることになります。
労災の休業補償給付等の申請の手続きの流れ
 労災事故に遭った際は、以下のような流れで手続きを進めます。まず事故発生直後は迅速に会社へ報告し、労災指定医療機関で治療を開始しましょう。
労災事故に遭った際は、以下のような流れで手続きを進めます。まず事故発生直後は迅速に会社へ報告し、労災指定医療機関で治療を開始しましょう。
-
労災事故の発生を会社に報告 – 事故や発症状況を勤務先に伝えます。
-
指定病院で治療開始 – 窓口で「労災保険を使いたい」と伝え、必要な診断書等をもらいます。
-
会社が労災申請の書類作成・提出 – 休業補償給付等の請求書類を会社経由で労基署に提出します(会社が非協力的な場合は被災労働者自身でも提出可能です)。
-
休業補償給付の支給決定 – 労働基準監督署による労災認定・審査のうえ、条件を満たせば治療費や休業補償給付が支給されます(初回の支給までに時間がかかることもあります)。
-
治療の継続・終了(症状固定) – ケガ・病気が完治するまで治療を続けます。症状が完治しなくても、一定期間治療してこれ以上良くならない状態を「症状固定」といいます。症状固定と判断された時点で治療は一区切りとなります。
-
後遺障害等級の認定 – 症状固定後も後遺症が残る場合は後遺障害等級認定の申請を行い、認定されれば障害補償給付や傷病補償年金など追加の給付を受ける手続きを進めます。
-
会社に対する損害賠償請求・示談交渉 – 労災の発生につき会社に過失(安全配慮義務違反など)がある場合、労災保険からの給付とは別に会社に慰謝料や逸失利益の賠償を求めることができます。まずは示談交渉で解決を図りますが、話し合いがまとまらなければ訴訟(裁判)に移行します。
※上記手続き全般について、自分で進めるのが難しい場合や会社の協力が得られない場合には、労災に強い弁護士に相談してサポートを受けることをおすすめします。では次に、本題である「休業補償はいつまで支給されるのか」「治療のため仕事をいつまで休めるのか」を詳しく見ていきましょう。
労災の休業補償給付はいつまでもらえる?
休業補償給付は休業4日目から支給開始
 労災による休業補償給付は、休業を開始した日から数えて4日目(通算で3日間の待期期間の後)から支給されます。労災で休んだ初日~3日目までは労災保険から給付が出ませんので注意しましょう(業務上の災害であればその期間の補償は会社負担です)。例えば金曜日に事故が起きて休業に入った場合、金土日が待期期間、翌月曜が4日目として労災保険からの休業補償支給対象日となります。
労災による休業補償給付は、休業を開始した日から数えて4日目(通算で3日間の待期期間の後)から支給されます。労災で休んだ初日~3日目までは労災保険から給付が出ませんので注意しましょう(業務上の災害であればその期間の補償は会社負担です)。例えば金曜日に事故が起きて休業に入った場合、金土日が待期期間、翌月曜が4日目として労災保険からの休業補償支給対象日となります。
なお、休業中の土日・祝日など所定休日も、本人が療養のため労働できず賃金を受けていなければ休業補償給付の支給対象に含まれます。会社の公休日であっても休業補償は支払われますので、「週末を挟むと補償が止まるのでは?」と心配する必要はありません。ただし有給休暇を消化した日や、休業中に一部出勤して賃金が発生した日については対象外となります(後述するように、部分的に出勤したからといって休業補償自体が打ち切られるわけではありません。その日数分を除いて引き続き補償は受けられます)。
休業補償給付はいつまで支給される?(打ち切りとなるケース)
 労災の休業補償給付に明確な支給期間の上限はなく、基本的には先述の支給条件を満たす限り支給が続きますが、労基署が、療養のため労働できない状態ではないと判断した場合には、休業補償給付は打ち切りになります。
労災の休業補償給付に明確な支給期間の上限はなく、基本的には先述の支給条件を満たす限り支給が続きますが、労基署が、療養のため労働できない状態ではないと判断した場合には、休業補償給付は打ち切りになります。
それ以外にも、次のような場合には、休業補償給付が打ち切りとなります。
-
ケガや病気が治ゆ(完治)した場合 – 医師により「治ゆ」(治癒)の診断がなされ復職可能となったら、その時点で休業補償給付は終了します。完治して仕事に復帰できるようになれば、もはや休業ではないため補償は打ち切られます。当然ですが、仕事に復帰して賃金を受け取るようになれば休業補償は受給できません。
-
症状固定と判断された場合 – 症状が残っていて完治していなくても、一定期間治療を続けてもそれ以上の改善が見込めなくなった状態を「症状固定」といいます(医師と本人が相談の上で決定します)。症状固定と医師に判断された時点で、医学的には治療の必要がない「治ゆ」と同視されるため、その日以降の休業補償給付は打ち切られます。※症状固定後の治療費についての労災給付(療養補償給付)も同様に打ち切りです。その後は後遺障害が残った場合に障害補償給付(一時金または年金)を受給する手続きを検討する流れになります。
-
休業開始から1年6ヶ月経過し重い障害が残っている場合 – 療養開始後1年6ヶ月(=18ヶ月)が経過しても傷病が治らず、かつその障害の程度が傷病等級第1級~第3級に該当すると労働基準監督署長に認定された場合、休業補償給付は「傷病(補償)年金」に切り替えられます。この切替えが行われると、それまで受け取っていた休業補償給付の支給は停止(打ち切り)となり、以後は定期的に年金形式の給付が支給されることになります。
休業補償期間中に一部出勤したらどうなる?
療養の途中で「体調が良い日だけ短時間出勤する」「リハビリ勤務を試みる」といったケースもあるでしょう。休業期間中に一時的に働いた場合、その出勤して賃金を得た日については休業補償給付の対象外となりますが、それを理由に休業補償給付自体が即座に打ち切られるわけではありません。 上記の支給条件③「賃金を受け取っていないこと」は、その日ごとに判断されます。したがって、休業中でも賃金の発生した日を除き、その他の休業日については引き続き休業補償給付を受給できます。例えば週に1度だけリハビリ出勤して給与をもらった場合、その週の残りの休業日については条件を満たす限り補償が支給され続けます。体調を見ながら段階的に復職を目指す場合でも、補償打ち切りを過度に心配せず治療に専念してください。
労災による休業はいつまで休める?
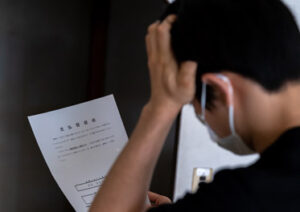 労災が原因で長期間仕事を休む場合、「会社をいつまで休職できるか」も重要なポイントです。労働基準法第19条により、業務上の災害で療養中の労働者については休業期間中およびその後30日間は原則として解雇が禁止されています。これは労災による治療に専念できるよう労働者を保護するための規定です。
労災が原因で長期間仕事を休む場合、「会社をいつまで休職できるか」も重要なポイントです。労働基準法第19条により、業務上の災害で療養中の労働者については休業期間中およびその後30日間は原則として解雇が禁止されています。これは労災による治療に専念できるよう労働者を保護するための規定です。
もっとも、解雇禁止には例外もあります。会社側が「打切補償」(平均賃金の1200日分の支払い)を行った場合などには、休業中であっても例外的に解雇が認められます(労基法19条ただし書き)。
打切補償は、療養開始後3年が経過しても傷病が治らない場合に会社が行うことができる制度で、この1200日分の補償を支払えば労基法上の解雇制限が解除され、会社は労働者を解雇できるようになります。
一方、通勤災害(通勤中のケガ等)で休業する場合には、上記の解雇制限規定は適用されません。休業期間の長短にかかわらず、会社は通常の労働者と同様の基準で解雇を判断できる立場にあります。ただし、だからといって「通勤災害で休んだから即解雇」などという乱暴な措置は許されません。労働契約法16条に定められた解雇権濫用法理により、「社会通念上相当でない解雇」は無効となるためです。通勤災害で長期休職する場合も、すぐに解雇される心配は基本的にいりませんが、休業期間が長期化すると徐々に解雇が有効と認められる蓋然性が高まってしまうのも事実です。通勤災害で療養が長引く際は、会社との十分なコミュニケーションを図り、復職の見通しなどについて誠実に説明するよう努めましょう。
労災の休業補償について弁護士に相談すべき場合
 労災による休業補償はあくまで減収分の一部を公的保険で補う制度であり、長期化すれば生活が苦しくなる場合もあります。また会社から解雇の圧力を受けたり、労災申請に非協力的だったりする不誠実な対応に悩まされるケースもあります。以下のような場合には、早めに労災に強い弁護士へ相談することをおすすめします。
労災による休業補償はあくまで減収分の一部を公的保険で補う制度であり、長期化すれば生活が苦しくなる場合もあります。また会社から解雇の圧力を受けたり、労災申請に非協力的だったりする不誠実な対応に悩まされるケースもあります。以下のような場合には、早めに労災に強い弁護士へ相談することをおすすめします。
労災を弁護士に依頼するメリットについて詳しくは、「労災を弁護士に依頼する5つのメリットとは?特に相談すべきケースは?」をご覧ください。
-
事故の原因について会社に落ち度(法的責任)がある場合: 労働災害が会社の安全配慮義務違反などによって発生した場合、労災保険の給付とは別に会社に対して損害賠償請求が可能です。例えば、本来設置すべき安全装置を怠ったために事故が起きた等、会社側に過失があるケースでは、労基署による休業補償や障害補償ではカバーしきれない慰謝料や後遺障害逸失利益の補填を求められます。会社に請求するには法律的な主張・立証が必要になるため、早期に弁護士に相談しておくと安心です。労災で骨折した場合の慰謝料について詳しく知りたい方は、「労災で骨折!見舞金はいくらもらえる?慰謝料や後遺症は?」をご覧ください。
-
負傷や後遺症の程度が重く損害額が大きい場合: ケガの治療期間が長期に及ぶ、手術や入院を繰り返した、後遺障害が残りそうだ…といった深刻なケースでは、その分労災保険給付だけでなく会社に請求できる慰謝料・賠償額も高額になる可能性があります。後遺障害等級が認定されるような場合、適切に手続きを踏めば数百万円~数千万円規模の賠償金を得られるケースもあります。将来にわたる収入減も含めた賠償を最大限確保するために、ぜひ専門の弁護士にご相談ください。労災で後遺障害等級を獲得した場合にもらえる金額について詳しく知りたい方は、「労災の後遺障害等級の金額は?障害補償給付を等級表でわかりやすく!」をご覧ください。
-
会社との手続きや交渉に不安がある場合: 労災申請の手続きが複雑で自分では対応しきれない、会社が労災隠し気味で協力してくれない、休業中の待遇や復職について会社とトラブルになっている――このような場合も弁護士が間に入ることで解決がスムーズになります。労働者側の立場で会社との交渉にあたってくれる弁護士に相談し、適切なアドバイスやサポートを受けましょう。
労災の休業補償期間に関するよくある質問【Q&A】
ここでは、休業補償の期間に関して、被災された方から特によく寄せられる質問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。
Q. 休業補償はいつから(何日目から)もらえますか?
A. 労災保険からの休業(補償)給付は、休業した日から数えて4日目から支給されます 。休業した初日から3日目までは「待期期間」と呼ばれ、労災保険からの給付対象にはなりません 。
ただし、この待期期間中の扱いが業務災害と通勤災害で異なります。
- 業務災害の場合:待期期間の3日間については、会社(事業主)が労働基準法に基づき、1日あたり平均賃金の60%を「休業補償」として支払う義務があります 。
- 通勤災害の場合:会社にこの支払義務はありません。したがって、最初の3日間は無給となるのが一般的です(有給休暇を使わない限り)。
Q. 土日や祝日、会社の公休日は期間に含まれますか?
A. はい、含まれます。 休業(補償)給付の支給要件は「療養のため労働できず、賃金を受けていない」ことであり、その日が会社の所定労働日であるか休日であるかは問いません 。したがって、医師の指示で休業している期間内であれば、土日祝日や会社の公休日であっても、その日数分を含めて休業(補償)給付が支払われます 。
Q. パートやアルバイトでも休業補償はもらえますか?
A. はい、全く問題なくもらえます。 労災保険は、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトといった雇用形態に関わらず、事業主と雇用関係にあるすべての「労働者」に適用されます 。支給される給付の内容や条件も、正社員と何ら変わりありません 。勤務日数や時間が短いパートの方でも、労災の要件を満たせば、休業4日目から休業(補償)給付を受け取ることができます。
Q. リハビリ出勤などで少し働くと、補償は打ち切られますか?
A. いいえ、直ちに打ち切られるわけではありません。 休業(補償)給付は日単位で判断されます。療養の途中で体調が良い日に短時間出勤するなど、部分的に働いて会社から賃金を受け取った日については、その日の分の休業(補償)給付は支給されません 。しかし、それ以外の休業した日については、引き続き要件を満たす限り給付を受けることができます 。段階的な職場復帰を目指す場合でも、補償が完全に打ち切られる心配を過度にする必要はありません。
Q. 会社を退職した場合、補償はもらえなくなりますか?
A. いいえ、引き続きもらえます。 労災保険の給付を受ける権利は、被災した労働者本人に属する権利であり、会社との雇用契約とは独立しています。したがって、労災の療養中に会社を自己都合で退職したり、解雇されたりした場合でも、支給要件を満たしている限り、休業(補償)給付は打ち切られることなく支給され続けます 。
Q. 申請を忘れていました。時効はありますか?
A. はい、あります。 休業(補償)給付を請求する権利には、2年間の消滅時効が定められています。この時効は、賃金を受けられなかった日(休業した日)ごとに進行し、その日の翌日から2年で完成します 。申請が遅れると、古い分から順に請求できなくなるため、注意が必要です 。
まとめ:労災の休業補償期間のポイント
 労災で仕事を休業する際に労基署から支給される休業補償は、休業4日目から支給開始し、被災労働者が療養のため労働できない間は支給され続けますが、労基署が療養のため労働できない状態ではなくなったと判断した場合には打ち切りになる可能性があります。
労災で仕事を休業する際に労基署から支給される休業補償は、休業4日目から支給開始し、被災労働者が療養のため労働できない間は支給され続けますが、労基署が療養のため労働できない状態ではなくなったと判断した場合には打ち切りになる可能性があります。
そのため、休業の必要がある場合には、労基署に休業補償の打ち切りをさせないよう、日頃から主治医に仕事の内容や休業の必要性について説明しておき、主治医が労基署の医療照会に復職可能と回答するという事態が生じないようにしておくことが大事です。
また、休業補償給付では休業による減収分の全額は賄えず(賃金の100%ではなく実質80%が補償)、長期の療養では経済的に厳しくなる可能性もあります。
必要に応じて会社に不足分の補償を求めることも検討できます。会社に事故の責任がある場合や、長期休業・重度障害で損害賠償額が大きくなりそうな場合には、早めに弁護士に相談してみてください。
労災の休業補償は被災労働者の生活を支える大切な制度ですが、制度の範囲で足りない部分は会社への請求やその他の制度で補填することも可能です。不安な点があれば一人で悩まず専門家に相談してみることをおすすめします。
労災被害にあったら労災に強い弁護士に無料相談・電話相談を!
 これまでご説明してきたとおり、労災は労基署と会社という2つの組織を相手にしなければならない上に、手続きも複雑であるため、労災で怪我をした本人やそのご家族だけで進めていくことには限界があります。
これまでご説明してきたとおり、労災は労基署と会社という2つの組織を相手にしなければならない上に、手続きも複雑であるため、労災で怪我をした本人やそのご家族だけで進めていくことには限界があります。
法律事務所リンクスの労災に強い弁護士の無料相談・電話相談では、手続きの進め方や後遺障害等級、慰謝料の見込みについて丁寧にご説明させて頂いております。
法律事務所リンクスでは着手金を0円とさせて頂いており、ご依頼頂ける場合にも経済的負担を心配される必要はございません。
まずはお気軽に法律事務所リンクスの無料相談・電話相談をご利用ください。
このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
全国の労働災害の被害者の救済のため無料電話相談に取り組む。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2015年に法律事務所リンクスを設立し、2016年に弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)として法人化。現在、東京と京都にオフィスがある。