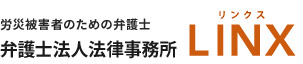労災で仕事中に死亡の金額は?保険金や遺族補償年金の計算方法は?

労災死亡事故は会社から被害者の落ち度を指摘されがち!
適正な賠償金の支払いを受けるため弁護士に相談を!
労災による死亡事故で亡くなられた場合、ご遺族が受け取れるお金には、労災保険から支給される遺族年金などの遺族補償給付と労災事故について会社に責任がある場合に支払われる損害賠償金があります。
労災保険から支払われる遺族補償給付は、遺族補償年金(一時金)、遺族特別年金(一時金)などがあり、労災でお亡くなりになられた方の死亡時の収入の金額とその収入によって生計を維持していた遺族の有無・数によって決まります。詳しくは後でご説明します。
労災死亡事故に責任がある会社から支払われる損害賠償金の相場は、死亡慰謝料2000万円~2800万円に加えて将来得ることができなくたった所得である逸失利益が数千万円です。
労災保険から支払われる遺族補償給付には死亡慰謝料が含まれていないので、労災が発生した責任が会社にある場合には、会社に死亡慰謝料を請求できることになります。
また、労災保険から支払われる遺族補償年金などは、将来得ることができなくたった所得である逸失利益の補償という位置づけですが、逸失利益の全額を埋めるのには足りないので、労災が発生した責任が会社にある場合には、会社に損害賠償請求をする必要があります。
このページでは、法律事務所リンクスの労災に強い弁護士が、遺族補償給付や損害賠償金を受け取る際のハードルを説明をした後で、制度の内容や金額についてご説明します。
労災事故で死亡した場合に支払われる金額
労災事故で死亡した場合に労災保険から支払われる金額
労災事故で死亡した場合に労災保険から支払われる金額には、
- 死亡時に生計を同じくしていた遺族がいる場合に支払われる遺族補償年金・遺族特別年金
- 遺族補償年金等の受給資格者がいない場合に支払われる遺族補償一時金・遺族特別一時金
- 遺族特別支給金
- 葬祭料
などがあり、労基署が労災死亡事故であると認めた場合に支払われます。
 死亡事故が労災認定されるには業務災害か通勤災害として認められる必要があります。
死亡事故が労災認定されるには業務災害か通勤災害として認められる必要があります。
特に業務災害として認められるには「業務遂行性」と「業務起因性」が必要ですが、例えば、会社側が、死人に口なしであることをいいことに、「会社が指示していない業務を遂行していて死亡したので、業務遂行性や業務起因性がなく労災ではない」と主張してくるかもしれません。
このような場合、労災であること自体が否定され、労災保険から遺族補償年金等が支払われなくなる可能性があるので、すぐに弁護士に相談する必要があります。
労災事故で死亡した場合に会社から支払われる金額
労災事故で死亡した場合に会社から支払われる主な金額には、
- 死亡慰謝料
- 死亡逸失利益
- 葬儀費用
などがあり、会社が労災事故に損害賠償責任を負う場合に支払われます。
 会社は損害賠償責任があることを認めなかったり、被害者の落ち度が大きいので労災保険から支払われた金額を超える損害賠償金を支払う必要はないなどと主張してくることがあります。
会社は損害賠償責任があることを認めなかったり、被害者の落ち度が大きいので労災保険から支払われた金額を超える損害賠償金を支払う必要はないなどと主張してくることがあります。
例えば、「マニュアルを整備し十分な指示をしていたのに、お亡くなりになったご家族が想定外の行動をして亡くなった」と主張してくるような場合です。
この場合、会社側は損害賠償金を支払おうとしませんので、弁護士を入れるなどして責任を認めさせる必要があります。
また、被害者にも大きな過失があるなどと主張して、損害賠償金の減額を主張してくる場合もよくあります。
例えば、作業員がヘルメットと安全ベルトをしていなかった場合に、「会社としては、ヘルメットをかぶること及び安全ベルトを付けることについて指示していたので、労災被害者に大きな過失がある」と主張してくるような場合です。
このような場合、労災被害者側としては、会社側の安全対策の実態に不備があったことなどを主張していく必要があり、そのためには労災に強い弁護士による対応が不可欠です。
労災死亡事故のご遺族のための無料相談実施中
 法律事務所リンクスの無料相談では、労災に強い弁護士が、労災でご家族を亡くされた方のための無料相談を実施しています。
法律事務所リンクスの無料相談では、労災に強い弁護士が、労災でご家族を亡くされた方のための無料相談を実施しています。
労災でご家族を亡くされた場合、悲しみに打ちひしがれる中で、今後の生活はどうなるのか、労基署や会社とのやり取りはどうすればよいのかといった不安が大きいこといます。
弁護士に依頼すれば、どのように対応すればよいかのアドバイスを受けたり、着手金0円で窓口を任せたりすることができます。
労災でご家族を亡くされた方は、0120-917-740にお電話を頂くか、LINEで労災の無料相談をお申し込みください。
労災事故で死亡した場合に労災保険から支払われる保険金
遺族補償年金
死亡時に生計を同じくしていた遺族がいる場合に支払われるのが、遺族補償年金・遺族特別年金・遺族特別支給金です。
遺族補償年金とは
遺族補償年金とは、労災によって死亡した被災者の遺族の生活を支えるために支給される年金です。
遺族補償年金の受給資格者と受給権者
遺族(補償)年金は、次に説明する「受給資格者」(受給する資格を有する遺族)のうちの最先順位者(「受給権者」といいます。)に対して支給されます(出典:厚生労働省徳島労働局「遺族(補償)給付」)。
受給資格者
遺族(補償)年金の受給資格者となるのは、労働者の死亡当時その者の収入よって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹ですが、妻以外の遺族については、労働者の死亡の当時に一定の高齢又は年少であるか、あるいは一定の障害の状態にあることが必要です。
なお「労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた」とは、もっぱら又は主として労働者の収入によって生計を維持されていることを要せず、労働者の収入によって生計の一部を維持していれば足り、いわゆる共稼ぎの場合もこれに含まれます。
受給権者
そのうち、実際に受給できる受給権者は、例えば夫が亡くなった場合、妻がいる場合には妻になります。これに対し、妻がいない場合で子がいる場合には子(ただし一定の障害がある場合を除くと18歳になった後の3月31日まで受給権あり)、子がいないか子がいる場合でもその子に受給権がない場合には父母(一定の障害がある場合を除いて60歳以上に受給権あり)などの順番で支給されます。
遺族補償年金の金額
支給額は遺族の数によって決まります。ここにいう遺族の数とは受給権者と受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数になります。
例えば、夫が亡くなって、妻がいる場合で、18歳になった後の3月31日を迎えていない子が生計を同じくしている場合を考えると、次の金額が支給されます。
| 遺族 | 金額 |
|---|---|
| 配偶者のみ | 給付基礎日額の153日分 |
| 配偶者と子1人 | 給付基礎日額の201日分 |
| 配偶者と子2人 | 給付基礎日額の223日分 |
| 配偶者と子3人 | 給付基礎日額の245日分 |
給付基礎日額とは、労災事故の直前3か月に支払われた賃金の総額(賞与等を除く)を日割りした金額のことです。
例えば、月給30万円の夫が亡くなった場合、給付基礎日額は1万円になり、遺族が妻のみであれば年間153万円が支給されます。
ただし、遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻のみの場合は給付基礎日額の175日分が支給されますので、給付基礎日額が1万円の場合には年間175万円が支給されます。
遺族補償年金の請求方法
遺族補償年金を請求するには、「遺族補償年金支給請求書」または「遺族年金支給請求書」を作成して、添付書類(死亡診断書、死体検案書、戸籍謄本、請求人が被災労働者の収入により生計を維持していたことを証明する資料など)と共に、管轄の労働基準監督署長に提出して請求します。
遺族補償年金の支給はいつまで?
自分の受給資格がある間は受給し続けることができます。
例えば、配偶者は再婚するまで、子や孫または兄弟姉妹については18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了するまで受給可能です。
そして、受給権者が死亡や再婚などで受給権を失ったときは、その次の順位者が受給権者となることができます。
遺族補償年金の時効は5年
遺族補償年金の時効は死亡の日の翌日から5年です。
遺族補償年金の前払い制度
遺族補償年金は、給付基礎日額の1000日分を限度として前払いで受け取ることができます。
前払一時金の支給を受けると、前払一時金の額に達するまで遺族補償年金の支給が停止されますが、支給総額に変更はありません。
前払一時金は、死亡の日の翌日から2年を経過すると、請求できなくなります。
遺族特別年金
遺族特別年金とは、遺族補償年金の受給資格がある遺族に対して、遺族補償年金とは別に支給される年金です。被災者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹が対象です。
例えば、夫が亡くなって、妻がいる場合で、18歳になった後の3月31日を迎えていない子が生計を同じくしている場合を考えると、次の金額が支給されま
| 遺族 | 金額 |
|---|---|
| 配偶者のみ | 算定基礎日額の153日分 |
| 配偶者と子1人 | 算定基礎日額の201日分 |
| 配偶者と子2人 | 算定基礎日額の223日分 |
| 配偶者と子3人 | 算定基礎日額の245日分 |
算定基礎日額とは、労災事故の直前1年間に支払われた賞与の総額を365日で割った金額のことです。
例えば、年間賞与73万円の夫が亡くなった場合、算定基礎日額は2000円になり、遺族が妻のみであれば年間31万2000円が支給されます。
ただし、遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻のみの場合は給付基礎日額の175日分が支給されますので、算定基礎日額が31万2000円の場合には年間35万円が支給されます。
遺族補償一時金・遺族特別一時金
遺族補償一時金・遺族特別一時金とは
遺族補償一時金・遺族特別一時金は、①または②の要件に該当するときに支給されます(出典:厚生労働省福井労働局「遺族(補償)等給付」)。
- 遺族(補償)年金を受けることができる遺族がいない場合
- 遺族(補償)等年金の受給権者が最後順位者まですべて失権し、かつ、受給権者であった遺族の全員に対して支払われた年金等の合計額が、給付基礎日額の1,000日分に満たない場合
失権とは受給資格者が死亡、婚姻、離縁、18歳に達するなどして受給資格を失うことを意味します。
下記の金額が支払われることになりますが、②の場合は遺族補償年金の受給権者が既に受給していた金額は差し引かれます。
遺族補償一時金・遺族特別一時金の受給権者
遺族補償一時金・遺族特別一時金の受給権者は、優先順位が高い順に、①配偶者、②労働者の収入により生計を維持していた子・父母・孫・祖父母、③その他の子・父母・祖父母、④兄弟姉妹となります。
遺族補償一時金の金額
給付基礎日額の1000日分が一時金として支払われます。
例えば、月給30万円の夫が亡くなった場合、給付基礎日額は1万円になり、1000万円が支給されます。
遺族特別一時金の金額
算定基礎日額の1000日分が一時金として支払われます。
例えば、年間賞与73万円の夫が亡くなった場合、算定基礎日額は2000円になり、200万円が支給されます。
遺族特別支給金
労災保険法に基づく特別支給金として300万円が支給されます。
葬祭料
葬祭料とは、亡くなった被災者の葬祭を執り行った人に対して労災保険から支給される費用ですが、葬儀にかかった費用の全額が支給されるわけではなく、次の2つのうちの多い金額を限度として支給されます。
・31万5000円+給付基礎日額の30日分
・給付基礎日額の60日分
葬祭料の時効は死亡の日の翌日から2年です。遺族補償年金よりも請求期限が短いのでご注意ください。
労災事故で死亡した場合に会社から支払われる損害賠償金
死亡慰謝料
労災の死亡慰謝料の相場は、お亡くなりになった被災者の立場によって、次の表のとおり2000万円~2800万円とされていますが、増減することがあります。
| 立場 | 金額 |
|---|---|
| 一家の支柱 | 2800万円 |
| 母親 | 2500万円 |
| その他 | 2000~2500万円 |
死亡逸失利益
 死亡逸失利益とは、労災で亡くなることなく生きて働くことができていれば得ることができた所得の損害賠償です。
死亡逸失利益とは、労災で亡くなることなく生きて働くことができていれば得ることができた所得の損害賠償です。
逸失利益の計算式次のとおりです。
基礎収入×(1―生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
基礎収入とは労災の発生前に支払を受けていた年収です。
生活費控除率とは、労災事故で亡くなった方が今後の労働により収入を得ることが不可能になる一方、ご存命であれば支出していた生活費を支出しないことになるため、これを割合的に差し引くという考え方です。
生活費控除率も立場によって異なります。
| 立場 | 生活費控除率 |
|---|---|
| 一家の支柱 | 被扶養者1人40% 2人以上30% |
| 女性 | 30% |
| 独身男性 | 50% |
就労可能年齢(多くの場合は67歳)に対応するライプニッツ係数とは、就労可能年数から「中間利息」を控除した係数のことです。
本来、逸失利益は「被害者が労働をすることで得るはずだった収入」を補償するものですから、事故がなければ、毎月の給料日などで少しづつ得ていくはずだったものです。
ですが、逸失利益は一括で支払われます。例えば逸失利益の金額が4500万円だったとしましょう。
- 毎年150万円ずつ30年かけて受け取る
- 一括で4500万円を受け取る
上記を比較すると、定期預金などに預けた際の利息は、後者の方が多くなりますので、一括で受け取る方が得になります。
これを損得の内容に調整するのに必要な係数がライプニッツ係数で次の表のとおりです。
2020年4月1日以降に発生した労災事故のライプニッツ係数表(3%)
| 期間 | ライプニッツ係数 | 期間 | ライプニッツ係数 |
| 1年 | 0.9709 | 35年 | 21.4872 |
| 2年 | 1.9135 | 36年 | 21.8323 |
| 3年 | 2.8262 | 37年 | 22.1672 |
| 4年 | 3.7171 | 38年 | 22.4925 |
| 5年 | 4.5797 | 39年 | 22.8082 |
| 6年 | 5.4172 | 40年 | 23.1148 |
| 7年 | 6.2303 | 41年 | 23.4124 |
| 8年 | 7.0197 | 42年 | 23.7014 |
| 9年 | 7.7861 | 43年 | 23.9819 |
| 10年 | 8.5302 | 44年 | 24.2543 |
| 11年 | 9.2526 | 45年 | 24.5187 |
| 12年 | 9.9540 | 46年 | 24.7754 |
| 13年 | 10.6350 | 47年 | 25.0247 |
| 14年 | 11.2961 | 48年 | 25.2667 |
| 15年 | 11.9379 | 49年 | 25.5017 |
| 16年 | 12.5611 | 50年 | 25.7298 |
| 17年 | 13.1661 | 51年 | 25.9512 |
| 18年 | 13.7535 | 52年 | 26.1662 |
| 19年 | 14.3238 | 53年 | 26.3750 |
| 20年 | 14.8775 | 54年 | 26.5777 |
| 21年 | 15.4150 | 55年 | 26.7744 |
| 22年 | 15.9369 | 56年 | 26.9655 |
| 23年 | 16.4436 | 57年 | 27.1509 |
| 24年 | 16.9355 | 58年 | 27.3310 |
| 25年 | 17.4131 | 59年 | 27.5058 |
| 26年 | 17.8768 | 60年 | 27.6756 |
| 27年 | 18.3270 | 61年 | 27.8404 |
| 28年 | 18.7641 | 62年 | 28.0003 |
| 29年 | 19.1885 | 63年 | 28.1557 |
| 30年 | 19.6004 | 64年 | 28.3065 |
| 31年 | 20.0004 | 65年 | 28.4529 |
| 32年 | 20.3888 | 66年 | 28.5950 |
| 33年 | 20.7658 | 67年 | 28.7330 |
| 34年 | 21.1318 | 68年 | 28.8670 |
例えば、年収500万円の40歳で被扶養者2名以上の一家の支柱である男性の死亡逸失利益を計算してみますと、次のとおりです。
年収500万円×(100%-生活費控除率30%)×18.327(27年のライプニッツ係数)=約6414万円
なお、労災保険から遺族補償年金を受け取っている場合には、会社が支払うべき死亡逸失利益は、遺族補償年金として支払われた金額を差し引いた額ということになります。
労災死亡事故発生から解決までの具体的な流れ
ご家族が亡くなられてから、正当な補償を受け取るまでには、いくつかの段階を踏む必要があります。全体像を把握しておくことで、ご遺族が「次に何をすべきか」を見失わずに、落ち着いて対応を進めることができます。
ステップ1:労災保険の申請
まず、国の制度である労災保険の給付を受けるための手続きを行います。これは、会社に責任があるかどうかに関わらず、労災と認定されれば給付を受けられる、ご遺族の生活を支えるための重要な第一歩です。
- 手続きの場所: 会社の所在地を管轄する労働基準監督署
- 必要な主な書類: 遺族(補償)給付支給請求書、死亡診断書、故人との関係を証明する戸籍謄本など
- おおよその期間: 請求してから支給が決定されるまで、通常4か月程度の調査期間がかかります。
会社が労災申請に協力してくれない場合の対処法
本来、会社は労働者の労災申請に協力する義務がありますが、残念ながら「手続きが面倒」「保険料が上がるのを懸念している」「会社のイメージダウンを恐れている」といった理由で、非協力的な態度をとる会社も存在します。
しかし、会社の協力がなくても労災申請は可能です。労災保険の利用は労働者に与えられた正当な権利であり、会社の一存で妨げることはできません。
労災の申請書には、会社の証明印を押す欄がありますが、会社が協力を拒否する場合は、その欄を空欄のまま労働基準監督署に提出できます。その際、会社が協力してくれない旨を説明すれば、問題なく申請は受理されます。
会社が労災の発生を隠そうとしたり、労災申請をしないように圧力をかけたりする行為は「労災隠し」と呼ばれ、法律で罰せられる犯罪行為です。もし会社からそのような対応をされた場合は、決して一人で悩まず、すぐに労働基準監督署や弁護士などの専門機関に相談してください。
証拠として、事故の状況がわかる写真やメモ、同僚の証言、会社とのやり取りの記録などを残しておくことが、後の手続きを有利に進める上で非常に重要になります。
ステップ2:会社への損害賠償請求の準備
労災保険の申請と並行して、会社への損害賠償請求の準備を進めます。会社の安全管理に問題があった場合、労災保険だけでは補償されない慰謝料や逸失利益の不足分を請求できます。
- 行うこと: 事故の証拠収集、損害額(慰謝料、逸失利益など)の計算
- 証拠の例: 事故現場の写真、同僚の証言、故人の日記やメール、タイムカードなど
ステップ3:会社との示談交渉
損害額が確定したら、会社に対して内容証明郵便などで請求書を送り、具体的な金額の支払いを求めて話し合い(示談交渉)を開始します。
- 交渉の相手: 会社の担当者、顧問弁護士、保険会社の担当者など
- 注意点: 会社側から提示される金額が、必ずしも適正な額とは限りません。安易に合意せず、専門家のアドバイスを求めることが重要です。
ステップ4:示談成立または裁判
交渉で双方が合意に至れば、「示談書」を作成して解決となります。もし交渉が決裂した場合は、裁判所に訴訟を提起し、法的な判断を求めることになります。
- 示談成立の場合: 示談書に記載された内容で賠償金が支払われ、紛争は終了します。
- 裁判の場合: 解決までに時間がかかる可能性がありますが、裁判所の判決によって強制的に賠償金の支払いを受けることができます。
労災死亡事故を弁護士に依頼するメリットと費用の詳細
ご家族を亡くされた悲しみの中で、複雑な手続きや会社との交渉をご遺族だけで行うのは、精神的にも時間的にも大きな負担となります。このような時、労災問題に詳しい弁護士はご遺族の力強い味方となります。
弁護士に依頼する5つのメリット
- 複雑な手続きをすべて任せられる 労災保険の申請から会社への損害賠償請求まで、多くの書類作成や手続きが必要です。弁護士に依頼すれば、これらの煩雑な手続きをすべて代行してもらえるため、ご遺族は精神的な負担から解放されます。
- 会社との交渉窓口になってもらえる 会社と直接交渉することは、ご遺族にとって非常につらい作業です。弁護士が代理人として交渉の窓口となることで、会社からのプレッシャーを直接受けることなく、冷静に話し合いを進めることができます。
- 法的に正当な賠償額を請求できる 弁護士は、過去の裁判例などに基づき、法的に認められる最大限の賠償額を算定します。会社側の提示額が不当に低い場合でも、専門的な知識を基に交渉し、適正な金額の獲得を目指します。
- 会社の責任を追及するための証拠集めをサポート 会社の責任を証明するためには、客観的な証拠が不可欠です。弁護士は、どのような証拠が有効かを的確に判断し、その収集をサポートします。
- 精神的な支えになる 今後の生活への不安や会社への不信感など、ご遺族が抱える様々な悩みに寄り添い、法的な観点からだけでなく、精神的な支えとなることも弁護士の重要な役割です。
弁護士費用の不安について
「弁護士に頼みたいけれど、費用が心配」という方も多いのではないでしょうか。しかし、最近ではご遺族の負担を軽減するため、多くの法律事務所が柔軟な費用体系を採用しています。
- 相談料・着手金が無料の事務所も多い 初回の法律相談を無料で行い、依頼時の「着手金」も無料とする「完全成功報酬制」をとる事務所が増えています。この場合、依頼時にまとまった費用を用意する必要はなく、最終的に会社から賠償金が支払われた際に、その中から報酬を支払う形になります。
- 成功報酬の目安 成功報酬は、獲得できた賠償金額の10%~20%程度に設定されていることが一般的です。費用体系は事務所によって異なりますので、相談の際に詳しく確認することが大切です。
大切なのは、費用の心配から専門家への相談をためらい、受け取れるはずの正当な補償を諦めてしまうことです。多くの事務所が初回の無料相談を実施していますので、まずは一度、話を聞いてみることをお勧めします。
労災の死亡事故に関するよくある質問
労災で死亡事故が起きた会社はどうなる?
労災で死亡事故が起きた会社は、法的・社会的に様々な制裁やペナルティを受ける可能性があります。詳しくは、以下の表をご覧ください。
| 内容 | |
| 刑事責任 | 「業務上過失致死罪」「労働安全衛生法違反」などで刑事責任を問われる可能性がある |
| 民事責任 | 労災の被災者遺族から損害賠償請求を受ける(慰謝料や逸失利益などの支払いを求められる) |
| 労基署からの指導・監督 | 会社に労働基準監督署の調査が入り違反があれば是正勧告が行われる |
| 企業イメージの低下 | 労災死亡事故が報道されることで、社会的信用やイメージが損なわれ、経営に悪影響がでる |
| 従業員の士気の低下 | 従業員の会社に対する信頼が低下し、士気が下がったり、退職者が増えたりする |
| 経済的損失 | 賠償金の支払や、安全対策強化にかかるコストなど、直接的な経済的損失が発生する |
労災の死亡事故の年間件数は?
厚生労働省の発表によると、2022年の労災による死亡者数は774人です。前年と比べると4人減っています。
労災死亡事故は労災に強い弁護士に無料相談ください
 これまでご説明してきたとおり、労災は労基署と会社という2つの組織を相手にしなければならない上に、手続きも複雑であるため、労災事故のご遺族だけで進めていくことには限界があります。
これまでご説明してきたとおり、労災は労基署と会社という2つの組織を相手にしなければならない上に、手続きも複雑であるため、労災事故のご遺族だけで進めていくことには限界があります。
法律事務所リンクスの労災に強い弁護士の無料相談・電話相談では、手続きの進め方や慰謝料の見込みについて丁寧にご説明させて頂いております。
法律事務所リンクスでは着手金を0円とさせて頂いており、ご依頼頂ける場合にも経済的負担を心配される必要はございません。
労災死亡事故でお悩みの方は法律事務所リンクスの弁護士による無料相談をご利用ください。
このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
全国の労働災害の被害者の救済のため無料電話相談に取り組む。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2015年に法律事務所リンクスを設立し、2016年に弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)として法人化。現在、東京と京都にオフィスがある。