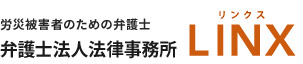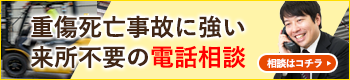機械に巻き込まれ事故で死亡の金額は?工場巻き込みの労災事例を解説

巻き込まれ挟まれ事故は死亡事故や重篤な後遺障害が起きやすい!
適正な賠償金を獲得するなら弁護士に相談を!
工場機械に巻き込まれたり挟まれる事故は、死亡や重大な後遺障害につながる可能性が高い事故類型です。
厚生労働省の統計によると、2023年における「はさまれ・巻き込まれ」を原因とする労働災害の発生件数は13928件であり、2023年の全労働災害135371件のうち、4番目に多い事故類型となっています。また死亡災害は合計108件発生しており3番目に多い原因となっています(参照:厚生労働省HP「労働災害統計」))。
このページでは、法律事務所リンクスの労災に強い弁護士が、工場機械に巻き込まれたり挟まれる事故の事例を紹介しながら、「適正な慰謝料をもらうための3つのポイント」「会社に損害賠償責任が認められる場合」「労災被害者に落ち度が認められて損害賠償金が減額される場合」「弁護士に依頼した方がよい理由」について、説明します。
指切断事故については「工場で指切断で労災の金額や後遺症は?指の怪我で仕事を休むと慰謝料は?」をご覧ください。
電話での依頼で解決される方多数!お気軽にご相談ください!
- お電話で
無料相談【全国対応】 - 0120-917-740
受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)
機械巻き込まれ・挟まれ事故で死傷した被害者・遺族が適正な慰謝料をもらうための3つのポイント
工場機械に巻き込まれたり挟まれる事故で、会社から適正な慰謝料をもらうためにはクリアしないといけない3つのポイントがあります。
- きちんと労災申請をする
- 元請業者・下請業者・孫請業者など複数の会社が関与している場合にどの会社に損害賠償請求するか
- 労災被害者の落ち度による減額幅を小さくする
①きちんと労災申請をする
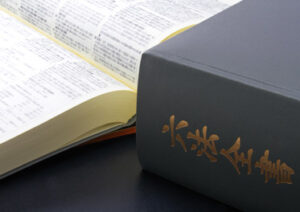 工場機械に巻き込まれたり挟まれる事故で労災被害者が死亡した場合、「死人に口なし」になってしまいかねませんので、どのような事故であったかを把握するため、きちんと労災申請をして、労働基準監督署に調査してもらわなければ、会社の責任を問えず、適正な慰謝料を受け取れなくなる可能性があります。
工場機械に巻き込まれたり挟まれる事故で労災被害者が死亡した場合、「死人に口なし」になってしまいかねませんので、どのような事故であったかを把握するため、きちんと労災申請をして、労働基準監督署に調査してもらわなければ、会社の責任を問えず、適正な慰謝料を受け取れなくなる可能性があります。
労災の死亡事故の注意点や金額について詳しく知りたい方は、「労災で死亡事故の金額は?保険金はいくら?遺族補償年金の計算は?」をご覧ください。
また、大怪我を負い、治療を続けたにもかかわらず後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定を受けないと、適切な慰謝料の支払いを受けることができません。
労災で適正な後遺障害等級の認定を受けるには、労災に強い弁護士に相談することが必要です。詳しくは「労災で後遺障害!後遺症認定率が高い診断書とは?申請の流れは?」をご覧ください。
②安全配慮義務違反を認めさせる
 工場機械に巻き込まれたり挟まれる労災事故が起きた場合に慰謝料を請求するには、安全配慮義務違反等の損害賠償責任を認めさせる必要があります。
工場機械に巻き込まれたり挟まれる労災事故が起きた場合に慰謝料を請求するには、安全配慮義務違反等の損害賠償責任を認めさせる必要があります。
安全配慮義務とは、工場機械に巻き込まれたり挟まれる労災事故を起こさないよう安全対策を取る義務のことです。
工場機械に巻き込まれたり挟まれる労災事故の場合、労働者側に落ち度があることが多いですが、会社には労働者が作業ミスをすることを想定して安全対策を取る義務(安全配慮義務)があるので、労働者に落ち度があるからと言って、安全配慮義務違反が認められないということにはなりません。
もっとも、会社側が、労働者の一方的過失による事故であると主張し、裁判所が会社側の安全配慮義務違反を認めなかったという事例もあるため、会社にどのような安全配慮義務違反があったのかについて、きちんと証明する必要があります。
具体的には、操作方法や作業手順、注意事項に関する安全教育の有無・内容、事故防止措置の有無・内容などを確認し、例えば「プレス機については、安全囲いを設ける等当該プレス等を用いて作業を行う労働者の身体の一部が危険限界に入らないような措置を講じなければならない。」(労働安全衛生規則131条)に違反していることなどを主張立証することが考えられますが、このようなことをきちんと主張立証するには、労災に強い弁護士への相談が不可欠です。
③労災被害者の落ち度による減額幅を小さくする
工場機械に巻き込まれたり挟まれる事故が起きる場合、会社に安全配慮義務違反が認められることが多いですが、労災被害者にも落ち度があると認められることが多いです。
労災被害者側としては、安全教育やマニュアルの不備、施設管理や人員配置の不備、危険な労務環境が日常的であったこと、労災被害者の経験の少なさなどを主張して、落ち度が低いことを主張立証していくことが必要となります。
労災被害者のための無料電話相談実施中
 法律事務所リンクスの無料電話相談では、労災に強い弁護士が、労災被害でお困りの被害者の方やご家族のための電話での無料相談を実施しています。
法律事務所リンクスの無料電話相談では、労災に強い弁護士が、労災被害でお困りの被害者の方やご家族のための電話での無料相談を実施しています。
労災で大怪我をした場合、仕事に復帰できるのか、今後の生活はどうなるのか、後遺障害が残ったらどうすればよいのかといった不安が大きいこといます。
弁護士に依頼すれば、どのように対応すればよいかのアドバイスを受けたり、着手金0円で窓口を任せたりすることができますので、治療や仕事復帰に集中することが可能です。
労災で怪我をしてお困りの被害者の方は、0120-917-740にお電話を頂くか、LINEで労災の無料相談をお申し込みください。
機械巻き込まれによる労災死亡事故の解説
衛生陶器製造工場で作業中の労働者が蓋成形機のトラブルに対処しようとして頭部を挟まれ死亡し6140万円余りの損害賠償が認められた事案
大津地裁平成22年6月22日判例時報2090号90頁
 A社との間で製造委託契約を締結しているB社は、従業員のCを工場内の作業に従事させており、労災被害者はD社の派遣社員として、労災事故発生当時、Cを組長とする組の作業員として成形された蓋を点検する業務に従事していました。
A社との間で製造委託契約を締結しているB社は、従業員のCを工場内の作業に従事させており、労災被害者はD社の派遣社員として、労災事故発生当時、Cを組長とする組の作業員として成形された蓋を点検する業務に従事していました。
A社は、蓋成形機のトラブルが発生した場合には、蓋成形機を一旦停止させトラブルに対処するというマニュアルを定めていましたが、トラブルが発生する度に蓋成形機を停止させると生産性が落ちることから、実際には、マニュアルは遵守されておらず、蓋成形機を停止させることなく、その背部に入り込んでトラブルに対処することが常態化していました。
労災被害者は、蓋成形機を停止させることなく、その背部に入り込んでトラブルに対処しようとして、頭部を挟まれ死亡しました。
労災被害者のご遺族は、A社、B社及びCに対し、損害賠償を請求したところ、裁判所は、6140万円余りの支払を命じました。
A社、B社およびCにはには損害賠償責任がある
労災被害者のご遺族は、Cについて、組長として組員の労災防止の責任者であったから、蓋成形機の作動中に製造ライン内部に労働者が立ち入らないよう組員に対する指導教育を行うべき義務があり、また、労働者の安全を確保するために、上記の点を改善するようA社に申し出る義務があったと主張しました。
裁判所も、Cは「組長として、労働者が作業手順を守り、かつ、安全に作業を進めるように、労働者を監視し、教育すべき立場にある被告Fとしては、本件マニュアルで定められているとおり、蓋成形機の作動中は蓋成形機の間に入り込まないよう、組員に対する指導教育を行うべき注意義務があった」ところこれを怠ったとして、Cの損害賠償責任を認めました。
そして、Cの雇用主でありB社はもちろんのこと、Cを指揮監督していたA社も実質的使用者であり、民法715条1項の使用者責任を負うとして、6140万円の支払を命じました。
労災被害者の落ち度はないと判断
A社、B社およびCは、労災被害者にも落ち度があったと主張しましたが、裁判所は、「本件マニュアルを定めながら、生産効率を求める余り、これに反する方法がとられていることを容認、放置してきた被告らの態度こそが非難されるべきであって、過失相殺をするのは相当でない。」として、労災被害者の落ち度を認めませんでした。
機械巻き込まれ事故で会社に損害賠償請求する流れ
これらの事例ように、はさまれ巻き込まれ事故について会社に責任がある場合には、会社に対して損害賠償請求をすることが可能です。
では、どのような場合に、会社に責任がある場合といえるのでしょうか。
会社が損害賠償責任を負う場合のうち代表的な3つの場合をご紹介します。
①安全配慮義務違反
 1つ目は「安全配慮義務」です。会社には、従業員の心身と健康と安全を守るべき義務があります。
1つ目は「安全配慮義務」です。会社には、従業員の心身と健康と安全を守るべき義務があります。
労災においては、「労働災害の危険を発見し、その危険を事前に排除する義務」ともいえます。
機械巻き込まれ事故の場合に問題となる義務については、
・機材の使い方に対する指導
・マニュアルの配布
・従業員の労働時間の管理
といった一般的な安全対策のほかに、
・覆い、囲いの設置
・安全囲いを設ける等当該プレス等を用いて作業を行う労働者の身体の一部が危険限界に入らないような措置
などの具体的な義務が定められています。
②使用者責任
2つ目は、「使用者責任」です。こちらは、従業員が、他の従業員や第三者に対して損害を与えてしまった場合に、会社も連帯して責任を負うことを指します。
現場責任者が機械の安全な使用方法を教えず、危険を放置した場合に、その使用者である会社も連帯して負わなければなりません。
会社は、従業員に仕事をさせることで利益を得たり、危険を拡散していたりしますので、安全に配慮した対策を講じていても、連帯責任を負うことになります。
③工作物責任
3つ目は、「工作物責任」です。労災が会社の設備や建物の欠陥によって引き起こされた場合、「工作物責任」が適用されます。
機械巻き込まれ事故の労災被害を弁護士に依頼した方がよい理由
 仕事で巻き込まれ事故にあった場合、労災に強い弁護士に依頼するのがおすすめです。主な理由は以下になります。
仕事で巻き込まれ事故にあった場合、労災に強い弁護士に依頼するのがおすすめです。主な理由は以下になります。
・そもそも、損害賠償請求は弁護士がいないと難しい
・弁護士に依頼すると慰謝料などの損害賠償金額が高くなりやすい
・面倒な労災や後遺障害認定(障害補償給付)の手続きを自分でしなくて済む
・会社とのやりとりを一任することでストレスを負わなくて済む
労災申請などの手続きは自分でもできますが、会社との示談交渉や裁判などは、弁護士がいないと話が進まない可能性も高いです。自己判断で進めようとすると、失敗して無駄な時間がかかったり、取り返しのつかないミスをする可能性もあります。
ですので、自ら行動をする前に、一度弁護士に相談だけでもすることをおすすめします。
機械巻き込まれ事故のまとめ
業務中に巻き込まれ事故にあった場合、労災認定され、労災保険から保険金が下りる可能性があります。
それだけでなく、労災の発生原因に関して、会社に落ち度がある場合「安全配慮義務」などを理由に、会社に対して損害賠償請求が可能です。
機械巻き込まれ事故は、死亡や重篤な後遺障害につながることも多いため、非常に危険です。
後遺障害認定された場合、労災保険から年金がもらえたり、会社に対して高額な損害賠償請求が可能になったりします。
損害賠償金は数百万円~数千万円に上ることもありますので、確実に請求するようにしましょう。そのためには、労災に強い弁護士に相談することが最も重要です。
巻き込まれ事故でお悩みの方や、労災に関して相談したいからは、法律事務所リンクスへご相談ください。労災に強い弁護士が、無料電話相談でわかりやすく説明いたします。
労災被害にあったら労災に強い弁護士に無料相談・電話相談を!
 これまでご説明してきたとおり、労災は労基署と会社という2つの組織を相手にしなければならない上に、手続きも複雑であるため、労災で怪我をした本人やそのご家族だけで進めていくことには限界があります。
これまでご説明してきたとおり、労災は労基署と会社という2つの組織を相手にしなければならない上に、手続きも複雑であるため、労災で怪我をした本人やそのご家族だけで進めていくことには限界があります。
法律事務所リンクスの労災に強い弁護士の無料相談・電話相談では、手続きの進め方や後遺障害等級、慰謝料の見込みについて丁寧にご説明させて頂いております。
法律事務所リンクスでは着手金を0円とさせて頂いており、ご依頼頂ける場合にも経済的負担を心配される必要はございません。
まずはお気軽に法律事務所リンクスの無料相談・電話相談をご利用ください。
このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
全国の労働災害の被害者の救済のため無料電話相談に取り組む。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2015年に法律事務所リンクスを設立し、2016年に弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)として法人化。現在、東京と京都にオフィスがある。