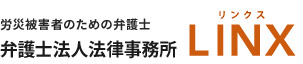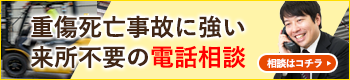労災の手続きの流れと期限は?労災申請から示談の注意点を解説

労災の手続きは複雑で大変!
示談する前に弁護士に相談を!!
労災事故にあった場合の労災申請手続きの流れは次のとおりです。
- 労災事故の発生を会社に報告する
- 治療を開始する
- 会社が労災申請の手続きを取る
- 休業補償の支給を受ける
- 治療を終了する(症状固定)
- 後遺障害の申請をする
- 会社との間で示談交渉をする
このページでは、法律事務所リンクスの労災に強い弁護士が、労災申請の流れや労災の手続きの期限について解説します。
電話での依頼で解決される方多数!お気軽にご相談ください!
- お電話で
無料相談【全国対応】 - 0120-917-740
受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)
労災申請の手続きの流れと期限~労災事故発生から示談交渉まで
労災事故にあった場合の労災事故発生から会社への損害賠償請求までの流れは次のとおりです
労災事故解決までの流れを動画でご覧になりたい方はこちらをご覧ください。
。
①労災事故の発生を会社に報告する

労災事故とは、仕事中または通勤中に発生した事故のことをいいます。 労災事故が発生したらすぐに会社に報告し、労基署に労災申請をしてもらう必要があります。
労基署が労災認定をすれば、療養補償給付(治療費)や休業補償給付が支給されます。労災認定を受けないと、会社に対する損害賠償請求が難しくなるので、きちんと認定を受ける必要があります。
② 治療開始
 労災事故で怪我をした被害者は、すぐに治療を開始しましょう。できることなら、労災発生日に受診するのがおすすめです。
労災事故で怪我をした被害者は、すぐに治療を開始しましょう。できることなら、労災発生日に受診するのがおすすめです。
労災が発生してから、治療開始までに時間がかかってしまうと、「けがが労災によって引き起こされたものであること」を証明するのが難しくなります。
けがと労災の因果関係を証明できないと、後々の保険金の支払いや、損害賠償請求に悪影響を及ぼす可能性があるので注意が必要です。
受診する際は、病院の受付で「労災保険を使います」と伝えましょう。労災の場合、治療費は労災保険で10割負担されるため、自分でお金を出す必要はありません。病院が労働基準監督署に治療費を請求する形で、支払いが行われるのが通常です。
③ 会社が労災申請の手続きを取る
 労災申請の手続きは会社がしてくれるのが通常です。
労災申請の手続きは会社がしてくれるのが通常です。
しかし、小さい会社で労災に対応できる総務がいない場合などには、対応してくれないか対応が遅い場合もあるため、労災被害者自らで必要書類を作成したり、労災の申請をする場合もあります。
その場合には、所轄の労働基準監督署に連絡をすれば、労災申請の方法や提出が必要な必要な書式を教えてもらうことができます。
④ 休業補償の支給
 労災で仕事を4日以上休む場合、労基署が休業補償を支払ってくれますが、 労災の休業補償は申請してから支払われるまで1か月以上かかることも多いです。
労災で仕事を4日以上休む場合、労基署が休業補償を支払ってくれますが、 労災の休業補償は申請してから支払われるまで1か月以上かかることも多いです。
労災保険が支払う休業補償には、給料の6割に当たる休業(補償)給付と2割に当たる特別支給金がありますが、会社に対して損害賠償請求をする際には、さらに4割の休業補償を請求することができます。
休業補償給付の支給の期限は2年ですので、早めに請求するようにしてください。
⑤ 症状固定(治療終了)

労災による怪我が完治せず、治療をしてもこれ以上よくならない状態になったら、治療効果がなくなるので、治療は終了になります。この状態のことを症状固定と呼びます。
症状固定となると、治療費や休業補償が打ち切られますので、症状固定のタイミングは慎重に見極める必要があります。
症状固定の際に後遺症が残っている場合には⑥の後遺障害等級認定の手続きを取る必要がありますが、後遺症がない場合には⑦の会社との示談交渉に移ります。
⑥ 後遺障害の申請をする
 後遺症が残っている場合、診断書を作成してもらわないと後遺障害の申請ができませんので、診断書を作成してもらいます。
後遺症が残っている場合、診断書を作成してもらわないと後遺障害の申請ができませんので、診断書を作成してもらいます。
その後、障害補償給付等の支給申請書などの必要書類と共に診断書を労働基準監督署に提出して、後遺障害の申請を行います。
その結果、後遺障害等級認定を受けることができたら、後遺障害等級に応じて障害補償給付が支払われます。
後遺障害の申請の期限は症状固定から5年ですが、労災保険が療養補償給付(治療費)を打ち切った場合には症状固定日に争いが生じる可能性があるので、打ち切りから5年以内に申請しておきましょう。
⑦ 会社との間で示談交渉をする
 治療が終了して後遺障害の有無が確定したら、損害額が確定するので計算して、会社との間での示談交渉に移ります。
治療が終了して後遺障害の有無が確定したら、損害額が確定するので計算して、会社との間での示談交渉に移ります。
示談交渉で折り合えない場合には裁判に移ることになります。
会社に対する損害賠償請求の期限は、労災事故発生または症状固定日から5年になります。
労災における示談の注意点
労災の示談交渉の注意点は次のとおりです。
- 後遺症が残るかどうか未確定の間は示談しない
- 適切な後遺障害等級を獲得してから示談する
- 示談金に漏れがないようにきちんと計算する
①後遺症が残るかどうか未確定の間は示談しない
 後遺症が残るかどうか未確定の間に示談してしまうと、後遺症が残ってしまった場合に追加の請求をすることは難しくなってしまいます。
後遺症が残るかどうか未確定の間に示談してしまうと、後遺症が残ってしまった場合に追加の請求をすることは難しくなってしまいます。
金銭的に困ったり、会社に申し訳ないと考えて、示談してしまう気持ちは分かりますが、示談は一度成立してしまうとやり直すことは原則としてできません。
どうしても示談をしたいのであれば、後遺症について追加で請求できる形で示談できないかアドバイスをさせて頂きますので、弁護士にご相談ください。
②適切な後遺障害等級を獲得してから示談する
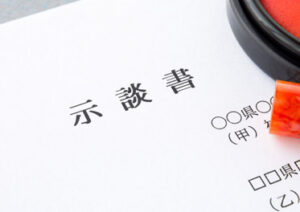 適切な後遺障害等級を獲得しないと十分な示談金を受け取ることができないので、適切な後遺障害等級を獲得することが大事です。
適切な後遺障害等級を獲得しないと十分な示談金を受け取ることができないので、適切な後遺障害等級を獲得することが大事です。
もっとも、労災被害者ご本人も医師でさえも後遺障害等級について必ずしも詳しいわけではなく、適切な後遺障害等級を獲得できないまま示談してしまうということが起きてしまいます。
労災事故で大怪我をしたら早めに労災に強い弁護士に相談して、後遺障害等級の見通しやそのために受けるべき検査のアドバイスをもらいましょう。
③示談金に漏れがないようきちんと計算する
示談はやり直せませんので、きちんと計算をする必要があります。
後遺障害等級に見合う示談金を受け取れるよう示談交渉をするには、交渉のプロである弁護士のサポートが不可欠です。
労災の示談を弁護士に依頼するメリット
労災の示談を弁護士に依頼するメリットは次のとおりです。
- 会社との間の対応窓口を任せられる
- 弁護士に依頼すると示談金が増額する
- 裁判になった場合にも対応できる
①会社との間の対応窓口を任せられる
労災被害にあった従業員自身が示談金を請求する場合、会社に遠慮してしまったり、会社から高圧的な態度に出られてしまったりして、いやな気持になったり、仕事に集中できなかったりするかもしれません。
この点、弁護士は交渉の代理人になれる唯一の国家資格なので、会社との間の交渉をすべて任せることができます。
②弁護士に依頼すると示談金が増額する
 労災被害にあった従業員自身が示談金を請求しても、その金額が誤っていたり、会社の顧問弁護士に足元を見られて、低い示談金額を提示されてしまったりする可能性が高いです。
労災被害にあった従業員自身が示談金を請求しても、その金額が誤っていたり、会社の顧問弁護士に足元を見られて、低い示談金額を提示されてしまったりする可能性が高いです。
示談交渉を弁護士に依頼すると、示談金が増額する可能性が高まります。弁護士は、労災被害者(被災者)の後遺障害の等級などに合わせて、最も高い基準である弁護士基準で示談金の請求を行うからです。
弁護士基準は、過去の裁判の結果などから導き出された金額であるため、法的根拠がありますし、裁判に発展したとしても、弁護士基準での請求が認められる可能性が高いです。
③裁判を見据えた示談交渉ができる
 ご本人で対応する場合、自身で裁判を起こすことが難しいためついつい不利な示談案に妥協しがちですし、いざ裁判になった場合に不利な資料を提出してしまうというようなことも起きてしまいます。
ご本人で対応する場合、自身で裁判を起こすことが難しいためついつい不利な示談案に妥協しがちですし、いざ裁判になった場合に不利な資料を提出してしまうというようなことも起きてしまいます。
弁護士に依頼する場合、弁護士は裁判を見据えて示談交渉をするので、強気の対応ができますし、裁判になった場合に不利になるような資料を提出することもありません。
労災被害にあったら労災に強い弁護士に無料相談・電話相談を!
 これまでご説明してきたとおり、労災は労基署と会社という2つの組織を相手にしなければならない上に、手続きも複雑であるため、労災で怪我をした本人やそのご家族だけで進めていくことには限界があります。
これまでご説明してきたとおり、労災は労基署と会社という2つの組織を相手にしなければならない上に、手続きも複雑であるため、労災で怪我をした本人やそのご家族だけで進めていくことには限界があります。
法律事務所リンクスの労災に強い弁護士の無料相談・電話相談では、手続きの進め方や後遺障害等級、慰謝料の見込みについて丁寧にご説明させて頂いております。
法律事務所リンクスでは着手金を0円とさせて頂いており、ご依頼頂ける場合にも経済的負担を心配される必要はございません。
まずはお気軽に法律事務所リンクスの無料相談・電話相談をご利用ください。
このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
全国の労働災害の被害者の救済のため無料電話相談に取り組む。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2015年に法律事務所リンクスを設立し、2016年に弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)として法人化。現在、東京と京都にオフィスがある。