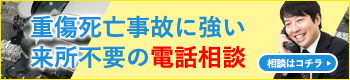後遺障害1級の慰謝料の金額は?慰謝料・逸失利益・介護費用・労災の年金を解説

後遺障害1級は弁護士への依頼で大幅増額します
認定がまだの方は早めの相談を
電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!
- お電話で
無料相談【全国対応】 - 0120-917-740
受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)
後遺障害1級の慰謝料は?介護を要する後遺障害1級の場合は?逸失利益を含めた金額は?
 後遺障害1級の慰謝料は、自賠責保険基準では1150万円(介護を要する場合は1650万円)ですが、弁護士基準(裁判基準)では2800万円です。
後遺障害1級の慰謝料は、自賠責保険基準では1150万円(介護を要する場合は1650万円)ですが、弁護士基準(裁判基準)では2800万円です。
後遺霜害1級の金額は、逸失利益を含めると、自賠責保険基準では3000万円(介護を要する場合は4000万円)であるのに対し、弁護士基準では1億円を超えることも多いです。
このページでは、法律事務所リンクスの後遺障害に詳しい弁護士が、後遺障害等級1級の慰謝料、逸失利益、介護費用について分かりやすく説明します。
交通事故の慰謝料全般について詳しくお知りになりたい方は、「交通事故の慰謝料相場!人身事故の賠償金はいくら?」をご覧ください。
労災の後遺障害等級ごとの金額について詳しく知りたい方は、「労災の後遺障害等級の金額は?障害補償給付を等級表でわかりやすく!」をご覧ください。
後遺障害1級の慰謝料の説明を動画でご覧になりたい方はコチラ
後遺障害1級の慰謝料の相場
後遺障害1級の慰謝料には、自賠責基準で介護を要しない場合、自賠責基準で介護を要する場合、弁護士基準の3つの基準があり、比較すると以下の表のようになります。
| 自賠責基準(介護を要しない) | 自賠責基準(介護を要する) | 弁護士基準(裁判基準) |
| 1150万円 | 1650万円 | 2800万円 |
自賠責基準は、交通事故被害者向けに最低限の補償を定めたものであるのに対し、弁護士基準は、過去の裁判例の積み重ねによって形成された、法的に最も正当とされる基準です。弁護士が被害者の代理人として交渉する際や、裁判になった際に用いられる高額な基準になります。
保険会社は営利企業であり、いわば交渉のプロです。被害者ご本人やご家族が直接交渉しても、「これが当社の基準です」と言われ、弁護士基準での支払いに応じることはまずありません 。しかし、弁護士が代理人として交渉の場に立つと、状況は一変します。弁護士は、法的に最も正当な「弁護士基準」を根拠に交渉を行います。保険会社側も、交渉が決裂して裁判になれば、最終的に裁判所が弁護士基準に基づいた判決を下すことを知っているため、交渉段階で大幅な増額に応じざるを得なくなるのです 。
後遺障害1級の後遺障害逸失利益
 後遺障害逸失利益は、後遺症が将来の仕事・家事に与える影響に対する補償です。次の3つの数字を掛け合わせて、補償額を決めることになります(参照:「逸失利益とは?損害賠償の計算を早見表でわかりやすく解説」)。
後遺障害逸失利益は、後遺症が将来の仕事・家事に与える影響に対する補償です。次の3つの数字を掛け合わせて、補償額を決めることになります(参照:「逸失利益とは?損害賠償の計算を早見表でわかりやすく解説」)。
- 被害者の収入(職がない方の場合は働いたら得られる見込みのある収入)
- 後遺障害等級ごとに決まっている労働能力喪失の割合
- 後遺障害が将来の仕事・家事に影響を及ぼす期間(労働能力喪失期間)
1級の場合、②は100%、③は症状固定から67歳までとされていますので、後遺障害の内容や被害者の収入・年齢によって、次のような後遺障害逸失利益が認められることになります。
| 収入・仕事 | 年齢 | 逸失利益 |
|---|---|---|
| 20代男性(平均賃金) | 25歳 | 547万×1×17.4232=9530万 |
| 主婦(女性平均賃金) | 40歳 | 372万×1×14.6430=5447万 |
| 会社員(年700万) | 55歳 | 700万×1×8.8633=6204万 |
後遺障害1級の介護費用
後遺障害1級の介護・介助費用を算定する際は、介助者が近親者か、職業介護者に依頼してのものかで金額感は異なります。
近親者による付添介護費
付添介護が必要な場合には、日額8000円程度が原則ですが、具体的看護の状況により増減します。
介護は必要ではないものの、日常生活動作の支援等の付添介助が必要な場合には、日額2000円~3000円程度が認められることがありますが、介助の必要性は第三者にはわかりにくいので、きちんと証明する必要があります。
これらの日額が、症状固定時の年齢から平均余命までの期間、認められることになります。
職業付添人の付添介護費
実費が原則で日額1万円~3万円程度ですが、職業付添人が付き添う必要性がある場合に限ります。
現に職業付添人が付いている場合には認められることが多いですが、そうでない場合には、近親者が高齢になるまで(一般的には近親者が67歳になるまで)は介護するものと考えて、付添介護費が計算されます。
| 年齢性別(平均余命) | 近親介助 | 近親介護 | 職業介護 |
|---|---|---|---|
| 25歳男性(56年) | 2047万 | 5459万 | 2.04億 |
| 40歳女性(47年) | 1968万 | 5250万 | 1.96億 |
| 55歳男性(27年) | 1603万 | 4274万 | 1.60億 |
後遺障害1級の金額の無料電話相談実施中
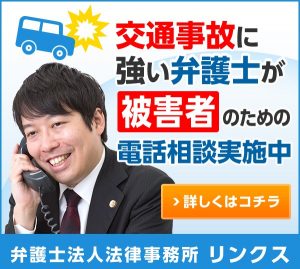 法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、後遺障害等級ごとの金額の見積もりをお伝えしています。
法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、後遺障害等級ごとの金額の見積もりをお伝えしています。
本来支払われるべき後遺障害の金額は裁判所が定めていますが、被害者本人が保険会社と示談交渉をしても、裁判所基準での支払いはしてくれません。
後遺障害等級に合った本来の金額を支払わせるためには、弁護士に相談する必要があります。
交通事故の後遺障害に強い弁護士に無料電話相談されたい方は、0120-917-740にお電話を頂くか、LINEで交通事故の無料相談をお申し込みください。
労災の後遺障害1級について無料相談したい方は、労災専門サイト「労災に強い弁護士への無料相談なら法律事務所リンクス」をご覧ください。
後遺障害1級の解決事例について詳しく知りたい方は、リンクスの弁護士が担当した「バイク事故で脳を損傷し後遺障害併合第1級の認定を受け1億円超を獲得した事例」をご覧ください。
後遺障害1級の獲得方法
後遺障害の等級認定は、通常「損害保険料率算出機構」に対して申請を行います。
申請手続きには、
- 加害者の保険会社を通じて行う事前認定
- 被害者が自分または代理人の弁護士が行う被害者請求
の2つの方法があります。
後遺障害1級が認定される可能性がある場合、申請手続きはなるべく「被害者請求」で行うことをおすすめします。
加害者側の保険会社は、保険金として後遺障害慰謝料を支払う側です。保険会社も民間企業である以上、原則支払いはなるべく抑えたいと考えており、障害の度合いが重く、賠償額が高額になる可能性のあるケースでは、慰謝料額に大きく影響する等級認定手続きを保険会社に委ねること自体がリスクとなり得ます。
保険会社を信じて丸任せにするのではなく、弁護士と相談の上、被害者請求で手続きを進めることで、被害者の実態に合った後遺障害診断書・検査結果・適切な説明を準備し、適正な等級認定を受けられます。
なお、後遺障害1級が見込まれる事案では、被害者自身が保険金を請求することができる能力がない場合もありますが、同居の親族の場合には被害者に代わって請求することができる場合があります。
後遺障害1級の認定にはとても時間がかかりますので、弁護士への相談をお勧めします。
法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、後遺障害1級の等級認定手続きや慰謝料の相場をお伝えしています。
交通事故の後遺障害でお困りの方は、お気軽にお電話でお問い合わせください。
後遺障害等級の併合・相当・加重
なかには、以前の事故によって既に後遺障害の認定を受けていたり、今回の事故で2ヵ所以上の後遺症に苦しんでいたりする方もいらっしゃるでしょう。そのようなケースの場合は、後遺障害等級と併合や相当、加重といった取り扱いを受けることができる可能性があります。
2つ以上の後遺障害が残存してしまった場合は、それらをまとめて1つの等級として認定するのが「併合」です。
また、自賠法施行令別表第1及び第2に定められていない後遺障害が残存した場合には、「各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする」といった「相当」に該当することがあります。今回の事故が発生する前に既に同一部位に障害があった場合には、後遺障害の程度を「加重」した取り扱いとなることがあります。
後遺障害1級に認定されたら「身体障害者手帳」の交付申請を
交通事故に遭い、後遺障害等級認定の申請を経て後遺障害1級の認定が認められた場合は、お住いの市区町村に身体障害者手帳の交付申請を忘れずに行うようにしましょう。
後遺障害等級認定は、後遺障害慰謝料や逸失利益など事故の加害者に対する賠償金請求に関わる手続きで、身体障害者手帳の交付手続きとはまったく別物です。
身体障害者手帳の交付を受けると、所得税・住民税の障害者控除、医療費の割引・助成、公共料金・公共交通機関運賃の割引など、行政による様々なサービスを受けることが出来ます。
後遺障害1級の認定を受けることによるデメリットは?
後遺障害等級認定を受けること自体にデメリットはありませんが、等級認定を受けるには症状固定をする必要があり、これに伴って、治療費や休業損害が打ち切りが問題となります。
特に、事故後ずっと入院している場合や介護が必要になった場合に、治療費や休業損害が打ち切られると、後遺障害の補償や介護費の支払を受けるまでの間、多額の自己負担が発生してしまう可能性があります。
そこで、このような場合には、症状固定前の段階で、症状固定後すぐに自賠責保険金(1級の場合は最高で4000万円が支給されます)を請求できるよう準備をしておく、障害者総合支援法や介護保険の利用の準備をしておくなど症状固定前の準備が肝心になります。このような場合には、できる限り早い段階で、後遺障害等級認定に精通した弁護士に無料相談することをお勧めします。
労災における後遺障害1級の慰謝料は?
 では、仕事中の労災により後遺障害が残存した場合の慰謝料はどうなるのでしょうか。
では、仕事中の労災により後遺障害が残存した場合の慰謝料はどうなるのでしょうか。
労災での後遺障害が認められると、等級に応じた障害補償給付を受け取ることができます。また、労災の後遺障害によって労働能力が失われると、以前と同様に働くことができない可能性があります。そのため、後遺障害がなければ将来的に得られていたと想定される利益(遺失利益)を補うため障害補償給付金が給付されます。
労災の後遺障害等級と給付金
労災の場合、後遺障害の等級に応じて障害(補償)給付金や障害特別年金/一時金、障害特別支給金が支払われます。
通勤中や就業中の事故で後遺障害認定1級が認められた場合、労災から支払われる補償金は以下の通りです。
| 後遺障害等級 | 障害(補償)給付 | 障害特別年金/一時金 | 障害特別支給金 |
|---|---|---|---|
| 後遺障害1級 | 給付基礎日額 x 313日分(年金) | 算定基礎日額 x 313日分(年金) | 342万円(一時金) |
労災障害給付では、後遺障害認定1級の場合、年金形式で障害補償給付金を受け取ることができます。
労災で年金が受給できるのはいつまで?
労災の後遺障害等級が7級以上の場合、年金形式で障害補償給付金を受給できます。障害補償給付金は被災者が死亡するまで受給可能です。
労災の後遺障害等級認定の審査・面談
労災の後遺障害等級の認定を受けるためには、労働基準監督署に申請を行います。労働基準監督署は、提出された障害給付支給請求書に基づいて審査を行います。審査は、書面のみではなく本人との面談なども行われます。後遺障害等級に認定されると、等級に応じた補償を受けることができます。
労災の後遺障害認定の決定
審査後に労災の後遺障害の認定基準に該当すると判断され、認定された等級に不満がない場合、手続きは終了となります。等級認定や障害認定が納得できない場合は、再審査などを検討することもあります。
労災の後遺障害が認定されないケース
後遺障害の認定を申請したすべてのケースが認定されるわけではありません。では、どのような場合で労災の後遺障害が認定されないのでしょうか。
後遺障害認定に必要な治療・検査を受けていない
後遺障害の認定を受けるためには、必要な治療や検査を受けていることが大切になってきます。検査の具体例としては、CTやMRIなどの精度の高い医療機器による検査です。精度の低い機器で検査を受けると、後遺障害の状況や症状が確認できない可能性があります。
医師からの後遺障害診断書がない
後遺障害認定の申請には後遺障害診断書が必要となります。また、医師の意見書の有無で認定を受けられる可能性が変わってくることがあります。
労災申請の時効切れ
障害補償給付の時効は労災が起こってから5年となっています。そのため、労災申請の手続きは時効までの期間に行う必要があります。
後遺障害等級第1級の主な認定基準
後遺障害等級第1級の認定基準は、以下のいずれかに該当する場合です。介護の必要の有無で2つの基準が設定されています。
介護が必要な場合
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
介護の必要がない場合
- 両眼が失明したもの
- 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
- 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
- 両上肢の用を全廃したもの
- 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
- 両下肢の用を全廃したもの
交通事故に強い弁護士への無料相談が不可欠
後遺障害1級に対する一般的な補償の基準は以上で説明したとおりですが、保険会社は
- このような重篤な後遺障害の場合には余命が短くなるので、平均余命までの介護費は認められない
- 障害者支援や介護保険を利用することで介護費の自己負担は少なくなる
- 職業付添人による介護の必要性は認められない
など、なにかしらの理由をつけて、できる限り介護費を減らそうとします。
また、一般的に後遺障害の等級認定が認められる確率は、すべての等級を含んだ値で約5%程度と言われています。その中でも、2018年度の後遺障害等級別認定数を見ると、後遺障害1級の認定を受けた人は別表1(要介護)・別表2(介護不要)を合計しても1.53%。(損害保険料率算出機構「自動車保険の概況」)もともと狭き門である後遺障害等級認定の中でも、後遺障害1級の認定には、その事態の重大さから非常に慎重で、厳密な審査が行われます。
重篤な被害を巡り、弁護士基準(裁判所基準)での後遺障害の補償を受け取るには、交通事故被害に強い弁護士への無料相談が不可欠です。遠慮なくリンクスの無料相談をご利用ください。
法律事務所リンクスの弁護士が無料電話相談で分かりやすく説明
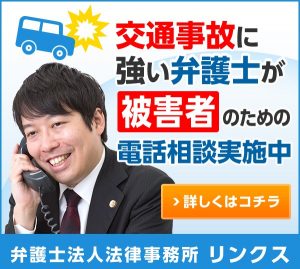 法律事務所リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、2000人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。
法律事務所リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、2000人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。
そして、1500人以上の交通事故被害者の方に適正な補償を実現させてきました。
法律事務所リンクスでは、無料電話相談を実施しておりますので、お気軽にお問合せください。
このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。