日本で死亡事故にあった中国人のご遺族が4000万円の賠償金を獲得した事例

中国人の死亡事故の賠償金は弁護士への依頼で変わる
弁護士のサポートで資料収集から交渉まで安心
 日本で中国籍の方が死亡事故に遭った場合でも、日本の法律に基づき、日本人と同様に慰謝料や損害賠償を請求することが可能です 。
日本で中国籍の方が死亡事故に遭った場合でも、日本の法律に基づき、日本人と同様に慰謝料や損害賠償を請求することが可能です 。
ただし、相続人の範囲は中国の法律(配偶者・子・父母が第1順位)に基づいて決まる点や、日本のような戸籍制度がなく相続関係の証明が困難な点 、逸失利益の算定方法など、特有の課題が生じます。
この記事では、法律事務所リンクスで中国籍の方の死亡事故を担当した弁護士谷優貴が、こうした制度や国境の壁をどのように乗り越え、約4000万円の賠償金を獲得したかの実例 を交えながら、必要な手続きや資料について具体的に解説します。
電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!
- お電話で
無料相談【全国対応】 - 0120-917-740
受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)
日本で中国人が交通事故に遭ったら、日本で慰謝料は請求できるの?
日本で交通事故に遭い、亡くなられた方が中国籍の場合でも、日本国内で発生した事故に日本の法律(民法・自動車損害賠償保障法)が適用されます。つまり、中国人であっても日本人と同じように、慰謝料や損害賠償を請求することが可能です。 慰謝料とは、交通事故によって生じた精神的苦痛に対して支払われるお金のことです。死亡事故の場合、死亡慰謝料・逸失利益・葬儀費用などが対象になります。これらは日本の自賠責保険(強制保険)と任意保険から支払われます。
自賠責保険と任意保険の違い
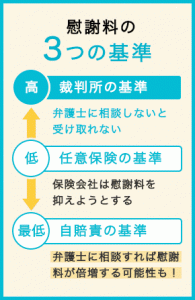 自賠責保険は、すべての自動車に加入が義務づけられている「最低限の補償」を目的とした保険です。主に被害者救済を目的としており、ケガ・後遺障害・死亡それぞれに支払限度額が定められています。死亡事故の場合、上限は3000万円までとされています。自賠責だけでは実際の損害を十分にカバーできないことも多く、慰謝料や逸失利益などがその上限を超えるケースがほとんどです。
自賠責保険は、すべての自動車に加入が義務づけられている「最低限の補償」を目的とした保険です。主に被害者救済を目的としており、ケガ・後遺障害・死亡それぞれに支払限度額が定められています。死亡事故の場合、上限は3000万円までとされています。自賠責だけでは実際の損害を十分にカバーできないことも多く、慰謝料や逸失利益などがその上限を超えるケースがほとんどです。
一方で、任意保険は自賠責では補えない部分を補償するための「上乗せ保険」です。加害者が加入している場合には、弁護士を通じて任意保険会社と交渉し、自賠責保険の支払額を超える部分について賠償金を請求します。任意保険には示談代行サービスも含まれており、交渉の相手方は加害者本人ではなく保険会社となるのが通常です。
このように、自賠責は「最低限の補償」、任意保険は「実損をカバーする補償」という位置づけで、両者を組み合わせることで初めて、被害者の実際の損害に見合った補償を受けることができます。
ただし、中国籍の方の損害賠償請求の場合、制度の理解や書類の準備が難しいという問題が起こります。警察や保険会社からの通知文書はすべて日本語で、しかも専門的な内容です。日本語を読めないまま署名や捺印をしてしまうと、不利な条件で示談が成立してしまう可能性もあります。
また、中国籍の方が亡くなられた場合、日本のような戸籍制度がない国では、家族関係や身分関係を証明する書類が存在しないことがあります。そのため、「相続人であること」を証明できず、慰謝料請求の手続きが進まないことも少なくありません。 しかし、弁護士を通じて手続きを進めれば、これらの問題は一つずつ解決できます。弁護士が代理人として保険会社と交渉し、必要書類を収集・整理し、交渉の全過程を日本語で代行します。
外国人であっても、日本国内で事故に遭った以上、法の下で保障される権利は平等です。 「日本語ができないから無理」「外国人だから難しい」と諦める必要はありません。弁護士が介入すれば、制度の壁を超えて正当な補償を受けることができますので安心してご依頼ください。
誰が請求できる?家族・親族の範囲と中国人特有の相続手続き
交通事故で亡くなられた場合、慰謝料を請求できるのは亡くなった被害者の法定相続人です。ただ、相続人全員が請求しないと、それぞれの相続持分に応じた慰謝料しか支払われないため、実務上では相続人全員が請求手続に関与することがほとんどです。ただ、中国国籍の方がお亡くなりになった場合、どのようにして相続人全員から依頼を受けるのか、そもそも誰が相続人となるのかということも含めて問題になります。
日本と中国における相続人の違い
「誰が相続人になるか」は、日本と中国で法律が異なります。まず、日本の法律(民法)では、次のように定められています。
- 配偶者は常に相続人となります。
- 第1順位は子、第2順位は父母、第3順位は兄弟姉妹です。
配偶者と子が相続人の場合は、それぞれ2分の1ずつ、 配偶者と父母が相続人の場合は、配偶者が3分の2、父母が3分の1、 配偶者と兄弟姉meが相続人の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。 このように、日本では「配偶者は常に相続人」とされ、血縁関係の濃さや経済的依存関係に基づいて、相続の順位と割合が細かく定められています。
これに対して、中国の法律では、相続順位は次のように定められています。
- 第1順位:配偶者・子・父母
- 第2順位:兄弟姉妹・父方の祖父母・母方の祖父母
中国では、第1順位の相続人(配偶者・子・父母)の相続分は原則として均等に分けられます。 つまり、配偶者と父母と子が同順位に並び、いずれも平等に相続するということになっております。これが、日本の相続における法律との大きな違いです。 これは、中国における「年長者を敬う」文化的価値観が法律の構造にまで反映されているためにこのような法制度になっているのです。日本では、子を中心に遺産を承継させるという発想になっていますが、中国では被相続人の親も子も同等に遺産を承継させる発想に基づく法律の制度となっているのです。
このように、日本と中国では相続の仕組みが大きく異なりますが、日本の法律では、「相続は、被相続人の本国法による。」と定められています。そのため、中国人であれば、その相続については中国の法律が適用されます。 したがって、日本で中国国籍の方が亡くなられた場合には、日本法の法律に基づいて損害賠償を請求していくことができますが、請求できる相続人には中国の法律に基づいて相続人となる者が請求することできるという点に注意が必要となります。
つまり、中国籍の方が交通事故で死亡した場合、当該被害者の損害賠償を請求できるのは、交通事故で亡くなった被害者の相続人となるところ、その相続人とは、死亡した被害者の配偶者、子及びその父母ということになります。 日本人が交通事故で亡くなった場合、その被害者に配偶者と子と父母がいるときであっても、配偶者と子のみが亡くなった方の損害賠償請求をすることができる相続人となりますが、中国籍の方が交通事故で死亡した場合、その父母も損害賠償請求をすることができる点に注意が必要となります。
どのようにして相続人らから必要な資料を取り寄せるか
 相続人が中国に住んでいる場合、当該相続人からも委任状や契約書を取り付ける必要があります。相続人の中に、日本に来られない高齢の父母が含まれる場合には、ビデオ通話や郵送、日本で暮らしている他の相続人に協力してもらう等をして委任状やご契約書をいただき、署名確認を行い、柔軟な方法で代理手続を整えています。 また、委任状だけでなくその相続人が当該被害者の相続人かどうかもあわせて立証する必要があります。
相続人が中国に住んでいる場合、当該相続人からも委任状や契約書を取り付ける必要があります。相続人の中に、日本に来られない高齢の父母が含まれる場合には、ビデオ通話や郵送、日本で暮らしている他の相続人に協力してもらう等をして委任状やご契約書をいただき、署名確認を行い、柔軟な方法で代理手続を整えています。 また、委任状だけでなくその相続人が当該被害者の相続人かどうかもあわせて立証する必要があります。
この相続人の確認を中国の書類で行わなければならないため、中国の制度上の立証方法を活用しなければならない場合もあります。日本では戸籍謄本を取得すればすぐに家族関係が証明できますが、中国では同等の書類が存在しないため、「親子関係」や「配偶者関係」を示す複数の証明書を組み合わせて、実質的に立証していく必要があります。一般的には、公証書といって日本の領事館が発行する中国における身分関係を示す証書を発行していただくことが多いです。ただ、その書類は中国語で記載されているので、それの日本語訳したものを自身で作成して提出していくことになりますが、それだけでは足りないと保険会社から言われるケースもあります。
資料の収集については、どういった資料が必要になるかを事前に知っておくことで手続きを簡略化することができますので、事故から早い段階で弁護士にご依頼されることをおすすめします。弁護士がどの資料をどのように整えれば法的に有効な証明となるのかを設計し、保険会社が納得できる形で書類を収集・整理して提出することで、中国籍の遺族でも日本の保険制度のもとで慰謝料請求を進めることが可能となります。 ただ、この資料の収集・整理には多くの手続きと保険会社との交渉を要するため、迅速に行うためにも弁護士に依頼して手続きを代わりに行ってもらうことが解決への近道になります。
慰謝料や逸失利益を請求するために必要な資料は?
慰謝料や損害賠償を請求するには、事故と被害の事実を証明する資料が必要です。一般的に、以下のような書類が求められます。
死亡診断書または死体検案書
親族関係を示す書類
他の相続人となる者が死亡している場合には、その相続人が死亡していることを示す資料(墓碑写真など)
収入証明(給与明細など)
葬儀費用の領収書
本人確認書類(パスポート・在留カードなど)
中国国籍の方の場合、これらを日本の形式に合わせて提出することが難しいことがあります。弁護士が関与し、どの資料をどこで入手できるのかを具体的に指示し、入手後は必要に応じて日本語訳を行い、整理します。 現地でどうしても取得できない資料がある場合には、宣誓書や写真などで補うことも可能です。中国で発行された公的書類を日本の保険会社に提出する場合、そのままでは受け付けられないことがあります。多くの書類は中国語で作成されるため、日本語訳の添付が必要です。翻訳は弁護士が内容を確認し、正確性を証明したうえで提出することで信用性が高まります。
中国人の逸失利益算定のポイント
 死亡慰謝料と並び、損害賠償額の中で大きな割合を占めるのが逸失利益です。逸失利益とは、将来得られるであろう利益のことをいいます。 外国人の場合、日本に住み続けるのか、それとも帰国するのかによって、将来得られる収入は大きく異なります。
死亡慰謝料と並び、損害賠償額の中で大きな割合を占めるのが逸失利益です。逸失利益とは、将来得られるであろう利益のことをいいます。 外国人の場合、日本に住み続けるのか、それとも帰国するのかによって、将来得られる収入は大きく異なります。
この点について、参考になる裁判例として、最高裁平成9年1月28日判決があります。 この判決は、外国人労働者が日本で事故に遭った場合の逸失利益算定の考え方を示した重要な判例となっております。 最高裁は、 「当該外国人がいつまで我が国に居住して就労するか、その後どの国で生活するかなどを証拠資料に基づき相当程度の蓋然性をもって予測し、将来の収入状況を推定すべきである。よって、日本での滞在可能期間内は日本の収入を基礎に、その後は想定される出国先(多くは母国)での収入を基礎に算定するのが合理的である。」 と述べました。
また、滞在期間の認定にあたっては、 「来日目的、事故当時の本人の意思、在留資格の有無と内容、 在留期間、更新の実績や蓋然性、就労の実態などを考慮して判断すべき」 としています。 つまり、被害者がどのくらい日本で働くことが現実的に見込まれるのかを資料で示すことで、日本ての収入を長く認めてもらうことが可能になります。 一方で、母国へ帰る蓋然性が高い場合には、その後の期間については母国の平均収入を基礎に算定することになります。
弁護士は、被害者の在留資格・更新の実績・就労状況・家族の居住実態などを整理し、 「日本での滞在と就労が相当期間続く」ことを資料で裏づけて主張します。 これにより、より現実的で公平な逸失利益の算定を実現できます。 日本国籍ではないからといって低く見積もられるべきではありません。実際の生活実体に即した数字を構築できるかどうかが弁護士の腕の見せどころであり、逸失利益を最大化できることが、依頼する大きなメリットの1つとなります。
領事館でも断られた…それでも諦めないために弁護士ができること
 日本の領事館や現地の行政機関に相談しても、「証明書は発行できない」と言われるケースは少なくありません。たとえば、両親の死亡証明や子どもの有無、配偶者関係など、日本の保険会社が求める形式の書類は、中国の制度上存在しないことが多いのです。
日本の領事館や現地の行政機関に相談しても、「証明書は発行できない」と言われるケースは少なくありません。たとえば、両親の死亡証明や子どもの有無、配偶者関係など、日本の保険会社が求める形式の書類は、中国の制度上存在しないことが多いのです。
弁護士が関与すれば、発行できない書類を他の方法で補うことができます。日本の領事館や中国の現地で発行される公証書による証明書と親族や知人の宣誓書、お墓の写真、家族の通信記録や写真などを複数組み合わせて提出する方法があります。弁護士は、これらの資料の信用性を高めるため、文書ごとに説明書及び意見書を添付し、「なぜこの資料で足りるのか」を法的に整理して主張します。さらに、弁護士は、複数の資料を単に提出するのではなく、それぞれの関係性を整理して「家族関係を一連のストーリーとして示す」ことに重点を置きます。
たとえば、お墓の写真に写る日付や墓碑の文字、通信履歴の日付などを突き合わせ、時系列で一貫性を立証します。また、提出書類にはすべて日本語訳を添付し、翻訳文には弁護士が署名を行って信頼性を担保します。 このように、形式的な公文書がなくても、複数の資料を「総合的に信用できる証明」として構成し、保険会社に理解してもらうことが可能です。制度の違いを超えて、実質的な真実を示すことこそ、弁護士の専門的な役割なのです。
また、手続面だけでなく、精神面・生活面のサポートも弁護士の役割です。 葬儀費用の支払いが難しい場合には、葬儀社に対して支払い猶予を交渉することもできます。 弁護士が間に入り、「保険金の入金後に必ず支払う」との旨を文書で示すことで、トラブルを防ぐことができます。 こうした細やかな支援によって、遺族の精神的負担を軽減し、前に進む力を取り戻してもらうことができます。
領事館で断られても、弁護士の知恵と工夫で請求を実現することは可能です。 法制度と文化の“間”をつなぐのが、弁護士の役割です。 こういった交渉が不可欠となるケースがほとんどのため、中国籍の方が交通事故でお亡くなりになった場合には、まず相談していただきたいです。必要な資料や道筋を丁寧に説明させていただきます。
弁護士が徹底サポート!国境と制度の壁を越え、約4000万円の賠償を実現した実例
相談のきっかけ
 これは、中国国籍の母(約75歳)が日本に旅行に来ていた際に、交通事故に遭い突然命を落としたため、そのご息女から依頼を受けた事例です。
これは、中国国籍の母(約75歳)が日本に旅行に来ていた際に、交通事故に遭い突然命を落としたため、そのご息女から依頼を受けた事例です。
母が交通事故で突然亡くなったことから、ひどく動揺しており、母の損害賠償請求をどうしたらいいのか、日本では損害賠償請求ができないのか、中国に在住している父もいるが日本に来ないといけないのか、必要な資料にはどういったものがあるのか、自身でそれを集めないといけないのか等、彼女が抱えていたのは損害賠償ができるのかという根本的な不安と、必要な書類が何一つ分からないという混乱でした。
弊所に相談があったのは、事故から間もない時期で、上記の内容の相談を受け、すぐに受任することとなりました。受任した後も、葬儀の準備も十分に整わないまま、日本の保険会社から送られてきた分厚い書類を前に、「どこに何を書けばいいのか」「このままでは何も進まない」と途方に暮れていましたが丁寧にどういったことを書けば良いかを説明して、少しでも混乱を招かないようにアドバイスさせていただきました。
リンクスの弁護士の活躍ポイント
 依頼当初、依頼者が最も不安を抱えていたのは、相手方の保険会社とのやり取りでした。保険会社からは日本語で書かれた多くの書類が届き、専門的な内容を理解できず、どのように返答すべきか分からないまま日数だけが経過していました。さらに、事故直後で葬儀の準備も整わず、葬儀費用を誰が、いつ支払うのかという現実的な問題にも直面していました。実際に、保険金の支払いが確定していなかったため、葬儀社への支払いを保留していたのです。
依頼当初、依頼者が最も不安を抱えていたのは、相手方の保険会社とのやり取りでした。保険会社からは日本語で書かれた多くの書類が届き、専門的な内容を理解できず、どのように返答すべきか分からないまま日数だけが経過していました。さらに、事故直後で葬儀の準備も整わず、葬儀費用を誰が、いつ支払うのかという現実的な問題にも直面していました。実際に、保険金の支払いが確定していなかったため、葬儀社への支払いを保留していたのです。
この状況を受け、リンクスの弁護士が葬儀社に直接連絡を取り、「保険金が支払われ次第、必ず支払いを行う」との旨を丁寧に説明し、葬儀会社にもご理解をいただき、一定期間支払いを猶”予してもらう交渉を行いました。また、保険会社にも並行して状況を説明し、支払見込み時期や必要書類の確認を進めることで、依頼者が二重に不安を抱えることのないように配慮しました。 弁護士が交渉の窓口となったことで、依頼者は葬儀や遺族との連絡に専念でき、感情的にも落ち着きを取り戻すことができました。法律的な手続だけでなく、「いま何に困っているのか」「どこに連絡すべきか」という生活上の問題を一つずつ整理して支えたことが、結果的に早期解決にもつながったのです。
書類も制度も“ないものだらけ”からのスタート
 このケースでは、死亡慰謝料を請求するにあたり、日本の保険会社が相続人関係を確認するための戸籍謄本や死亡証明を求めてきました。つまり、お亡くなりになった交通事故被害者の相続人が誰で何人いるのかをまずは確定しなければならなかったのです。相続人が明らかにならない限り、損害賠償請求をできる人物が他にもいるということになり、保険会社は示談ができないからです。
このケースでは、死亡慰謝料を請求するにあたり、日本の保険会社が相続人関係を確認するための戸籍謄本や死亡証明を求めてきました。つまり、お亡くなりになった交通事故被害者の相続人が誰で何人いるのかをまずは確定しなければならなかったのです。相続人が明らかにならない限り、損害賠償請求をできる人物が他にもいるということになり、保険会社は示談ができないからです。
しかし、中国には日本の戸籍に相当する制度がなく、同様の書式も存在しません。領事館に相談しても、「死亡証明書や相続人証明は発行できない」との回答でした。ですので、「必要だが存在しない書類」をどうやって補うかという難題が立ちはだかりました。上述したように、中国の法律では相続人は、配偶者、子、その父母となります。ですので、まずはその被害者の父母が、被害者の死亡時には既に亡くなっていることを示す必要がありました。
リンクスの弁護士が、日本で暮らす依頼者及びそのご家族と密に連携し、被害者の父母が既にお亡くなりになっていることを示す資料として、両親の死亡を証明するためのお墓の写真、父母は既に亡くなっていることを示す宣誓書(念書)など、現地で収集可能な範囲の資料を一つずつ集めていきました。これらの資料は日本の形式に沿ってはいませんが、リンクスの弁護士が法的な意味づけと背景説明を文書化し保険会社に提出しました。
その際、「中国ではこれ以上の公的証明は存在しない」「これが最も合理的で信頼性のある立証手段である」と明確に説明する文書も添付しました。さらに、提出資料にも一定の日本語による補足を添付し、各証明資料の作成経緯や入手先、撮影日などを明示しました。これにより、保険会社が内容を理解しやすくなるだけでなく、資料の信頼性も高まりました。また、翻訳文についても弁護士が確認していることを付記した文書を添付することで責任を明確化し、「形式は異なっても実質的な証明力がある」ことを示す形で整理しました。 これらの作業を通じて、被害者家族の努力と現地での立証の難しさを丁寧に伝えることで、書類不足を理由に手続きが止まることを防ぎ、保険会社の理解と承認を引き出すことができました。
「形式ではなく実質」を理解してもらうための交渉
 保険会社は当初、慎重な態度を示しました。なぜなら、そもそも保険会社でも中国国籍の方が死亡事故に遭った場合に、請求が認められるために必要となる資料が定まっていないからです。 そのため、必要となる書類を保険会社から言われることはなく、こちらが必要と考える資料を提出して、この資料で十分であると主張する意見書を合わせて提出し、説得できてはじめて保険会社が保険金を支払うかどうかを決めるのです。
保険会社は当初、慎重な態度を示しました。なぜなら、そもそも保険会社でも中国国籍の方が死亡事故に遭った場合に、請求が認められるために必要となる資料が定まっていないからです。 そのため、必要となる書類を保険会社から言われることはなく、こちらが必要と考える資料を提出して、この資料で十分であると主張する意見書を合わせて提出し、説得できてはじめて保険会社が保険金を支払うかどうかを決めるのです。
リンクスの弁護士は対立ではなく、保険会社を納得できるような交渉を重ねて、保険会社からあとは、どういった資料があれば保険金が支払われるのかと交渉を重ねることを心がけました。 資料の信頼性を支えるために、撮影日や撮影者の確認、第三者の陳述書なども追加し、「不備」ではなく「合理的代替」であることを根気強く説明しました。 時間をかけた交渉の末、保険会社は相続人の特定を正式に認めました。
また、交渉の過程では、弁護士が日本の民法や自賠責保険制度の趣旨を踏まえ、「形式的な証明書がなくても、実質的に相続関係が明らかであれば支払いを拒む理由はない」と法的に整理して説明しました。さらに、相続人確認の目的が「重複支払いの防止」であることを踏まえ、提出資料がその目的を十分に果たしていることを丁寧に論証しました。 こうした法的根拠に基づいた誠実な交渉姿勢が、保険会社の理解を得る決め手となり、形式ではなく実質を重んじた柔軟な対応を引き出すことができました。
賠償金額の算定と粘り強い交渉
 次に課題となったのは、逸失利益と過失割合の調整です。リンクスの弁護士は、亡くなられた方の年齢や生活状況を考慮し、日本で一般的に使われる「主婦モデル・75歳以上の平均余命」を基準に逸失利益を算定しました。また、事故態様から20%の過失が指摘されましたが、現場状況を分析し、その過失が損害全体を不当に減らすことのないよう粘り強く交渉しました。結果として、保険会社は弁護士の主張を全面的に受け入れ、総額約4000万円の賠償金を支払うことを承諾しました。形式上の壁を越え、実質的な公正を実現できた瞬間でした。
次に課題となったのは、逸失利益と過失割合の調整です。リンクスの弁護士は、亡くなられた方の年齢や生活状況を考慮し、日本で一般的に使われる「主婦モデル・75歳以上の平均余命」を基準に逸失利益を算定しました。また、事故態様から20%の過失が指摘されましたが、現場状況を分析し、その過失が損害全体を不当に減らすことのないよう粘り強く交渉しました。結果として、保険会社は弁護士の主張を全面的に受け入れ、総額約4000万円の賠償金を支払うことを承諾しました。形式上の壁を越え、実質的な公正を実現できた瞬間でした。
弁護士の役割は「法を使う」だけではない
手続きの間、ご遺族は深い悲しみの中にありました。書類作成の際には涙を流され、今回の突然な事故による理不尽さと辛い気持ちを語られました。リンクスの弁護士は、ただ法的代理人として動くだけではなく、精神的な支えとして、逐一手続きの進捗を説明し、「今できることを、私たちがすべてやります」と何度も繰り返しました。葬儀費用の支払いについても、保険金の入金を待たなければならない状況だったため、リンクスの弁護士やスタッフが葬儀社に直接交渉し、「支払いを待ってもらう」合意を取り付けました。これにより、ご遺族は金銭面の心配をせず、葬儀や遺族との話し合いに専念することができました。
さらに、弁護士は単に金銭的補償を実現するだけでなく、依頼者が抱える日常生活上の不安にも寄り添いました。事故後しばらくは、書類や保険会社からの通知を見ることさえ辛く、気持ちが整理できない時期もありました。リンクスの弁護士やスタッフは、必要な手続きを段階的に整理し、「今やるべきこと」「後からで大丈夫なこと」を一つずつ説明し、依頼者の負担を減らす工夫を続けました。また、保険会社との連絡窓口をすべて引き受け、依頼者が精神的に追い詰められないよう調整しました。こうした心のケアと実務支援を両立することこそ、法律事務所の本当の役割だといえます。
国境を越えて、想いをつなぐ
この事例が示すように、中国国籍の方が被害にあっても日本の法律のもとで慰謝料を請求することは可能です。大切なのは、制度の違いを理解した上で、正しい順序で動くことです。法律事務所リンクスでは、書類をそろえること以上に不安を払拭できるように心がけ、解決の道筋を正確に説明できるように配慮しています。「日本の制度は難しそう」「言葉が通じないから無理だ」と感じている方も、まずは相談してみてください。国境を越えても、正しい手続きを重ねれば、あなたの権利は守られます。私たちは、その道を一歩ずつ、ともに歩むお手伝いをいたします。
法律事務所リンクスは死亡事故の解決実績多数
 法律事務所リンクスの弁護士は、5000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、2500人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。その中で、数多くの死亡事故を解決し、適正な補償を実現させてきました。
法律事務所リンクスの弁護士は、5000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、2500人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。その中で、数多くの死亡事故を解決し、適正な補償を実現させてきました。
法律事務所リンクスでは、死亡事故で適正な補償をお受け取りになられたい方 をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談・電話相談を実施させて頂いておりますので、次のバナーから是非ご利用ください。
このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。






