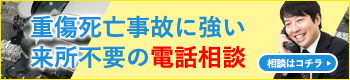【むち打ちによる耳鳴り】交通事故が原因の後遺障害に必要な検査は?

耳鳴りのポイントは客観的な検査による証明。
症状がある方は早く専門医の受診を。
むちうちで耳鳴りが起こるメカニズムは、①むちうちで首の近くにある自律神経の中継地点が刺激され、②自律神経の1つである交感神経が過度に興奮し、③脳や内耳の血管が収縮して血流が低下し、④内耳が酸素や栄養不足に陥って聴覚細胞が機能不全を起こし、⑤「キーン」「ジー」といった異常な電気信号を脳に送り続け、⑥脳がこの信号を「耳鳴り」として認識するというものです。
むち打ちによる耳鳴りが続く場合、後遺症が残存したと評価されて、後遺障害12級または14級が認められることがありますが、「後遺障害」として認定されるかどうかは、 交通事故の専門知識と、医学的知見に基づいた精密な立証 が不可欠となる、非常に難しい問題で、特に、自賠責保険の認定基準では、「難聴」を伴わないと判断された耳鳴りは、原則として「非該当」という非常に厳しい判断が下されてしまいます。
 法律事務所リンクスには、耳鳴りの「非該当」の壁 を、専門的な医学的知見と豊富な経験事例を踏まえた的確な主張により打ち破り、後遺障害 14級を獲得したという解決事例があります。
法律事務所リンクスには、耳鳴りの「非該当」の壁 を、専門的な医学的知見と豊富な経験事例を踏まえた的確な主張により打ち破り、後遺障害 14級を獲得したという解決事例があります。
このページでは、法律事務所リンクスの後遺障害に精通している弁護士新居功韻が、むち打ちによる耳鳴りの発生メカニズムから、後遺障害認定の具体的な検査方法、そして自賠責保険の厳しい認定基準をクリアするための弁護士の「具体的戦略」までを、わかりやすく徹底解説します。
交通事故後の耳鳴りによる後遺障害12級の獲得事例や慰謝料の計算方法については、「事故後耳鳴りが治らない?後遺障害診断書で12等級認定&逸失利益の相場獲得」をご覧ください。
電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!
- お電話で
無料相談【全国対応】 - 0120-917-740
受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)
むち打ちによる耳鳴りの発生メカニズムと種類:なぜ、首の損傷が耳に響くのか?
まずは、「なぜ、首のむち打ちで耳鳴りが起こるのか?」という、多くの被害者の方が疑問に思う、交通事故における耳鳴りの 医学的・生理学的背景 について、詳しくご説明します。
1. むち打ちと耳鳴りを結びつける「自律神経の乱れ」
交通事故の衝撃は、単に筋肉や骨にダメージを与えるだけではありません。特に、首(頸部)には、私たちの身体のあらゆる機能をコントロールする 非常に重要な神経系 が集中しています。
(1) 頚部の神経系の構造と事故の衝撃
 頚椎と靭帯・筋肉の損傷: 追突などの強い衝撃(加速度)により、首が鞭のようにしなる(むち打ち)ことで、頚椎周辺の靭帯、筋肉、関節包などが損傷を受けます。この損傷自体が、首の痛み(頚部痛)の主原因です。
頚椎と靭帯・筋肉の損傷: 追突などの強い衝撃(加速度)により、首が鞭のようにしなる(むち打ち)ことで、頚椎周辺の靭帯、筋肉、関節包などが損傷を受けます。この損傷自体が、首の痛み(頚部痛)の主原因です。
星状神経節と交感神経の過興奮: 首の前側、のど仏の奥あたりには、「星状神経節(せいじょうしんけいせつ)」 と呼ばれる、自律神経の大きな中継地点があります。これは、心臓の鼓動、血圧、発汗など、生命維持に不可欠な機能をコントロールする 「交感神経」が多く集まっている場所です。
衝撃による神経の圧迫・刺激: むち打ちにより、首の筋肉の緊張や炎症、あるいは直接的な刺激によって、この星状神経節を含む 交感神経が過度に興奮 してしまいます。
(2) 自律神経の乱れが引き起こす耳の機能不全
 自律神経は、脳や内耳(聴覚や平衡感覚を司る器官)への血流をコントロールしています。交感神経が過度に興奮すると、以下のメカニズムで耳鳴りが発生すると考えられています。
自律神経は、脳や内耳(聴覚や平衡感覚を司る器官)への血流をコントロールしています。交感神経が過度に興奮すると、以下のメカニズムで耳鳴りが発生すると考えられています。
血管の異常な収縮: 過度の交感神経の興奮は、脳や内耳の 血管を収縮 させ、血流を低下させます。
内耳の酸素・栄養不足: 内耳(蝸牛)にある聴覚細胞は、非常に酸素不足に敏感です。血流低下により、内耳が酸素や栄養不足に陥ると、機能不全を起こします。
異常な電気信号の発生: 機能不全を起こした聴覚細胞が、 「キーン」「ジー」といった異常な電気信号 を脳に送り続け、これが「耳鳴り」として認識されます。
この一連の症状は、しばしば バレー・リュー症候群(頚部交感神経症候群)や頚性神経筋症候群 と呼ばれ、耳鳴り、めまい、頭痛、吐き気、肩こりなど、多岐にわたり不定愁訴(ふていしゅうそ)を伴うことが特徴です。
知っておきたいポイント:
むち打ちによる耳鳴りは、耳鼻科的な「内耳の直接的な損傷」が認められなくても、自律神経系の影響(頚椎捻挫)が原因で発生します。
症状は事故直後だけでなく、自律神経の乱れが顕在化する 数週間後 に現れるケースもあり、症状が出たらすぐに医師に申告し、カルテに記録してもらうことが極めて重要です。
2. 耳鳴りの種類と特徴:後遺障害認定に不可欠な情報
耳鳴りには、様々な音の種類や聞こえ方があり、これらを正確に医師に伝えることが、後遺障害認定のための診断書作成において非常に重要な要素になります。
| 項目 | 特徴(医師への申告・カルテ記載の重要性) |
| 音の種類 | 「キーン」「ジー」「ピー」といった単調な音(純音性耳鳴)、あるいは「ボー」「ザー」といった雑音(ノイズ性耳鳴)。事故との関連で多いのは「キーン」という高音性のものです。 |
| 聞こえ方 | 常時聞こえている(常時耳鳴)、時々聞こえる、脈打つように聞こえる(拍動性耳鳴)など。「常時」であることの立証が、認定要件の根幹です。 |
| 周波数(高さ/ピッチ) | 低い音、高い音など、 どの高さの音で耳鳴りがしているか 。後述のピッチマッチ検査で特定され、この周波数での聴力低下が難聴の立証の鍵となります。 |
| 大きさ(ラウドネス) | 「微か」「我慢できないほど大音量」など、耳鳴りの音量。後述のラウドネスバランス検査で客観的な大きさ(デシベル)が測定されます。 |
交通事故による耳鳴りの場合、特に聴力検査で異常が無いとされる高音域(8000Hz以上)で耳鳴りを感じるケースがあり、これが一般的な「難聴」の基準(6分法)から外れ、後遺障害認定を難しくする最大の原因となっています。
自賠責保険の「耳鳴り」後遺障害認定基準の壁:なぜ「非該当」になるのか?
自賠責保険が耳鳴りを後遺障害として認めるための基準は、非常に厳格で、その構造を理解することが、適切な対応の第一歩となります。
1. 「難聴に伴い」の要件が難関となる理由
自賠責保険が耳鳴りに対して後遺障害を認定するのは、原則として難聴(聴力低下)を伴うものに限られます。この「難聴に伴い」という要件が、むち打ちによる耳鳴りの認定における、最大の壁となります。
| 等級 | 認定基準(自賠責保険・労災保険基準) |
| 12級相当 | 難聴に伴い 著しい耳鳴りが常時あると、 耳鳴りに係る検査によって 客観的に評価できるもの。 |
| 14級相当 | 難聴に伴い 常時耳鳴りがあることが、 合理的に説明できる もの。 |
(1) 「難聴」を伴わないと判断される典型例
むち打ちによる自律神経系の影響で生じる耳鳴りでは、以下の理由から「難聴」を伴わないと判断され、「非該当」となるケースが頻発します。
高音域のみの聴力低下: 耳鳴りの原因となる高音域(4000Hzや8000Hz)でのみ、軽度の聴力低下がある。
6分法による「正常」評価: 後述の自賠責の聴力評価方法(6分法)を用いると、上記1.の軽度な高音域の低下が平準化され、「難聴なし(正常値)」と判断されてしまう。
耳鳴りの客観的証拠不足: ピッチマッチ・ラウドネスバランス検査などの 耳鳴りに係る検査 を受けていない、または受けたが結果が不明瞭である。
2. 認定の判断基準となる「聴力」の測定方法:自賠責の基準と耳鳴りの課題
後遺障害の判断においては、耳鳴りの存在そのものだけでなく、「難聴」の有無を判断するために、主に以下の方法で聴力が測定されます。
(1) 純音聴力検査と「6分法」の壁
最も一般的な検査で、様々な高さ(周波数)の音が聞こえる最小音量(閾値:いきち)を測定します。
自賠責の聴力障害(難聴)認定基準: 聴力障害(難聴)そのものの後遺障害等級は、以下の「6分法」と呼ばれる計算式により求められます。
平均純音聴力レベル = (A + 2B + 2C + D)/6
A:500Hzの音に対する純音聴力レベル (db)
B:1000Hzの音に対する純音聴力レベル (db)
C:2000Hzの音に対する純音聴力レベル (db)
D:4000Hzの音に対する純音聴力レベル (db)
耳鳴り認定の課題:
この6分法では、日常生活の会話に必要な 500Hzから4000Hz までの聴力を重視して評価されます。
しかし、むち打ちに伴う耳鳴りのケースでは、耳鳴りが生じている特定高音域(8000Hz)のみで聴力低下があることがあり、6分法で計算すると聴力レベルが低く評価され、結果として「難聴なし(正常値)」と判断されてしまいます。
これが、自賠責で「難聴に伴わない」として「非該当」の判断を受ける最大の要因となります。
(2) 耳鳴りの存在を証明する「ピッチマッチ・ラウドネスバランス検査」
これは、耳鳴りの後遺障害認定、特に 12級相当 の認定に不可欠な、 耳鳴りの存在を客観的に裏付ける ための検査です。
ピッチマッチ検査(高さを測る): 被害者の方が訴える耳鳴りと同じ高さ(周波数)の音を探し出し、耳鳴りの音の高さ(ピッチ)を特定します。
ラウドネスバランス検査(大きさを測る): 特定したピッチの音が、どれくらいの音量(デシベル)に相当するのか、耳鳴りの大きさを客観的に測定します。
他覚的所見としての位置づけ: これらの検査は、被害者の主観的な訴えを、客観的な数値として裏付ける「他覚的所見」としての役割を果たし、「常時耳鳴りがあること」の立証に不可欠です。
これらの検査で「常時耳鳴りがあること」を証明できても、前述の通り「難聴を伴い」という要件をクリアできなければ、後遺障害は認められません。
「耳鳴り」で後遺障害等級が認定された場合の後遺障害慰謝料と逸失利益
後遺障害等級(12級または14級)が認定された場合、被害者は主に後遺障害慰謝料と逸失利益の2種類の賠償金を受け取ることができます。
① 後遺障害慰謝料の算定
後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことによる精神的な苦痛に対して支払われるものです。慰謝料にはいくつかの算定基準がありますが、弁護士基準(裁判基準)が最も高額になります 。
等級 | 弁護士基準(裁判基準)の慰謝料額 |
14級 | 約110万円 |
12級 | 約290万円 |
② 逸失利益の算定
逸失利益は、後遺障害によって労働能力が制限され、将来にわたって収入が減ってしまうことに対する補償です 。
逸失利益は、以下の計算式で算定するのが一般的です。
逸失利益= 基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
項目 | 概要 |
基礎収入 | 事故前の年収(給与所得者、自営業者)、または事故前の平均収入(主婦・学生など) |
労働能力喪失率 | 後遺障害により失われた労働能力の割合 |
労働能力喪失期間 | 労働能力が失われる期間(原則として症状固定時から67歳まで) |
等級ごとの労働能力喪失率
- 14級:労働能力喪失率は5%です。
- 12級:労働能力喪失率は14%です。
逸失利益の算定における注意点
耳鳴りなどの症状で後遺障害が認定されても、保険会社は逸失利益の請求に対して「軽微な後遺障害のため、実際の労働能力には影響がない」と主張し、請求を認めない、または減額を求めてくることがあります。逸失利益を適正に獲得するためにも、専門的な知識を持つ弁護士による立証が不可欠です 。
③ 後遺障害認定の重要性
後遺障害が認定されると、被害者が受け取るべき賠償金(後遺障害慰謝料、逸失利益など)は、数百万円単位で増額する可能性があります 。特に「非該当」とされた判断を覆し、14級や12級を獲得するためには、医学的知見に基づいた専門的な立証戦略が不可欠です 。
リンクスの解決事例:自賠責・紛争処理機構の「非該当」を覆し、後遺障害14級を獲得した専門戦略
ここからが、まさに法律事務所リンクスが持つ専門性と実績を証明する、解決事例の詳細です。自賠責保険や紛争処理機構で非該当とされた絶望的な状況を、いかにして覆し、後遺障害等級を獲得したかをご紹介します。
【解決事例の概要】
| 項目 | 状況・診断結果 |
| 症状 | むち打ちに伴う常時耳鳴り(キーンという高音) |
| 聴力低下 | “高音域( 4000Hz, 8000Hz )のみ 軽度低下(20db台) 。6分法で計算すると正常値の範囲内。” |
| 耳鳴り検査 | 8000Hzにてピッチマッチ・ラウドネスバランス検査で 耳鳴りの存在確認 。 |
| 自賠責及び紛争処理機構の判断 | 「難聴を伴い」との自賠責の要件を満たさないとの理由により非該当 。 |
| 争点 | 軽度な 特定音域のみ の聴力低下が、自賠責の認定基準における「難聴」に該当するか。 |
| 最終結果 | 後遺障害等級14級 の認定を獲得。 |
難聴を伴わないとされた判断の壁を破る「二つの戦略」
 被害者の方は、耳鳴り検査で症状が確認できたにもかかわらず、自賠責保険、さらには自賠責保険の判断を審査する自賠責紛争処理機構でも、一貫して「難聴に伴い」との要件を満たさないとして非該当の判断を受けてしまいました。
被害者の方は、耳鳴り検査で症状が確認できたにもかかわらず、自賠責保険、さらには自賠責保険の判断を審査する自賠責紛争処理機構でも、一貫して「難聴に伴い」との要件を満たさないとして非該当の判断を受けてしまいました。
これは、自賠責が、 6分法による平均純音聴力レベルが一定の閾値を超えない限り、「難聴なし」と形式的に判断する 運用に起因していると考えられます。
当事務所は、この形式的な判断を覆すため、以下の二つの専門的な主張を、 裁判所 (または裁判所での和解交渉)にて展開しました。
戦略1:顧問医の医学意見書による医学的観点からみた「難聴」の立証
法律事務所リンクスでは、医学的な知識が不可欠な耳鳴りや自律神経系の障害について、顧問医と緊密に連携を取り、症状の 医学的真実 を立証します。
一般的な難聴基準の問題提起:6分法では測り切れない難聴が医学的に存在することを論理的に主張しました。
耳鳴りの原因と聴力の連関の強調:耳鳴りが客観的に認められた 8000Hz という 特定の高音域 で、被害者には軽度ながらも一貫して聴力低下(20db台)が認められている事実を、データの詳細な分析によって指摘しました。
「難聴」の再定義:顧問医の知見に基づき、特定の音域での聴力低下と一貫した左右差を踏まえ、被害者の聴力低下が 医学的には「難聴」に該当する という 専門的な意見書 を作成し、提出しました。
これにより、自賠責が形式的に判断した「難聴なし」という見解を、 客観的な医学的根拠 をもって否定し、裁判官(または相手方保険会社)の理解を深めました。
戦略2:過去の認定事例に基づく「両耳の左右差」の強調
さらに、当事務所は、過去の膨大な交通事故解決事例の知見を活かし、 聴力の「左右差」という、自賠責の審査基準の裏側にある実務上の重要ポイント を主張に組み込みました。
一貫した左右差の発見とデータ分析:被害者の方の聴力データを、事故直後から症状固定時まで時系列で分析したところ、事故後、一貫して両耳の聴力に左右差(右耳の方が聞こえが悪いなど)が認められていることを発見し、これを証拠として提示しました。
自賠責の審査における実務の指摘:リンクスは、過去の経験事例から、自賠責保険が聴力のレベル(db)だけでなく、 両耳の聴力の比較(左右差)も、「難聴に伴い」という要件を満たすか否かを判断する重要な判断材料 としている事例が存在することを熟知していました。
主張の強化:裁判所に対し、上記自賠責の内部的な判断基準を指摘し、医学的観点のみならず、 自賠責保険の過去の運用に照らしても「難聴に伴い」と認められうる ことを、より強固に裏付けました。この主張は、聴力レベルという形式的な基準にこだわりがちな相手方保険会社に対しても、プレッシャーを与える効果がありました。
裁判所の判断:難聴の要件を認め、後遺障害14級を認定

これらの戦略により、裁判所は、本件の軽度な高音域の聴力低下と一貫した左右差が、「難聴に伴い」との要件を満たすものと判断しました。その結果、裁判所により下記金額の賠償が認められました。
賠償項目 | 裁判所認定額(概算) | 備考 |
後遺障害慰謝料 | 約110万円 | 等級14級に対する慰謝料。弁護士基準(裁判基準)が適用されています。 |
逸失利益 | 約360万円 | 後遺障害により将来の労働能力が失われたことへの補償 です。 |
最終的な総額 | 約600万円 | 治療費、休業損害、傷害慰謝料などを含むすべての損害項目、過失相殺、調整金加算後の合計額。 |
この結果は、むち打ちによる耳鳴りが「難聴を伴い」の要件を満たさないとして非該当(後遺障害慰謝料及び逸失利益が認められない)とされた判断を覆し、後遺障害14級を認めさせたことで、得られた正当な補償です。
この事例からも、耳鳴りの後遺障害認定においては、自賠責の形式的な判断(6分法など)に捕らわれず、医学的知見に基づいた専門的な立証戦略が極めて重要であることが示されています。
耳鳴りの後遺障害認定で「非該当」とならないための注意点と対策
この解決事例が示すように、耳鳴りの後遺障害認定は、単に病院で検査を受けるだけでは不十分です。交通事故被害者の方が、症状にふさわしい補償を獲得するために、 治療初期から弁護士と連携して行うべき対策 をお伝えします。
1. 治療初期から専門的な検査を受け、証拠を揃える
耳鳴りの症状がある場合は、必ず早期に耳鼻咽喉科を受診し、むち打ちの治療と並行して耳の検査も進めることが重要です。
| 対策項目 | 具体的行動と目的 |
| 早期の耳鼻科受診 | 症状を自覚した直後に受診し、「事故との因果関係」をカルテに残す。時間が経つほど因果関係を否定されやすくなります。 |
| 必須検査の実施 | 「純音聴力検査」「ピッチマッチ・ラウドネスバランス検査」は必ず受けて、結果を診断書に添付してもらう。これらは「常時耳鳴りがあること」の客観的な証拠です。 |
| 高音域の聴力への注意 | 一般的な検査の結果が正常でも、「耳鳴りがする周波数(特に4000Hz以上)」での聴力低下がないか、詳細な検査結果を必ず医師に確認してもらい、記録に残す。 |
| 3回検査の実施 | 純音聴力検査は、日を改めて 3回 実施し、そのうち良い方の聴力レベルを除く 2回の平均 で、難聴の等級認定が判断されるため、症状固定までに複数回実施することが望ましいです。 |
2. 症状の一貫性を正確に記録・申告する

自賠責や裁判所は、症状が事故によって生じたこと(因果関係)と、症状が一貫して続いていること(永続性)を重視します。
事故直後からの申告:耳鳴りが事故直後からあった場合は、必ず 診断書やカルテに「耳鳴りあり」と記載 してもらうように、主治医に伝えましょう。
詳細な記録の継続:症状の「 高さ(ピッチ) 」、「 大きさ(ラウドネス) 」、「 常時かどうか 」、「 生活への影響 」などを、 治療日誌 などに細かく記録し、診察の度に医師に伝えましょう。
これが後に「難聴に伴い著しい耳鳴りが 常時ある と評価できるもの」、「難聴に伴い 常時耳鳴りがある ことが合理的に説明できる」という後遺障害の認定基準を満たすための証拠となることがあります。
医師との綿密な連携:医師は治療の専門家ですが、必ずしも後遺障害認定基準の専門家ではありません。後遺障害診断書に「難聴の左右差」や「高音域の聴力低下」が明確に記載されるよう、弁護士と連携して医師に適切な情報提供を行う必要があります。
3. 6分法だけでは不十分!弁護士の専門性が不可欠
本事例のように、自賠責保険の「6分法」の基準では「難聴」に当てはまらない、ある特定音域のみに聴力低下が認められるというケースは多々あります。
| 弁護士に依頼する理由 | リンクスが提供する専門性 |
| 医学的立証の困難さ | 被害者ご自身が、自賠責の基準や医学的な専門知識を駆使して、審査機関と争うのは極めて困難です。 |
| 弁護士の役割 | 弁護士は、「難聴」と「耳鳴り」の存在を医学的に立証し、「難聴に伴い」という要件を満たすよう、法的かつ医学的な論理構成を行います。 |
| 経験事案の活用 | 経験事案が豊富 な弁護士だからこそ、本事例のように、自賠責で非該当とされても、 医学顧問の知見 や 豊富な経験事例 を駆使して判断を覆すことが可能になります。 |
| 適正な賠償金への増額 | 後遺障害が認定されると、 後遺障害慰謝料 や 逸失利益 といった賠償項目が加算され、賠償額の総額が大幅に増額します。弁護士は、最も高い基準である弁護士基準(裁判基準)での増額交渉を行います。 |
法律事務所リンクスがお約束する「耳鳴り」後遺障害サポート
耳鳴りの症状は、見た目ではわからないため、時に保険会社から軽視されがちです。しかし、この症状は、日常生活や仕事に深刻な影響を及ぼす、まぎれもない「後遺障害」です。
法律事務所リンクスは、交通事故の被害者様の「声なき声」を代弁し、正当な補償を獲得するために、以下の強みをもって闘います。
1. 【顧問医との強力な連携】による医学的真実の立証
 耳鳴りや自律神経系の障害は、画像所見(レントゲンやMRI)に異常が現れにくいため、その立証には困難が伴います。
耳鳴りや自律神経系の障害は、画像所見(レントゲンやMRI)に異常が現れにくいため、その立証には困難が伴います。
徹底的な資料分析: 難解な純音聴力検査やピッチマッチ検査のデータ、カルテなどの医学的資料を、専門医(顧問医)と徹底的に分析します。
説得力ある医学意見書の作成: 自賠責の形式的な判断に捕らわれない、 「高音域の聴力低下」や「聴力の左右差」が医学的に「難聴」であることを証明する専門的な医学意見書 を作成・提出し、立証の質を格段に高めます。
2. 【豊富な裁判実績と知見】による戦略的な等級獲得
自賠責保険の非該当の判断は、一度下されると覆すことが困難です。リンクスの実績が、その壁を打ち破ります。
非該当を覆した経験の活用: 自賠責の非該当を覆し、 異議申立てや裁判等で等級を獲得した経験 を活かし、「難聴に伴い」という最も難しい要件をクリアするための具体的な立証戦略を立てます。
紛争処理機構・裁判所での徹底的な争い: 自賠責で非該当となった場合でも、 自賠責紛争処理機構への異議申立 、さらには 裁判 を見据えた準備を行うことで、最終的な等級獲得の可能性を最大限に引き上げます。
3. 【適正な賠償金への増額】による生活の再建
耳鳴りの後遺障害(14級または12級)が認定されることで、被害者の方が受け取るべき賠償金は、非該当の場合と比較して大きく増額します。
後遺障害慰謝料の獲得: 14級の場合、 弁護士基準で約110万円 、12級の場合、 約290万円 という後遺障害慰謝料が加算されます(非該当の場合はゼロ)。
逸失利益の請求: 後遺障害によって労働能力が制限されたことに対する補償である 逸失利益 も請求可能となります。
弁護士基準による増額交渉: 入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益なども、最も高額な弁護士基準(裁判基準)で交渉することで、獲得できる賠償金総額が大幅に増額し、被害者様の生活再建を力強くサポートします。
耳鳴りという辛い症状を抱えながら、保険会社との煩雑な交渉を続ける必要はありません。
自賠責保険で「非該当」とされた方も、諦める前に必ず一度、法律事務所リンクスにご相談ください。
私たちが、あなたの症状にふさわしい正当な補償を獲得できるよう、全力で、そして専門知識をもってサポートいたします。
まとめ:むち打ちによる耳鳴りの後遺障害認定は弁護士に相談を
| 項目 | むち打ちによる耳鳴り 後遺障害認定の真実 | リンクスに依頼するメリット |
| 後遺障害の最大の壁 | 自賠責の「 難聴に伴い 」の要件(6分法での平均聴力レベルのみで判断されがち) | 顧問医の医学意見書 により、高音域の軽微な聴力低下を医学的に「難聴」と認められるとして立証。 |
| 必要な検査 | 純音聴力検査 (複数回)、 ピッチマッチ・ラウドネスバランス検査 | 医師への情報提供を行い、 必要な検査 と 診断書の適切な記載 をサポート。 |
| 認定の秘訣 | 正確な 医学的知識 と 後遺障害認定要件 の理解 | 過去の認定事例を踏まえた 聴力の左右差 の分析により、自賠責の形式的判断を覆す 法的・医学的論理構成 を構築。 |
| 得られる結果 | 後遺障害14級(または12級)の認定と、 適正な賠償金 (弁護士基準)の獲得。 | 賠償金の大幅な増額 と、保険会社との交渉からの解放。 |
「耳鳴りだけでは認定されない」という誤解を捨て、まずは当事務所にご相談ください。あなたの症状は必ず証明でき、正当な補償を獲得できる可能性があります。
リンクスは耳鳴りの後遺障害等級の獲得実績多数
 リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からのご依頼を解決してきました。
リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からのご依頼を解決してきました。
その中で、耳鳴りの後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。
リンクスでは、耳の後遺障害でお困りの方、適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談 をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。
このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。