後遺障害13級の金額や慰謝料は?県民共済や労災も解説

後遺障害13級は弁護士への依頼で数百万超えも
認定がまだの方は早めの相談を
電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!
- お電話で
無料相談【全国対応】 - 0120-917-740
受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)
後遺障害13級の金額や慰謝料は?
後遺障害等級13級の金額は、自賠責基準では139万円ですが、弁護士に依頼したら慰謝料180万円+逸失利益で数百万円~1000万円です。
後遺障害13級の金額は慰謝料と逸失利益の計算から成り立っていますので、保険会社の提示する示談金(賠償金)にもこの2つの項目がありますが、自賠責基準の139万円をそのまま提示してくる場合もあります(労災で後遺障害13級が認定された場合には、障害補償給付として給付基礎日額(給与相当額)×101日分、障害特別一時金として算定基礎日額×101日分、障害特別支給金として14万円が支払われます。)。
それは、保険会社は、自賠責基準に従って支払っている限りは、その金額を後で自賠責から回収できるので、懐が痛まないからです。
しかし、本来支払われるべき後遺障害13級の金額は、このような金額ではありません。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、弁護士に依頼した場合に支払われる後遺障害13級の金額や県民共済の後遺障害等級との関係について、ご説明します。
交通事故の慰謝料全般について詳しくお知りになりたい方は、「交通事故の慰謝料相場!人身事故の賠償金はいくら?」をご覧ください。
労災の後遺障害等級ごとの金額について詳しく知りたい方は、「労災の後遺障害等級の金額は?障害補償給付を等級表でわかりやすく!」をご覧ください。
後遺障害13級の金額の説明を動画でご覧になりたい方はコチラ
後遺障害13級の金額の無料電話相談実施中
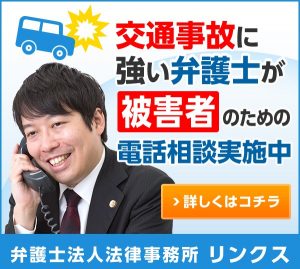 法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、後遺障害等級ごとの金額の見積もりをお伝えしています。
法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、後遺障害等級ごとの金額の見積もりをお伝えしています。
本来支払われるべき後遺障害の金額は裁判所が定めていますが、被害者本人が保険会社と示談交渉をしても、裁判所基準での支払いはしてくれません。
後遺障害等級に合った本来の金額を支払わせるためには、弁護士に相談する必要があります。
交通事故の後遺障害に強い弁護士に無料電話相談されたい方は、0120-917-740にお電話を頂くか、LINEで交通事故の無料相談をお申し込みください。
労災の後遺障害13級について無料相談したい方は、労災専門サイト「労災に強い弁護士への無料相談なら法律事務所リンクス」をご覧ください。
後遺障害13級の慰謝料
後遺症が残ったことで受けた精神的苦痛に対する補償で、後遺障害等級によって決まります。
13級の場合は180万円です。
後遺障害13級の逸失利益
 後遺障害逸失利益は、後遺症が将来の仕事・家事に与える影響に対する補償です。次の3つの数字を掛け合わせて、補償額を決めることになります(参照:「逸失利益とは?損害賠償の計算を早見表でわかりやすく解説」)。
後遺障害逸失利益は、後遺症が将来の仕事・家事に与える影響に対する補償です。次の3つの数字を掛け合わせて、補償額を決めることになります(参照:「逸失利益とは?損害賠償の計算を早見表でわかりやすく解説」)。
- 被害者の収入(職がない方の場合は働いたら得られる見込みのある収入)
- 後遺障害等級ごとに決まっている労働能力喪失の割合
- 後遺障害が将来の仕事・家事に影響を及ぼす期間(労働能力喪失期間)
13級の場合、②は9%、③は症状固定から67歳まで(ただし症状によっては5~10年程度に制限されることがある)とされていますので、後遺障害の内容や被害者の収入・年齢によって、次のような後遺障害逸失利益が認められることになります。
| 収入・仕事 | 年齢 | 逸失利益 |
|---|---|---|
| 20代男性(平均賃金) | 25歳 | 547万×0.09×17.4232=857万 |
| 会社員(年収400万) | 40歳 | 400万×0.09×14.6430=527万 |
| 主婦(女性平均賃金) | 55歳 | 372万×0.09×10.8377=362万 |
後遺障害13級の金額の計算
後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を合計した次の金額になります(後遺障害の補償とは別に休業補償や慰謝料は支払われるので、実際に示談する額はより大きくなります。)。
| 収入 | 逸失利益 | 慰謝料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 20代男性 | 857万 | 180万 | 1037万 |
| 年400万 | 527万 | 707万 | |
| 主婦 | 362万 | 542万 |
県民共済に加入している場合の後遺障害等級
県民共済の後遺障害等級は自賠責と1つずれることがあります。県民共済で13級の場合は自賠責で14級、県民共済で12級の場合は自賠責で13級というようにです。
県民共済に加入している場合は、後遺障害13級の認定によって県民共済からも保険金を受け取れる可能性があるので、加入している県民共済に問い合わせてみることをおすすめします。
県民共済は都道府県ごとに名称が異なる(例えば京都府の場合は京都府民共済)ので、問い合わせ先を間違えないようにしましょう。
また、加入している保険の種類や特約(医療特約をつけているかなど)によって、保険金の有無や金額が異なる場合があるので、保障内容をよく確認しておくことも大切です。
例えば、県民共済で一般に評判になる保障内容の例としては、日帰り入院や通院などを含めて総合的に保障するタイプ(総合保障1型、総合保障2型、総合保障3型など)や、一定以上の年齢で加入できる熟年タイプ(熟年2型や熟年4型など)があります。
後遺障害等級第13級の主な認定基準
後遺障害等級第13級の認定基準は、以下のいずれかに該当する場合です。
- 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
- 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
- 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
- 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
- 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 一手(利き手かどうかに関わらず)のこ指の用を廃したもの
- 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの
- 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
- 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
- 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
- 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
後遺障害13級の主な解決実績
後遺障害13級で多いのが下肢の短縮の事例です。下肢の短縮は骨折に伴って生じますので、関節の機能障害や痛みと併合して上位の後遺障害等級が認定されることが多いです。後遺障害等級13級で諦めず、上位の後遺障害等級を狙いましょう。
リンクスの解決事例
リンクスの弁護士のアドバイスで下肢短縮で後遺障害13級を含む併合11級が認定され1800万円を獲得した事例
法律事務所リンクスの弁護士が無料電話相談で分かりやすく説明
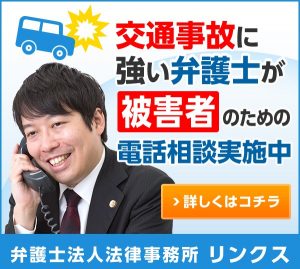 法律事務所リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、2000人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。
法律事務所リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、2000人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。
そして、1500人以上の交通事故被害者の方に適正な補償を実現させてきました。
法律事務所リンクスでは、無料電話相談を実施しておりますので、お気軽にお問合せください。
このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。







