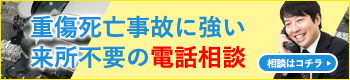【高次脳機能障害1級】高次脳機能障害で後遺障害1級が認められるための自賠責や障害年金の基準は?

高次脳機能障害1級は弁護士への依頼で大幅増額します
認定がまだの方は早めの相談を
電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!
- お電話で
無料相談【全国対応】 - 0120-917-740
受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)
高次脳機能障害1級~自賠責と労災の認定基準の違い
交通事故で高次脳機能障害となった場合に、後遺障害1級に相当する後遺障害慰謝料・逸失利益・介護費の補償を受けるには、原則として自賠責保険で1級を獲得しなければなりません。
自賠責保険で1級を獲得するには、被害者の方の病状が自賠責保険の1級の基準を満していることを証明する必要がありますが、以下のように分かりにくい基準になっているため、医師にきちんと証明してもらう必要があります。
自賠責保険における1級の基準とは?
自賠責保険で高次脳機能障害の1級が認められるには、「神経系統の機能又は障害に著しい障害を残し 、 常に介護を要するもの(身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、 生活維持に必要な身の回りの動作に全面的介護を要するもの)」という基準を満たす必要があるとされていますが、これだけではよく分からないかもしれません。
労災保険における1級の基準とは?
そこで、労災保険の1級の基準を参考にすることがあります。労災保険で1級が認められるには、「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身の回り処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」であることが必要とされています。
その具体例として、「重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの」か「高次脳機能障害による高度の痴ほうや情意の荒廃があるため、常時監視を要するもの」が挙げられています。
労災保険の基準の方がやや詳しいですが、常時介護や常時監視が認められるには、必要な介護の内容や介護の実態を証明する必要がありますし、仮に証明できたとしても、保険会社は裁判をしなければ適正な介護費を支払わないのが現状です。
したがって、高次脳機能障害で1級を獲得しようと考えるのであれば、最初から交通事故に強い弁護士に無料相談し、等級の獲得、介護費の証明から裁判までサポートを受けることが不可欠です。
後遺障害1級の場合の後遺障害慰謝料・逸失利益・介護費用の計算について詳しくお知りになりたい方は、後遺障害1級の慰謝料・逸失利益・介護費の相場が知りたいのですが?をご覧ください。
交通事故による高次脳機能障害や外傷性脳損傷は弁護士に相談して適切な賠償金を
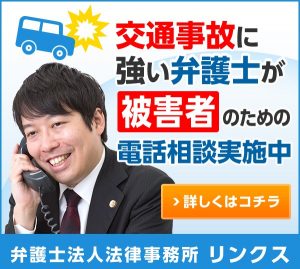 交通事故で脳に損傷を負った場合、重度の意識障害で寝たきりになったり介護が必要になる方もいれば、そこまでには至らないが様々な症状に悩まされる方もいます。様々な症状の中には頭痛やめまい、目・耳の障害、嗅覚・味覚の障害、上下肢のしびれや運動障害などの身体に現れる障害もありますが、他人からは分かりにくい障害もあります。例えば、記憶障害、集中力の低下、作業ができなくなる、感情のコントロールができなくなる、人格の変化等が生じる高次脳機能障害はその1つです。
交通事故で脳に損傷を負った場合、重度の意識障害で寝たきりになったり介護が必要になる方もいれば、そこまでには至らないが様々な症状に悩まされる方もいます。様々な症状の中には頭痛やめまい、目・耳の障害、嗅覚・味覚の障害、上下肢のしびれや運動障害などの身体に現れる障害もありますが、他人からは分かりにくい障害もあります。例えば、記憶障害、集中力の低下、作業ができなくなる、感情のコントロールができなくなる、人格の変化等が生じる高次脳機能障害はその1つです。
このように脳損傷による症状は複雑な上に、高次脳機能障害の場合には第三者に理解してもらえないことが多いため、生活において様々な困難が生じる可能性がありますし、そもそもどのように進めたらよいか分からないという被害者の方やご家族の方もいらっしゃることと思います。
法律事務所リンクスでは、このような高次脳機能障害の被害者の方のサポートに特に力を入れており、高次脳機能障害支援センターの支援マップに支援機関として掲載されており、代表弁護士の藤川は高次脳機能障害支援センターの講師を務めたこともあります。
また、当事務所の弁護士・スタッフの多くが、高次脳機能障害支援センターの研修を受講するなど、高次脳機能障害の被害者の方のサポート体制を整えております。
交通事故による高次脳機能障害の被害者の方やご家族の方のための無料電話相談を実施しておりますので、0120-917-740にお電話を頂くか、LINEで交通事故の無料相談をお申し込みください。
高次脳機能障害の初期対応・病院の選び方について約3分の動画で知りたい方はコチラ
リンクスの弁護士が考える後遺障害1級認定のポイント
リンクスの弁護士の経験からすれば、1級が認められた被害者の方の場合、高次脳機能(精神機能)の異常だけでなく、身体機能に相当な支障が出ていることが多いという印象です。
特に、当初は身体機能にそこまでの支障がなかったが、徐々に身体機能に相当な支障が出てきたという場合には、精神機能の異常に伴って、身体機能に深刻な支障が出てきたことも合わせて証明する必要があります。
リンクスの弁護士が担当させて頂いた被害者様の中には、初診時の意識障害はほぼなかったにもかかわらず、その後、精神機能・身体機能の異常が進行して全介助状態となり、1級となった方がいらっしゃいます。
この方の場合、脳損傷に由来しないものも含めた身体機能の障害により精神機能が悪化して、精神機能の悪化に伴い生命維持に必要な動作について全介助状態になるという悪循環が発生してしまったわけです。
リンクスの弁護士は、医師に文書を作成してもらって、このようなメカニズムを証明することで、自賠責保険に事故による脳の損傷と症状の経過との間に相当因果関係があることを認めさせ、1級の認定を受けることができました。
高次脳機能障害の後遺障害診断書の作成の仕方について約5分の動画で知りたい方はコチラ
高次脳機能障害1級の場合の障害年金
交通事故で高次脳障害1級になった場合、障害年金が支給される可能性が高いです。
障害年金では、高次脳機能障害は、「症状性を含む器質性精神障害」の一部とされており、等級認定基準は以下のとおりです(以下は「国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正について」(平成25年3月29日)より抜粋しました)。
(1) 症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害を含む。)とは、先天異常、頭部外傷、変性疾患、新生物、中枢神経等の器質障害を原因として生じる精神障害に、膠原病や内分泌疾患を含む全身疾患による中枢神経障害等を原因として生じる症状性の精神障害を含むものである。
(2) 各等級等に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの |
2級 | 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 1 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの 2 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの |
障害手当金 | 認知障害のため、労働が制限を受けるもの |
(3) 脳の器質障害については、精神障害と神経障害を区分して考えることは、その多岐にわたる臨床症状から不能であり、原則としてそれらの諸症状を総合して、全体像から総合的に判断して認定する。
(5) 高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活又は社会生活に制約があるものが認定の対象となる。その障害の主な症状としては、失語、失行、失認のほか記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがある。
なお、障害の状態は、代償機能やリハビリテーションにより好転も見られることから療養及び症状の経過を十分考慮する。
また、失語の障害については、本章「第6節 言語機能の障害」の認定要領により認定する。
(6) 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
交通事故に強い弁護士への無料相談が不可欠
このように、明らかに後遺障害1級に該当するように見えても、その証明は必ずしも簡単ではありませんし、仮に1級の認定を受けたとしても、保険会社は「このような重篤な後遺障害の場合には余命が短くなるので、平均余命までの介護費は認められない」だとか「障害者支援や介護保険を利用することで介護費の自己負担は少なくなる」だとか「職業付添人による介護の必要性は認められない」だとかの理由をつけて、できる限り介護費を減らそうとします。
適正な後遺障害等級の認定を受け、きちんとした補償を受け取るには、交通事故被害に強い弁護士への無料相談が不可欠です。遠慮なくリンクスの無料相談をご利用ください。
このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。