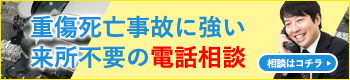交通事故の示談の流れや期間は?弁護士が交渉したらどうなる?

交通事故解決までの流れを知ることで
示談の方法を間違えないようにする。
交通事故の示談とは、交通事故の被害者側と加害者側の話し合いによって、加害者側が被害者側に損害賠償としていくら支払うのか、いつまでにどのような方法で支払うのかなどを合意することです。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、「交通事故の示談とは」「交通事故の示談の注意点」について説明します。
交通事故の示談金の計算方法について詳しく知りたい方は、「交通事故示談金!相場や内訳の計算を弁護士が解説」をご覧ください。
電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!
- お電話で
無料相談【全国対応】 - 0120-917-740
受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)
交通事故における示談とは?
 交通事故の示談とは、交通事故の被害者側と加害者側の話し合いによって過失割合や損害額を決定し、加害者側が被害者側に損害賠償としていくら支払うのか、いつまでにどのような方法で支払うのかなどを合意することです。
交通事故の示談とは、交通事故の被害者側と加害者側の話し合いによって過失割合や損害額を決定し、加害者側が被害者側に損害賠償としていくら支払うのか、いつまでにどのような方法で支払うのかなどを合意することです。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、「交通事故の示談とは」「交通事故の示談の種類・内訳」「交通事故の示談交渉の話し合いの内容」「交通事故の示談の流れ」「交通事故の示談の注意点」などについて詳しくご説明します。
交通事故の示談金の計算方法について詳しく知りたい方は、「交通事故示談金!相場や内訳の計算を弁護士が解説」をご覧ください。
交通事故で示談になると、合意内容を示談書または免責証書に記載することが多く、示談書または免責証書を取り交わすとその合意内容を撤回することは原則不可となります。
一度示談してしまうと取り返しがつかないので、示談する前に弁護士の無料相談を利用することが大事です。
交通事故で示談する前に!リンクスの無料電話相談で損していないかチェック!
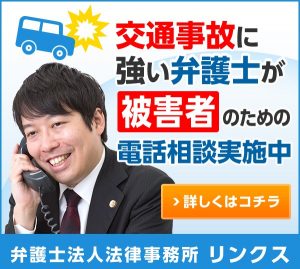 交通事故で示談交渉をする前や示談金の提案を受けた後でも、示談前であれば弁護士の無料相談で適正な示談金額をチェックすることができます。
交通事故で示談交渉をする前や示談金の提案を受けた後でも、示談前であれば弁護士の無料相談で適正な示談金額をチェックすることができます。
法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、交通事故の正しい示談の仕方や適正な示談金の額を分かりやすく説明しておりますので、0120-917-740にお電話を頂くか、LINEで交通事故の無料相談をお申し込みください。
交通事故を弁護士に依頼した場合の示談交渉のメリットについて動画で知りたい方はこちら
交通事故における示談の種類・内訳
交通事故の示談には、人身損害の示談と物損の示談があり、それぞれ種類と内訳が異なります。
人身損害の示談の種類と内訳
人身損害の示談は傷害、後遺障害、死亡の3種類に分かれます。
傷害部分の示談とは交通事故で怪我をしたことによって発生する損害に関する示談であり、後遺障害部分の示談とは怪我が後遺障害として残ったことで発生する損害に関する示談であり、死亡損害の示談とは交通事故で死亡したことによって本人及び家族に発生する損害に関する示談です。
通常はまとめて示談することになりますが、後遺障害が残った場合には別途協議することにして、傷害部分を先行して示談することもあります。
それぞれの内訳を表にしましたのでご覧ください。逸失利益という言葉は聞きなれないかもしれませんが、後遺障害が残ったり事故でお亡くなりになったことで将来得られた収入を得られなくなったことに対する損害賠償のことを意味します。
人身損害の種類 | 主な内訳 |
傷害 | ・治療費 |
後遺障害 | ・後遺障害逸失利益 |
死亡 | ・死亡逸失利益 |
物損の示談の種類と内訳
物損の示談は、修理が相当な場合と修理が相当でない場合(全損の場合)の2種類に分かれます。
修理が相当であるか相当でないかは、修理費が、時価相当額に買替諸費用を加えた金額を上回るかどうかによって決まり、上回る場合には修理するよりも買い替えるのが合理的なので全損となり修理が相当でないことになります。
物損の示談 | 主な内訳 |
修理が相当な場合 | ・修理費 |
全損の場合 | ・時価相当額 |
交通事故の示談交渉で保険会社と話し合いをする内容
では、交通事故の被害者は、保険会社とどのような話し合いをする必要があるのでしょうか。示談交渉の主な内容をご説明します。
慰謝料の示談交渉
慰謝料の金額を決める基準には、低い方から自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準があります。
保険会社は、被害者本人と示談交渉している間は自賠責基準や任意保険基準でしか慰謝料を支払おうとしませんが、弁護士を立てた場合には弁護士基準で支払います。
したがって、慰謝料が問題となる人身事故の場合には、弁護士を立てないと損をすることになります。
詳しくは「交通事故の慰謝料相場!人身事故の賠償金はいくら?」をご覧ください。
過失割合の示談交渉
10対0の事故では問題になりませんが、それ以外の事故で必ず問題となるのが過失割合です。
交通事故の被害者が加害者に請求できるのは、加害者の過失割合分になるので、過失割合は示談金額に大きな影響を与えます。
例えば、交通事故で被害者が受けた損害の総額が1000万円だった場合、10対0の事故であれば1000万円を請求できますが、9対1の事故であれば900万円、8対2の事故であれば800万円になります。
9対1事故の示談金の相場については「9対1事故の示談金相場は?慰謝料や治療費は?むちうち通院なら?」をご覧ください。
8対2事故の示談金の相場については「過失割合が8対2事故の示談金相場は?慰謝料治療費修理代はいくら?」をご覧ください。
過失割合の示談交渉で重要な資料は、警察が事故現場を捜査した結果をまとめた実況見分調書やドライブレコーダー、防犯カメラなどです。
人身事故扱いになっていない場合には実況見分調書は作成されませんので、お互いの言い分が違う場合には、警察に人身事故扱いにしてもらうため、診断書を提出することも検討しなければならなくなります。
後遺障害部分の示談交渉
後遺障害が残った場合、自賠責保険に後遺障害の申請をして後遺障害等級を認定してもらうことになりますが、保険会社は自賠責保険の認定した後遺障害等級に対応する示談金を支払おうとしないことがあります。
このような場合、被害者としては、弁護士を立てて後遺障害が残ったことによってどれくらいの被害を受けているかを主張して示談交渉をすることになりますが、折り合えない場合には裁判をすることになります。
死亡事故の示談交渉
死亡事故の場合、慰謝料や死亡逸失利益の金額が高額となるため、どの基準で示談交渉をするかで示談金額が大きく異なることとなります。
このような場合、弁護士を立てないと、適切な基準の損害賠償金額を受け取ることが難しいでしょう。
交通事故の示談の期間はどれくらいかかる?長引く場合も!
人身損害の示談の期間
人身事故の示談にかかる期間は、交通事故発生からは6か月~1年が多いですが、交渉開始からは2~3か月のことが多いです。
通常の打撲捻挫であれば2~3カ月で完治しますので、その後の交渉の期間を含めても、6か月程度で示談が成立する可能性があります。
これに対して、むちうちで6か月通院した場合、それから交渉になるので、後遺症が残らなくても交通事故発生から8~9か月、後遺症が残った場合には後遺障害等級認定に時間を要するので1年近くかかることもあります。
そして、骨折など完治までに時間がかかるためお怪我の場合には治療期間が1年以上かかることがあり、後遺障害等級認定の期間も合わせると、1年半~2年の期間を要することになります。
示談前でも後遺障害等級が認定されれば、自賠責保険からまとまった金額の保険金を受け取ることができますので、適正な損害賠償を受けたいのであれば示談を焦ってはいけません。
物損の示談の期間
物損の示談の期間は、過失割合や修理費、時価額に争いがなければすぐですが、いずれかに争いがある場合には人身事故の示談と同時期まで待つ場合もあります。
交通事故の示談の流れ
人身事故の示談の流れ
交通事故が発生してから、保険会社から示談金が支払われるまでの基本的な流れは以下の通りです。
- 事故発生
- 入通院
- 休業補償・治療費の打切り
- 後遺障害診断書の作成
- 後遺障害等級認定
- 示談交渉の準備
- 示談交渉
- 示談成立
① 事故発生

「交通事故に遭ったらまず落ち着いて。初期対応を手順に沿って確実に」
交通事故を起こした場合、まずは気持ちを落ち着かせることが重要です。身体的にも心情的にも、突然の事故のショックがあり、多少の動揺はやむを得ない状況ではありますが、まずは冷静になって初期対応を確認し、手順に沿って確実に進めていきましょう。
加害者・被害者を問わず、ドライバーには、適切な初期対応を行うことが法律により義務付けられています。交通事故の発生時に取るべき初期対応とは下記の通りです。
- 運転を停止する
- 負傷者の救護
- 道路上の危険防止
- 警察への通報
- 保険会社への通知
交通事故が発生した場合、被害者・加害者ともにドライバーは運転を停止。負傷者がいる場合、周囲の応援を呼びかけながら119番通報・AEDの手配など、負傷者の救護に必要な対応を取ります。
※交通事故を起こしたドライバーが、負傷者の救護を行わず、その場を離れてしまうと、その行動は「ひき逃げ」となります。事故車の移動、三角表示板や発煙筒などで事故発生を後続の車に知らせ、道路の安全を確保した上で、警察への通報、保険会社への連絡、互いの連絡先交換等を行います。
「警察への通報は加害者・被害者双方に課せられた義務」
交通事故が発生した場合の警察への通報は、道路交通法ですべての運転者に定められた義務です。通報を怠ると、報告義務違反として2ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金を科せられるおそれがあります。
対象が「すべての運転者」なので、警察への届出は加害者だけでなく、被害者にも義務付けられています。
加害者の中には、警察への届出を嫌がり、その場で示談を申し出てくる場合がありますが、絶対に応じてはいけません。
たとえ現地での示談でも、応じてしまえば、当事者間の合意として有効とみなされてしまいます。一度示談してしまうと、事故後に怪我や損害が発覚した場合でも、治療費・損害賠償の請求は出来ません。加害者が自分に都合の悪い部分を隠した通報を行っている可能性もあります。被害者の方でも、交通事故に遭ってしまった場合は警察へ連絡し、正確な状況を伝えた上で、人身事故として届け出を行うことが重要です。
「初期対応と合わせて事故状況の確認を」
交通事故の被害者となった場合、初期対応とあわせて行っておくべきなのが「事故状況の確認」です。
- 事故状況の撮影・記録
- 加害者の氏名・住所・連絡先の確認
- 加害車両の車種・ナンバープレートの記録
- 加害者の加入保険会社・証明書番号
- 目撃者の確認
事故直後の状況を正確に記録しておくことが、以後の示談交渉、過失割合の設定でも重要になります。スマートフォンで事故現場の撮影、加害者側の氏名・連絡先・ナンバープレートのメモするなど、可能な限り状況を記録しておきましょう
事故現場にたまたま居合わせた目撃者がいれば、協力をあおぎ、連絡先を教えてもらうことで、公平な立場からの証言を確保できます。
またドライブレコーダーに記録された映像も、事故状況の確認に役立つでしょう。
② 治療

「病院で治療を受け人身事故の扱いにする」
交通事故で怪我をしても、病院で治療を受けなければ人身事故の扱いになりません。ですから、病院には必ず行くようにしてください。また、警察に人身事故の届出をしないと、警察がきちんと事故状況を記録に残してくれませんので、事故状況や過失割合が問題になりそうな場合には、できる限り早く病院で診断書を取得して、人身事故の届出をしてください。警察への対応について詳しく知りたい方は、Q&Aの警察の項目をご覧ください。
「病院対応で悩んだら弁護士の無料相談へ」
交通事故被害者が悩むことの1つに病院対応があります。どのような病院に通院したらよいのか、病院を変更してもよいのか、治療費をどうするのか、様々な問題があります。これらの対応を誤ると、治療期間の短縮、慰謝料の減額、後遺障害の不認定といった不利益を被る可能性がありますので、弁護士の無料相談を利用されることをお勧めします。病院への対応について詳しく知りたい方は、Q&Aの病院の項目をご覧ください。
③ 休業補償・治療費の打ち切り

「保険会社は予告なく打ち切ることも」
保険会社は、交通事故からしばらくすると、休業補償や治療費を打ち切ることがあります。休業補償や治療費を打ち切られた場合の対処法は、被害者の方の置かれた状況や保険会社の担当者の対応等によって、ケース・バイ・ケースですので、弁護士への相談が必要です。詳しくは治療費・休業補償の相談がしたいをご覧ください。
④ 後遺障害診断書の作成

「等級が獲れる後遺障害診断書の作成を」
後遺障害等級認定獲得には、きちんと検査をして、適切な後遺障害診断書を作成してもらうことが一番大事です。一度診断書が作成されると、加筆修正してもらうのは難しくなりますので、作成を依頼する前に後遺障害に詳しい弁護士に相談することが大事です。リンクスでは適切な後遺障害診断書を作成してもらえるよう、後遺障害診断書の作成ガイドをお渡ししています。
詳しくは後遺障害診断書のもらい方が知りたいをご覧ください。
⑤ 後遺障害等級認定手続

「後遺障害等級認定の前に弁護士に相談を」
後遺障害認定手続では、自賠責保険調査事務所が後遺障害診断書の内容で後遺障害を証明できているかを確認します。といっても、後遺障害を証明するための資料を集めてくれるわけではありません。被害者の方から積極的に後遺障害を証明する資料を提出しなければ、後遺障害として認定してくれません。どのような資料を準備しなければならないかについては、症状によって異なりますので、後遺障害認定に詳しい弁護士への相談が不可欠です。
⑥ 示談交渉の準備
「弁護士基準で示談しないと損」
保険会社と示談交渉する際、交通事故のプロである保険会社は被害者を丸め込んで、できる限り低い自賠責基準の慰謝料で示談しようとします。
実は、交通事故には3つの基準があります。交通事故被害の必要最低限を補償する自賠責基準、自賠責基準をベースに設定された任意保険会社基準、そして、過去の判例等もふまえて交通事故被害者が本来受け取れる金額を定めた弁護士基準(裁判所基準)の3つです。最も高額な慰謝料を請求できる弁護士基準は、その名の通り、弁護士を通じて慰謝料請求することで利用できる基準です。
本来より低い示談金だったとしても、一度示談してしまったら、取り消すことはできません 。示談交渉をする前に、示談交渉に強い弁護士に弁護士基準の慰謝料を聞き、その違いを確認しましょう。詳しくは「交通事故の慰謝料を弁護士基準にする方法」をご覧ください。「弁護士への相談は相手方保険会社が嫌がられる?」
ご相談者の方が「交通事故への対応を弁護士に任せる」旨を伝えた際、相手方保険会社の担当者に難色を示されたというのは、実際のところ、よくある話です。
これは、担当者自身が、保険会社が定めた基準よりも弁護士基準の方が高額で、想定より多くの慰謝料支払いが発生することをよく理解しているからこそのリアクションと言えるでしょう。
⑦ 示談交渉

「提示された示談金が適切かどうか見積をとる」
保険会社が提示した示談金を聞いても、その金額が適切なのか分かりません。慰謝料、後遺症という金額の内訳を見て、自賠責基準、任意基準という説明を受けても、その基準で正しいのかを確認する方法がありません。残念ながら、リンクスの弁護士に持ち込まれたケースのほとんどが、 被害者に不利な基準で計算していますので、増額できる可能性が高いです。リンクスの弁護士の慰謝料増額実績について知りたい方は、リンクスの弁護士の慰謝料増額実績をご覧ください。
⑧ 示談成立

「示談成立すれば慰謝料・損害賠償を含む示談金の支払い」
保険会社が最終的に提示してきた示談内容に対して、被害者の方の納得が行けば、示談は成立となります。
示談金(保険金)が支払われる時期は、最終的には交渉次第とはなりますが、示談成立後、約10日~2週間月程度の間で入金されるのが一般的です。「決裂した場合、裁判等で争うことに」
保険会社の提示した示談内容に納得が行かない場合、調停や裁判、あるいはADR機関を利用して条件の交渉を進めることになります。
交渉がもつれ、裁判等も考慮に入れた対応を進める際、弁護士は、最終的な着地も見据え、被害者が負った実際の被害に見合う最大限の補償を獲得できるようサポートします。
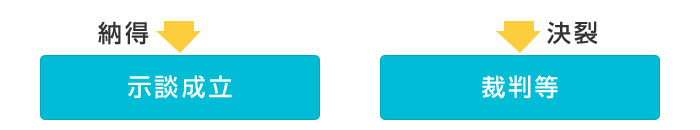
物損事故の示談の流れ
物損事故の場合の基本的な解決の流れは、以下の通りとなります。
- 事故発生
- 車両の修理費の算定
- 損害額の確定
- 示談交渉
- 示談成立~示談金(保険金)の支払い
物損事故が発生したら警察への通報が必要
物損事故の場合も、道路交通法に定められた義務である以上、警察への通報は必要で、怠れば罰金を科せられるおそれがあります。
また、警察への連絡を怠ると、事故があった事実を示す公式な記録が残らないことになります。警察による調査書類は、交通事故の責任や損害賠償を争う際の重要な資料です。保険会社との交渉はもちろん、事故後に身体症状があらわれ人身事故へ切り替えが必要となった場合も、警察への通報を行わずに済ませたことは、問題ある対応とみなされるでしょう。
たとえ物損事故でも、交通事故を起こした場合は警察へ通報、事故直後の状況を保存し、適切な調査をしてもらうことが、結果的にドライバーの身を助け、リスク回避につながります。
物損事故発生後にでも身体に少しでも異変を感じるなら病院へ
交通事故の発生後、もし少しでも身体の異変を感じるなら、病院へ行って診断を受けるようにしましょう。慰謝料・損害賠償による交通事故の解決を考える場合、「その事故が物損事故か人身事故か」で、請求できる項目も金額も大きく異なります。
慰謝料を請求できない物損事故。示談の焦点は車を修理するか全損になるか
怪我人のいない物損事故の場合、治療費を請求できないのは当然として、原則、慰謝料も請求できません。物損のみの損害は、一般的に財産的な損害が賠償されることで、精神的苦痛も慰謝される、と考えられているためです。
物損事故の場合、被害者が加害者に請求できるのは、車の修理費や積荷など、交通事故により発生した財産的損害のみが対象となります。
修理費については、車両の時価を比較して、修理費の方が高い場合には、全損扱いになり、修理費ではなく、車両の時価が支払われることになります。
物損事故は自賠責保険の対象外
そもそも自賠責保険は、交通事故被害者の治療・回復に必要な最低限を補償する制度です。物損事故は、交通事故被害者の身体的損害ではなく、財産的損害にあたるため、自賠責保険の対象外となります。自賠責保険からは支払いを受けられないため、物損事故に対する損害賠償は、加害者が加入している保険の「対物賠償補償」の範囲で、保険会社から支払われるのが一般的です。加害者が万一任意保険に加入していない場合、損害賠償はすべて加害者本人に支払わせることになります。
交通事故の示談交渉の注意点
その場で示談しないこと
事故発生直後「免許の点数がギリギリの人」や「運転を職業としている人」などから、その場で示談を申し込まれることがあります。
- すべての損害をきちんと負担するから物損事故にしてほしい
- 今すぐ〇円払うのでこれで許してほしい など
相手方に同情してしまったり、「必要なお金さえ負担してくれるのであれば別にいいか…」などと思ったりする気持ちもわからなくはないですが、その場で提案に乗るのはやめておきましょう。
仮に相手の提案に乗って物損事故で処理をしたとしても、その後、相手方が約束を守ってくれるという保証はありません。
また、その場でよく考えずに示談してしまうと、後から覆すのが難しくなります。
そういった理由で、その場での示談や、相手の提案に安易に乗ってしまうのはおすすめしません。
相手の保険会社の言いなりにならないこと
交通事故が起こると、多くのケースでは加害者側の任意保険会社と示談交渉をすることになります。
任意保険会社は自社の利益を増やすため、被害者にとっては損となる提案をしてくる可能性が高いです。
- 相場に見合わない示談金の提案
- 早すぎるタイミングでの治療費の打ち切り
- 症状固定前の示談の申し出 など
相手の保険会社の言いなりになっていると、知らずしらずのうちに損をすることになります。
相手の提案を鵜呑みにすることなく、妥当な提案かどうかきちんと判断しましょう。
おかしいと思ったら反論するか、弁護士に依頼して示談交渉を代行してもらうなどの対抗措置を取らなくてはなりません。
納得するまで示談書にサインしないこと
上記「相手の保険会社の言いなりにならないこと」にも繋がっていますが、相手が提案してくる示談案に納得ができるまで、示談書にサインしてはいけません。
一度示談が成立してしまうと、後から覆すのは難しいからです。
示談書の内容に何か不満がある方は、示談書の内容が妥当かどうか、弁護士にチェックしてもらうといいでしょう。
時効を迎えると請求できないこと
交通事故の損害賠償請求権には時効があります。時効を迎えると、加害者に被害分の請求をすることができなくなります。
- 物損事故の場合…事故発生日の翌日から3年
- 人身事故…事故発生翌日から5年
事故で後遺症がある場合は、症状固定をした翌日から5年となります。
示談交渉に、お互いが加入している任意保険会社が関与していれば、時効を迎えることはまずないでしょう。
しかし、自分で示談交渉をしている場合、面倒になって問題を放置していると、最終的に時効を迎えてしまいます。
示談がまとまらないと裁判になること
示談は両者の話し合いですので、お互いの言い分がぶつかりあったとき、どちらかが譲歩しなければ決着はつきません。
示談で決着がつかなければ、調停や裁判など、裁判所を交えた手続きを行うことになります。
この場合、別途弁護士費用がかかりますので、それを払ってでも裁判に進むべきか、譲歩して示談で決着をつけるべきか、どっちが得なのか、判断する必要があります。
交通事故の示談交渉を弁護士に任せるメリット
 示談交渉を弁護士に依頼するメリットは多くありますので、紹介します。
示談交渉を弁護士に依頼するメリットは多くありますので、紹介します。
相手方とのやりとりを一任できる
まず、相手の保険会社とのやりとりを一任できます。弁護士は依頼者の代理人となってくれます。
必要な連絡はすべて弁護士に届くようになりますので、自分で何かを考えたり、返信をしたりする必要がなくなります。
また、相手の保険会社からの連絡は良い内容ばかりではないので、返信に困ったり、ストレスがたまったりすることも考えられます。
弁護士にやりとりを任せておくことで、手間やストレスを回避することができます。
示談交渉がスムーズに進む
相手の保険会社は、自社の利益をあげるため、なるべく示談金の支払いが少なくなるように交渉してきます。
ここでこちらが折れてしまえば示談金が安くなってしまいますし、折れなければ交渉が長引きます。
弁護士に示談交渉を依頼することで、裁判を想定した法的根拠のある主張が可能になりますし、相手の保険会社に言いくるめられる心配もなくなるため、話し合いがスムーズに進みます。
慰謝料が増額する
慰謝料に関してですが、弁護士に依頼すると、自分で交渉するより高い金額を相手に請求することができます。
弁護士は「実際に裁判になったら被害者に支払われるであろう慰謝料の額」を加害者側にそのまま請求するからです(弁護士基準・裁判基準)。
これを拒否すると本当に裁判になってしまう可能性があるため、様々な面からみても、加害者側には反論するメリットがありません。
慰謝料に関しては、弁護士に依頼するのとしないのとでは金額にかなり差があります。
慰謝料が気になる方は一度相談だけでもすることをおすすめします。
交通事故の示談でよくある質問
交通事故の示談の相場は?
交通事故の示談の相場は、次のとおりです。
| 交通事故の内容 | 示談金の相場 |
|---|---|
| 物損事故 | 数万円~数十万円 |
| 人身事故で怪我が完治した場合 | 数十万円~100万円 |
| 人身事故で後遺障害が残った場合 | 数百万円~数千万円 |
| 死亡事故 | 数千万円~1億円程度 |
詳しくは「交通事故示談金!相場や内訳の計算を弁護士が解説」をご覧ください。
交通事故の示談を弁護士に依頼するベストなタイミングは?
交通事故の示談を弁護士に依頼するベストなタイミングは「できる限り早く」です。
早ければ早いほど有利な資料を整えることができます。
遅くなると保険会社にペースを握られるので、挽回することが難しくなる可能性が出てきます。
保険会社の示談金の計算で確認すべきポイントは?
保険会社は、被害者本人に対しては、休業補償や慰謝料の基準を下げたりしてきますので、要注意です。
詳しくは「交通事故の慰謝料を自分で弁護士基準に?保険会社が嫌がる負けない交渉術!」をご覧ください。
法律事務所リンクスの弁護士が無料電話相談で分かりやすく説明
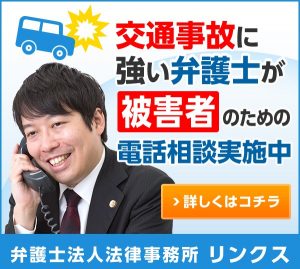 法律事務所リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、2000人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。
法律事務所リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、2000人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。
そして、1500人以上の交通事故被害者の方に適正な補償を実現させてきました。
法律事務所リンクスでは、無料電話相談を実施しておりますので、お気軽にお問合せください。
このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。
リンクスの顧問医のご紹介

- 顧問医師
- 濱口 裕之/はまぐち ひろゆき
法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。
私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。
私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。
| 経歴 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄病医 日本リウマチ学会専門医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO |
|---|
LINX無料相談の5つのメリット
- 交通事故の流れを図で分かりやすく
- お客様の置かれた状況を親身になって
- 後遺障害等級の見込みをプロの目線で
- 獲得できる賠償金は漏れなく最大限
- お客様にとって最適な解決をアドバイス
交通事故でお悩みの方全国で実績豊富なリンクスにご相談ください!
交通事故のトラブルを保険会社に任せていませんか?弁護士費用特約を利用すれば費用もかからず
交渉から解決までを一任可能。弁護士に依頼するだけで慰謝料が大幅に増額するケースも
- お電話で
無料相談【全国対応】 -
0120-917-740
受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)