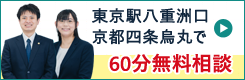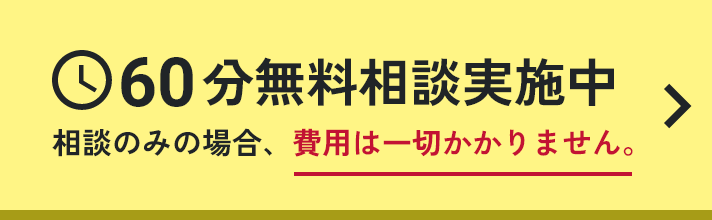遺産隠しは罪?相続通帳見せないでも財産隠匿口座は調査でバレる?
1000万円の遺産隠しを取り戻した事例
遺産隠しとは?罪になる?罰則は?時効は?通帳は見せないとダメ?

「遺産隠し」「相続財産隠し」とはお亡くなりになられた被相続人の相続財産や口座を管理していた人が、相続した通帳を見せないであったり、被相続人に無断で口座から生前に出金して遺産相続した現金を隠すことをいいます。
相続財産隠しは横領罪に当たるように見えますが、刑法第244条1項は配偶者、直系血族、同居の親族との間で横領をしたとしても刑を免除していますので、犯罪にはならず、罰則はないのが原則です(後見人に就任している場合には業務上横領罪が成立し、刑が免除されない可能性があります。)。
したがって、相続財産隠しで警察は動いてくれません。税務署が遺産隠しを指摘する場合はありますが、余程のことがなければ動いてはくれません。
遺産隠しは他の相続人が調査しなければバレませんし、相続財産の開示義務もありません(遺言執行者に就任している場合には相続財産の開示義務があります。)。
このような場合、遺産を隠された相続人としては、隠された相続財産や口座を調査して、遺産の返還を求めることが必要になります。
遺産隠しの時効は、口座から出金されてから10年となるのが原則ですが(金融機関の取引履歴も過去10年分しか取得できないのが通常です)、場合によっては20年まで認められることもあります。
ただ、遺産隠しを知ってから遅くとも5年以内に請求をしないといけませんので、遺産を隠された相続人としては、できる限り早く相続財産隠しの調査に着手する必要があります。
このページでは、法律事務所リンクスの相続に強い弁護士が、遺産隠しの調査方法についてご説明します。
なお、遺産を隠していないにもかかわらず、遺産を隠したと疑われている場合については、「遺産を使い込んだと疑われている」をご覧ください。
法律事務所リンクスは相続の相談が60分無料!
 法律事務所リンクスでは、遺産相続に強い弁護士による60分無料相談を実施しています。
法律事務所リンクスでは、遺産相続に強い弁護士による60分無料相談を実施しています。
相談に当たっては、ご予約いただいた際にご事情を伺い、調査をした上で相談に臨みますので、無料相談の時間内で充実した情報を提供しております。
相談者様が聞き足りなかったということが起きないようにしておりますし、ホワイトボードを使うなどして分かりやすく説明していますので、お気軽にお問い合わせください。
遺産隠しの調べ方を動画でご覧になりたい方はコチラ
遺産隠しはバレる?隠された相続財産を調査する方法
取引履歴の取寄せ
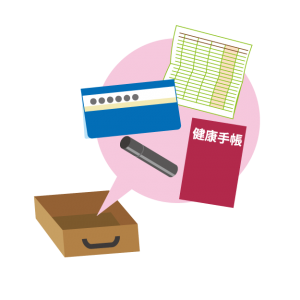
遺産隠しを疑われている人が相続財産を開示してくれればよいですが、そう易々と自分が管理している相続財産を開示してくれるとは限りません。
そのような場合には、自ら預貯金等の取引履歴を取り寄せたり、銀行に調査を掛ける必要があります。
相続人であれば取引履歴を取り寄せることができますが、自分で金融機関所定の書類を集めなければなりませんので、面倒かもしれません。
弁護士の場合には、費用は掛かりますが、お客様から委任状をもらって取り寄せたり、場合によっては弁護士会を通じた照会によって、取引履歴を取り寄せることが可能です。
取引履歴の調査

取引履歴を取り寄せると、不自然な出金や解約がないかを調査することになります。
一度に多額の出金や継続的に不自然な出金があった場合、不必要な解約があった場合には、遺産隠しが疑われます。
取引履歴には様々な情報が集約されています。他の金融機関の被相続人名義の口座への振込履歴がある場合には、その金融機関に被相続人名義の口座が残っている可能性が考えられますし、被相続人が年金受給者であったにもかかわらず取引履歴に年金の入金記録がない場合には、やはり他の金融機関に被相続人名義の口座がある可能性が考えられます。
このような相続財産を綿密に調査するには、証拠読みのプロである弁護士が必要です。
遺産隠しの証明には、他にも証明しなければならないことがあります。詳しくお知りになりたい方は、「遺産の使込みを証明したい」をご覧ください。
相続税の申告をしている場合
相続税の申告をしている場合、こちらには隠している遺産も申告している可能性があります。あなた自身も一緒に税理士に依頼している場合には、税理士に相続税の申告書を見せてもらうようにしてください。税理士に聞きにくい場合には、弁護士に依頼して頂ければ、弁護士から税理士に相続税の申告書を見せるよう求めます。
口座がある金融機関が分からない場合
このような場合、被相続人の財産を管理していた相続人に聞くほかありません。といっても、遺産隠しをしている相続人が、他の相続人から求められて、安易に開示するとは思えませんので、遺産相続に強い弁護士にご相談いただく必要があるように思います。
遺産隠しの解決方法
遺産が使い込まれた場合、その遺産を返還してもらうには、3つの方法が考えられます。
1 遺産分割協議における解決
遺産分割協議の際に、遺産を隠した相続人が遺産隠しを認めた場合には、他の相続人がその分だけ遺産を多めに受け取ることで遺産隠しの問題を解決できる可能性があります。
しかし、遺産を隠した人が、本人同士の話し合いで、遺産隠しを素直に認めるということはあまり考えられませんし、遺産隠しではなく生前贈与を受けたと主張しだすことも考えられますので、遺産隠しという相続トラブルの専門家である弁護士に依頼することが必要であると思います。
2 遺産分割調停における解決
 遺産隠しをした人は、家庭裁判所などの第三者に言われなければ遺産隠しを認めない場合も多いので、このような場合には遺産分割調停の利用が考えられます。
遺産隠しをした人は、家庭裁判所などの第三者に言われなければ遺産隠しを認めない場合も多いので、このような場合には遺産分割調停の利用が考えられます。
遺産分割調停では、遺産隠しの厳密な証明が求められますので、証明のプロである弁護士の関与が不可欠だと思います。
調停手続きの流れ
- 申立て: 相手方となる相続人の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者全員が合意した家庭裁判所に申し立てます。費用は、収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手代数千円程度と、比較的低額です 。第1回調停期日: 申立てから1ヶ月~2ヶ月後に第1回の期日が指定されます。当日は、原則として申立人と相手方は別の待合室で待機し、交互に調停室に呼ばれて、それぞれ個別に調停委員と話をします。そのため、相手と直接顔を合わせることはほとんどありません 。
- 話し合いの進行: 調停委員が双方から事情や希望を聞き取り、対立点を整理し、解決案を提示するなどして、合意形成を目指します。期日はおよそ1ヶ月に1回のペースで開かれ、解決までには半年から1年以上かかることも珍しくありません 。
- 調停成立: 話し合いがまとまり、相続人全員が分割内容に合意すると「調停成立」となります。裁判所がその合意内容をまとめた「調停調書」を作成し、この調書は判決と同じ法的効力を持ちます。この調書を使って、不動産の登記や預貯金の名義変更などの手続きを進めることができます 。
参照:裁判所HP「遺産分割調停」
調停を有利に進めるための重要戦略
調停は話し合いの場ですが、ただ感情をぶつけるだけでは良い結果は得られません。有利な解決を目指すためには、周到な準備と戦略が不可欠です。
- 準備がすべて: 自分の主張を法的に整理し、時系列や資産リストを明確にまとめておくことが重要です 。
- 証拠が王様: あなたの主張の説得力は、それを裏付ける客観的な証拠にかかっています。調査で入手した預金の取引履歴、名寄帳、不動産の評価書など、すべての証拠を整理して提出しましょう 。
- 調停委員を味方につける: 調停における最も重要な聴衆は、中立な調停委員です。感情的な非難や相手の悪口は避け、冷静かつ論理的に自分の主張の正当性を説明し、調停委員に「こちらの主張はもっともだ」と理解してもらうことが、良い結果への近道です 。
- 譲歩点を見極める: 調停は妥協の産物です。すべての要求が100%通ることは稀です。「これだけは譲れない」という核心部分と、「この部分なら譲歩できる」という点をあらかじめ決めておくことで、交渉を柔軟に進めることができます 。
- 弁護士の力: 遺産分割調停の約8割には弁護士が関与しているというデータもあります 。弁護士は、あなたの主張を法的に説得力のある形に構成し、複雑な手続きを代行し、あなたに代わって冷静に交渉を進めてくれます。専門家のサポートは、精神的な負担を軽減するだけでなく、結果を大きく左右する要因となります 。
3 裁判における解決
遺産分割調停で遺産隠しを証明し、家庭裁判所が相手方に遺産隠しを認めるよう説得したとしても、相手方が遺産隠しを認めなければ、隠された遺産の返還を強制できません。
このような場合には、地方裁判所に遺産の返還を求める不当利得返還訴訟か損害賠償請求訴訟を提起するしかありませんが、「消滅時効」という厳しい時間制限が設けられています。この期限を過ぎると、たとえ証拠が揃っていても権利を主張できなくなってしまいます。
【重要】法的措置のタイムリミット(時効期間)
| 法的請求権 | 時効期間 | いつからカウントが始まるか(起算点) |
| 不当利得返還請求 | 5年 または 10年 | 権利を行使できることを知った時から5年、または、権利が発生した時(使い込み行為の時)から10年の、いずれか早い方 。 |
| 不法行為に基づく損害賠償請求 | 3年 | 損害および加害者を知った時から3年、または、使い込み行為から20年。 |
使い込み行為から10年以上経過している場合には、不法行為に基づく損害賠償請求をする必要がありますが、使い込みを知ってから3年以内に請求しなければなりません。遺産の使い込みが発覚したら、一刻も早く専門家に相談し、行動を起こすことが極めて重要です。
遺産隠しで1000万円以上を取り戻した交渉事例
無料相談に至る経緯
ご相談者様はお亡くなりになられた被相続人のご兄弟(相続分4分の1)だったのですが、被相続人の妻(相続分4分の3)から、預金の残高も取引履歴も示されないまま、口座の解約に協力するよう一方的に求められて不安になり、リンクスの無料相談にお越しになられました。
リンクスからのご提案
 リンクスの弁護士は、無料相談の際に、次のようなご提案をさせて頂きました。
リンクスの弁護士は、無料相談の際に、次のようなご提案をさせて頂きました。
- 被相続人の妻に預金の残高証明や取引履歴を開示するよう求める。
- 開示されない場合にはリンクスの方で取り寄せて調査する。
- 不正出金があれば被相続人の妻の相続分から差し引いてもらう。
ご相談者様は、リンクスの弁護士の方針に納得され、ご依頼を受けることとなりました。
リンクスにおける解決方法
① 取引履歴の開示請求
まず、相手方に弁護士が依頼を受けたことを示す受任通知を送って取引履歴の開示を求めたところ、相手方はすぐに弁護士を入れてきました。そこで、弁護士の方に取引履歴の開示を求めたところ、お亡くなりになる直前に多額の出金がなされていることが明らかになりました。
② 出金の趣旨の確認
相手方の弁護士は葬儀費用などに使用したと説明しましたが、当初そのような説明がなされていなかったことから、遺産に持ち戻すように主張しました。
③ 交渉で解決
結局、相手方は1000万円以上の出金を認め、依頼者はその他の相続財産を含め約1800万円の遺産を取得する形で遺産分割協議がまとまりました。
遺産隠しに関するよくある質問(FAQ)
Q1:他の相続人が財産を隠しているようです。まず最初にすべきことは何ですか?
A:まず、内容証明郵便を利用して、正式に財産開示を求める書面を送付することをお勧めします。相手が無視する可能性はありますが、「正式に開示を求めた」という記録を残すことは、その後の調停などであなたが誠実に対応してきた証拠となります。内容証明郵便の作成・送付自体は数千円で可能ですが、弁護士名で送付することで相手に相当な心理的圧力をかけることができます(弁護士依頼の場合の費用目安:3万円~5万円程度)。
Q2:親が亡くなる前に、遺産隠しを防ぐ方法はありますか?
A:はい、予防策はあります。最も効果的なのは、親御さんが生前のうちに、遺言書を作成してもらうことです。特に、弁護士や信託銀行など、中立的な第三者を「遺言執行者」に指定した公正証書遺言を作成しておくことが最善の策です。遺言執行者には法律上の厳格な財産開示義務があるため、特定の相続人による財産隠しを強力に防ぐことができます 。また、元気なうちから財産目録を作成してもらい、家族間で情報を共有しておくことも有効です。
Q3:相手は「親からもらった贈与だ」と主張しています。どう反論すればよいですか?
A:これは使い込みを正当化するためによく使われる主張です。あなたは、それが贈与ではなく無断の引き出しであったことを主張する必要があります。贈与であったことの証明責任は、多くの場合、贈与を受けたと主張する側にあります。仮に生前贈与であったと認められたとしても、その贈与は「特別受益」として、その相続人の本来の相続分から差し引いて計算されるべきものかもしれません 。これは複雑な法律論争になるため、弁護士を立てて調停の場で解決を図るのが賢明です。
Q4:裁判所の手続きには、どのくらいの費用がかかりますか?
A:遺産分割調停の申立て自体の費用は、収入印紙代や郵便切手代で数千円程度と安価です 。主な費用は、弁護士に依頼した場合の弁護士費用です。弁護士費用は法律事務所によって異なりますが、一般的には、事件に着手する際の「着手金」として20万円~40万円程度、そして事件解決時に得られた経済的利益に応じて支払う「報酬金」(獲得額の10%~16%程度が目安)から構成されます 。決して安価ではありませんが、高額な遺産を取り戻すためには必要な投資と言えるでしょう。
遺産隠しを弁護士に依頼する5つのメリット
遺産隠しは、法律知識だけでなく、交渉力や調査能力も求められる複雑な問題です。当事者だけで解決しようとすると、かえって事態を悪化させてしまうことも少なくありません。弁護士に依頼することで、以下のような多くのメリットが得られます。
- 証拠収集を強力にサポートしてくれる 弁護士は取引履歴や医療記録など様々な証拠を収集することができます 。これにより、交渉や裁判を有利に進めるための土台を固めることができます。
- 感情的な対立を避け、冷静な交渉を代理してくれる 親族間の金銭トラブルは、どうしても感情的になりがちです。弁護士が第三者として間に入ることで、当事者同士が直接顔を合わせるストレスから解放され、冷静かつ論理的な話し合いが可能になります 。
- 法的に最適な請求方法を判断してくれる 不当利得返還請求と不法行為に基づく損害賠償請求のどちらを選択すべきか、あるいは訴訟と調停のどちらが適切かなど、状況に応じた最善の法的戦略を専門的な知見から判断してくれます 。
- 複雑な裁判手続きをすべて任せられる 訴状の作成から証拠の提出、期日への出廷まで、訴訟や調停に関する煩雑で専門的な手続きをすべて一任できます。これにより、時間的・精神的な負担が大幅に軽減されます 。
- 遺産分割全体の解決まで見据えたサポートが受けられる 遺産隠しの解決は、遺産分割のスタートであってゴールではありません。弁護士は、隠された財産の返還だけでなく、その後の最終的な遺産分割協議や手続きまで、相続問題全体の円満な解決を見据えた包括的なサポートを提供してくれます 。
遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要

このように、遺産隠しには様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。
遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。
司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律や交渉の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた場合や交渉が必要な場合に対応ができません。
弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。
法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
ページトップに戻る