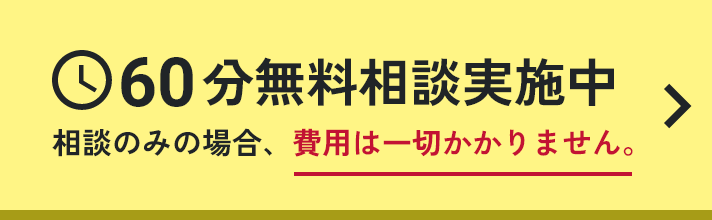遺産を前妻の子に渡したくない!夫の死を知らせない相続させない方法
前妻(夫)の子がいる夫婦のとるべき相続対策とは?

遺産相続で前妻の子に渡したくない方へ
夫と前妻との間の子供も夫の相続人となります。前妻の子の法定相続分は、現在婚姻関係にある配偶者間の子供の法定相続分と平等です。
妻と前の夫との間の子供も同様ですが、このページではよく問題となる前妻の子に遺産を渡したくない場合の話をします。
ご覧になっている方が前妻(夫)の子供に当たり、遺産を受け取りたいとお考えの場合には、「前妻の子の相続は?後妻との関係は?離婚した親が死んだら連絡来る?」をご覧ください。
さて前妻の子に遺産を渡さないことはできるのでしょうか?
前妻の子に相続させない方法は?
前妻の子に遺産を渡したくないという場合、夫がご存命であれば遺言書を作成することで一定の生前対策が可能ですので、後で説明します。
これに対して、夫が遺言書を残さずに亡くなった場合、前妻の子との間で話し合いをしなければ、夫の財産を相続することができません。では、どうすればよいのでしょうか。
前妻の子に夫の死を知らせたくない場合
前妻の子に夫の死を知らせたくないというお気持ちは分かりますが、夫の死を知らせないと相続の話ができませんので、夫の死を知らせる必要があります。ご自身で夫の死を知らせるのに抵抗があるという場合には、遺産相続の交渉になっても対応できる唯一の専門家である弁護士にご相談ください。
前妻の子に相続の連絡をしたくない場合
ご自身で前妻の子に相続の連絡をすることで、あらぬ揉め事が生じてしまう可能性があります。そのようなことが心配な方は、遺産相続に強い弁護士に無料相談して対策を検討してからでも遅くないと思います。
前妻の子の居場所が分からない場合
前妻の子の居場所が分からない場合、夫の戸籍を遡って、前妻の子の戸籍の附票を取得することで、前妻の子の住民票上の住所を確認することが可能です。弁護士に依頼をすれば居場所を調査することは可能です。
前妻の子への手紙の文例をどうするか
- 相続放棄をお願いする
- 相続分の放棄または相続分の譲渡をお願いする
- 一部の遺産を渡す提案をして遺産分割協議書の作成に協力してもらう
① 相続放棄のお願い
前妻の子が相続放棄をしてくれれば遺産を渡さなくて済みますが、家庭裁判所で手続を取らなければならないので面倒に思われるかもしれません。また、当初から相続放棄をお願いした場合、不信感を抱かれてしまい相続トラブルになる可能性があります。
② 相続分の放棄または相続分の譲渡のお願い
相続分の放棄または相続分の譲渡は、家庭裁判所での手続が不要ですので簡単ですが、聞きなれない言葉ですし、相続放棄と同じような効果があるので、やはり抵抗感を示される可能性があります。
③ 一部の遺産を渡す提案をして遺産分割協議書の作成への協力を依頼
相続の場合、全面勝利はありませんし、それを狙うとかえって負けになることが多いです。リンクスの弁護士の経験上、当初から一部の遺産を渡す提案をすれば、その額が前妻の子の法定相続分に不足していてもそれで納得し、遺産分割協議書の作成に協力してくれることが多いように思います。
前妻の子に相続させないための生前対策
夫がまだご存命の場合には、いくつかの生前対策が可能です。
- 遺言書の作成
- 生前贈与
- 生命保険への加入
1 遺言書の作成
前妻の子に遺産を残したくない場合、遺言書を作成しなければ法定相続分通りの相続となり、前妻の子に遺産が渡ってしまうので、遺言書を作成する必要があります。
もっとも、遺言書と言えども相続人の最低限の取り分である遺留分を奪うことはできませんので、遺留分対策を含めた相続対策をする必要があります。
前妻の子に遺産を渡さないための相続について詳しく知りたい方は、「財産を渡したくない相続人がいる」をご覧ください。
2 生前贈与
前妻の子に渡したくない財産については、別の家族に生前贈与をしておくことで、その財産は前妻の子に渡らなくなります。
生前贈与をすれば遺言書は不要かというとそうではありません。
単に生前贈与しただけでは、遺産分割する際に、生前贈与を受けた相続人の取り分から特別受益として差し引かれてしまうからです。
その相続人に多めに財産をあげる趣旨で生前贈与をしたのであれば、「〇〇に生前贈与した財産は遺産分割の対象財産に加えないし、〇〇の相続分から差し引かない」旨の意思表示(特別受益の持ち戻し免除の意思表示)を残しておくことが考えられます。
もっとも、そのように書くことで、生前贈与をした事実が明らかになってしまうので、遺留分侵害額請求の対象になってしまうというデメリットもあります。
どのような場合に特別受益の持ち戻し免除の意思表示を遺言書に記載するかは、遺産相続に強い弁護士にご相談頂く必要があります。
3 生命保険への加入
生命保険は遺産分割の対象外なので、生命保険への加入は前妻の子に財産を渡さないための有効な対策になります。
遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要

このように、前妻の子との遺産分割交渉や遺言書・生前対策には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士による無料診断を受けられることをお勧めしております。
遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。
司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。
弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。
法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
ページトップに戻る