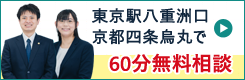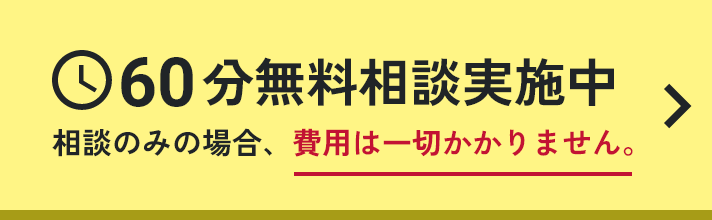相続財産調査とは?費用時間は?誰に頼む?亡くなった人の財産を調べる
相続財産がどうなっているのか知りたいのですが?
相続財産調査とは、亡くなられた方(被相続人)が所有していた財産と債務のすべてを網羅的に洗い出し、その内容と評価額を確定させる一連の作業を指します 。
調査の対象となる「相続財産」には、一般的にイメージされる預貯金や不動産といった「プラスの財産」だけでなく、借金やローン、保証債務といった「マイナスの財産」も含まれます 。法律上、相続とは被相続人の財産に属した「一切の権利義務」を引き継ぐこととされており、プラスの財産だけを選んで相続することはできません 。
具体的には、以下のようなものがすべて調査対象となります。
- プラスの財産(積極財産)
- 不動産(土地、建物、マンション)
- 預貯金(普通預金、定期預金、ネット銀行口座)
- 現金
- 有価証券(株式、投資信託、国債、社債)
- 生命保険金、損害保険の解約返戻金
- 自動車、貴金属、骨董品、美術品
- ゴルフ会員権、リゾート会員権
- 貸付金、売掛金
- 知的財産権(著作権、特許権など)
- 仮想通貨などのデジタル資産
- マイナスの財産(消極財産)
- 借入金(住宅ローン、カードローン、消費者金融からの借金)
- 未払いの税金(固定資産税、住民税など)
- 未払いの医療費、公共料金
- 買掛金
- 保証債務(他人の借金の連帯保証人になっている場合など)
重要なのは、これらの財産を一括で照会できるような便利なシステムは存在しないという点です 。不動産は法務局や市町村役場、預貯金は各金融機関、株式は各証券会社といったように、一つひとつ地道に調査していく必要があります。
相続財産調査の目的

手間と時間がかかる相続財産調査ですが、これを行わなければ、その後の相続手続きが一切進まないだけでなく、深刻なリスクを抱えることになります。調査が不可欠である理由は、主に以下の3つの目的に集約されます 。
- 公平な遺産分割協議のため 遺言書がない場合、相続人全員で「誰が、どの財産を、どれだけ相続するか」を話し合う「遺産分割協議」を行います。この協議の前提となるのが、全財産を正確にリストアップした「財産目録」です。もし調査に漏れがあり、協議成立後に新たな財産が見つかった場合、遺産分割協議をやり直さなければならない場合があります。これは単に手間がかかるだけでなく、相続人間の不信感を生み、円満な話し合いを困難にさせ、深刻な「争続」へと発展する大きな原因となります 。
- 相続放棄の判断のため 被相続人に多額の借金があった場合、相続人は家庭裁判所に申し立てることで、財産を一切相続しない「相続放棄」を選択することができます 。しかし、この判断を下すためには、財産と負債の全体像を正確に把握することが絶対条件です。調査が不十分なまま相続してしまった後で巨額の借金が発覚しても、原則としてその返済義務を免れることはできません 。
- 正確な相続税申告のため 相続財産の総額が基礎控除額()を超える場合、相続税の申告と納付が必要です 。財産調査は、そもそも相続税の申告が必要かどうか、必要であれば納税額はいくらになるのかを計算するための基礎となります。調査漏れによって申告額が過少であった場合、後日税務調査で指摘され、「過少申告加算税」や悪質な場合には「重加算税」といったペナルティが課される可能性があります。また、期限内に申告しなかった場合は「無申告加算税」、納付が遅れれば「延滞税」も発生します 。
相続財産調査にかかる時間は?期限はいつまで?手続きを急ぐべき2つのタイムリミット
相続財産調査そのものに法律で定められた「何月何日まで」という明確な期限はありません 。しかし、調査結果を用いて行う後続の手続きには厳格な期限が設けられており、これが事実上のタイムリミットとなります。
法律上の「調査期限」はないが、実質的なタイムリミットが存在する
相続手続きは、複数の法的な期限が連鎖しています。財産調査はこれらの期限を守るための準備作業であるため、各期限から逆算してスケジュールを立てる必要があります 。特に重要なのが「3ヶ月」と「10ヶ月」という2つの数字です。
【最重要】相続開始から3ヶ月:相続放棄の判断
 相続手続きにおける最初の、そして最も重要な期限が、相続放棄・限定承認の申述期限です。これは原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」と定められています 。
相続手続きにおける最初の、そして最も重要な期限が、相続放棄・限定承認の申述期限です。これは原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」と定められています 。
この期間内にプラスの財産とマイナスの財産の全体像を把握し、もし負債が資産を上回る(債務超過)可能性がある場合には、家庭裁判所での手続きを完了させなければならないというのが原則で、熟慮期間と言われます。
もっとも、この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても、なお、単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には、家庭裁判所は、申立てにより、この3ヶ月の熟慮期間を伸長することができるとされていますので、延長すればさらに3ヶ月は相続放棄するかどうかを熟慮することができます(参照:裁判所HP「相続の承認又は放棄の期間の伸長」)。
熟慮を過ぎてしまうと、原則としてすべての財産と負債を無条件に引き継ぐ「単純承認」をしたものとみなされ、後から多額の借金が見つかっても相続放棄は認められなくなります 。このため、負債の有無の調査は最優先で行う必要があります。
【最終目標】相続開始から10ヶ月:相続税の申告・納付
 次に訪れる重要な期限が、相続税の申告・納付期限です。これは「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」と定められています 。
次に訪れる重要な期限が、相続税の申告・納付期限です。これは「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」と定められています 。
この日までに、すべての相続財産の評価額を算出し、遺産分割協議を終え、誰がいくら納税するのかを確定させて税務署に申告し、納税まで済ませる必要があります 。財産の評価には時間がかかるものも多いため、10ヶ月という期間は決して長くはありません。
結論:理想的な調査期間は「相続開始後4~5ヶ月以内」の完了
これらの期限を踏まえると、相続財産調査は相続発生後、可能な限り速やかに開始し、相続放棄の熟慮期間の延長が効く「4~5ヶ月以内」に完了させることが理想的です 。4~5ヶ月で調査の全体像を把握できれば、残りの1ヶ月で相続放棄すべきか否かをじっくり検討し、必要な手続きを行う時間的余裕が生まれます。すべての手続きを円滑に進めるためにも、迅速な行動が求められます。
また、相続放棄する必要がない場合でも、相続税の申告期限間際になると相続税の申告費用が割増しになることもありますし、仮に相続税の申告が不要な場合でも遺産隠しなどが発生してはいけませんので、半年程度で相続財産の調査を完了させることをお勧めします。
【実践】相続財産調査の進め方|7つのステップで漏れなく把握する
ここからは、実際に相続財産調査をどのように進めていくのか、具体的な7つのステップに沿って解説します。この手順は、まず相続放棄の判断という最も緊急性の高いリスクに対応し、その後、網羅的に財産を確定させていくという、リスク管理の観点から最適な流れで構成されています。
Step 1: 手がかりを探す|故人の遺品整理
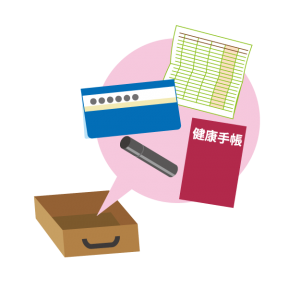 調査の第一歩は、被相続人の自宅や身の回りから、財産に関するあらゆる「手がかり」を見つけ出すことです 。遺品整理は、単なる片付けではなく、財産調査の基礎となる情報を集める作業と捉えましょう。
調査の第一歩は、被相続人の自宅や身の回りから、財産に関するあらゆる「手がかり」を見つけ出すことです 。遺品整理は、単なる片付けではなく、財産調査の基礎となる情報を集める作業と捉えましょう。
- 重要書類:
- 預貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカード
- 保険証券(生命保険、火災保険、自動車保険など)
- 不動産の権利証(登記識別情報通知書)、売買契約書
- 株券、証券会社の取引残高報告書
- 年金手帳、年金証書
- 借金の契約書、ローン返済予定表
- 郵便物:
- 金融機関からの残高通知や満期案内
- 証券会社からの取引報告書、配当金支払通知書
- 保険会社からの契約内容のお知らせ
- 市区町村からの固定資産税・住民税の納税通知書
- カード会社からの利用明細書、金融業者からの督促状
- 意外な手がかり:
- 金融機関名の入ったカレンダー、ボールペン、ティッシュなどのノベルティグッズ
- 手帳、日記、エンディングノート、メモ書き
- 貸金庫の鍵や契約書
- デジタル遺品:
- パソコンやスマートフォンのメール、ブックマーク、アプリ。ネット銀行やネット証券、仮想通貨取引所などの利用履歴がないか確認します 。
これらの手がかりを元に、問い合わせるべき金融機関や役所のリストを作成していきます。
Step 2: 相続人を確定させる|調査の前提となる戸籍収集
 金融機関や役場に財産の照会を行う際、まず「請求者が正当な相続人であること」を証明する必要があります 。そのために不可欠なのが、相続人を法的に確定させるための戸籍収集です。
金融機関や役場に財産の照会を行う際、まず「請求者が正当な相続人であること」を証明する必要があります 。そのために不可欠なのが、相続人を法的に確定させるための戸籍収集です。
具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本をすべて取得します 。被相続人が何度も転籍や結婚を繰り返している場合、この収集作業は非常に煩雑になります 。
集めた戸籍謄本は、その後の不動産登記や預貯金の解約手続きでも必要になります。複数の金融機関に提出するたびに戸籍一式を揃えるのは大変なため、「法定相続情報一覧図」の作成を強くお勧めします 。これは、収集した戸籍謄本の内容を一枚の証明書にまとめたもので、法務局で無料で発行してもらえます。この一覧図の写しを提出すれば、多くの手続きで戸籍謄本一式の提出が不要になり、時間と費用を大幅に節約できます 。
詳しくは、法務局の法定相続情報証明制度のウェブサイトをご確認ください。
Step 3: マイナスの財産(負債)の調査【最優先事項】
相続放棄の3ヶ月という期限を考慮し、プラスの財産よりも先にマイナスの財産の調査に着手することが、リスク管理の鉄則です。
借入金・ローン(住宅・カード等)の調べ方
まず、被相続人の遺品から金銭消費貸借契約書や督促状、ローン返済の明細書などを探します 。預金通帳の取引履歴に、毎月決まった日に一定額の引き落としがあれば、それはローンの返済である可能性が高いです 。
しかし、書類が見つからない、あるいは故人が借金を隠していた可能性も否定できません。そこで最も確実な方法が、信用情報機関への情報開示請求です 。信用情報機関には個人のローンやクレジットの契約内容、返済状況が記録されています。主要な機関は以下の3つで、それぞれに照会をかけることで、大半の金融機関からの借入を網羅できます 。
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC): 主にクレジットカード会社、信販会社が加盟。
- 株式会社日本信用情報機構(JICC): 主に消費者金融会社が加盟。
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC): 主に銀行、信用金庫、信用組合が加盟。
相続人として故人の情報を開示請求するには、郵送での手続きが基本となり、死亡の事実がわかる戸籍謄本や、請求者が相続人であることを証明する書類などが必要となります。
保証債務(連帯保証人など)の調べ方
借金以上に厄介なのが、被相続人が誰かの「連帯保証人」になっていたケースです。保証債務も相続の対象となり、主債務者が返済不能になった場合、相続人が返済義務を負うことになります 。
保証契約書などの書類を探すのが基本ですが、信用情報機関の記録には載らないことも多く、発見が非常に困難です。被相続人が会社を経営していたり、親族や友人に頼まれて保証人になったりする可能性が少しでも考えられる場合は、人間関係からも情報を集めるなど、慎重な調査が必要です 。
未払いの税金・社会保険料の調べ方
自宅に届いている郵便物の中から、税務署や市区町村役場からの納税通知書や督促状がないかを確認します 。固定資産税、住民税、国民健康保険料などが未納になっているケースがあります。
Step 4: プラスの財産(資産)の調査【種類別】
マイナスの財産の調査と並行して、プラスの財産の調査を進めます。
預貯金(普通・定期・ネット銀行)の調べ方
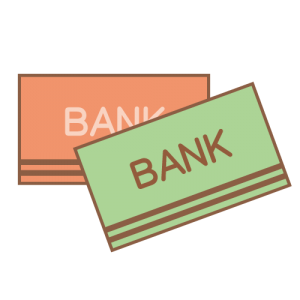 Step 1で見つけた手がかりを元に、取引のあった金融機関(銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行など)をリストアップします。各金融機関の窓口または郵送で、以下の2つの書類を取得します。
Step 1で見つけた手がかりを元に、取引のあった金融機関(銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行など)をリストアップします。各金融機関の窓口または郵送で、以下の2つの書類を取得します。
- 残高証明書: 必ず被相続人の死亡日時点の日付で発行を依頼します 。これは相続財産の額を確定させ、相続税申告でも必須となる書類です。
- 取引履歴明細書(入出金明細): 過去の取引履歴を取得することで、定期的な保険料の支払いや、不明な入出金から、他の財産(保険契約や借金など)の手がかりが見つかることがあります 。
取引があったと思われるものの通帳やカードが見つからない場合は、金融機関に「全店照会」を依頼できることがあります。これにより、その金融機関の全支店における被相続人名義の口座の有無を調べることができます(一部、対応していない金融機関もあります) 。
不動産(土地・建物・マンション)の調べ方
不動産の調査は、以下の手順で進めます。
- 特定: まずは、毎年4月~6月頃に市区町村から送られてくる「固定資産税・都市計画税 納税通知書」に同封されている「課税明細書」を探します 。ここには、その市区町村内に被相続人が所有する課税対象の不動産がすべて記載されており、最も確実な手がかりとなります。
- 名寄帳の取得: 納税通知書が見つからない場合や、私道など固定資産税が課税されていない非課税不動産の存在を確認したい場合は、不動産所在地の市区町村役場(都税事務所)で「名寄帳(なよせちょう)」を取得します 。これは、その市区町村が管理する名義人ごとの不動産一覧表です。
- 権利関係の確認: 特定した不動産の詳細な情報を確認するため、管轄の法務局で「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得します。これにより、正確な所在地、面積、所有者、抵当権の有無などを確認できます 。
- 評価額の算出:
- 相続税申告・遺産分割の基準: 「固定資産評価証明書」を市区町村役場で取得します。この評価額が、相続税計算や登記費用の基準となります。
- 実際の価値: 遺産分割協議で公平を期すためには、実際の市場価格(実勢価格)を把握することが重要です。不動産業者に査定を依頼し、大まかな売却価格を把握しておくと良いでしょう 。
有価証券(株式・投資信託)の調べ方
証券会社からの「取引残高報告書」や、株式を発行している会社からの「配当金計算書」「株主総会招集通知」などが手がかりになります 。ネット証券を利用していた場合は、故人のパソコンやスマートフォンのメール履歴も重要な情報源です 。
どの証券会社と取引があったか全くわからない場合は、「証券保管振替機構(ほふり)」に情報開示請求を行うのが有効です 。これにより、被相続人名義の口座が開設されている証券会社をすべてリストアップすることができます。
生命保険・損害保険の調べ方
保険証券や保険会社からの郵便物を探すのが第一です 。もし手がかりが一切見つからない場合は、「一般社団法人生命保険協会」が運営する「生命保険契約照会制度」を利用できます 。これは、相続人が一度の申請で、協会に加盟するすべての生命保険会社(42社)に対して契約の有無を一括で照会できる非常に便利な制度です 。
また、死亡保険金だけでなく、火災保険や傷害保険などの「損害保険」にも、解約時に戻ってくるお金(解約返戻金)がある場合があり、これも相続財産に含まれるため注意が必要です 。
その他の資産(自動車・貴金属・デジタル資産等)の調べ方
- 自動車: 車検証で所有者名義を確認します。中古車販売業者などに査定を依頼し、価値を把握します。
- 貴金属・骨董品: 専門の鑑定業者に評価を依頼する必要があります 。
- デジタル資産: 仮想通貨やネット上のサービスなどは、IDやパスワードがわからないと調査が極めて困難です。故人のメールやメモから手がかりを探すしかありません 。
Step 5: 調査に必要な書類一覧と取得方法
相続財産調査では、様々な公的書類が必要になります。手続きごとに個別に集めると非効率なため、あらかじめ全体像を把握し、計画的に収集することが重要です。
相続財産調査の必要書類マスターリスト
Step 6: 財産目録の作成|調査結果を法的に有効な一覧に
すべての調査が完了したら、その結果を「財産目録」という一つの書類にまとめます 。財産目録は、遺産分割協議や相続税申告の基礎となる、調査の集大成です。
法律で定められた厳格な書式はありませんが、誰が見ても財産の内容が正確に特定できるよう、詳細に記載する必要があります 。裁判所や国税庁が公開している書式を参考にすると良いでしょう 。
- 記載すべき項目例:
- 不動産: 所在地、地番、家屋番号、地目、地積(面積)、固定資産税評価額、相続人の持分など 。
- 預貯金: 金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、死亡日の残高 。
- 有価証券: 証券会社名、銘柄、株数(口数)、死亡日の評価額 。
- 借入金: 借入先、借入残高、利率、最終返済日など。
- プラスの財産とマイナスの財産を明確に分けて記載し、最後に合計額を算出します。
Step 7: 調査完了後の手続きへ|遺産分割協議と相続税申告
完成した財産目録を元に、いよいよ本格的な相続手続きへと移行します。主な手続きは「遺産分割協議」と「相続税申告」です 。財産目録が正確であればあるほど、これらの手続きはスムーズに進みます。
相続財産調査は誰に頼む?自分でできるか専門家に依頼するかの判断基準
相続財産調査は、相続人であれば誰でも自分で行うことが法的に可能です 。しかし、その手間やリスクを考えると、専門家に依頼した方が良いケースも少なくありません。
相続人自身で調査を行うメリット・デメリット
ご自身で調査を行う最大のメリットは、専門家への報酬費用を節約できる点です 。被相続人が生前に財産を整理しており、財産の種類が預貯金と自宅のみといったように限定的でシンプルな場合には、ご自身での調査も可能でしょう 。
一方で、デメリットも数多く存在します。
- 多大な時間と手間がかかる: 金融機関や役所の窓口は平日の日中にしか開いていないことが多く、仕事を持つ方にとっては大きな負担となります 。
- 調査漏れのリスク: 専門知識がないと、調査すべき財産の種類や調査方法がわからず、財産や負債を見落とす危険性が高まります。前述の通り、調査漏れは将来のトラブルに直結します 。
- 相続人間のトラブルの火種: 一人の相続人が主導して調査を行った場合、他の相続人から「財産を隠しているのではないか」「調査が不正確だ」といった疑念を抱かれ、関係が悪化する可能性があります 。
専門家への依頼を強く推奨するケース
 以下のようなケースでは、ご自身で抱え込まず、専門家の力を借りることを強く推奨します 。
以下のようなケースでは、ご自身で抱え込まず、専門家の力を借りることを強く推奨します 。
- 財産の全体像が全くわからない、手がかりが少ない
- 不動産、株式、投資信託など、財産の種類が多岐にわたる
- 相続財産の総額が大きく、相続税の申告が必要になる可能性が高い
- 被相続人が会社を経営していた、あるいは個人事業主だった
- 相続人同士の関係が良くない、または将来的に揉める可能性がある
- 平日に役所や金融機関を回る時間が取れない
- 相続人が遠方に住んでおり、物理的に調査が困難
依頼できる専門家の種類と最適な選び方
相続財産調査を依頼できる専門家には、主に弁護士、司法書士、税理士、行政書士がいます。それぞれに専門分野と得意領域があり、「誰に頼むのが一番良いか」は、ご自身の状況によって異なります。以下の比較表を参考に、最適な専門家を選びましょう。
相続財産調査を依頼できる専門家比較表
| 専門家 | 主な業務範囲 | 依頼すべきケース | 注意点・限界 | 費用相場(調査のみ) |
| 弁護士 | 相続手続き全般、遺産分割交渉・調停・審判の代理、財産調査、遺言執行 | 相続人間で争いがある、またはその可能性がある場合。 遺産分割で揉めて交渉が必要な場合。 | 紛争解決が主業務のため、他の専門家より費用が高額になる傾向がある。 | 10万円~30万円以上 |
| 司法書士 | 不動産の相続登記(名義変更)、財産調査、財産目録作成、遺産分割協議書作成 | 相続財産に不動産が含まれ、名義変更まで任せたい場合。 相続人間に争いがない場合。 | 遺産分割に関する交渉や調停・審判の代理はできない。 | 10万円~30万円 |
| 税理士 | 相続税の申告・納税手続き、財産評価、財産調査、財産目録作成 | 相続税の申告が必要な場合、または必要かどうかの判断が難しい場合。 | 相続登記や遺産分割交渉はできない。税務代理が主業務。 | 財産額の0.5%~1.0%(申告業務込み) |
| 行政書士 | 財産調査、戸籍収集、遺産分割協議書作成、自動車の名義変更など | 相続人間に争いがなく、相続税申告も不要な場合。 書類収集など事実証明に関する書類作成を安価に依頼したい場合。 | 不動産の相続登記や税務申告、交渉代理は一切できない。 | 数万円~ |
このように、もし相続人間で揉めている、あるいは揉めそうな場合は、唯一交渉代理権を持つ弁護士が最適です。不動産の名義変更が主な目的なら司法書士、相続税が関わるなら税理士が不可欠となります。ご自身の状況を冷静に分析し、最もニーズに合った専門家を選ぶことが重要です。
相続財産調査にかかる費用相場
相続財産調査にかかる費用は、ご自身で行うか、専門家に依頼するかで大きく異なります。
自分で調査する場合の実費(数千円〜数万円)
ご自身で調査を行う場合、専門家への報酬はかかりませんが、公的書類の取得に必要な実費が発生します 。
- 戸籍謄本・除籍謄本: 1通450円~750円
- 登記事項証明書: 1通600円(窓口申請の場合)
- 固定資産評価証明書・名寄帳: 1通300円程度
- 残高証明書: 1通800円~1,000円程度
これらの書類を複数取得するため、合計で数千円から、戸籍の収集が複雑な場合は数万円程度かかることが一般的です 。
専門家に依頼する場合の報酬(10万円〜30万円が一般的)
専門家に相続財産調査を依頼する場合の費用相場は、10万円から30万円程度が一般的です 。ただし、これはあくまで目安であり、事案の複雑さによって変動します。
費用を左右する要因
専門家への報酬額は、主に以下の要因によって決まります 。
- 財産の種類と数: 不動産や非上場株式など、評価が複雑な財産が多いほど高くなります。
- 調査対象機関の数: 照会先の金融機関や役所の数が多いほど、手間が増え費用がかさみます。
- 相続人の数と関係: 相続人が多い、あるいは戸籍の収集が複雑な場合は、相続人確定作業の費用が加算されます。
- 依頼する専門家の種類: 一般的に、行政書士が最も安価で、司法書士、税理士、弁護士の順に高くなる傾向があります。
依頼する際は、必ず事前に見積もりを取り、業務範囲と費用体系を明確に確認することが重要です。
相続財産調査に関するよくある質問(FAQ)
Q1: 故人が隠していた財産(へそくり等)を見つける方法はありますか?
A1: 確実な方法はありませんが、可能性を高めることはできます。預貯金の取引履歴を数年分遡って確認し、不自然な大口の出金や定期的な資金移動がないかチェックします。また、金融機関に貸金庫の契約がないか照会することも有効です 。遺品整理の際は、故人が大切にしていたであろう場所(金庫、仏壇、机の鍵付きの引き出しなど)を重点的に探すことが手がかりにつながる場合があります。
A2: 発覚した財産の種類とタイミングによって影響が異なります。
- プラスの財産の場合: 遺産分割協議をやり直す必要がある場合があります。相続税の申告期限後に見つかった場合は、税務署へ修正申告を行い、追加の納税が必要になることがあります 。
- マイナスの財産(借金)の場合: 相続放棄の期限(3ヶ月)を過ぎてから見つかった場合、原則として返済義務を負うことになります。これは相続において最も避けたい事態の一つです 。
Q3: ネット銀行や仮想通貨などのデジタル遺産はどうやって調べますか?
A3: デジタル遺産の調査は非常に困難です。手がかりは、故人のパソコンやスマートフォンの閲覧履歴、メールの受信箱、パスワード管理アプリなどに残されていることが多いです 。取引所やネット銀行からのメール通知などが発見の糸口になります。しかし、ログインIDやパスワードが不明な場合、アクセス権を証明して開示を求めるには、法的な手続きが必要になるなど、専門家の助けなしでは難しいのが現状です。
Q4: 調査のために故人の預金口座からお金を引き出すと、相続放棄できなくなりますか?
A4: 非常に注意が必要な問題です。相続財産を自分のために使う(例:自分の生活費に充てる、自分の借金返済に使う)と、相続を承認した(法定単純承認)とみなされ、原則として相続放棄ができなくなります。ただし、故人の葬儀費用や、故人自身の未払いの医療費など、社会通念上相当な範囲での支払いに充てる場合は、単純承認とはみなされないことが多いです。しかし、判断が難しいため、もし預金を引き出す必要がある場合は、必ず事前に弁護士などの専門家に相談してください。
Q5: 遠方に住んでいても財産調査はできますか?
A5: 可能です。戸籍謄本や残高証明書など、多くの書類は郵送で取り寄せることができます 。
まとめ:正確な相続財産調査が、円満な相続と将来の安心を守る鍵
相続財産調査は、相続手続きという長い道のりの、最も重要で基礎となる工程です。その目的は、単に財産をリストアップすることに留まりません。
- 公平な遺産分割を実現し、家族間の無用な争いを防ぐため。
- 予期せぬ借金から身を守るため、相続放棄という重要な選択肢を確保するため。
- 正確な税務申告を行い、将来の追徴課税リスクを回避するため。
この調査は、相続放棄の「3ヶ月」、相続税申告の「10ヶ月」という厳格な期限に縛られており、迅速かつ正確な行動が求められます。財産の種類が少なければご自身で進めることも可能ですが、少しでも不安や困難を感じる場合は、決して一人で抱え込まず、早期に専門家へ相談することが賢明な判断です。
正確な財産調査は、故人が遺した大切な財産を円満に次の世代へ引き継ぎ、何よりも相続人ご自身の将来の安心を守るための、不可欠な鍵となるのです。
遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要

このように、相続財産調査には様々な難しい問題がありますし、その後の手続きでは交渉が必要になる場合もございますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。
遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。
司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律や交渉の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた場合や交渉が必要な場合に対応ができません。
弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。
法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
ページトップに戻る