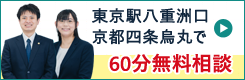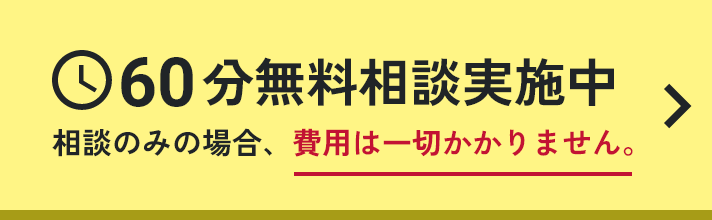相続財産の開示義務はある?遺産の開示拒否には内容証明で請求?
相続財産を開示させる方法を解説
相続が発生した際、「他の相続人が遺産をすべて開示してくれない」「財産を隠しているのではないか」という疑念や不安は、多くの方が直面する深刻な問題です。特に、亡くなった方(被相続人)の財産を特定の相続人が管理していたケースでは、その不透明さからトラブルに発展しがちです。
まず結論からお伝えすると、原則として、ある相続人が他の相続人に対して、相続財産の一覧をすべて開示する法的な義務はありません 。この法律上の現実が、多くの相続トラブルの根源となっています。
しかし、財産の開示を拒否されたとしても、決して泣き寝入りする必要はありません。あなたには、ご自身の権利として遺産を調査し、法的な手続きを通じてご自身の正当な取り分を確保する道が残されています。
この記事では、法律事務所リンクスの遺産相続に強い弁護士が、相続財産の開示義務の原則から、遺産の開示を拒否された場合の具体的な調査方法、そして隠された財産を取り戻すための法的手続きまで解説します。
遺産隠しの解決方法について詳しくは、「遺産隠しは罪?相続通帳見せないでも財産隠匿口座は調査でバレる?」をご覧ください。
相続財産の開示請求は拒否できる?ペナルティはない?
原則:相続財産の開示請求は拒否できるし、ペナルティはない
 日本の民法には、相続人の一人が他の相続人に対し、自発的に全相続財産の一覧を開示することを義務付ける直接的な規定は存在しません 。法律は、各相続人が対等な立場で、それぞれが自ら財産調査を行う権利を有するという前提に立っています。
日本の民法には、相続人の一人が他の相続人に対し、自発的に全相続財産の一覧を開示することを義務付ける直接的な規定は存在しません 。法律は、各相続人が対等な立場で、それぞれが自ら財産調査を行う権利を有するという前提に立っています。
そのため、他の相続人に「全財産リストを開示してください」と要求しても、相手がそれに応じなかったとしても、その行為自体が直ちに違法となるわけではありませんし、ペナルティもありません。
相続人の権利を完全に失わせる制度として「相続欠格」があります(民法第891条)が、この制度が適用されるのは、次のような場合に限られ、相続財産の隠匿は含まれません。
- 被相続人や他の相続人を殺害、または殺害しようとして刑に処せられた。
- 詐欺や強迫によって、被相続人に遺言をさせたり、撤回・変更させたりした。
- 相続に関する遺言書を偽造、変造、破棄、または隠匿した。
法律事務所リンクスは相続の相談が60分無料!
 法律事務所リンクスでは、遺産相続に強い弁護士による60分無料相談を実施しています。
法律事務所リンクスでは、遺産相続に強い弁護士による60分無料相談を実施しています。
相談に当たっては、ご予約いただいた際にご事情を伺い、調査をした上で相談に臨みますので、無料相談の時間内で充実した情報を提供しております。
相談者様が聞き足りなかったということが起きないようにしておりますし、ホワイトボードを使うなどして分かりやすく説明していますので、お気軽にお問い合わせください。
相続財産隠しについて動画でご覧になりたい方はコチラ
例外:遺言執行者は相続財産の開示請求を拒否できない
被相続人が遺言書を残し、その中で「遺言執行者」を指定していた場合、話は根本から変わります。遺言執行者とは、遺言の内容を忠実に実現するために、財産の管理や各種手続きを行う権限と義務を負う人物です。
遺言執行者がいる場合、あなたはもはや「情報を求める権利がない」立場から、「法律で定められた明確な権利を持つ」立場へと変わります。遺言執行者は、他の相続人に対して、以下のような法律上の重い義務を負っています。
遺言執行者の任務開始と遺言内容の通知義務
遺言執行者は、その任務を開始したとき、遅滞なく、遺言の内容を相続人全員に通知しなければなりません 。これにより、あなたは遺言の存在とその概要を正式に知ることができます。
財産目録の作成・交付義務
これが遺言執行者の最も重要な義務の一つです。遺言執行者は、遅滞なく相続財産の目録を作成し、それを相続人に交付する義務があります(民法第1011条)。この「財産目録」こそ、あなたが求めている相続財産の一覧そのものです。預貯金、不動産、有価証券など、プラスの財産もマイナスの財産(借金など)もすべて記載されたリストを受け取る権利が、あなたには法律で保障されているのです 。
参照:法務省HP「遺言執行者の権限の明確化等 」
任務の状況報告義務
相続人は、いつでも遺言執行者に対して、遺言執行の事務処理状況について報告を求めることができます(民法第645条の準用)。手続きがどこまで進んでいるのか、不明な点があれば説明を求めることが可能です。
この開示義務は、遺留分(法律で最低限保障された相続分)を持つ相続人だけでなく、遺留分がない相続人に対しても等しく適用されると解されています 。
もし遺言執行者がこれらの義務を怠り、財産目録の交付を拒んだり、報告に応じなかったりした場合は、家庭裁判所に遺言執行者の解任を申し立てたり、任務懈怠を理由に損害賠償を請求したりすることも可能です 。したがって、遺言執行者の存在は、相続財産の開示における極めて強力な切り札となり得るのです。
相続財産の開示を受けられない場合の対策
相続財産が開示されない場合、相続財産を調査する必要が生じます。
各資産の種類ごとに、どこで何をすべきかを次の表にまとめています。
ご自身で調査することも可能ですが、作業量が多く大変なので弁護士への依頼をお勧めします。
| 資産の種類 | 調査方法 | 調査先 | 必要な主な書類 | 専門家からのヒント |
| 預貯金 | 残高証明書、取引履歴の取得 | 各金融機関(銀行、信用金庫など) | 被相続人の除籍謄本、相続人であることがわかる戸籍謄本、請求者の本人確認書類・印鑑 | 被相続人の自宅にあったカレンダーや粗品のボールペン、郵便物などが金融機関を特定する手がかりになります 。取引履歴からは、保険料の引き落としなど、他の資産の存在が判明することもあります 。 |
| 不動産 | 名寄帳(なよせちょう)/固定資産課税台帳の取得 | 財産があると思われる市区町村役場の資産税課など | 上記と同様の相続関係を証明する書類一式 | 「名寄帳」は、その市区町村内に個人が所有する不動産をすべて一覧にしたもので、未知の不動産を発見するのに最も効果的です 。 |
| 上場株式・投資信託 | 登録済加入者情報の開示請求 | 株式会社証券保管振替機構(通称「ほふり」) | ほふり所定の請求書、相続関係証明書類、被相続人の住所証明書類、請求者の印鑑証明書など | ほふりの開示でわかるのは「どの証券会社に口座があるか」までです。その後、各証券会社に別途、残高証明書などを請求する必要があります 。 |
| 生命保険 | 契約内容の照会 | 各生命保険会社 | 死亡診断書、相続関係証明書類など | どの保険会社と契約していたか不明な場合、預貯金の取引履歴から保険料の支払先を探すのが有効な手段です 。 |
| 貸金庫 | 契約の有無の照会と開扉請求 | 各金融機関 | 相続関係証明書類など。開扉には相続人全員の立ち会いと実印を求められることが多い。 | 不動産の権利証や株券、貴金属など、重要な資産が保管されている可能性があります 。 |
預貯金の詳しい調査手順
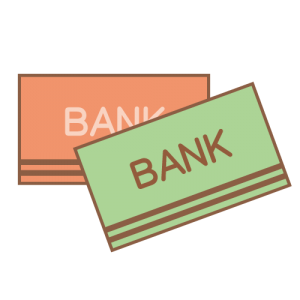 預貯金の調査では、「残高証明書」と「取引履歴」の2種類を取得することが重要です。
預貯金の調査では、「残高証明書」と「取引履歴」の2種類を取得することが重要です。
- 残高証明書: 被相続人が亡くなった日時点での預金残高を証明する書類です。遺産分割の対象となる金額を確定するために必要です。
- 取引履歴: 過去の入出金の流れがすべて記録されています。特に被相続人の死亡前後の不自然な出金(使い込み)を調べるためには必須の書類です 。
金融機関は通常、過去10年分の取引履歴を保存してるのが原則です 。調査の際は、被相続人の最後の戸籍謄本(死亡の事実が記載されたもの)、ご自身の現在の戸籍謄本(あなたが相続人であることを証明するため)、そして運転免許証などの本人確認書類と印鑑を持参して、金融機関の窓口で手続きを行います 。
不動産の詳しい調査手順
 不動産調査の鍵は「名寄帳(なよせちょう)」です。これは、特定の人がその市区町村内に所有している不動産(土地・家屋)をすべてリストアップした台帳です 。被相続人がどこに不動産を持っていたか完全にはわからなくても、心当たりのある市区町村役場の資産税課(固定資産税担当課)で名寄帳の写しを請求することで、隠れた不動産を発見できる可能性があります 。
不動産調査の鍵は「名寄帳(なよせちょう)」です。これは、特定の人がその市区町村内に所有している不動産(土地・家屋)をすべてリストアップした台帳です 。被相続人がどこに不動産を持っていたか完全にはわからなくても、心当たりのある市区町村役場の資産税課(固定資産税担当課)で名寄帳の写しを請求することで、隠れた不動産を発見できる可能性があります 。
手続きは、預貯金調査と同様に、相続人であることを証明する戸籍謄本一式と本人確認書類を持参して行います 。名寄帳で不動産の地番などが判明したら、次にその情報を元に管轄の法務局で「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得します。これにより、不動産の正確な情報や所有権の状況を最終確認できます 。
有価証券の詳しい調査手順
株式や投資信託などの有価証券は、証券会社を通じて取引されるため、どの証券会社に口座があったかを特定する必要があります。しかし、被相続人がどの証券会社を利用していたか不明なケースは少なくありません。
このような場合に利用するのが、「証券保管振替機構(ほふり)」への開示請求です 。ほふりは、日本国内の上場株式などを集中的に管理している機関であり、相続人はここに照会することで、被相続人が口座を開設していた証券会社や信託銀行の一覧を知ることができます。
手続きは、ほふりのウェブサイトから専用の請求書類を入手し、必要事項を記入の上、戸籍謄本などの相続関係を証明する書類や手数料を添えて郵送で行います 。
ここで非常に重要な注意点があります。ほふりからの回答でわかるのは、あくまで「口座を開設していた金融機関名」までです。その口座に具体的にどのような銘柄が、どれくらいの株数あったのかという詳細な内容までは記載されていません。したがって、ほふりの開示結果を受け取った後、判明した各証券会社に対して、個別に残高証明書の請求手続きを行う必要があります 。
財産発見後の法的措置:遺産分割or返還請求
調査の結果、財産が発見された場合、次はその財産を正当に分割し、場合によっては使い込まれた分を取り戻すための具体的な行動に移ります。
遺産分割
遺産分割協議
相続財産が残っている場合には、遺産分割協議をして相続財産を分けることになりますが、相続財産の開示を拒否している相続人の場合、遺産分割協議に応じない可能性が高いです。
その場合には、次に説明する遺産分割調停をする必要があります。
遺産分割調停
遺産分割調停とは、家庭裁判所において、裁判官1名と民間の良識ある有識者から選ばれた調停委員2名以上で構成される「調停委員会」を仲介役として、相続人全員が遺産分割について話し合う手続きです 。
調停の目的は、中立的な第三者の助言を受けながら、当事者全員が納得できる合意点を見つけ出すことです 。調停委員が一方的に分割方法を決めるのではなく、あくまで話し合いを円滑に進めるための手助けをしてくれます。
調停が不成立の場合:最終手段としての「審判」
万が一、調停で話し合いがまとまらなかった場合、手続きは自動的に「遺産分割審判」に移行します 。
審判では、話し合いではなく、裁判官がこれまで提出されたすべての証拠や主張を審査し、法的な基準に基づいて最終的な遺産の分割方法を決定します。これにより、紛争には必ず決着がつきますが、その内容は必ずしも当事者の希望に沿うものとは限りません。最後まで話し合いでの解決を目指す姿勢が重要です。
返還請求
発見された財産が、既に相手によって費消されていた(使い込み)場合、その金銭的価値を取り戻すための請求を行います。これには主に2つの法的構成があり、それぞれ時効(請求できる期間の制限)が異なるため、注意が必要です。
不当利得返還請求
これは、「相手は法律上の正当な理由なくあなたの財産(相続分)によって利益を得て、あなたに損失を与えたのだから、その利益を返しなさい」と請求するものです 。法的根拠は民法第703条にあります 。遺産の使い込みに対して一般的に用いられる請求方法です。
不法行為に基づく損害賠償請求
これは、「相手の行為(使い込み)は、あなたの権利を侵害する違法な行為(不法行為)であり、それによって生じた損害を賠償しなさい」と請求するものです。
消滅時効に注意
これらの請求権には「時効」という厳しい時間制限が設けられています。この期限を過ぎると、たとえ証拠が揃っていても権利を主張できなくなってしまいます。
【重要】法的措置のタイムリミット(時効期間)
| 法的請求権 | 時効期間 | いつからカウントが始まるか(起算点) |
| 不当利得返還請求 | 5年 または 10年 | 権利を行使できることを知った時から5年、または、権利が発生した時(使い込み行為の時)から10年の、いずれか早い方 。 |
| 不法行為に基づく損害賠償請求 | 3年 | 損害および加害者を知った時から3年、または、使い込み行為から20年。 |
使い込み行為から10年以上経過している場合には、不法行為に基づく損害賠償請求をする必要がありますが、使い込みを知ってから3年以内に請求しなければなりません。遺産の使い込みが発覚したら、一刻も早く専門家に相談し、行動を起こすことが極めて重要です。
まとめ
本記事で解説してきたように、「相続財産を開示する法的な義務は原則としてない」ですが、相続財産の調査をして、法的手続きをとることで解決可能です。しかし、あなたは決して無力ではありません。解決への道筋は明確です。
このプロセスにおいて最も重要なのは、「時間」です。使い込みの返還請求権などには、3年や5年といった短い時効が設定されており、行動が遅れれば取り戻せるはずの財産も取り戻せなくなります。
相続財産の調査や法的な手続きは非常に複雑であり、専門的な知識がなければ有利に進めることは困難です。遺産隠しを疑ったとき、それは感情的な対立に陥るのではなく、冷静に、そして迅速に専門家である弁護士に相談すべきサインです。プロフェッショナルの助言とサポートを得ることが、あなたの正当な権利を守り、公正な解決に至るための最も確実な道筋となるでしょう。
遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要

このように、相続財産の開示には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。
遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。
司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律や交渉の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた場合や交渉が必要な場合に対応ができません。
弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。
法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
ページトップに戻る