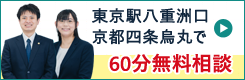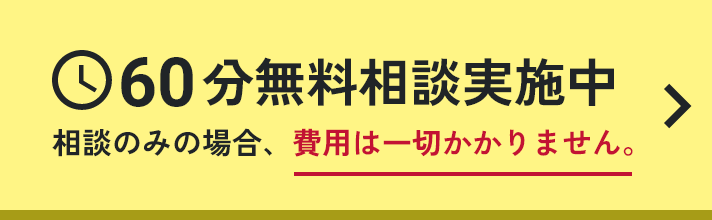遺産相続の使い込みで泣き寝入りしない!横領の立証方法
遺産の使い込みはどのように証明すればよい?
遺産相続の使い込みとは、被相続人の財産を、相続人の一人が、被相続人の同意なく勝手に、自分のために使用したり、処分したりすることです。特に、被相続人が認知症などで財産管理能力が低下しているのをいいことに無断で引き出したことが死後に発覚し、遺産分割の際に問題となることが多いです。
遺産相続の使い込みは、不当利得や横領に当たる場合には取り戻せる可能性が十分にありますが、客観的な「証拠」を集める必要があります。
このページでは、法律事務所リンクスの遺産相続に強い弁護士が、遺産の使い込みが疑われる場合にまず確認すべきことから、返還請求を成功させるための具体的な証拠集め、法的な手続き、そして注意すべき時効まで、問題解決の全手順を解説します。
遺産を使い込まれたと疑われている方は「遺産の使い込みを疑われているが潔白を証明したい」をご覧ください。
まずは遺産の使い込みが横領や不当利得に当たるかを確認
「遺産の使い込みではないか」と疑念を抱いたとき、まず冷静にその支出が本当に「不当なもの」なのかを見極める必要があります。全ての出金が使い込みに該当するわけではないため、正当な支出との境界線を理解することが、その後の対応を円滑に進めるための第一歩となります。
まず、被相続人の財産から支出されていても、使い込みとは言えないケースがあります。具体的には、被相続人自身の生活費、入院や介護にかかった医療費、税金の支払いなど、本人のために使われた費用は正当な支出とみなされます 。また、社会通念上、妥当な範囲の葬儀費用も、相続財産から支払われることが一般的です。
これに対し、被相続人の入院中や介護施設入所中など、本人が動けないはずの時期に、多額の現金が繰り返し引き出されている場合、誰が引き出したかが明らかになれば、その者に対して、横領に当たるとして民事の損害賠償請求や不当利得返還請求をすることができる可能性が高くなります。
もっとも、使い込まれた遺産の返還を求めるには、①預貯金等が引き出されたこと、②預貯金等の引き出しをした者の特定、③②の者による預貯金等の引き出しが無断であったことまたは引き出した預貯金が不当に使込まれたこと立証する必要がありますので、専門家である弁護士に相談することが必要です。
法律事務所リンクスは相続の相談が60分無料!
 法律事務所リンクスでは、遺産相続に強い弁護士による60分無料相談を実施しています。
法律事務所リンクスでは、遺産相続に強い弁護士による60分無料相談を実施しています。
相談に当たっては、ご予約いただいた際にご事情を伺い、調査をした上で相談に臨みますので、無料相談の時間内で充実した情報を提供しております。
相談者様が聞き足りなかったということが起きないようにしておりますし、ホワイトボードを使うなどして分かりやすく説明していますので、お気軽にお問い合わせください。
遺産の使い込みの立証方法を動画でご覧になりたい方はコチラ
相続の使い込みの立証方法

相続人が、遺産の使い込みの返還を求めることができるのは、使い込んだ人が亡くなられた被相続人の財産に損失を与えて不当に利得したからであり、これを不当利得返還請求と言います。
相手方が遺産を使い込んで不当に利得したことを認めてくれれば、不当利得の返還を求めるだけでよいですが、遺産である預金を引き出したことや使い込んだことを認めてくれない場合に不当利得の返還を求めるには、次の3つの事実を証明する必要があります。
- 預貯金が引き出されていること
- 預貯金を引き出した者の特定
- 預貯金の引き出しが無断であったこと
逆に言えば、遺産を使い込まれたと疑われている人は、①か②か③のどれかの反論に成功すれば、使い込みを否定することができます。
1 預貯金が引き出されていること
取引履歴の取寄せ
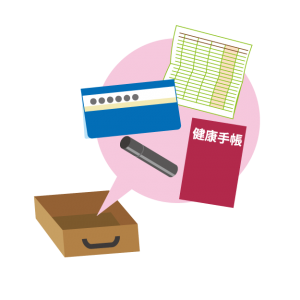
遺産である預金の使い込みを疑われている人が相続財産を開示してくれればよいですが、そう易々と自分が管理している相続財産を開示してくれるとは限りません。
また、その相続人が相続財産を開示してくれたとしても、巧妙に遺産が隠されている可能性がありますし、遺産を使い込んだことを認めない可能性があります。
そのような場合には、自ら預貯金等の取引履歴を取り寄せたり、銀行に調査を掛ける必要があります。
相続人の場合、預貯金等が存在する(した)金融機関名(と支店名)を知っていれば、その金融機関に開示請求することで、取引履歴を取り寄せることができますが、自分で金融機関所定の書類を集めなければなりませんので、面倒かもしれません。
弁護士の場合、相続人の代理人として、被相続人の取引履歴を取り寄せることが可能です。ただし、取引履歴は取り寄せ時点からさかのぼって10年分しか請求できないことが多いので、10年使く前に引き出された可能性があるのであれば、早めに取寄せなければなりません。
取引履歴の調査
取引履歴を取り寄せると、不自然な出金や解約がないかを調査することになります。
一度に多額の出金や継続的に不自然な出金があった場合、不必要な解約があった場合には、使い込みが疑われます。
取引履歴には様々な情報が集約されています。例えば、どの支店で出金されたのか、その出金は窓口なのかATMなのかなどは、誰が引き出したのかのヒントになります。
また、他の金融機関の被相続人名義の口座への振込履歴がある場合には、その金融機関に被相続人名義の口座が残っている可能性が考えられますし、被相続人が年金受給者であったにもかかわらず取引履歴に年金の入金記録がない場合には、やはり他の金融機関に被相続人名義の口座がある可能性が考えられます。
このような相続財産を綿密に調査するには、証拠読みのプロである弁護士が必要です。
2 預貯金等を引き出した者の特定
預貯金等を引き出したものを特定しないと、別の人が遺産を使い込んだ可能性が残るため、使い込んだ遺産を返還するよう請求することはできません。
とはいえ、遺産を使い込んだことを直接証明することは難しいことが多いので、遺産が使い込まれた時期にその遺産を管理していたことを証明することで、別の人が遺産を使い込んだ可能性を否定することが必要となります。
相手方が遺産である預金が使い込まれた時期に、その預金口座を管理していたことについては認めてくれる場合も多いです。この場合には、被相続人が出金に同意していたのか、無断で引き出したのかという問題になります(3の「無断引き出しの証明」参照)。
これに対して、遺産が使い込まれた時期に、遺産である預金を誰が管理していたことを否定された場合には、証明のハードルが上がります。被相続人自身に遺産の管理能力がなく、唯一の同居人である相手方が遺産を管理していたとしか考えられないという場合には、相手方が遺産の管理者であったことは否定できないでしょうが、微妙なケースも多いです。
リンクスの経験した事例では、相手方が預金を管理していたのを否定したのに対し、相手方が被相続人と同居していたこと、被相続人が証券被害に遭っていたり、医療機関の診療記録や介護を担当していたケアマネージャーへの照会内容からして、被相続人が認知症であったと考えられること、相手方のブログで預金が引き出された後で豪華な海外旅行に何度も掛けていたことなどを証明することで、裁判所に相手方が遺産を管理していたことを認めてもらい、1000万円を超える使い込みを認めてもらったことがあります。
このように、医療機関の診療記録や介護の記録が大事になることが多いですが、保存期間がありますので、くれぐれもご注意ください。
3 預貯金等が無断で引き出されたこと
1の引き出しの事実と2の遺産の管理者であった事実が証明されれば、預貯金等の引き出しの事実はほぼ明らかとなったことになりますが、預貯金等を引き出していたとしても、本人の同意を得ていれば何の問題もありませんので、無断の引き出しであったことを証明する必要があります。
もっとも、1の引き出しの事実と2の遺産の管理者であった事実の証明によって、預貯金等の引き出しはほぼ明らかとなっているわけですから、遺産の使い込みを否定したい側としても、被相続人にどのような形で預貯金等の引き出しの了承を得ていたのかを積極的に明らかにしていかなければなりません。
例えば、
・本人からその都度了承をとっていたのか、包括的な了承を得ていたのか
・引き出した預貯金等を本人等に渡していたのか、渡しはせずに本人のために使用していたのか
・本人のために使用していたとすれば、その使途は何だったのか
・贈与を受けたのだとすれば、贈与の証拠は何なのか
などを説明する必要があります。
遺産の使い込みは横領罪になる?
使い込みが立証できて横領に当たるとしても、刑事事件における横領罪に問われるかどうかは別の問題で、親族間の窃盗や横領は刑事罰に問われないケースが多いです。
これは刑法の「親族相盗例」という法律の特例によるもので、配偶者や直系の血族、同居の親族間での窃盗・横領等は刑が免除されると定められているからです。
ただ、これはあくまで刑事罰が科されないというだけであり、使い込んだ財産を返還する民事上の義務がなくなるわけではありません。
遺産の使い込みが疑われる場合には、弁護士に相談するなどして、返還を求めることは可能です。では、どのようにして取り戻すのでしょうか。
使い込まれた遺産を取り戻すための3つのステップ
証拠がある程度集まったら、次はいよいよ遺産を取り戻すための具体的な行動に移ります。
ステップ1:取引履歴をもとに事実関係を確認する
まずは、集めた取引履歴を基に、使い込みをしたと思われる相手に対し、預貯金の引き出しについての事実関係を確認します。
相手方が引き出しの事実を認めた場合には、預貯金等を引き出したものが特定できたことになるので、被相続人から同意を得ていたのかや、使途を確認することになります。
この際、相手方が後から違うことを言い出さないように、録音しておくことをお勧めします。
ステップ2:弁護士に相談・依頼する
相手方が預貯金の引き出しを認めなかったり、預貯金の引き出しを認めたものの、被相続人から同意を得ていたとか、被相続人のために使用したなどと主張する場合には、交渉がまとまらないケースも少なくありません。親族同士であるため感情的な対立が激化し、冷静な話し合いが困難になることも多いでしょう。
そのような状況に陥った場合は、速やかに弁護士に相談・依頼することを検討すべきです。法律の専門家である弁護士が代理人として交渉の窓口に立つことで、相手方も事の重大さを認識し、真摯な対応に転じる可能性があります 。弁護士は法的な根拠に基づいて相手の責任を明確にし、論理的に交渉を進めるため、当事者同士で話すよりも円満かつ迅速な解決が期待できます。
ステップ3:法的手続きで返還を求める
弁護士を介した交渉でも解決しない場合は、裁判所を利用した法的手続きに移行します。主な方法として、「不当利得返還請求訴訟」と「遺産分割調停」の2つが挙げられます。
不当利得返還請求訴訟:最も一般的な方法
これは、法律上の正当な理由なく他人の財産によって利益を得た者に対し、その利益の返還を求める民事訴訟です 。遺産の使い込みは、まさにこの「不当利得」に該当する典型例です。被相続人の生前に行われた使い込みの返還を求める場合、この訴訟が最も一般的な手段となります。訴訟では、原告側(請求する側)が、相手による使い込みの事実を証拠に基づいて立証する必要があります。
遺産分割調停:相続人同士の話し合いで解決を目指す
遺産分割調停は、相続人全員が遺産の分け方について合意できない場合に、家庭裁判所で調停委員を介して話し合い、解決を目指す手続きです 。
この手続きは、あくまで現存する遺産の分割が目的ですが、使い込みをした人が特定できている場合、他の相続人全員の同意があれば、その使い込まれた財産を「遺産に持ち戻して(遺産に含めて)」分割協議を行うことが可能になりました 。
これにより、別途訴訟を起こすことなく、遺産分割の一環として使い込み問題を解決できる道が開かれました。調停では、当事者が直接顔を合わせる必要はなく、調停委員が個別に意見を聞き取りながら調整を進めてくれるため、感情的な対立を避けやすいというメリットがあります 。
ただし、相手が使い込みの事実を頑なに否定し、相続人全員の合意が得られない場合は、調停での解決は困難となり、別途訴訟が必要になることもあります。
どちらの手続きを選択すべきかは、使い込みが行われた時期や、他の相続人との関係性など、状況によって異なります。弁護士と相談の上、最適な戦略を立てることが重要です。
【重要】返還請求のタイムリミット「時効」に注意
使い込まれた遺産を取り戻す権利は、永久に保障されるわけではありません。法律には「時効」という制度があり、一定期間が経過すると権利を主張できなくなってしまいます。使い込みに気づいたら、迅速に行動を起こすことが何よりも重要です。
返還請求の主な法的根拠である「不当利得返還請求」と、もう一つの選択肢である「不法行為に基づく損害賠償請求」では、時効の期間が異なります。
- 不当利得返還請求権の時効 民法第166条の規定により、以下のいずれか早い方が到来した時点で時効が成立します 。
- 権利を行使できることを知った時(使い込みの事実と犯人を知った時)から5年
- 権利を行使できる時(使い込み行為があった時)から10年
- 不法行為に基づく損害賠償請求権の時効 民法第724条の規定により、以下のいずれか早い方が到来した時点で時効が成立します 。
- 損害及び加害者を知った時から3年
- 不法行為の時(使い込み行為があった時)から20年
例えば、使い込みの事実を知ってから4年が経過してしまった場合、「不法行為」としての請求(時効3年)はできなくなりますが、「不当利得」としての請求(時効5年)はまだ可能です。このように、複数の請求権が存在することで、状況によっては救済の道が残されている場合があります。
この時効の進行を止める(法律上は「完成猶予」や「更新」といいます)ためには、内容証明郵便で返還を催告したり、裁判所に訴訟や調停を申し立てたりする必要があります 。証拠収集には時間がかかることも多いため、「まだ大丈夫」と安易に考えず、使い込みが発覚した時点ですぐに専門家へ相談することが、権利を守る上で極めて重要です。
遺産の使い込みに関するよくある質問(FAQ)
Q. 明確な証拠がない場合、諦めるしかないのでしょうか?
A. 諦めるのは早計です。「払戻請求書の筆跡」のような決定的な証拠がなくても、状況証拠を積み重ねることで使い込みを立証できる可能性はあります。例えば、「被相続人が寝たきりだった時期の出金記録」や「相続人の収入に見合わない高額な支出」などを組み合わせることで、相手の主張の矛盾を突くことができます。どのような情報が証拠になり得るかを含め、まずは弁護士に相談してみることをお勧めします 。
Q. 使い込んだ相手にお金がない場合、取り戻せませんか?
A. 残念ながら、相手に資力(支払い能力)がなければ、たとえ裁判で勝訴しても現実的に回収することは困難です。これが返還請求における大きな壁の一つです 。しかし、弁護士に依頼すれば、相手の財産状況を調査することも可能です。すぐに返済できなくても、相手が受け取るはずの相続分から相殺したり、将来の収入からの分割払いを約束させたりするなど、様々な解決策を探ることができます。
Q. 弁護士費用はどのくらいかかりますか?
A. 弁護士費用は法律事務所や事案の難易度によって異なりますが、一般的には「相談料」「着手金」「報酬金」で構成されます。相談料は初回無料の事務所も多くあります 。着手金は依頼時に支払う費用で20万円から50万円程度、報酬金は実際に回収できた金額の4%から16%程度が相場とされています 。まずは無料相談などを利用して、費用体系について明確な説明を受けるとよいでしょう。
Q. 裁判をせずに解決する方法はありますか?
A. はい、あります。全てのケースが裁判になるわけではありません。実際には、弁護士が代理人として交渉を行うことで、訴訟に至らずに和解(示談)で解決するケースも数多くあります。また、家庭裁判所での「遺産分割調停」も、裁判官や調停委員が間に入って話し合いによる解決を目指す手続きであり、訴訟とは異なります (参照:裁判所HP「遺産分割調停」)。
遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要

このように、遺産の使込みの証明には、様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。
弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。
法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
ページトップに戻る