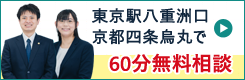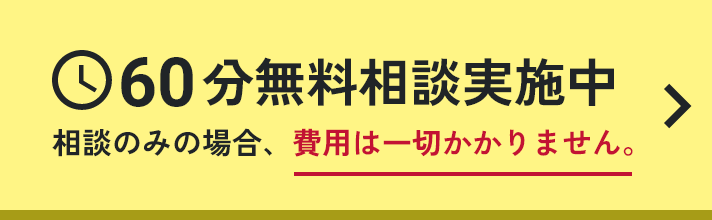遺留分の時効は1年!侵害額請求に相続から5年10年かかると中断できない?
遺留分の時効や中断方法が知りたいのですが?
遺留分の時効とは、「遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。」(民法1048条前段)ことを意味します。
時効を止める(更新する)には、相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年以内に、内容証明郵便などで遺留分侵害額請求をすることの意思表示をする必要があります。
なお、遺留分侵害額請求権を行使する人が遺留分の侵害を知らなかったとしても、相続の開始から10年が経過すると遺留分侵害額請求権が行使できなくなりますので、自筆証書遺言や公正証書遺言をきちんと調査する必要があります。
また、相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年以内に、内容証明郵便などで遺留分侵害額請求をすることの意思表示をしたとしても、意思表示から5年が経過した場合には、遺留分侵害額請求権が消滅します。
これらの時効は、それぞれ起算点(カウントが始まるタイミング)や性質が異なり、ご自身の状況に応じてどの時効が適用されるのかを正確に理解することが、権利を守るための第一歩です。
この記事では、法律事務所リンクスの遺産相続問題に精通した弁護士が、この複雑な遺留分の3つの時効制度について、全体像から具体的な手続き、注意すべき落とし穴まで、わかりやすく解説します。
最重要!「知ってから1年」の短期消滅時効
3つの時効の中で、最も注意が必要で、かつ多くの方が権利を失う原因となるのが、この「1年の短期消滅時効」です。
「1年の時効」とは?(民法1048条)
民法第1048条には、遺留分侵害額の請求権について次のように定められています。
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
これは、遺留分を請求する権利があることを知っていながら、長期間その権利を行使しない状態を放置させず、法律関係を早期に安定させるための規定です 。ご家族が亡くなってから四十九日や一周忌を終え、落ち着いてから考えよう、と思っているうちに、この1年という期間はあっという間に過ぎてしまいます 。
時効がスタートする「起算点」とはいつ?
この1年の時効がいつからカウントされ始めるのか、すなわち「起算点」が極めて重要です。条文にある通り、起算点となるためには、以下の2つの条件が両方とも満たされる必要があります 。
①相続の開始(被相続人の死亡)を知った時
これは、被相続人が亡くなったという事実を知った時点を指します 。通常は、ご家族が亡くなった連絡を受けた日などがこれにあたります。
②遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時
こちらが非常に複雑で、トラブルになりやすい点です。単に「遺言書があるらしい」とか「生前に贈与があったらしい」と知っているだけでは、通常、時効はスタートせず、その贈与や遺贈の内容を知り、それによって自分の遺留分が侵害されていることまで認識する必要があります 。
具体的には、以下のような状態を指します。
- 「全財産を長男に相続させる」という遺言書の内容を具体的に読んだ、または聞かされて理解した時。
- 被相続人の遺産総額がおおよそどのくらいかを把握した上で、特定の相続人や第三者への多額の生前贈与の事実を知り、その結果として自分の取り分が遺留分を下回ることを認識した時。
「知った時」が争点になるケースと具体例
この「知った時」は、遺留分権利者の主観的な認識の問題であるため、後から「いつ知ったのか」をめぐって相手方と争いになることが多いです 。
【争点になりやすいケース】
- ケース1:遺言書の内容を伝えられたが、ちゃんと見ていない
- 他の相続人から「親父の遺言では、お前に財産はいかないことになっている」と口頭で伝えられたが、遺言書の現物は見ていない場合。相手方は「伝えた時点で知ったはずだ」と主張し、こちらは「具体的内容を知らないので時効は始まっていない」と反論する、といった対立が起こり得ます。
- ケース2:遺産の全体像が不明
- 特定の不動産が兄に遺贈されたことは知っていても、他にどれだけの預貯金や有価証券があるか分からず、自分の遺留分が侵害されているかどうかの判断がつかない場合。遺産の全容が判明して初めて侵害を認識した、と主張することになります。
このように、「知った時」の証明は非常に難しく、裁判になった場合、立証の負担や訴訟の長期化という大きなリスクを伴います。そのため、法的な観点からの最も安全な戦略は、「知った時」がいつかという不毛な争いを避けるため、原則として被相続人が亡くなってから1年以内に請求のアクションを起こすことです 。
法律事務所リンクスは遺留分侵害額請求の相談が60分無料!
 法律事務所リンクスでは、遺留分に強い弁護士による60分無料相談を実施しています。
法律事務所リンクスでは、遺留分に強い弁護士による60分無料相談を実施しています。
相談に当たっては、ご予約いただいた際にご事情を伺い、調査をした上で相談に臨みますので、無料相談の時間内で充実した情報を提供しております。
相談者様が聞き足りなかったということが起きないようにしておりますし、ホワイトボードを使うなどして分かりやすく説明していますので、東京で相続に強い弁護士に相談されたい方は「東京で相続を弁護士に無料相談なら法律事務所リンクス」のサイトから、京都で相続に強い弁護士に相談されたい方は「京都で相続を弁護士に無料相談なら法律事務所リンクス」のサイトからお気軽にお問い合わせください。
遺留分請求の注意点について動画でご覧になりたい方はコチラ
遺留分の時効を止める方法(時効の完成猶予と更新)
では、迫りくる時効を止めるには、具体的にどうすればよいのでしょうか。民法改正により、従来の「時効の中断」という言葉は、「時効の完成猶予」と「時効の更新」という概念に整理されました 。
- 時効の完成猶予: 時効の完成が一時的にストップ(猶予)されること。
- 時効の更新: それまで進行していた時効期間がリセットされ、ゼロから再びカウントが始まること。
ここでは、1年の時効と5年の時効、それぞれを止めるための具体的な方法を解説します。
1年の時効を止める最も確実な方法:内容証明郵便による請求
1年の短期消滅時効の完成を阻止するためには、期間内に相手方に対して「遺留分侵害額を請求する」という明確な意思表示を行う必要があります。口頭や普通のメール、手紙では、後から「言った」「言わない」の水掛け論になり、証拠として不十分です。
最も確実で、法的に推奨される方法が「配達証明付き内容証明郵便」の送付です 。
内容証明郵便とは?
内容証明郵便とは、郵便局が「いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛に差し出されたか」を証明してくれるサービスです。さらに「配達証明」を付けることで、「相手がその郵便物をいつ受け取ったか」まで証明できます。これにより、期限内に請求の意思表示を行ったという動かぬ証拠を残すことができるのです。
記載すべき必須事項と文例
内容証明郵便に記載する内容は、この段階では詳細な金額計算などは不要です。重要なのは、遺留分を請求する意思を明確に伝えることです 。
【記載必須事項】
- 通知人の氏名・住所(あなた)
- 被通知人の氏名・住所(請求相手)
- 被相続人の氏名と死亡日
- 遺留分を侵害する遺言や贈与の特定(例:「〇年〇月〇日付の自筆証書遺言により」など)
- 遺留分侵害額請求権を行使する旨の明確な意思表示
- 通知日
【文例】
遺留分侵害額請求通知書
被通知人:〇〇 〇〇 様
私は、貴殿に対し、以下の通り通知いたします。
令和〇年〇月〇日に逝去した被相続人〇〇 〇〇(以下「被相続人」といいます)の相続が開始いたしました。
被相続人が作成した令和〇年〇月〇日付の遺言は、被相続人の全財産を貴殿に相続させる内容となっており、これにより私の遺留分が侵害されております。
つきましては、本書面をもって、民法第1046条に基づき、貴殿に対し遺留分侵害額の支払いを請求いたします。
速やかに、遺産内容を開示の上、具体的な金額について協議いたしたく、本書面到達後2週間以内にご連絡くださいますようお願い申し上げます。
令和〇年〇月〇日
通知人:〇〇 〇〇 住所:東京都〇〇区〇〇 氏名:〇〇 〇〇 印
誰に送るべきか?(受遺者・受贈者全員)
遺留分を侵害している原因が複数ある場合(例:長男への遺言による遺贈と、次男への生前贈与)、その原因となっている財産を受け取った全員に対して、それぞれ内容証明郵便を送付する必要があります 。誰か一人にでも送り忘れると、その人に対する請求権は時効消滅してしまう可能性があるため、注意が必要です。
遺留分を請求した後の注意点は?

① 遺留分を請求しても簡単に応じてくれることはない
被相続人から遺贈・生前贈与を受けた人は、自分がそれだけの財産を受け取るのにふさわしいからこそ受け取ったと考えるので、遺留分を請求されても応じてくれないことが多いです。
また、遺留分を請求した場合、感情がもつれてしまって相手からの反論を誘発し、結果的に遺留分の請求にとって不利な事態に追い込まれることがあります。
きちんとした形で遺留分を請求したいとお考えであれば、どのような形で請求するか、相手方が支払わない場合にどのような対応をするかなどについて、最初から遺産相続問題に強い弁護士に無料相談された方がよいと思います。
② 遺留分の請求には理屈と証拠が必要
財産をもらって当たり前と考えている相手方に遺留分を支払わせるには、遺留分の金額とその根拠について、説得力をもって正確に説明することが大事になります。
また、仮に支払ってもらえない場合、調停や裁判を起こすことを検討しなければなりませんが、遺留分の調停や裁判で重要なのは理屈と証拠です。
したがって、遺留分を請求する段階から、調停・裁判を見据えて証拠を集めつつ、説得力のある理屈を立てておく必要があります。
遺留分を請求したいとお考えの方は「遺留分を請求したい」をご覧ください。
知らなくても権利が消える「相続開始から10年」の除斥期間
1年の短期消滅時効とは別に、遺留分にはもう一つの絶対的な時間制限が設けられています。それが「相続開始から10年」の除斥期間です。
「10年の除斥期間」とは?
民法第1048条の後半部分には、次のように規定されています。
相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
これは、被相続人が亡くなってから10年が経過すれば、たとえ遺留分権利者が相続の開始(親の死亡など)や遺留分を侵害する遺言・贈与の存在を全く知らなかったとしても、遺留分を請求する権利は完全に消滅するという規定です 。
この制度が設けられている背景には、法律関係の安定を優先するという考え方があります。何十年も経ってから突然、相続の権利を主張する人が現れると、すでに完了した遺産分割が覆されたり、遺産を元に事業を行っていたり、不動産を売却してしまっていたりした場合に、社会的な混乱が生じかねません。そこで、10年という長い期間をもって、相続に関する権利関係を確定させる目的があるのです 。
消滅時効との違い – 10年経過で自動的に権利が消滅
1年の「消滅時効」と10年の「除斥期間」の決定的な違いは、その効果の発生方法にあります 。
- 消滅時効(1年): 相手方による「時効の援用」があって初めて権利が消滅する。
- 除斥期間(10年): 期間が経過すれば、誰の主張も必要なく、自動的に権利が消滅する。
つまり、10年の除斥期間が経過してしまった場合、もはや議論の余地なく、権利は法律上存在しなくなります。
10年の除斥期間は止められない(中断・更新は不可)
もう一つの重要な特徴は、この10年の期間は、一度スタートしたら誰にも止められないという点です 。後述する「時効の完成猶予・更新」といった、時効の進行をストップさせたりリセットさせたりする手続きは、除斥期間には適用されません 。相続開始の瞬間から、10年後のゴールに向かって、時計の針は確実に進み続けます。
特に注意すべきケース(長年音信不通だった場合など)
この10年の除斥期間によって権利を失うリスクが特に高いのは、以下のような方々です。
- 前妻・前夫との間の子で、被相続人と長年音信不通だった場合
- 親が亡くなった事実を知らされないまま10年が経過してしまうケースは少なくありません 。
- 海外に居住しており、日本の家族との連絡が途絶えがちだった相続人
- 複雑な家庭環境で、自分が相続人であることを認識していなかった場合
このような状況にある方は、権利を失わないためにも、定期的に戸籍謄本を取り寄せて親族の状況を確認するなど、自ら情報を得る努力が必要になる場合もあります。
見落とし厳禁!請求後に発生する「5年の金銭債権時効」
無事に1年(または10年)の期限内に遺留分侵害額請求の意思表示ができたとしても、それで安心はできません。ここからが第2フェーズであり、見落としがちな「5年の時効」が登場します。
なぜ5年の時効が存在するのか?2019年民法改正が鍵
この5年の時効を理解するためには、2019年7月1日に施行された改正民法の内容を知る必要があります。この改正により、遺留分制度は根本的に変わりました 。
改正前:遺留分減殺請求権(現物を取り戻す権利)
2019年6月30日以前に開始した相続では、「遺留分減殺請求権」という権利が適用されていました。これは、侵害された遺留分に相当する**遺産そのもの(現物)を取り戻す権利です 。
例えば、兄が相続した不動産に対して遺留分減殺請求をすると、その不動産の共有持分(例:4分の1)が自動的に自分のものになりました。不動産の所有権(共有持分)には消滅時効がないため、一度権利を主張すれば、その後何年経っても権利が消えることはありませんでした 。
しかし、この制度には大きな問題がありました。請求の結果、一つの不動産や会社の株式を複数の相続人が共有することになり、売却や経営方針の決定が困難になるなど、新たな紛争の火種となっていたのです 。
改正後:遺留分侵害額請求権(お金を請求する権利)
この問題を解決するため、2019年7月1日以降に開始した相続では、「遺留分侵害額請求権」という制度に変わりました。これは、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求する権利です 。
これにより、遺産そのものが共有状態になることを避け、金銭で解決できるようになったのです。しかし、この変更が新たな時効問題を生み出しました。
「金銭の支払いを請求する権利」は、法律上「金銭債権」と呼ばれます。そして、一般的な金銭債権には、民法の規定により5年の消滅時効が定められているのです 。
つまり、遺留分侵害額請求の意思表示をした瞬間、あなたの権利は「遺産を取り戻す権利」から「お金を払ってもらう権利(金銭債権)」に姿を変え、その瞬間から新たに「5年の時効」のカウントがスタートする、という仕組みなのです 。
5年の時効の起算点と注意点
5年の時効の起算点は、遺留分侵害額請求の意思表示が相手方に到達した時です 。
ここで最も注意すべき落とし穴は、内容証明郵便で請求の意思表示を送付して1年の時効をクリアしたことに安心してしまい、その後の交渉や手続きを放置してしまうことです 。
相手方がすんなり支払いに応じれば問題ありませんが、金額の算定で揉めたり、支払いを拒否されたりして交渉が長引くことは珍しくありません。そうこうしているうちに請求から5年が経過してしまうと、せっかく確保した金銭を支払ってもらう権利が時効で消滅し、一円も回収できなくなってしまうのです 。
相続開始時期による違い(2020年3月31日以前は10年)
さらに複雑な点として、この金銭債権の時効期間は、遺留分侵害額請求権を行使した時期によって異なります。これは、債権の時効に関する民法のルール自体が2020年4月1日に改正されたためです 。
- 2020年3月31日以前に遺留分侵害額請求の意思表示をした場合
- 発生した金銭債権の時効は、改正前の民法が適用され10年となります 。
- 2020年4月1日以降に遺留分侵害額請求の意思表示をした場合
- 発生した金銭債権の時効は、改正後の民法が適用され5年となります 。
現在発生するほとんどのケースでは5年の時効が適用されることになりますが、過去の相続案件に関わる場合はこの違いを念頭に置く必要があります。
5年の時効の進行を止める方法
内容証明郵便を送付して金銭債権が発生した後、5年の時効の進行を止める(更新する)には、より強力な法的アクションが必要となります。
交渉による相手方の承認(債務承認)
相手方との交渉の中で、相手が「遺留分侵害額として〇〇円を支払う義務があることを認めます」といった内容の書面(示談書や合意書など)に署名・捺印した場合、これは「債務の承認」にあたります。債務の承認があると、その時点で時効は更新(リセット)され、そこから新たに5年のカウントが始まります 。
裁判上の請求(調停の申立て・訴訟の提起)
相手が支払いに応じない、または交渉が進まない場合は、裁判所の手続きを利用する必要があります。
- 遺留分侵害額請求調停の申立て: 家庭裁判所に調停を申し立てると、その手続きが終了するまでの間、時効の完成が猶予されます。調停が成立すれば、その合意内容(調停調書)に基づき時効が更新されます 。
- 訴訟の提起: 調停が不成立に終わった場合などは、地方裁判所(または簡易裁判所)に訴訟を提起します。訴訟を提起すると、判決が確定するまで時効の完成が猶愈され、判決が確定すると時効が更新されます 。
5年の期限が迫っている場合は、悠長に交渉を続けるのではなく、時効完成を阻止するために、速やかにこれらの法的手続きに移行することが不可欠です。
【注意】時効を止められない行為
多くの方が誤解しがちな点として、以下のような行為は、原則として遺留分の時効を止める効果(完成猶予・更新)がありません。
口頭での請求や単なる話し合い
証拠が残らない口頭での請求や、法的な権利行使の意思表示とまでは言えない単なる話し合いの申し入れでは、時効を止めることはできません 。
遺産分割協議の申入れ
遺留分侵害額請求と遺産分割協議は、法律上、全く別の手続きです。そのため、遺産分割協議やその調停を申し立てたとしても、それだけでは遺留分侵害額請求の時効は止まりません 。
遺言無効確認訴訟の提起
これは最も重大な落とし穴です。「遺言書自体が無効だ」と主張する「遺言無効確認訴訟」と、「遺言書は有効だが内容が不公平だ」と主張する「遺留分侵害額請求」は、法的なゴールが全く異なります 。
遺言無効を主張して裁判で争っている間も、遺留分侵害額請求の1年の時効は容赦なく進行します 。もし遺言無効の訴えが認められなかった場合、その時にはすでに遺留分の時効が完成しており、もはや何も請求できなくなるという最悪の事態に陥りかねません。
このようなリスクを避けるための鉄則は、遺言の有効性に疑問がある場合でも、それとは別に、念のため(予防的に)1年の期限内に内容証明郵便で遺留分侵害額請求の意思表示をしておくことです。これにより、両方の可能性を追求する道が確保されます。
遺留分侵害額請求の時効に関するよくあるご質問(FAQ)
Q1: 遺言書の存在を相続開始から3年後に知りました。もう遺留分は請求できませんか?
A1: いいえ、まだ請求できる可能性が高いです。1年の短期消滅時効は、「①相続の開始(死亡の事実)」と「②遺留分を侵害する遺言の存在」の両方を知った時からスタートします 。ご質問のケースでは、遺言書の存在を知った3年後の時点から1年のカウントが始まりますので、そこから1年以内であれば請求は可能です。
ただし、相続開始から10年が経過すると、たとえ遺言を知らなかったとしても除斥期間によって権利が消滅してしまうため、その期限には注意が必要です 。
Q2: 遺言の無効を主張して争っている間も、遺留分の時効は進みますか?
A2: はい、その通りです。時効は進行します。これは非常に多くの方が陥る危険な誤解です 。裁判所に「この遺言は無効だ」と訴えている行為と、「遺留分を請求する」という意思表示は、法律上全く別の行為とみなされます。遺言無効の裁判の結果を待っている間に1年の時効が完成してしまうリスクがあります。遺言の有効性を争う場合であっても、必ず並行して、1年以内に内容証明郵便で遺留分侵害額請求の意思表示を行っておくべきです 。
Q3: 相手が話し合いに応じてくれません。5年の時効が迫っている場合どうすればいいですか?
A3: 請求の意思表示をしてから発生した金銭債権の5年の時効が迫っている場合、単に話し合いを続けていても時効は止められません。時効の完成を阻止するためには、法的な手続きに移行する必要があります。具体的には、家庭裁判所に「遺留分侵害額請求調停」を申し立てるか、地方裁判所に「訴訟を提起する」必要があります 。これらの手続きを開始すれば、その手続きが終了するまで時効の完成は猶予されますので、権利を失うことはありません 。
Q4: 10年の除斥期間が過ぎてしまったら、もう絶対に何もできませんか?
A4: 残念ながら、原則として何もできなくなります。10年の除斥期間は、相続の開始や遺留分侵害の事実を知っていたか否かにかかわらず、相続開始から10年が経過した時点で自動的に権利を消滅させる絶対的な期限です 。時効の完成猶予や更新といった制度も適用されないため、この期間が経過してしまった権利を覆すことは、極めて困難です 。
Q5: 内容証明郵便を送るのに弁護士は必要ですか?費用はどのくらいかかりますか?
A5: ご自身で作成して送付することも不可能ではありません。しかし、弁護士に依頼することを強くお勧めします。弁護士が作成・送付することで、以下のようなメリットがあります。
- 法的に正確な文書を作成できる: 記載漏れや不適切な表現により、後々不利になるリスクを避けられます。
- 請求相手を特定できる: 誰に送るべきかを正確に調査し、送り漏れを防ぎます。
- 相手に本気度を伝えられる: 弁護士名で通知が届けば、相手方も真摯に対応せざるを得なくなり、その後の交渉がスムーズに進む可能性が高まります。
- 精神的負担の軽減: 感情的な対立になりがちな相手方とのやり取りを、すべて弁護士に任せることができます。
弁護士費用は事案によって異なりますが、内容証明郵便の作成・送付にかかる費用は、それによって確保できる遺留分の金額を考えれば、権利を守るための必要不可欠な初期投資と言えます。多くの法律事務所では初回相談を無料で行っており、具体的な費用についても事前に明確な見積もりを提示しますので、まずは一度ご相談ください 。
まとめ:遺留分の時効は複雑かつ短期間。権利を守るため今すぐ弁護士へ相談を
本記事で解説してきた通り、遺留分を請求する権利には、3つの異なる時効が存在し、それぞれが複雑に絡み合っています。
- 「知ってから1年」 の短期消滅時効は、あまりにも短く、少しの油断で権利を失う最大の原因です。
- 「相続開始から10年」 の除斥期間は、知らなくても進行する絶対的なタイムリミットです。
- 「請求してから5年」 の金銭債権時効は、権利行使後も安心できない、見落としがちな第二の壁です。
特に、「遺言無効を主張していれば遺留分の時効は止まる」といった誤解は、取り返しのつかない事態を招きかねません。
ご自身の正当な権利が、単に法律を知らなかった、あるいは手続きを少し先延ばしにしてしまったという理由だけで永遠に失われてしまうのは、あまりにも悲しいことです。遺留分に関する問題は、時間が経てば経つほど不利になります。もし、ご自身の遺留分が侵害されている可能性があると感じたら、迷わず、そして一日も早く、遺産相続問題に精通した弁護士にご相談ください。
弁護士は、あなたの状況を法的に正確に分析し、時効が完成する前に何をすべきか、最も確実で有効な手段を提示します。大切な権利を守り、悔いのない解決を目指すために、今すぐ行動を起こすことが何よりも重要です。
遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要

このように、遺留分は請求方法が難しい上に、1年という短期の消滅時効がありますので、できる限り早い段階から、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。
とりわけ、相手方が早期に遺留分を支払わない場合には、消滅時効が成立しないよう、訴訟を視野に入れた対応を検討しなければなりません。
その場合には、遺留分請求訴訟の経験がある弁護士に依頼する必要が出てきます。
法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が、遺留分を請求したい方のための無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
ページトップに戻る