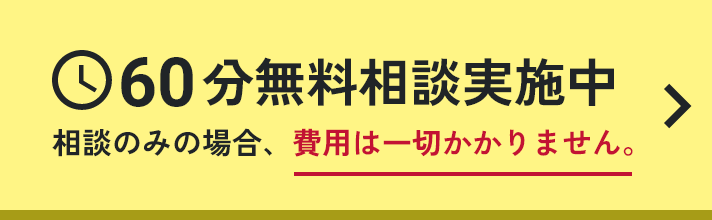遺留分侵害額請求の弁護士相談ガイド|費用・選び方・解決までの流れを徹底解説
遺留分は弁護士に依頼すべき?自分でした場合との違いは?
相続が発生し、遺言書の内容に納得がいかない場合、遺留分侵害額請求という選択肢がありますが、「弁護士に相談すべきか」 「費用はどれくらいかかるのか」 「そもそも弁護士の選び方がわからない」 と悩まれるかもしれません。
この記事では、法律事務所リンクスの相続に強い弁護士が、遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット・デメリット、弁護士費用の相場、そして弁護士選びのポイントを徹底的に解説します。
請求する側、される側のそれぞれの視点から、弁護士に依頼した場合とそうでない場合の違いを比較し、あなたの状況に最適な選択ができるようサポートします。
さらに、 遺留分侵害額請求の流れや、よくある質問にも弁護士が答えますので、 ぜひ最後まで読んで、円満な解決を目指しましょう。
遺留分侵害額請求の流れについて動画でご覧になりたい方はこちらをご覧ください。
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する前に知っておくべきこと
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する前に、弁護士費用の内訳や相場、費用を抑えるポイント、契約時の注意点などを把握しておくことが重要です。
これらの情報を事前に知っておくことで、安心して弁護士に依頼し、スムーズに遺留分侵害額請求を進めることができるからです。
以下では請求する側と請求される側に分けて説明します。
【請求する側】遺留分侵害額請求における弁護士費用の内訳と相場
 遺留分侵害額請求する側の弁護士費用は、主に以下の項目で構成されています。
遺留分侵害額請求する側の弁護士費用は、主に以下の項目で構成されています。
相談料・着手金については、多くの事務所が有料としていますが、無料にしている事務所もあります。
法律事務所リンクスも無料にしております(参考:「法律事務所リンクスの遺留分の弁護士費用」)
| 費用項目 | 概要 | 料金体系 |
|---|---|---|
| 相談料 | 弁護士に相談する際にかかる費用 | 時間制(30分5000円~10000円)または無料 |
| 着手金 | 弁護士に正式に依頼する際に支払う費用 | 請求額の5.5~8.8%(税込)または無料 |
| 報酬金 | 事件が成功した場合に支払う費用 | 回収額の11~16.5%(税込) |
| 日当 | 弁護士が遠方に出張する際に発生する費用(裁判所への出廷など) | 移動時間や距離に応じて設定 |
| 実費 | 事件処理のために実際にかかる費用(印紙代、交通費、宿泊費など) | 実費を精算 |
【請求される側】既に具体的な金額を請求されている場合とされていない場合とで弁護士費用が異なる
既に具体的な金額を請求されている場合、弁護士費用は、既に請求されている額と実際に支払った額の差額を経済的利益として、これに11~22%を乗じて計算することが多いです。
これに対し、まだ具体的な金額を請求されていない場合には、そのような計算方法は取れないので、遺留分侵害額を支払った後に残った確保財産を経済的利益として、2~5%という低い割合を掛けて計算するという方式を採用している事務所があり、法律事務所リンクスも同様の遺留分侵害額請求の料金体系を取っています。
| 依頼する側 | 費用項目 | 相場 |
|---|---|---|
| 既に具体的な金額を請求されている場合 | 着手金 | 33万~55万円(税込) |
| 報酬金 | 減額幅の11~22%(税込) | |
| その他 | 相談料、実費、日当など | |
| まだ具体的な金額を請求されていない場合 | 着手金 | 33万~55万円(税込) |
| 報酬金 | 財産確保額の2~5% | |
| その他 | 相談料、実費、日当など |
費用を抑えるための3つのポイント
弁護士費用は高額になることもありますが、以下のポイントを意識することで費用を抑えることができます。
- 無料相談を活用する: 初回相談を無料で行っている事務所を利用することで、相談料を節約して、自分に合った弁護士を探すことができます。
- 着手金が無料の弁護士を選ぶ: 着手金が無料の弁護士を選ぶことで、初期費用を抑えることができます。
- 料金体系が明確な事務所を選ぶ:料金体系が明確な事務所を選ぶことで予測していなかった弁護士費用を支払わなくて済みます。
弁護士に依頼する際の注意点:契約前に確認すべきこと
弁護士に依頼する際には、契約内容をしっかりと確認することが重要です。特に、以下の点に注意しましょう。
- 費用に関する明確な説明: 弁護士費用(着手金、報酬金、実費など)の内訳や計算方法について、明確な説明を受けましょう。
- 成功報酬の条件: 成功報酬が発生する条件(どのような結果が出た場合に成功とみなされるか)を確認しましょう。
- 弁護士の経験と実績: 遺留分侵害額請求に関する弁護士の経験や実績を確認しましょう。
これらの点を確認し、納得した上で契約を結ぶようにしましょう。
【徹底比較】遺留分請求に強い弁護士の選び方
遺留分侵害額請求を成功させるためには、弁護士選びが非常に重要です。しかし、弁護士の数は多く、どのように選べば良いか迷ってしまう方もいるでしょう。ここでは、遺留分請求に強い弁護士の選び方を徹底的に解説します。
遺留分請求に強い弁護士の5つの特徴
遺留分請求に強い弁護士には、以下の5つの特徴があります。
| 特徴 | 詳細 |
|---|---|
| 相続問題の解決実績が豊富 | 遺留分侵害額請求を含む相続問題の解決実績が豊富であることは、弁護士選びの重要な指標となります。実績が多いほど、様々なケースに対応できる知識やノウハウを持っていると考えられます。 |
| 遺留分請求に関する専門知識 | 遺留分請求は、民法の専門的な知識を必要とする分野です。遺留分に関する法改正や判例にも精通している弁護士を選びましょう。 |
| 交渉力とコミュニケーション能力 | 遺留分請求は、他の相続人との交渉が不可欠です。依頼者の意向を的確に伝え、有利な条件を引き出すための交渉力と、依頼者との円滑なコミュニケーションを図れる能力が求められます。 |
| 費用体系が明確 | 弁護士費用は、着手金、報酬金、実費など、様々な項目があります。事前に費用体系について明確な説明を受け、納得できる弁護士を選びましょう。 |
| 親身な対応 | 遺留分請求は、感情的な対立を伴うこともあります。親身になって相談に乗ってくれ、精神的なサポートをしてくれる弁護士を選びましょう。 |
弁護士選びで失敗しないためのチェックリスト
弁護士選びで失敗しないために、以下のチェックリストを活用しましょう。
- 相続問題の相談実績を確認する
- 遺留分請求に関する専門知識の有無を確認する
- 弁護士費用の見積もりを複数社から取る
- 弁護士との相性を確認する
- 事務所の規模やアクセスの良さを確認する
無料相談を最大限に活用する方法
多くの弁護士事務所では、無料相談を実施しています。無料相談を最大限に活用することで、弁護士選びのミスマッチを防ぎ、より良い弁護士を見つけることができます。
- 事前に相談内容を整理しておく
- 質問したいことをリストアップしておく
- 弁護士の言っていることが分からない時は遠慮なく質問する
無料相談では、弁護士の専門知識や人柄、事務所の雰囲気などを知ることができますので、ぜひ活用してください。
法律事務所リンクスは遺留分侵害額請求の60分無料相談実施中!
 法律事務所リンクスでは、遺留分侵害額請求の経験が豊富な弁護士が60分無料相談を実施しています。
法律事務所リンクスでは、遺留分侵害額請求の経験が豊富な弁護士が60分無料相談を実施しています。
無料相談ではホワイトー度を利用しながら、遺留分侵害額請求の進め方や注意点、請求できる金額の見通しや弁護士費用のお見積りを分かりやすくご説明させて頂きます。
相談にお越しになったからと言って、依頼しないといけないというわけではございません。
お客様の立場に寄り添って親身なご相談を心がけておりますので、0120‐917‐740または問合せフォームからどうぞお気軽にお問い合わせください。
遺留分請求を弁護士なしで行うリスクとデメリット
自分でできる範囲とは?メリット・デメリットを比較
遺留分侵害額請求を自分でしようと思った場合、次のようなことをご自身でする必要があります。
どこまでご自身で対応できるのかをよく考えましょう。
- 遺言書の開示・確認
- 相続財産の調査・評価
- 遺留分侵害額の計算
- 相手方への請求書(内容証明郵便)の送付
- 交渉(電話、手紙、直接会っての話し合い)
自分で遺留分侵害額請求を進められれば、次のようなメリットがあります。
| メリット | 詳細 |
|---|---|
| 弁護士費用を抑えられる | 弁護士に依頼しないため、弁護士費用(着手金、報酬金など)は発生しません。 |
| 自分のペースで進められる | 専門家との打ち合わせなどの時間を調整する必要がなく、ご自身のペースで手続きを進めることができます。 |
他方で、自分で遺留分侵害額請求を進める場合、次のようなデメリットやリスクがありますので、懸念がある場合には弁護士に依頼することを検討すべきです。
| デメリット | 詳細 |
|---|---|
| 法的な知識が必要 | 遺留分侵害額の計算や、相手方との交渉には、ある程度の法律知識が必要です。知識不足の場合、不利な条件で合意してしまう可能性があります。 |
| 時間と労力がかかる | 相続人の調査、遺留分侵害額の計算、書類作成、相手方との交渉など、多くの時間と労力がかかります。 |
| 交渉が難航する可能性がある | 相手方が専門家(弁護士など)を立ててきた場合、交渉が難航する可能性があります。また、感情的な対立が激化し、冷静な話し合いができない場合もあります。 |
| 時効のリスクがある | 遺留分侵害額請求には時効があります。手続きに手間取っているうちに時効が成立してしまうと、権利を失う可能性があります。 |
弁護士に依頼した場合との違い:時間・労力・金額
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼した場合、ご自身で行う場合と比較して、時間、労力、金額にどのような違いがあるのでしょうか。
| 比較項目 | 自分で対応 | 弁護士に依頼 |
|---|---|---|
| 時間 | 多くかかる | 大幅に削減 |
| 労力 | 多くかかる | 大幅に削減 |
| 法的な知識 | 必要 | 不要(弁護士が対応) |
| 交渉力 | 低い場合が多い | 高い |
| 精神的な負担 | 大きい | 軽減 |
| 費用 | 少ない | 弁護士費用が発生 |
弁護士に依頼することで、時間と労力を大幅に削減できるだけでなく、法的な知識や交渉力といった面でも有利に進めることができます。また、精神的な負担も軽減されるでしょう。
こんなケースは弁護士必須!自分で対応できない事例
 以下のようなケースでは、弁護士に依頼することを強くおすすめします。
以下のようなケースでは、弁護士に依頼することを強くおすすめします。
- 遺言書や相続財産の開示がされない場合
遺言書や相続財産が開示されない場合、そもそも交渉に入ることすらできません。このような場合には、弁護士に依頼して、遺言書や相続財産を開示させたり、調査してもらうことが必要です。
- 相手方が弁護士を立てている場合
相手方が既に弁護士を立てている場合、ご自身で対応することは非常に不利です。弁護士は、法的な知識や交渉力に長けているため、ご自身で対抗することは難しいでしょう。
- 遺産の内容が複雑な場合
相続財産に不動産、株式、事業承継など、複雑な要素が含まれる場合、遺留分侵害額の計算や評価が難しくなります。専門家である弁護士に依頼することで、正確な評価を行い、適切な請求額を算出してもらうことができます。
- 訴訟に発展する可能性が高い場合
交渉が決裂し、訴訟に発展する可能性が高い場合、ご自身で対応することは非常に困難です。訴訟には、専門的な知識や経験が必要となるため、弁護士に依頼することをおすすめします。
- 時効が迫っている場合
遺留分侵害額請求には時効があり、相続の開始及び遺留分の侵害を知ってから1年以内に行う必要があります。時効が迫っている場合、迅速な対応が必要となるため、弁護士に依頼することをおすすめします。
これらのケースに該当する場合は、弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることを検討しましょう。
【請求する側/される側】弁護士に依頼するメリット・デメリット
請求する側のメリット:交渉力UP、証拠収集、精神的負担軽減
遺留分侵害額請求を検討している方は、感情的になりやすく、冷静な交渉が難しい場合があります。弁護士に依頼することで、以下のメリットが期待できます。
| メリット | 詳細 |
|---|---|
| 交渉力UP | 弁護士は法律の専門家として、法的根拠に基づいた主張を展開し、有利な条件で交渉を進めることができます。ご自身で交渉するよりも、相手方に対するプレッシャーとなり、交渉がスムーズに進む可能性が高まります。 |
| 証拠収集 | 遺留分侵害額を算定するためには、相続財産の正確な情報が必要です。弁護士は、金融機関への照会や不動産の評価など、専門的な知識と経験を活かして必要な証拠を収集します。 |
| 精神的負担軽減 | 相続問題は、親族間の感情的な対立を伴うことが多く、精神的な負担が大きくなりがちです。弁護士に依頼することで、煩雑な手続きや相手方との交渉を代行してもらい、精神的な負担を軽減することができます。 |
請求する側のデメリット:弁護士費用が発生する
弁護士に依頼する最大のデメリットは、弁護士費用が発生することです。弁護士費用は、着手金、報酬金、実費などから構成されており、遺留分侵害額や事件の難易度によって異なります。費用倒れにならないように、事前に弁護士に見積もりを依頼し、費用対効果を検討することが重要です。
請求される側のメリット:適切な対応、訴訟リスク回避、精神的負担軽減
遺留分侵害額請求を受けた場合、請求額が妥当かどうか、どのように対応すべきかなど、様々な疑問や不安が生じるでしょう。弁護士に依頼することで、以下のメリットが期待できます。
| メリット | 詳細 |
|---|---|
| 適切な対応 | 弁護士は、請求内容を精査し、法的根拠に基づいた適切な対応をすることができます。不当な請求に対しては、毅然とした態度で反論し、法的リスクを最小限に抑えることができます。 |
| 訴訟リスク回避 | 遺留分侵害額請求は、交渉が決裂した場合、訴訟に発展する可能性があります。弁護士に依頼することで、訴訟リスクを回避するための戦略を立て、和解交渉を有利に進めることができます。 |
| 精神的負担軽減 | 遺留分侵害額請求への対応は、精神的な負担が大きくなりがちです。弁護士に依頼することで、煩雑な手続きや相手方との交渉を代行してもらい、精神的な負担を軽減することができます。 |
請求される側のデメリット:弁護士費用が発生する、財産減少の可能性
請求される側が弁護士に依頼する場合も、弁護士費用が発生します。また、遺留分侵害額請求が認められた場合、財産を減少させる可能性があります。しかし、弁護士に依頼することで、請求額を減額したり、分割払いの交渉をしたりするなど、財産減少を最小限に抑えるためのサポートを受けることができます。
遺留分の請求を弁護士に依頼して解決するまでの流れ
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼した場合、どのような流れで解決へと進んでいくのでしょうか。ここでは、依頼から解決までの一般的なステップを解説します。
ステップ1:無料相談で弁護士に相談
 まずは、遺留分侵害額請求に注力している弁護士に相談してみましょう。多くの弁護士事務所では、初回相談を無料で行っています。無料相談では、以下の点について相談し、弁護士に依頼するべきか、どのような解決方法があるのか見極めましょう。
まずは、遺留分侵害額請求に注力している弁護士に相談してみましょう。多くの弁護士事務所では、初回相談を無料で行っています。無料相談では、以下の点について相談し、弁護士に依頼するべきか、どのような解決方法があるのか見極めましょう。
- 相続の状況
- 遺言書の内容
- ご自身の希望
- 弁護士費用の見積もり
ステップ2:弁護士との委任契約
 相談の結果、弁護士に依頼することを決めたら、委任契約を結びます。委任契約書には、以下の内容が記載されているか確認しましょう。
相談の結果、弁護士に依頼することを決めたら、委任契約を結びます。委任契約書には、以下の内容が記載されているか確認しましょう。
- 委任する業務の範囲(遺留分侵害額請求に関する一切の業務など)
- 弁護士費用(着手金、報酬金、実費など)
- 契約解除に関する事項
- その他、重要な事項
弁護士費用の内訳や料金体系は明確に提示・説明してもらうようにしましょう。後々のトラブルを避けるため、不明な点は必ず質問し、納得した上で契約することが重要です。
ステップ3:遺留分侵害額の計算・請求
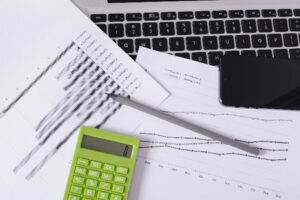 委任契約後、弁護士は遺留分侵害額を正確に計算します。そのため、相続財産の調査や評価を行います。弁護士から調査や評価をする上で必要な資料を求められた場合には、協力してあげてください。
委任契約後、弁護士は遺留分侵害額を正確に計算します。そのため、相続財産の調査や評価を行います。弁護士から調査や評価をする上で必要な資料を求められた場合には、協力してあげてください。
遺留分侵害額が確定したら、相手方(遺留分を侵害している相続人や受遺者)に対して、遺留分侵害額を請求します。
ステップ4:交渉による解決
 遺留分侵害額請求後、まずは相手方との交渉による解決を目指します。弁護士が代理人として交渉することで、ご自身で交渉するよりも有利な条件で合意できる可能性が高まります。
遺留分侵害額請求後、まずは相手方との交渉による解決を目指します。弁護士が代理人として交渉することで、ご自身で交渉するよりも有利な条件で合意できる可能性が高まります。
ステップ5:調停・訴訟による解決
 交渉がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停では、調停委員が間に入り、双方の主張を聞きながら、合意を目指します。
交渉がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停では、調停委員が間に入り、双方の主張を聞きながら、合意を目指します。
調停をしても意味がない場合には、調停を経ずに訴訟を提起し、裁判所に判断を委ねることになります。
弁護士は、交渉、調停、訴訟の全ての段階で、あなたの代理人として、法的な知識と経験を活かし、最大限のサポートを行います。
遺留分侵害額請求に関するQ&A|弁護士がよくある質問に答えます
Q1:遺留分侵害額請求の時効はいつまで?
A. 遺留分侵害額請求権には、時効があります。具体的には、以下の2つの期間が定められています。
| 期間 | 起算点 | 内容 |
|---|---|---|
| 1年 | 相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったとき | この期間内に請求しないと、時効により権利が消滅します。 |
| 10年 | 相続開始の時 | 相続の開始及び遺留分の侵害を知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過すると、権利は消滅します。 |
重要なのは、これらの期間を過ぎてしまうと、原則として遺留分侵害額請求ができなくなるということです。ただし、時効の完成が猶予されたり、更新(中断)されたりするケースもありますので、弁護士にご相談ください。
また、5年間の金銭支払請求権の時効にも注意が必要です。書面などによる侵害額請求権行使の意思表示と同時に、この時効のカウントがスタートします。遺留分侵害額請求権を行使しても、何もせずこの期間が過ぎると金銭請求はできなくなります。
Q2:弁護士費用は分割払いできますか?
A. 弁護士費用を分割払いにできるかどうかは、弁護士事務所によって異なります。多くの事務所では、ご依頼者の経済状況などを考慮し、柔軟に対応してくれる場合があります。 初めての法律相談の際に、費用の見積もりと合わせて、分割払いの可否についても確認しておきましょう。
Q3:親族間で争いたくないのですが…
A. 親族間の争いは、精神的な負担が大きいため、できる限り避けたいものです。弁護士に依頼することで、感情的な対立を避け、冷静な話し合いを進めることができます。 弁護士は、法的な知識に基づいて、客観的な視点から解決策を提案し、円満な解決をサポートします。また、調停や裁判などの手続きにおいても、ご依頼者の意向を尊重しながら、適切な対応を行います。
Q4:相手が話し合いに応じてくれません…
A. 相手が話し合いに応じてくれない場合でも、諦める必要はありません。弁護士に依頼することで、内容証明郵便を送付したり、法的な手続き(調停や訴訟)を提起したりすることができます。 弁護士は、ご依頼者の代理人として、相手方と交渉を行い、法的な根拠に基づいて、粘り強く解決を目指します。また、裁判所での手続きにおいても、ご依頼者の権利を最大限に擁護します。
Q5:成功報酬はどのタイミングで支払うのですか?
A. 成功報酬の支払いタイミングは、弁護士事務所との契約内容によって異なります。一般的には、以下のいずれかのタイミングで支払うことが多いです。
- 示談成立時
- 調停成立時
- 訴訟判決確定時
- 和解成立時
契約を結ぶ前に、成功報酬の金額だけでなく、支払い時期についても明確に確認しておくことが重要です。
まとめ|遺留分侵害額請求は弁護士に相談して円満解決を目指しましょう
遺留分侵害額請求は、複雑な法律知識や交渉スキルが求められるため、弁護士に依頼することで、ご自身の権利を最大限に実現できる可能性が高まります。この記事では、遺留分侵害額請求における弁護士の必要性、費用相場、選び方、注意点、そして解決までの流れについて詳しく解説しました。
弁護士に依頼することで、交渉力UPや証拠収集のサポート、精神的な負担軽減など、多くのメリットが得られます。特に、親族間の争いを避けたい場合や、相手が話し合いに応じてくれない場合には、弁護士の介入が有効です。
遺留分侵害額請求は、請求する側、される側、どちらの立場であっても、弁護士に相談することで、より円満な解決を目指せるでしょう。
遺留分侵害額請求についてお悩みの方は、ぜひ一度、専門の弁護士にご相談ください。無料相談などを活用し、ご自身の状況に合った最適な解決策を見つけましょう。
遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要

このように、遺留分侵害額請求は方法が難しい上に、1年という短期の消滅時効がありますので、できる限り早い段階から、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。
とりわけ、相手方が早期に遺留分を支払わない場合には、消滅時効が成立しないよう、訴訟を視野に入れた対応を検討しなければなりません。
その場合には、遺留分請求訴訟の経験がある弁護士に依頼する必要が出てきます。
法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が、遺留分侵害額請求をしたい方のための無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
ページトップに戻る