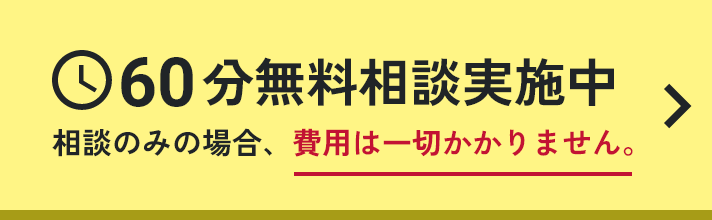遺留分の計算!侵害額のシミュレーションは計算方法シートで!
遺留分の具体的な計算方法が知りたいのですが?
遺留分とは、相続人が最低限相続できると遺産の取り分のことです。
遺留分を計算するには、遺留分の基礎となる財産の価額に、各相続人の遺留分の割合(個別的遺留分)を掛けて算出します。
遺留分の割合は、相続人の構成に応じて、次のとおりになります。
したがって、配偶者と子供の場合には、配偶者の遺留分は
子供のみの場合には、
このページでは、法律事務所リンクスの遺留分に強い弁護士が、遺留分とは何かという基本的な知識から、ご自身のケースに合わせた正確な計算方法、具体的なシミュレーション、そして実際に遺留分を請求するための手続きまで、分かりやすく解説します。
遺留分とは?最低限の遺産を保障する重要な権利
遺留分とは、簡単に言えば、法律によって一定の相続人に保障された「遺産の最低限の取り分」のことです 。故人(被相続人)は遺言によって財産の分け方を自由に決めることができますが、この遺留分という権利を侵害することはできません 。
例えば、「全財産を長男に相続させる」という内容の遺言書があったとしても、配偶者や他の子供たちは、自身の遺留分に相当する財産を取り戻す権利を持っています。
遺留分と法定相続分の違い【遺言の効力で変わる】
遺留分とよく似た言葉に「法定相続分」があります。この二つは明確に異なるもので、特に遺言書の有無によってその役割が大きく変わります。
- 法定相続分: 遺言書がない場合に、民法で定められた相続割合の目安です。相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で合意すれば、この割合と異なる分け方も可能です 。あくまで遺産分割の基準となるものです。
- 遺留分: 遺言書があることによって、ご自身の取り分が、最低限保障されるべき取り分を下回った場合に問題となる権利です。遺言の内容が遺留分を侵害している場合、その侵害された分を取り戻すために主張することができます 。
つまり、法定相続分は遺産分割の「基準」であり、遺留分は不公平な遺言から相続人を守るための「最低保障」と理解すると分かりやすいでしょう。
遺留分が認められる相続人(遺留分権利者)の範囲
遺留分は、すべての相続人に認められているわけではありません。法律で遺留分が保障されているのは、故人と特に近しい関係にある以下の相続人(遺留分権利者)に限られます 。
- 配偶者: 常に遺留分が認められます。
- 子供や孫(直系卑属): 子供が相続人となる場合、遺留分が認められます。子供が既に亡くなっている場合は、その子供である孫(代襲相続人)に遺留分が認められます。
- 父母や祖父母(直系尊属): 子供や孫がいない場合に相続人となる父母や祖父母にも、遺留分が認められます。
兄弟姉妹に遺留分がない理由
故人の兄弟姉妹(またはその子供である甥・姪)が相続人になるケースもありますが、兄弟姉妹には遺留分が認められていません 。
これは、遺留分制度の主な目的が、故人の財産によって生計を立てていた配偶者や子供など、より生活的に密接な関係にあった遺族を保護することにあるためです。兄弟姉妹は、配偶者や親子に比べて、経済的な依存関係が薄いと一般的に考えられているため、遺留分の保護の対象外とされています。
法律事務所リンクスは遺留分侵害額請求の相談が60分無料!
 法律事務所リンクスでは、遺留分に強い弁護士による60分無料相談を実施しています。
法律事務所リンクスでは、遺留分に強い弁護士による60分無料相談を実施しています。
相談に当たっては、ご予約いただいた際にご事情を伺い、調査をした上で相談に臨みますので、無料相談の時間内で充実した情報を提供しております。
相談者様が聞き足りなかったということが起きないようにしておりますし、ホワイトボードを使うなどして分かりやすく説明していますので、お気軽にお問い合わせください。
遺留分の請求の進め方について動画で知りたい方はこちらをご覧ください。
【相続人別】遺留分の割合が一目でわかる計算シート
ご自身の遺留分が具体的にどのくらいの割合になるのかは、誰が相続人になるかによって決まります。相続人の組み合わせごとに、個別の遺留分割合を以下の早見表にまとめました。まずはご自身のケースがどれに当てはまるかを確認してみてください。
| 相続人の構成 | 各相続人の遺留分割合 | |||
| 配偶者 | 子供 | 父母 | 兄弟 | |
| 配偶者のみ | 1/2 | |||
| 配偶者と子供 | 1/4 | 1/4の人数割 | ||
| 配偶者と親 | 1/3 | 1/6の人数割 | ||
| 配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | なし | ||
| 子供のみ | 1/2の人数割 | |||
| 親のみ | 1/3の人数割 | |||
| 兄弟姉妹のみ | なし | |||
遺留分の計算方法|3つのステップで正確に算出する
遺留分を請求できる金額(遺留分侵害額)を正確に知るためには、単に割合を掛けるだけでは不十分です。計算は、以下の3つのステップに沿って進める必要があります。この手順を踏むことで、ご自身が法的にいくら請求できるのかを明確にできます。
ステップ1:遺留分算定の基礎となる財産を確定する
最初に、遺留分を計算する元となる「財産の総額」を確定させます。これは、故人が亡くなったときに持っていた財産そのものではなく、過去の贈与なども含めて計算される特別なものです 。これを「遺留分算定の基礎となる財産」と呼びます。
計算式は以下の通りです。
計算に含めるプラスの財産(相続財産・生前贈与など)
プラスの財産には、以下のものが含まれます 。
- 相続開始時の財産: 故人が亡くなった時点で所有していた預貯金、不動産、株式などのプラスの財産。遺言によって特定の人に遺贈された財産もすべて含みます。
- 相続人以外への贈与: 相続開始前1年以内に行われた贈与。
- 相続人への特別受益となる贈与: 相続開始前10年以内に行われた、結婚資金、事業を始めるための資金、住宅購入資金など、「特別受益」にあたる贈与 。
- 遺留分を害することを知って行われた贈与: 贈与した側(故人)と受け取った側の双方が、他の相続人の遺留分を侵害すると知りながら行った贈与。これには期間の制限がなく、10年以上前のものでも計算に含まれます 。
計算から差し引くマイナスの財産(借金など)
プラスの財産の合計額から、故人が残した借金や未払金などの債務全額を差し引きます 。葬儀費用は、相続人が負担すべきものとされ、原則としてここには含まれません 。
ステップ2:あなたの遺留分額を計算する
ステップ1で算出した「遺留分算定の基礎となる財産」に、ご自身の「個別的遺留分割合」を掛けて、理論上の遺留分額を算出します 。
個別的遺留分割合は、前述の「遺留分割合の早見表」で確認した割合を使用します。このステップで算出されるのは、あくまで法律上保障されているあなたの取り分の「総額」です。
ステップ3:請求できる遺留分侵害額を算出する
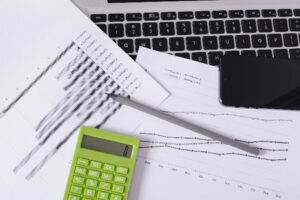 最後に、実際に相手方に金銭で請求できる「遺留分侵害額」を計算します。これは、ステップ2で計算した遺留分額から、あなたが既に受け取った、あるいは受け取ることになっている財産を差し引いた金額です 。
最後に、実際に相手方に金銭で請求できる「遺留分侵害額」を計算します。これは、ステップ2で計算した遺留分額から、あなたが既に受け取った、あるいは受け取ることになっている財産を差し引いた金額です 。
ここで注意すべき重要な点があります。ステップ1の基礎財産を計算する際、相続人への特別受益は過去10年分に限定されていました。しかし、このステップ3で差し引くあなたが受けた特別受益には、10年という期間制限がありません。つまり、たとえ20年前に住宅購入資金の援助を受けていたとしても、その金額はあなたの遺留分額から差し引かれることになります。
この3ステップを経て算出された金額が、あなたが遺留分を侵害している相手に対して具体的に「支払ってください」と請求できる法的な権利額となります。
【立場別】遺留分侵害額の計算シミュレーション!子供のみ子供2人の場合などを解説
それでは、具体的な事例をもとに、3ステップの計算方法をシミュレーションしてみましょう。ここでは、計算を分かりやすくするため、遺留分算定の基礎となる財産を6,000万円と仮定します。
配偶者が遺留分侵害額請求をする場合の計算シミュレーション

① 相続人が配偶者のみの場合
配偶者の遺留分の割合
配偶者の遺留分は2分の1です。
したがって、遺留分算定基礎財産が6000万円だとすると、遺留分は3000万円です。
配偶者の遺留分侵害額請求額の計算方法
亡くなった夫(妻)が自分以外の人に遺留分算定基礎財産の2分の1に当たる3000万円を超える財産を遺贈・生前贈与等していた場合、残りの財産は3000万円を下回ることになり、配偶者の遺留分が侵害されることになりますので、侵害されている額の分だけ遺留分侵害額請求をすることができます。
例えば、自分以外の人に4000万円を遺贈・生前贈与等していた場合、配偶者は2000万円しか取得できず、遺留分3000万円の内の1000万円が侵害されることになりますので、1000万円の遺留分侵害額請求をすることができます。
② 相続人が配偶者と子供1人の場合
配偶者の遺留分の割合
配偶者の遺留分は4分の1です。
したがって、遺留分算定基礎財産が6000万円だとすると、遺留分は1500万円です。
配偶者の遺留分侵害額請求額の計算方法
子供に多額の相続・遺贈・生前贈与があった場合
亡くなった夫(妻)が子供に遺留分算定基礎財産の4分の3に当たる4500万円を超える財産を相続・遺贈・生前贈与等していた場合、残りの財産は1500万円を下回り、配偶者の遺留分が侵害されることになりますので、侵害されている額の分だけ遺留分侵害額請求をすることができます。
例えば、子供に5000万円を相続・遺贈・生前贈与等していた場合、配偶者は最高で1000万円しか取得できず、その場合に遺留分が500万円分侵害されることになりますので、500万円の遺留分侵害額請求をすることができます。
相続人以外に多額の相続・遺贈・生前贈与があった場合
相続人以外に遺贈・生前贈与があった場合には、残りの財産を子供と分けることになりますので、配偶者の取得できる財産はより少なくなりますので、相続人以外に渡った額がより少なかったとしても、配偶者の遺留分が侵害されることになります。
例えば、相続人以外に3000万円を超える財産を遺贈・生前贈与等していた場合、残りの財産は3000万円を下回ることになります。
この場合、配偶者は、残りの財産を共同相続人である子供と分けることになりますが、法定相続分である2分の1を取得しても、1500万円を下回る額となり、配偶者の遺留分に達しないことになります。
③ 相続人が配偶者と親の場合
配偶者の遺留分の割合
配偶者の遺留分は3分の1です。
したがって、遺留分算定基礎財産が6000万円だとすると、遺留分は2000万円です。
配偶者の遺留分侵害額請求額の計算方法
親に多額の相続・遺贈・生前贈与があった場合
亡くなった夫(妻)が親に遺留分算定基礎財産の3分の2に当たる4000万円を超える財産を相続・遺贈・生前贈与等していた場合、残りの財産は2000万円を下回ることになり、配偶者の遺留分が侵害されることになりますので、侵害されている額の分だけ遺留分侵害額請求をすることができます。
例えば、親に5000万円を相続・遺贈・生前贈与等していた場合、配偶者は最高で1000万円しか取得できず、その場合に遺留分が1000万円分侵害されることになりますので、1000万円の遺留分侵害額請求をすることができます。
相続人以外に多額の相続・遺贈・生前贈与があった場合
相続人以外に遺贈・生前贈与があった場合には、残りの財産を親と分けることになりますので、配偶者の取得できる財産はより少なくなりますので、相続人以外に渡った額がより少なかったとしても、配偶者の遺留分が侵害されることになります。
例えば、相続人以外に3000万円を超える財産を遺贈・生前贈与等していた場合、残りの財産は3000万円を下回ることになります。
この場合、配偶者は、残りの財産を共同相続人である親と分けることになりますが、法定相続分である3分の2を取得しても、2000万円を下回る額となり、配偶者の遺留分に達しないことになります。
④ 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者の遺留分の割合
配偶者の遺留分は2分の1です。
したがって、遺留分算定基礎財産が6000万円だとすると、遺留分は3000万円です。
配偶者の遺留分侵害額請求額の計算方法
兄弟姉妹に多額の相続・遺贈・生前贈与があった場合
亡くなった夫(妻)が兄弟姉妹に遺留分算定基礎財産の2分の1に当たる3000万円を超える財産を相続・遺贈・生前贈与等していた場合、残りの財産は3000万円を下回ることになり、配偶者の遺留分が侵害されることになりますので、侵害されている額の分だけ遺留分侵害額請求をすることができます。
例えば、親に4000万円を相続・遺贈・生前贈与等していた場合、配偶者は最高で2000万円しか取得できず、その場合に遺留分が1000万円分侵害されることになりますので、1000万円の遺留分侵害額請求をすることができます。
相続人以外に多額の相続・遺贈・生前贈与があった場合
相続人以外に遺贈・生前贈与があった場合には、残りの財産を兄弟姉妹と分けることになりますので、配偶者の取得できる財産はより少なくなりますので、相続人以外に渡った額がより少なかったとしても、配偶者の遺留分が侵害されることになります。
例えば、相続人以外に2000万円を超える財産を遺贈・生前贈与等していた場合、残りの財産は4000万円を下回ることになります。
この場合、配偶者は、残りの財産を共同相続人である兄弟姉妹と分けることになりますが、法定相続分である4分の3を取得しても、3000万円を下回る額となり、配偶者の遺留分に達しないことになります。
子供が遺留分侵害額請求をする場合の計算シミュレーション
① 相続人が配偶者と子供1人の場合
子供の遺留分の割合
子供の遺留分は4分の1です。
したがって、遺留分算定基礎財産が6000万円だとすると、遺留分は1500万円です。
子供の遺留分侵害額請求額の計算方法
配偶者に多額の相続・遺贈・生前贈与があった場合
亡くなった親が配偶者に遺留分算定基礎財産の4分の3に当たる4500万円を超える財産を相続・遺贈・生前贈与等していた場合、残りの財産は1500万円を下回り、子供の遺留分が侵害されることになりますので、侵害されている額の分だけ遺留分侵害額請求をすることができます。
例えば、配偶者に5000万円を相続・遺贈・生前贈与等していた場合、子供は最高で1000万円しか取得できず、その場合に遺留分が500万円分侵害されることになりますので、500万円の遺留分侵害額請求をすることができます。
相続人以外に多額の相続・遺贈・生前贈与があった場合
相続人以外に遺贈・生前贈与があった場合には、残りの財産を配偶者と分けることになりますので、子供の取得できる財産はより少なくなりますので、相続人以外に渡った額がより少なかったとしても、子供の遺留分が侵害されることになります。
例えば、相続人以外に3000万円を超える財産を遺贈・生前贈与等していた場合、残りの財産は3000万円を下回ることになります。
この場合、子供は、残りの財産を共同相続人である配偶者と分けることになりますが、法定相続分である2分の1を取得しても、1500万円を下回る額となり、子供の遺留分に達しないことになります。
② 相続人が配偶者と子供2人の場合
子供の遺留分の割合
子供全体の遺留分は4分の1なので、子供1人の遺留分はその2分の1の8分の1になります。
したがって、遺留分算定基礎財産が6000万円だとすると、遺留分は子供全体で1500万円、子供1人当たり750万円になります。
子供の遺留分侵害額請求額の計算方法
配偶者に多額の相続・遺贈・生前贈与があった場合
亡くなった親が配偶者に遺留分算定基礎財産の4分の3に当たる4500万円を超える財産を相続・遺贈・生前贈与等していた場合、残りの財産は1500万円を下回り、子供の遺留分が侵害されることになりますので、侵害されている額の分だけ遺留分侵害額請求をすることができます。
例えば、配偶者に5000万円を相続・遺贈・生前贈与等していた場合、子供2人は最高で1000万円しか取得できません。
この場合、子供1人当たり500万となり、その場合に遺留分が250万円分侵害されることになりますので、250万円の遺留分侵害額請求をすることができます。
1人の子供に多額の相続・遺贈・生前贈与があった場合
亡くなった親が、1人の子供に3750万円を超える財産を相続・遺贈・生前贈与等していた場合、残りの財産は2250万円を下回ります。
この場合、もう1人の子供は、残りの財産を共同相続人である配偶者と分けることになります。
親の法定相続分が2分の1、もう1人の子供の法定相続分が4分の1なので、2250万円を2:1で分けた場合、もう1人の子供の取得財産は750万円を下回る額となり、子供1人当たりの遺留分に達しないことになります。
相続人以外に多額の相続・遺贈・生前贈与があった場合
相続人以外に遺贈・生前贈与があった場合には、残りの財産を配偶者と分けることになりますので、子供の取得できる財産はより少なくなりますので、相続人以外に渡った額がより少なかったとしても、子供の遺留分が侵害されることになります。
例えば、相続人以外に3000万円を超える財産を遺贈・生前贈与等していた場合、残りの財産は3000万円を下回ることになります。
この場合、子供は、残りの財産を共同相続人である配偶者と分けることになりますが、法定相続分である4分の1を取得しても、750万円を下回る額となり、子供の遺留分に達しないことになります。
③ 相続人が子供1人のみの場合
子供の遺留分の割合
子供の遺留分は2分の1です。
したがって、遺留分算定基礎財産が6000万円だとすると、遺留分は3000万円です。
子供の遺留分侵害額請求額の計算方法
親が自分以外の人に遺留分算定基礎財産の2分の1に当たる3000万円を超える財産を遺贈・生前贈与等していた場合、残りの財産は3000万円を下回ることになり、子供の遺留分が侵害されることになりますので、侵害されている額の分だけ遺留分侵害額請求をすることができます。
例えば、自分以外の人に4000万円を遺贈・生前贈与等していた場合、子供は2000万円しか取得できず、遺留分が1000万円分侵害されることになりますので、1000万円の遺留分侵害額請求をすることができます。
④ 相続人が子供2人のみの場合
子供の遺留分の割合
子供全体の遺留分は2分の1なので、子供1人の遺留分はその2分の1の4分の1になります。
したがって、遺留分算定基礎財産が6000万円だとすると、遺留分は子供全体で3000万円、子供1人当たり1500万円になります。
子供の遺留分侵害額請求額の計算方法
1人の子供に多額の相続・遺贈・生前贈与があった場合
亡くなった親が1人の子供に遺留分算定基礎財産の4分の3に当たる4500万円を超える財産を相続・遺贈・生前贈与等していた場合、残りの財産は1500万円を下回り、もう1人の子供の遺留分が侵害されることになりますので、侵害されている額の分だけ遺留分侵害額請求をすることができます。
例えば、1人の子供に5000万円を相続・遺贈・生前贈与等していた場合、もう1人の子供は最高で1000万円しか取得できず、遺留分が500万円分侵害されることになりますので、500万円の遺留分侵害額請求をすることができます。
相続人以外に多額の相続・遺贈・生前贈与があった場合
相続人以外に遺贈・生前贈与があった場合には、残りの財産を子供2人で分けることになり、子供1人当たりで取得できる財産はより少なくなりますので、相続人以外に渡った額がより少なかったとしても、子供の遺留分が侵害されることになります。
例えば、相続人以外に3000万円を超える財産を遺贈・生前贈与等していた場合、残りの財産は3000万円を下回ることになります。
この場合、子供は、残りの財産を分けることになりますが、法定相続分である2分の1を取得しても、1500万円を下回る額となり、子供1人当たりの遺留分に達しないことになります。
親が遺留分侵害額請求をする場合の計算シミュレーション
① 相続人が親と配偶者の場合
親の遺留分の割合
親全体の遺留分は6分の1です。
したがって、遺留分算定基礎財産が6000万円だとすると、遺留分は1000万円です。
親の遺留分侵害額請求額の計算方法
配偶者に多額の相続・遺贈・生前贈与があった場合
亡くなった子が配偶者に遺留分算定基礎財産の6分の5に当たる5000万円を超える財産を相続・遺贈・生前贈与等していた場合、残りの財産は1000万円を下回り、親の遺留分が侵害されることになりますので、侵害されている額の分だけ遺留分侵害額請求をすることができます。
例えば、配偶者に5500万円を相続・遺贈・生前贈与等していた場合、配偶者は最高で500万円しか取得できず、その場合に遺留分が500万円分侵害されることになりますので、500万円の遺留分侵害額請求をすることができます。
相続人以外に多額の相続・遺贈・生前贈与があった場合
相続人以外に遺贈・生前贈与があった場合には、残りの財産を配偶者と分けることになりますので、親の取得できる財産はより少なくなりますので、相続人以外に渡った額がより少なかったとしても、親の遺留分が侵害されることになります。
例えば、相続人以外に3000万円を超える財産を遺贈・生前贈与等していた場合、残りの財産は3000万円を下回ることになります。
この場合、親は、残りの財産を共同相続人である配偶者と分けることになりますが、法定相続分である3分の1を取得しても、1000万円を下回る額となり、親の遺留分に達しないことになります。
② 相続人が親のみの場合
親の遺留分の割合
親の遺留分は3分の1です。
したがって、遺留分算定基礎財産が6000万円だとすると、遺留分は2000万円です。
親の遺留分侵害額請求額の計算
親が自分以外の人に遺留分算定基礎財産の3分の2に当たる4000万円を超える財産を遺贈・生前贈与等していた場合、残りの財産は2000万円を下回ることになり、親の遺留分が侵害されることになりますので、侵害されている額の分だけ遺留分侵害額請求をすることができます。
例えば、自分以外の人に5000万円を遺贈・生前贈与等していた場合、親は1000万円しか取得できず、遺留分が1000万円分侵害されることになりますので、1000万円の遺留分侵害額請求をすることができます。
第三者への寄付や負債がある場合の遺留分の計算方法
 以下では第三者への寄付や負債があるというもう少し複雑な計算が必要となる事例も紹介しておきます。
以下では第三者への寄付や負債があるというもう少し複雑な計算が必要となる事例も紹介しておきます。
Aは配偶者を既に亡くし、長男Bと長女Cがいる。
Aは亡くなるときに自宅不動産(3000万円)と預金1000万円を保有していた。
AはBに亡くなる9年前に生前贈与として1000万円を渡していたほか、亡くなる2年前に社会福祉法人Dに1000万円の寄付をしていた。
また、Eに600万円の借金をしていた。
Aは自宅不動産をBに相続させ、預金1000万円をCに相続させ、Eへの借金600万円はAが返済するよう遺言書を作成して亡くなった。
Cの遺留分はいくらか?
遺留分算定基礎額
自宅3000万円+預金1000万円+相続人Bへの生前贈与1000万円ー600万円=4400万円
相続人Bへの生前贈与は9年前なので、遺留分算定の基礎となる。
他方で、社会福祉法人への寄付は相続人以外への生前贈与であるから、相続開始前1年間にされたものでなければ遺留分算定の基礎とならないところ、寄付がされたのは亡くなる2年前なので、遺留分算定の基礎とならない。
Cの遺留分の割合
相続人は子供のみなので遺留分は2分の1の人数割りの4分の1となる。
遺留分の額
4400万円×4分の1=1100万円
では、CはBに遺留分1100万円-相続した預金1000万円=100万円を請求できるということになるのでしょうか?
また、相続した負債の扱いはどうなるのでしょうか?
遺留分侵害額の計算方法

今までご説明してきた遺留分の額は、相続人の最低限の取り分ですが、既にいくらか取り分をもらっている場合には、請求できるのは遺留分のうちまだ受け取っていない額です。
これからお話するのは、まだ受け取っていない遺留分が侵害された状態にある部分の額(遺留分侵害額)の計算方法です。
遺留分侵害額は、次のような計算式で算出します。
遺留分の額-(相続による純取り分+相続とは別に死因贈与で得る額+生前贈与等で既に得ている額)
相続による純取り分とは?
相続では、プラスの財産だけでなくマイナスの財産である負債を負担することがあります。
したがって、プラスの財産だけを受け取ったものとして差し引かれてしまうと、マイナスの財産による不利益が評価されなくなり、不公平です。
そこで、プラスの相続財産からマイナスの相続財産を差し引いた純取り分を受け取ったものとして差し引くことになっています。
例えば、預金1000万円を相続するが、負債600万円の2分の1の300万円も相続する場合、純取り分は次のようになります。
1000万円-300万円=700万円
具体的な計算方法
先ほどの例に戻って遺留分侵害額の計算方法をご説明しましょう。
事例の内容
Aには子供Bと子供Cがいる。
Aは亡くなるときに自宅不動産(3000万円)と預金1000万円を保有していた。
AはBに生前贈与として1000万円を渡していたほか、亡くなる2年前に社会福祉法人Dに1000万円の寄付をしていた。
また、Eに600万円の借金をしていた。
Aは自宅不動産をBに相続させ、預金1000万円をCに相続させ、Eへの借金600万円はAが返済するよう遺言書を作成して亡くなった。
Cの遺留分はいくらか?
遺留分算定基礎額
自宅3000万円+預金1000万円+相続人Bへの生前贈与1000万円ー600万円=4400万円
相続人Bへの生前贈与は9年前なので、遺留分算定の基礎となる。
他方で、社会福祉法人への寄付は相続人以外への生前贈与であるから、相続開始前1年間にされたものでなければ遺留分算定の基礎とならないところ、寄付がされたのは亡くなる2年前なので、遺留分算定の基礎とならない。
Cの遺留分の割合
相続人は子供のみなので遺留分は2分の1の人数割りの4分の1となる。
遺留分の額
4400万円×4分の1=1100万円
遺留分侵害額
このケースでは、負債600万円の負担割合が決められていないので、法定相続分に応じて300万円ずつ負担すると考える。
そうすると、相続による純取り分は、預金1000万円-負債300万円=700万円となる。
遺留分の額1100万円-相続による純取り分700万円=400万円
したがって、遺留分侵害額は400万円となり、これを請求する権利を有していることになる。
遺留分を請求する手続きの流れ
遺留分侵害額を計算し、請求する権利があることが分かったら、次に行動に移します。手続きは、話し合いから始まり、合意できなければ裁判所の手続きへと段階的に進んでいくのが一般的です。
ステップ1:内容証明郵便で請求の意思を伝える(交渉)
まず、遺留分を侵害している相手(遺贈や贈与を多く受け取った人)に対して、「遺留分侵害額を請求します」という意思表示を行います 。
この意思表示は口頭でも可能ですが、後から「言った」「言わない」という争いを避けるため、内容証明郵便を利用するのが最も確実です。内容証明郵便は、いつ、どのような内容の文書を、誰が誰に送ったのかを郵便局が証明してくれるサービスです。これにより、時効の進行を止めるための証拠を残すことができます。
この通知を送った後、相手方との直接交渉が始まります。ここで双方が合意できれば、最も円満かつ迅速な解決となります。
ステップ2:家庭裁判所の「遺留分侵害額の請求調停」
当事者間の話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てます 。
日本の法律では、遺留分のような家庭に関する金銭トラブルは、いきなり訴訟(裁判)を起こすのではなく、まず調停で話し合うことが原則とされています(調停前置主義)。
調停とは、裁判官と民間の有識者からなる調停委員が間に入り、中立的な立場で双方の主張を聞き、解決策を提示したり助言をしたりしながら、合意を目指す話し合いの手続きです 。手続きは非公開で行われるため、プライバシーは守られます。
申立てには、収入印紙1,200円分と、連絡用の郵便切手代(数千円程度)が必要です 。調停で合意が成立すると、その内容をまとめた「調停調書」が作成されます。この調書は、確定判決と同じ法的効力を持ち、相手が支払いに応じない場合は強制執行も可能です 。
手続きの詳細は、裁判所のウェブサイトで確認できます。遺留分侵害額の請求調停 (裁判所)
ステップ3:調停不成立の場合は「訴訟」へ
調停で話し合いがまとまらず、不成立となった場合には、最終手段として地方裁判所(または簡易裁判所)に「遺留分侵害額請求訴訟」を提起することになります 。
訴訟は、調停とは異なり、公開の法廷で行われます。原告と被告がそれぞれの主張と証拠を提出し、最終的に裁判官が法に基づいて判決を下します。調停から自動的に訴訟に移行するわけではないため、改めて訴状を提出する必要があります 。訴訟は手続きが非常に専門的かつ複雑になるため、この段階では弁護士への依頼が不可欠と言えるでしょう。
遺留分計算に関するよくある質問(FAQ)
遺留分の計算や請求に関しては、個別性の高い疑問が多く寄せられます。ここでは、特に重要な質問についてQ&A形式で解説します。
その他の遺留分に関するよくある質問は、「遺留分侵害額請求Q&A」をご覧ください。
Q1. 生命保険金は遺留分の計算に含めますか?
A1. 原則として含めませんが、例外があります。
受取人が指定されている生命保険金は、民法上、相続財産ではなく「受取人固有の財産」とされています。そのため、原則として遺留分算定の基礎となる財産には含まれません 。
しかし、判例では例外を認めています。保険金の額が遺産総額に対して著しく高額であるなど、生命保険金を含めないと相続人間で到底是認できないほどの著しい不公平が生じる「特段の事情」がある場合には、例外的に特別受益に準ずるものとして、計算に含めるべきとされることがあります 。この判断は非常に専門的であり、個別の事情を総合的に考慮して決まります 。
Q2. 不動産の価値はどのように評価しますか?
A2. 相続開始時点の「時価」で評価するのが原則です。
遺留分の計算における不動産の評価は、生前贈与された時点や遺言を作成した時点ではなく、故人が亡くなった相続開始時点の時価(実勢価格)を基準とします 。
時価を算出するには、いくつかの方法があります。
- 固定資産税評価額: 固定資産税の基準となる価格。時価の70%程度が目安。
- 路線価: 相続税や贈与税の計算に用いられる価格。時価の80%程度が目安。
- 公示価格: 国が示す土地取引の目安となる価格。
- 不動産業者の査定価格: 実際に市場で売買される価格に近い評価。
どの評価方法を用いるかについて法律上の決まりはありません。そのため、遺留分を請求する側は評価額が高くなる方法(例:不動産業者の査定)を主張し、請求される側は低くなる方法(例:固定資産税評価額)を主張するため、争点になりやすいポイントです 。話し合いで合意できない場合は、最終的に不動産鑑定士による鑑定や、裁判所が選任した鑑定人の評価によって決まることもあります。
Q3. 遺留分請求に時効はありますか?【重要】
A3. はい、非常に短い時効がありますので注意が必要です。
遺留分を請求する権利(遺留分侵害額請求権)には、以下の2つの時効期間が定められています 。
- 相続の開始と、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年
- 上記を知らなくても、相続開始の時から10年
特に「知った時から1年」という期間は非常に短く、この期間を過ぎてしまうと権利が消滅してしまいます 。遺留分が侵害されている可能性があると気づいたら、速やかに行動を起こすことが極めて重要です。
Q4. 2019年の法改正で何が変わりましたか?
A4. 最も大きな変更点は、遺留分侵害額を「金銭」で請求するようになったことです。
2019年7月1日に施行された改正民法により、遺留分制度は大きく変わりました。最大のポイントは、請求権が「金銭債権化」されたことです 。
- 改正前: 遺留分を侵害された場合、不動産などの「現物」そのものの返還を求めることが原則でした。これにより、不動産が共有状態になるなど、複雑な問題が生じていました。
- 改正後: 遺留分侵害額に相当する**「金銭」の支払いを請求する**権利に一本化されました。これにより、不動産などの財産を売却することなく、金銭で解決することが可能になり、より柔軟な対応ができるようになりました。
また、金銭を支払う側がすぐに現金を用意できない場合には、裁判所に申し立てて支払期限の猶予を求めることも可能になりました 。この改正については、
相続に関するルールが大きく変わります (法務省)のページでも解説されています。
Q5. 遺留分を放棄することはできますか?
A5. はい、可能ですが、時期によって手続きが異なります。
遺留分は権利であるため、放棄することも可能です 。
- 相続開始前(生前)の放棄: 相続が始まる前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可を得る必要があります 。単に「遺留分を放棄します」という念書を交わしただけでは法的な効力はありません。
- 相続開始後の放棄: 相続が始まった後に放棄する場合は、特別な手続きは不要です。遺留分を侵害している相手に対して、請求権を行使しない意思を伝えれば足ります。一度時効(1年)が経過すれば、権利は自動的に消滅します。
遺留分の計算や請求は弁護士への相談が安心
ここまで見てきたように、遺留分の計算と請求には、法律の専門知識が不可欠です。遺留分算定の基礎となる財産の範囲の特定、不動産などの複雑な財産評価、相手方との交渉、そして家庭裁判所での調停や訴訟といった手続きは、ご自身だけで進めるには大きな負担と困難が伴います 。
特に、1年という短い時効期間を考慮すると、迅速かつ的確な対応が求められます。
相続問題に精通した弁護士に相談することで、以下のようなサポートが期待できます。
- 正確な遺留分侵害額の計算
- 財産調査の代行
- 相手方との交渉代理
- 内容証明郵便の作成・送付
- 調停や訴訟における代理人としての活動
遺留分は、法律で認められたあなたの正当な権利です。その権利を確実に守り、精神的な負担を軽減しながら円満な解決を目指すために、まずは一度、専門家である弁護士に相談されることを強くお勧めします。
遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要

このように遺留分の計算には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士による無料診断を受けられることをお勧めしております。
遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。
司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。
弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。
法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が遺留分の無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士費用について
遺留分侵害額請求
| 取得額 | 着手金 | 成功報酬 |
| ~300万円に当たる部分 |
0円 |
16.5%+22万 |
|
~3000万円に当たる部分 |
11% | |
| ~1億円に当たる部分 | 8.8% | |
| 1億円を超える部分 | 5.5% |
※1 遺留分の請求が困難な事案では着手金を頂く場合があります。
※2 弁護士費用とは別に実費(各種資料取得費用、通信費等)がかかります。
※3 弁護士費用は消費税込です。
ページトップに戻る