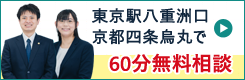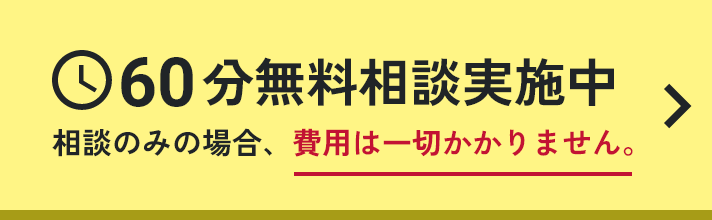遺産分割調停とは?申立書からの流れや期間は?弁護士費用は?
遺産分割調停を申し立てられた側が一切支払うお金がないと言われていたのに700万円を取得することに成功した事例
遺産分割調停とは?
 遺産分割調停とは、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)では合意に至らない場合や、一部の相続人が話し合いに一切応じないといった状況で、家庭裁判所を通じて解決を図るための法的な手続きです 。この手続きでは、民間の有識者から選ばれる調停委員2名が間に入り、各相続人の主張を整理しながら、円満な合意形成を目指します 。
遺産分割調停とは、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)では合意に至らない場合や、一部の相続人が話し合いに一切応じないといった状況で、家庭裁判所を通じて解決を図るための法的な手続きです 。この手続きでは、民間の有識者から選ばれる調停委員2名が間に入り、各相続人の主張を整理しながら、円満な合意形成を目指します 。
調停は、訴訟のように裁判官が一方的に判決を下すものではなく、あくまで当事者間の「話し合い」を基本とします。しかし、単なる話し合いと大きく異なるのは、ここで成立した合意内容が「調停調書」という公的な書面に記載される点です 。この調停調書は、確定した判決と同じ法的効力を持ち、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなど、法的な手続きを進めるための根拠となります。もし相手方が合意内容を守らない場合には、この調書に基づいて強制執行を行うことも可能です 。
このページでは、法律事務所リンクスの相続に強い弁護士が、遺産分割調停について詳しくご説明すると共に、遺産分割調停を申し立てられた側が一切支払うお金がないと言われていたのに700万円を取得することに成功した事例をご紹介します。
【立場別】遺産分割調停に臨む上での弁護士からのアドバイス
遺産分割調停に臨むにあたり、あなたが「申し立てる側(申立人)」なのか、「申し立てられた側(相手方)」なのかによって、取るべき対応や心構えが異なります。
遺産分割調停を申し立てる方(申立人)へ
申立ての趣旨と理由を明確に準備する
調停を有利に進めるためには、申立ての段階で「どの遺産を、どのように分割してほしいのか」という希望(申立ての趣旨)と、「なぜそのように分割するのが妥当なのか」という根拠(申立ての理由)を、具体的かつ論理的に示すことが重要です。弁護士は、依頼者の希望をヒアリングし、それを法的に説得力のある主張へと構成し直すサポートをします。
主張を裏付ける証拠を徹底的に集める
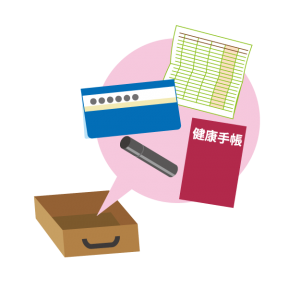 調停は、証拠に基づいた議論の場です。特に、特別受益(例えば、特定の相続人が被相続人から住宅購入資金の援助を受けていたなど)や寄与分(長年にわたり被相続人の介護を一身に担ってきたなど)を主張する場合には、それを裏付ける客観的な証拠がなければ、調停委員を納得させることはできません。預金通帳の取引履歴、日記、介護記録、領収書など、考えられるあらゆる証拠を、弁護士と共に徹底的に収集しましょう。
調停は、証拠に基づいた議論の場です。特に、特別受益(例えば、特定の相続人が被相続人から住宅購入資金の援助を受けていたなど)や寄与分(長年にわたり被相続人の介護を一身に担ってきたなど)を主張する場合には、それを裏付ける客観的な証拠がなければ、調停委員を納得させることはできません。預金通帳の取引履歴、日記、介護記録、領収書など、考えられるあらゆる証拠を、弁護士と共に徹底的に収集しましょう。
譲れる点と譲れない点を決めておく
調停は話し合いの場であるため、自身の主張が100%通るとは限りません。どこかで譲歩が必要になる場面も想定されます。事前に「この財産だけは絶対に取得したい」「この点については譲歩しても構わない」といった優先順位を明確にし、落としどころを見据えた交渉戦略を弁護士と共に練っておくことが、最終的に満足のいく結果を得るための鍵となります。
法律事務所リンクスは遺産分割の相談が60分無料!
 法律事務所リンクスでは、遺産分割に強い弁護士による60分無料相談を実施しています。
法律事務所リンクスでは、遺産分割に強い弁護士による60分無料相談を実施しています。
相談に当たっては、ご予約いただいた際にご事情を伺い、調査をした上で相談に臨みますので、無料相談の時間内で充実した情報を提供しております。
相談者様が聞き足りなかったということが起きないようにしておりますし、ホワイトボードを使うなどして分かりやすく説明していますので、お気軽にお問い合わせください。
相談者様が聞き足りなかったということが起きないようにしておりますし、ホワイトボードを使うなどして分かりやすく説明していますので、東京で相続に強い弁護士に相談されたい方は「東京で相続を弁護士に無料相談なら法律事務所リンクス」のサイトから、京都で相続に強い弁護士に相談されたい方は「京都で相続を弁護士に無料相談なら法律事務所リンクス」のサイトからお気軽にお問い合わせください。
遺産分割調停の進め方を動画でご覧になりたい方はコチラ
遺産分割調停を申し立てられた方(相手方)へ
裁判所からの呼出状(通知書)が届いたら、まず弁護士に相談を
ある日突然、家庭裁判所から「遺産分割調停期日呼出状」という書類が届いたら、決して無視してはいけません。呼出状を無視して調停を欠席し続けると、相手方の主張が全面的に認められた内容で調停が進んでしまったり、審判に移行して著しく不利な決定が下されたりする危険性があります 。通知が届いた時点で、速やかに相続問題に詳しい弁護士に相談することが、ご自身の権利を守るための最善の初動です。
相手方の申立書を分析し、的確な反論を準備する
 呼出状と共に送られてくる申立書には、相手方が主張する遺産の分割方法や、その根拠が記載されています。弁護士は、その内容を専門的な視点で精査し、遺産目録に漏れや誤りはないか、相手方の主張に法的な問題点はないかなどを徹底的にチェックします。その上で、事実と異なる点や法的に不当な要求に対して、的確な反論を準備します。
呼出状と共に送られてくる申立書には、相手方が主張する遺産の分割方法や、その根拠が記載されています。弁護士は、その内容を専門的な視点で精査し、遺産目録に漏れや誤りはないか、相手方の主張に法的な問題点はないかなどを徹底的にチェックします。その上で、事実と異なる点や法的に不当な要求に対して、的確な反論を準備します。
ご自身の希望や主張も積極的に行う
相手方の主張に反論するだけの受け身の姿勢では、有利な解決は望めません。相手方の提案をただ待つのではなく、「自分はこうしたい」という希望の分割案や、ご自身の寄与分、相手方の特別受益など、主張すべき点を積極的に調停の場で訴えていくことが重要です。弁護士と共に攻めの姿勢で臨み、ご自身の正当な権利を主張していきましょう。
次の事案は、相手方から3000万円の生前贈与があると言われて、当方に支払うお金はないと言われてた事案です。
遺産分割調停を申し立てられた側が一切支払うお金がないと言われていたのに700万円を取得することに成功した事例
相談のきっかけ
 相談者はお亡くなりになられた方(父)の二男で、母と長男から遺産分割を申し立てられたということで相談にいらっしゃいました。母と長男からは父から二男に3000万円の生前贈与があるから、二男には相続分がないという主張をされていて、二男も一部認めているという状況でした。
相談者はお亡くなりになられた方(父)の二男で、母と長男から遺産分割を申し立てられたということで相談にいらっしゃいました。母と長男からは父から二男に3000万円の生前贈与があるから、二男には相続分がないという主張をされていて、二男も一部認めているという状況でした。
リンクスの弁護士のアドバイス
リンクスの弁護士は、生前贈与について、実際に受け取ったものとそうではないものを仕分けしてその根拠を示すことが大事であること、母が亡くなった時の二次相続に備えて、適切な遺産分割をすることをアドバイスしました。
遺産分割調停の成立
その結果、数ヶ月で700万円を支払ってもらう形で、調停を成立させることに成功しました。
遺産分割調停の流れと期間|申立てから解決までの全ステップ
遺産分割調停は、申立ての準備から始まり、いくつかのステップを経て解決に至ります。ここでは、その全体像を具体的に解説します。
Step 1: 遺産分割調停の申立て前の準備(弁護士への相談と調査)
調停を申し立てる前に、まずは相続問題に詳しい弁護士に相談し、法的な見通しや戦略を立てることが極めて重要です 。弁護士は、依頼を受けるとまず以下の調査に着手します。
- 相続人の確定: 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を全て収集し、法的に誰が相続人となるのかを正確に確定させます。相続関係が複雑な場合でも、漏れなく調査します 。
- 相続財産の調査: 不動産の登記事項証明書や名寄帳、預貯金の残高証明書、有価証券の取引報告書などを取り寄せ、被相続人が遺した財産の全容を明らかにします 。
- 特別受益・寄与分の証拠収集: 特定の相続人への生前贈与を示す資料(預金通帳の記録など)や、被相続人への特別な貢献(介護記録、療養費の領収書など)を裏付ける証拠を、調停が始まる前に収集します 。
これらの準備を事前に行うことで、調停の場で迅速かつ的確な主張を展開することが可能になります。
Step 2: 遺産分割調停の申立手続き
準備が整ったら、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行います。
管轄裁判所の確認(申立てはどこにする?)
遺産分割調停は、原則として「相手方のうちの一人の住所地」を管轄する家庭裁判所に申し立てます 。当事者全員が合意すれば、それ以外の家庭裁判所を選択することも可能です 。
申立てに必要な書類一覧と入手方法
申立てには、多数の書類が必要となります。特に「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」の収集は、本籍地の変更が多い場合などには非常に手間がかかる作業であり、弁護士に依頼する大きなメリットの一つです 。
ご自身で申立てを行う場合、弁護士費用とは別に以下の実費がかかります。
- 申立手数料: 収入印紙1,200円(被相続人1人あたり) 。
- 郵便切手代: 裁判所からの書類送付用。数千円程度。
- 書類取得費用: 戸籍謄本や登記事項証明書などの取得費用。数千円から、相続人が多い場合は数万円になることもあります 。
- 不動産鑑定費用: 不動産の評価額に争いがあり、裁判所による鑑定が必要となった場合、数十万円の鑑定費用が別途発生することがあります 。
Step 3: 調停期日の進行
申立てが受理されると、約1ヶ月から2ヶ月後に第1回目の調停期日が指定されます。調停は平日の日中に行われ、1回の期日にかかる時間は約2時間程度です 。
期日当日、申立人と相手方は別々の待合室で待機し、交互に調停室に呼ばれます。そこで調停委員に対し、自身の主張を伝えたり、相手方の主張に対する反論を行ったりします。基本的に相手方と直接顔を合わせることはないため、冷静に話し合いを進めることができます 。
調停においては、調停委員から資料の提出を求められたり、法律的な論点についての意見を聴かれたりします。弁護士は、この進行に合わせて、依頼者の利益が最大化されるよう、適切なタイミングで主張と立証活動を行います。
Step 4: 調停の終了(成立・不成立・取下げ)
調停は、通常1回では終わらず、数ヶ月から1年以上かけて複数回の期日を重ねます。最終的に、以下のいずれかの形で終了します。
調停成立:合意内容が「調停調書」に記載される
全ての相続人が遺産の分割方法について合意に至ると、調停は「成立」となります。合意内容は裁判所書記官によって「調停調書」にまとめられ、この調書は確定判決と同じ法的効力を持ちます 。この調書を使えば、不動産の所有権移転登記や、預貯金の解約・名義変更といった手続きを単独で行うことが可能になります 。
調停不成立:自動的に「遺産分割審判」へ移行
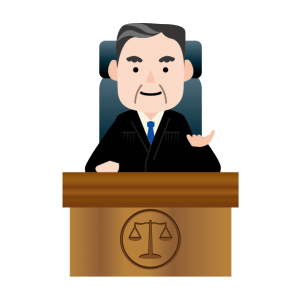 話し合いを重ねても、どうしても合意の見込みが立たない場合、調停は「不成立」として終了します。この場合、手続きは自動的に「遺産分割審判」へと移行します 。
話し合いを重ねても、どうしても合意の見込みが立たない場合、調停は「不成立」として終了します。この場合、手続きは自動的に「遺産分割審判」へと移行します 。
審判手続きでは、調停のように話し合いで解決を目指すのではなく、裁判官が、調停の過程で提出された全ての資料や各当事者の主張を法的な観点から総合的に判断し、遺産の分割方法について最終的な決定(審判)を下します 。この審判には、当事者の合意がなくても法的拘束力が生じ、その内容に従わなければなりません。
こで重要なのは、調停から審判への移行が「自動的」かつ「連続的」であるという点です。調停で提出した主張や証拠は、そのまま審判の判断材料となります。つまり、調停での対応が不十分だった場合、それが直接、審判での不利な結果に繋がるのです。したがって、調停の初期段階から、最終的に審判になる可能性も見据えた一貫性のある戦略を立てることが不可欠であり、この点においても弁護士のサポートが極めて重要となります。
遺産分割調停の弁護士費用について
弁護士への依頼を検討する際に、最も気になるのが費用でしょう。弁護士費用は事務所によって異なりますが、一般的に以下の内訳で構成されています。
弁護士費用の内訳(相談料・着手金・報酬金・実費)
相談料: 弁護士に正式に依頼する前の法律相談にかかる費用です。30分5,000円程度が相場ですが、「初回相談無料」としている法律事務所も多くあります 。
着手金: 弁護士に事件を依頼する際に、最初に支払う費用です。結果にかかわらず返金されないのが一般的です。遺産の総額や事案の複雑さに応じて変動しますが、20万円~60万円程度が目安です。事務所によっては定額制を採用している場合もあります 。法律事務所リンクスの場合には、着手金無料で対応することが可能です。詳しくは、法律事務所リンクスの遺産相続の弁護士費用をご覧ください。
報酬金: 事件が解決した際に、得られた経済的利益(取得した遺産の額など)に応じて支払う成功報酬です。経済的利益の4%~16%程度が一般的で、利益が大きくなるほど料率は低くなる傾向があります 。
実費・日当: 収入印紙代、郵便切手代、交通費、戸籍等の取得費用などの実費が別途かかります。また、弁護士が裁判所へ出頭する際に、1回あたり数万円の日当が発生する場合があります 。
法律事務所の料金体系の確認ポイント
弁護士を選ぶ際には、料金体系がウェブサイトなどで明確に示されているかを確認することが重要です。また、当初の見積もり以外に追加費用が発生する可能性があるのか、どのような場合に発生するのかを事前に確認しておきましょう。
特に注意したいのが、遺産分割協議の代理交渉から調停に移行した場合の費用です。事務所によっては、調停に移行する際に別途着手金が必要になる場合がありますが、協議から調停への移行では追加の着手金がかからない料金体系の事務所もあります 。
費用対効果の考え方:弁護士依頼で得られる経済的利益
弁護士費用は決して安価ではありませんが、その費用対効果を考えることが重要です。例えば、総額5,000万円の遺産があり、ご自身で対応した場合は法定相続分である1,250万円しか取得できなかったところ、弁護士に依頼して寄与分などが認められた結果、1,750万円を取得できたとします。この場合、弁護士費用が仮に200万円かかったとしても、差し引きで300万円の経済的利益を得たことになります。
このように、弁護士費用は単なるコストではなく、ご自身の正当な財産を最大限確保するためのリターンが見込める投資と考えることができます 。
遺産分割調停に関するよくあるご質問(FAQ)
Q. 調停には必ず本人が出席しなければなりませんか?
A. 原則として本人の出席が求められますが、弁護士を代理人に選任している場合、事情によっては弁護士のみの出席で手続きを進めることが認められるケースもあります 。遠方にお住まいの方や、仕事の都合で平日の出頭が難しい方、感情的な対立から相手方と顔を合わせたくない方にとっては、大きなメリットとなります。
Q. 調停はどのくらいの期間がかかりますか?
A. 事案の複雑さや当事者間の対立の度合いによりますが、一般的には半年から1年程度かかることが多いです。裁判所の統計データを見ても、1年以内に終結する事件が最も多いですが、争点が多岐にわたる複雑な案件では2年以上を要することもあります 。
Q. 相手が遠方に住んでいる場合、どこの裁判所に申し立てますか?
A. 原則は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です 。例えば、申立人が東京在住でも、相手方が大阪在住であれば、原則として大阪家庭裁判所に申し立てることになります。ただし、当事者全員が合意すれば、東京家庭裁判所など、合意した場所の裁判所で調停を行うことも可能です。
Q. 不動産の評価額で揉めている場合はどうなりますか?
A. 当事者間で評価額の合意ができない場合、最終的には裁判所が選任する不動産鑑定士による鑑定が行われることがあります 。鑑定結果は客観的な評価として尊重されますが、鑑定には数十万円の費用がかかり、その費用は原則として当事者が負担することになります 。
Q. 特別受益や寄与分も調停で主張できますか?
A. はい、主張できます。むしろ、特別受益や寄与分の存在は、遺産分割調停における最も主要な争点の一つです。東京家裁の「段階的進行モデル」においても、「各相続人の取得額」を確定する段階で中心的に議論されます 。ただし、これらの主張を裁判所に認めてもらうためには、客観的で説得力のある証拠の提出が不可欠です。
Q. 調停で決まった内容に従わない相続人がいたらどうなりますか?
A. 調停が成立して作成された「調停調書」には、確定した判決と同じ法的な強制力があります 。もし相手方が調停で決まった義務(例えば、代償金の支払いや不動産の名義変更協力など)を履行しない場合、調停調書に基づいて相手方の財産を差し押さえるなどの強制執行手続きをとることが可能です。
Q. 弁護士に依頼するタイミングはいつが最適ですか?
A. 相続人間の話し合いで少しでも「こじれそうだ」「感情的な対立が深まっている」と感じた時点、あるいは相手方から弁護士を通じて連絡が来た時点、そして裁判所から調停の呼出状が届いた時点が、弁護士に相談・依頼する最適なタイミングです。問題が深刻化する前に、できるだけ早い段階で専門家の助言を得ることが、有利な解決に繋がる可能性を高めます。
遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要

このように、遺産分割調停には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。
弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。
法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
ページトップに戻る