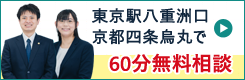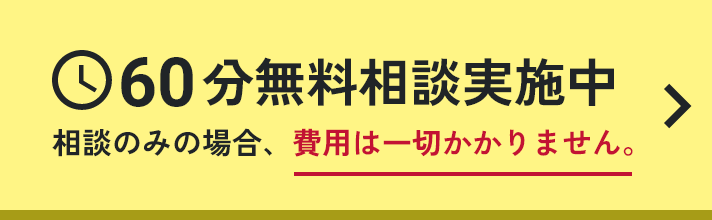相続不動産の査定や評価額の調べ方は?遺産分割と相続税で違う?
不動産の査定・鑑定をして取得額が数百万円増えた事例を紹介
相続した不動産の査定や評価額の調べ方には、次の方法があります。
- 固定資産税の納税通知書で固定資産税評価額を調べる
- 税理士に路線価などを基に相続税評価額を計算してもらう
- 不動産会社に実勢価格(時価)を査定してもらう
- 不動産鑑定士に実勢価格(時価)を鑑定してもらう
不動産の評価額の調べ方としてどの方法を採用するかは、相続税の申告、遺産分割、遺留分侵害額の請求などのうち、どの手続きに用いるかで異なります。
このページでは、法律事務所リンクスの相続に強い弁護士が、固定資産税評価額、相続税評価額、実勢価格(時価)という3つの評価方法の具体的な調べ方から、計算シミュレーション、相続人間で意見が対立した場合の対処法まで具体的に解説します。
相続不動産の査定が必要な理由
相続財産の中に不動産がある場合、不動産を査定して評価する必要があるのは、次の3つの理由によります。
- 不動産の評価が決まらないと遺産総額が決まらないので、誰がいくらもらえばよいか決められない
- 不動産の評価が決まらないと不動産を取得する人がいくら相続したことになるかが決まらないので、その人がもらい過ぎなのか、その人にまだ遺産を分けないといけないのかが分からない
- 不動産を取得する人がもらい過ぎだとした場合、代償金を支払わないといけないが、その額が決まらない
法律事務所リンクスは相続の相談が60分無料!
 法律事務所リンクスでは、遺産相続に強い弁護士による60分無料相談を実施しています。
法律事務所リンクスでは、遺産相続に強い弁護士による60分無料相談を実施しています。
相談に当たっては、ご予約いただいた際にご事情を伺い、調査をした上で相談に臨みますので、無料相談の時間内で充実した情報を提供しております。
相談者様が聞き足りなかったということが起きないようにしておりますし、ホワイトボードを使うなどして分かりやすく説明していますので、東京で相続に強い弁護士に相談されたい方は「東京で相続を弁護士に無料相談なら法律事務所リンクス」のサイトを、京都で相続に強い弁護士に相談されたい方は「京都で相続を弁護士に無料相談なら法律事務所リンクス」のサイトからお気軽にお問い合わせください。
不動産の相続の進め方を動画でご覧になりたい方はコチラ
相続不動産の3つの評価方法と具体的な調べ方
固定資産税評価額:固定資産税など各種税金の基準となる価格
固定資産税評価額は、固定資産税や都市計画税、不動産取得税、登録免許税といった地方税を計算する際の基準となる価格です 。土地や家屋が所在する市区町村(東京23区の場合は東京都)が、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて3年ごとに評価を見直しています 。
この評価額は、毎年春に送られてくる固定資産税の納税通知書に記載されており、最も手軽に確認できる公的な価格です 。納税通知書を紛失してしまった場合でも、不動産の所在地を管轄する市区町村の役所(または都税事務所)の窓口で「固定資産評価証明書」を取得できます 。
相続人間で合意がある場合、固定資産税評価額を遺産分割や遺留分侵害額請求の基準として用いることもありますが、実勢価格(時価)よりも低いのが一般的であるため、実勢価格(時価)の6~7割程度とみて固定資産評価額を割り戻して、不動産の評価額とすることが多いです。
相続税評価額(路線価または倍率方式):相続税計算のためだけの特別な価格
相続税評価額は、相続税や贈与税を計算するためだけに用いられる特別な評価額です 。国税庁が定めた財産評価基本通達に基づいて算出され、公平な課税を実現するために、全国一律の基準で評価されます。
土地の評価
市街地の土地については、道路(路線)ごとに定められた1平方メートルあたりの価格である「路線価」を用いて評価する「路線価方式」が用いられます。路線価は公示価格の80%程度を目安に設定されています 。
一方、路線価が定められていない郊外や農村部などの土地は、固定資産税評価額に一定の「倍率」を掛けて評価する「倍率方式」が用いられます 。この評価額はあくまで課税のための基準であり、実際の市場価値である実勢価格とは異なることを明確に理解しておく必要があります。
これらは、国税庁のウェブサイトで調べて計算することができますが、計算方式が複雑で専門知識を要するため、正確な評価額を知りたい場合は税理士などの専門家に相談することをお勧めします 。
路線価についても、相続人間で合意があれば、遺産分割の基準として用いられることもありますが、実勢価格(時価)よりも低いのが一般的であるため、7~8割程度とみて路線価を割り戻して、不動産の評価額とすることが多いです。
建物の評価
建物の相続税評価額は、土地と比べてシンプルです。原則として、その建物の「固定資産税評価額」がそのまま相続税評価額となります 。したがって、固定資産税の納税通知書に記載されている建物の価格を確認すれば、それが評価額です。
ただし、被相続人がその建物を他人に貸していた場合(アパートや貸家など)は例外です。この場合、借主の権利(借家権)を考慮して評価額が減額されます 。この計算も専門的な知識が必要となるため、該当する場合は専門家への相談が賢明です。
実勢価格(時価):遺産分割で最も重視される「売れる価格」
実勢価格とは、実際に市場で売買される価格、いわゆる「時価」のことです 。これは、特定の買い手や売り手の事情に左右されない、客観的な市場価値を反映した価格です。遺産分割協議において、相続人間の公平性を確保するために最も重視されるのが、この実勢価格です 。なぜなら、不動産を現金に換えた場合にいくらになるかを示す、最も現実的な価値だからです。
不動産会社による査定
実勢価格を知る最も手軽で一般的な方法が、不動産会社に無料査定を依頼することです。特に、相続した不動産の所在地に詳しい地元の不動産会社に依頼すると、地域の実情に即した査定が期待できます。
査定を依頼する際は、1社だけでなく、2~3社に依頼するのがポイントです 。不動産会社によって査定額にばらつきが出ることがあり、複数の査定書を比較することで、より客観的な価格帯を把握できます。査定書には、査定額の根拠(周辺の取引事例や物件の長所・短所など)が記載されているため、相続人間での話し合いの材料としても役立ちます。ただし、この査定はあくまで売却する場合の「見込み価格」であり、法的な拘束力はない点に注意が必要です 。
不動産鑑定士による鑑定
不動産鑑定士による鑑定は数十万円の費用がかかりますが、その評価書は公的な証明力が高く、裁判所での手続きにおいても有力な証拠となります 。
国土交通省が公表している「公示価格」は、一般の土地取引において客観的な価格の目安を提供し、不動産鑑定の基準となっていますが、あくまで標準地の1平方メートルあたりの単価であり、個別の不動産の価格を直接示すものではありません。
しかし、他の評価額を算出する際の重要な基準となっており、例えば実勢価格は公示価格の1.1倍から1.2倍程度になることが多いとされています 。相続する不動産の近くにある標準地の公示価格を調べることで、その地域の地価水準を把握し、実勢価格を推測する際の参考になります。
遺産分割では不動産の評価額のうちどれを使うべき?
原則は「実勢価格(時価)」
遺産分割では「実勢価格(時価)」を用いるのが原則です 。家庭裁判所での調停や審判においても、実勢価格が基準とされます。
その理由は、相続人間の「公平性」を最も正確に反映できる価格だからです。例えば、相続税の計算に用いる相続税評価額(路線価)は、実勢価格の約8割程度に設定されています。もしこの低い評価額を基準に遺産分割を行うと、不動産を現物で取得した相続人は、実勢価格との差額分だけ他の相続人より多くの価値を得ることになり、不公平が生じます 。実勢価格は、その不動産が持つ本来の財産的価値を示すため、この価格を基準にすることで、各相続人が受け取る価値を等しくすることが可能になるのです。
例外:相続人全員が合意すれば他の評価額も利用可能
原則は実勢価格ですが、相続人全員が合意する場合には、実勢価格以外の評価額(例えば、手軽に確認できる固定資産税評価額など)を基準に遺産分割を行うことも法的に可能です 。
例えば、不動産鑑定士に鑑定を依頼する費用や手間を省きたい場合や、相続人同士の関係が非常に良好で、多少の評価額の差は問題にしないというケースでは、便宜的に他の評価額が用いられることがあります。
注意点:評価の基準時点は「遺産分割協議が成立した時点」
もう一つ、非常に重要でありながら見落とされがちなのが、評価の「基準時点」です。不動産の価格は経済状況によって常に変動します。
相続税の計算では「被相続人が亡くなった日(相続開始日)」の評価額を用いますが、遺産分割協議では、原則として「遺産分割協議が成立した時点」の評価額を基準とします 。相続開始から遺産分割協議が成立するまでに数ヶ月、場合によっては数年かかることもあり、その間に不動産価格が大きく変動する可能性があるためです。
例えば、相続開始時には5,000万円の価値だった不動産が、協議成立時には市況の好転で6,000万円に値上がりしていたとします。この場合、相続開始時の5,000万円を基準に代償金を計算すると、不動産を取得した相続人だけが値上がり益を享受することになり、不公平です。したがって、分割時の最新の時価を基準とすることが、公平な分割を実現するために不可欠なのです。
相続人同士で評価額に合意できない場合の対処法
遺産分割協議を進める中で、不動産の評価額について相続人間の意見がまとまらず、話し合いが行き詰まってしまうことは少なくありません。そのような場合でも、感情的にならず、法的な手続きに沿って段階的に解決を図ることが重要です。一般的には次のように進みます。
①交渉のプロである弁護士に無料相談する
評価額に関する対立が生じた、あるいはその兆候が見られた時点で、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが、円満かつ有利な解決への近道です。弁護士は、最後の手段ではなく、むしろ最初の相談相手として非常に有効です。
弁護士は、以下のような多岐にわたるサポートを提供できます。
- 交渉代理: 依頼者の代理人として、他の相続人と冷静かつ法的な根拠に基づいて評価額の交渉を行います。
- 戦略的助言: 不動産鑑定士に依頼すべきか、その費用対効果はどうか、どのような証拠を集めるべきかといった戦略的なアドバイスを提供します。
- 法的手続きの代理: 遺産分割調停や審判になった場合、依頼者の利益を最大化するために、法廷で適切な主張・立証活動を行います 。
相続問題に精通した弁護士が介入し、不動産会社から査定を取るなどすることで、客観的な事実に基づいた建設的な話し合いを進めることが可能になります。
②家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる
弁護士が依頼を受けても遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることになります 。
調停は、裁判官と民間の有識者からなる調停委員が間に入り、当事者双方の意見を聞きながら、話し合いによる解決を目指す手続きです。非公開で行われ、訴訟(裁判)よりも柔軟な解決が期待できます。
対処法3:調停不成立の場合は遺産分割審判へ移行
調停でも話し合いがまとまらなかった場合、手続きは自動的に「遺産分割審判」へと移行します 。審判は、調停のような話し合いの手続きではなく、裁判官が当事者双方から提出された主張や証拠を基に、法的な判断を下す手続きです。
不動産の評価額が争点となっている場合、当事者双方で合意の上、不動産鑑定士を選任して鑑定を行うよう促されることが一般的です。裁判所が関与する形で鑑定が行われるため、その結果は当事者にとって重い意味を持ち、合意形成の大きな後押しとなります 。
審判手続きでも合意が成立しない場合、裁判官は強制力がある審判を下します。審判では、裁判官が最終的な不動産の評価額を決定し、それに基づいて「不動産は長男が取得し、長男は他の相続人に代償金として〇〇円を支払え」といった形で、遺産の分割方法を命じます。この審判の内容には法的な拘束力があり、当事者はそれに従わなければなりません。ここまで進むと、当事者の意向とは関係なく、裁判所の判断によって分割方法が決定されることになります。
次の解決事例は、審判手続きまで進んだものの、不動産鑑定士による鑑定を基に、合意が成立した事例です。
遺産分割調停・審判で不動産の査定・鑑定をして取得額が数百万円増えた事例
無料相談に至る経緯
父親を亡くされたご相談者様は、義理の母の弁護士から遺産分割調停を申し立てられました。
遺産分割調停で問題となったのが、父親名義の2つの家の取扱いで、ご相談者様は、自分が利用している家については、自分がお金を出してリフォームも済ませているので、単独取得したいというご意向をお持ちでした。
無料相談でのご提案

リンクスの弁護士は、無料相談で次のようなことをご提案しました。
- 不動産会社の査定を取って、2つの家の評価額をどうするかを協議する
- リフォームによって価値が増えている分については、ご相談者による寄与分であると主張し、法定相続分(2分の1)とは別に取得できるようにする
- 相手方が不動産会社の査定に納得しなければ、不動産鑑定士による鑑定を求める
ご相談者様は、リンクスの弁護士の説明に納得し、依頼されることになりました。
解決方法
リンクスの弁護士は、不動産会社の査定を取り、リフォーム部分の価値も説明しましたが、相手方弁護士はその評価額に納得しませんでした。
そこで、裁判所に選任された不動産鑑定士と共に現地に赴き、立地やリフォームの内容を見てもらいました。その結果、リフォーム部分に数百万円の価値を認めさせることに成功しました。
相続不動産の評価に関するよくある質問(FAQ)
相続不動産の評価に関して、多くの方が抱く疑問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。
Q1: 費用をかけずに自分で評価額を調べる方法はありますか?
はい、概算であれば費用をかけずに調べる方法があります。まず、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」で近隣の実際の取引価格を調べたり、国税庁のウェブサイトで相続税路線価を確認したりすることで、大まかな価格水準を把握できます。また、複数の不動産会社に依頼すれば、無料で査定書を取得することも可能です。ただし、これらはあくまで目安です。相続人間で争いがある場合や、法的に有効な評価額が必要な場合は、費用をかけて不動産鑑定士に鑑定を依頼する必要があります。
Q2: 土地と建物で評価方法が違うのはなぜですか?
土地と建物は、その性質が異なるため、評価方法も分けられています。土地は、利用状況によって価値が変動することはあっても、物理的になくなることはなく、その場所自体に価値があります。そのため、路線価や公示価格といった公的な指標を基に評価されます。一方、建物は建築された瞬間から経年劣化が始まり、時間とともに価値が減少していく「減価資産」です。そのため、同じ建物を今建てたらいくらかかるかという「再建築価格」から、築年数に応じた価値の減少分(経年減点補正)を差し引いて評価されます。この考え方が、固定資産税評価額に反映されています。
Q3: アパートが建っている土地や、人に貸している土地の評価額は安くなりますか?
はい、相続税の計算上は評価額が安くなります。アパートやマンションなど、賃貸用の建物が建っている土地は「貸家建付地(かしやたてつけち)」と呼ばれます。また、土地そのものを他人に貸している場合は「貸宅地(かしたくち)」と呼ばれます。これらの土地は、所有者が自分で自由に使用することができず、借主の権利によって利用が制限されるため、更地(自用地)に比べて財産的価値が低いと判断されます。そのため、相続税評価額を計算する際には、一定の割合で評価額が減額される仕組みになっています 。ただし、その計算は複雑なため、税理士などの専門家による正確な評価が必要です。
Q4: 弁護士、税理士、不動産鑑定士、誰に相談すればよいのでしょうか?
どの専門家に相談すべきかは、直面している課題によって異なります。
- 相続税の申告や計算、節税対策が目的であれば、税務の専門家である税理士に相談します 。
- 不動産の客観的で法的な価値証明が必要な場合(特に争いがある場合)は、評価の専門家である不動産鑑定士に依頼します 。
- 他の相続人との交渉や、遺産分割調停・審判といった法的手続きが必要な場合は、法律と交渉の専門家である弁護士に相談・依頼する必要があります 。
多くの場合、これらの専門家は連携して問題解決にあたります。相続人間でトラブルが発生している、あるいは発生しそうな場合は、まず弁護士に相談し、必要に応じて他の専門家と連携してもらうのがスムーズです。
Q5: 古い家で価値がないと思いますが、評価は必要ですか?
はい、必要です。建物自体が古く、市場での売買価値がほとんどゼロに近い(いわゆる「古家」)場合でも、相続財産として法的に評価し、遺産分割協議書や相続税申告書に記載しなければなりません。建物の評価額がゼロであっても、その建物が建っている土地には価値があるため、土地の評価は必ず必要になります。財産目録から意図的に除外すると、後で問題になる可能性があるため、価値がないと思われる不動産でも必ず評価の対象に含めてください。
Q6: 複数の土地を相続した場合、すべて同じ方法で評価しますか?
いいえ、必ずしも同じ方法ではありません。特に相続税評価額の計算においては、それぞれの土地が所在する場所によって評価方法が異なります。例えば、Aの土地は市街地にあるため「路線価方式」で評価し、Bの土地は郊外にあるため「倍率方式」で評価するというように、物件ごとに適切な方法を選択する必要があります。遺産分割のための実勢価格を調べる際も、それぞれの土地の特性(住宅地、商業地、農地など)に応じて、最も適した査定・鑑定方法を検討することが重要です。
まとめ:相続不動産の評価は目的の理解と専門家への相談が円満解決の鍵
相続不動産の評価は、多くの方にとって初めての経験であり、その複雑さに戸惑うのは当然のことです。本記事で解説してきたように、不動産には異なる評価基準が存在し、それぞれに目的と調べ方があります。この複雑な仕組みを乗り越え、円満な相続を実現するための最も重要なポイントは、以下の2点に集約されます。
- 評価の「目的」を明確にすること。
- 遺産分割のためであれば、相続人間の公平性を期すために「実勢価格(時価)」を基準とします。
- 相続税申告のためであれば、課税の基準となる「相続税評価額(路線価・倍率方式)」を用います。
この大原則を理解するだけで、どの評価額に注目すべきかが明確になり、手続きの混乱を大幅に減らすことができます。
- 必要に応じて、ためらわずに専門家の助けを借りること。 ご自身で公的な資料を調べて大まかな評価額を把握することは可能ですが、特に土地の評価には専門的な補正計算が伴い、誤った評価は相続人間のトラブルや税務上のリスクに直結します。
相続手続きは、法律、税務、不動産の知識が複雑に絡み合う専門領域です。公平で円滑な遺産分割を実現し、ご自身の正当な権利を守るためには、相続問題に精通した専門家のサポートが不可欠です。当事務所は、相続法務の専門家として、不動産評価に関するアドバイスから、遺産分割協議の代理交渉、調停・審判の対応まで、依頼者一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。どうぞお一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要

このように、不動産の査定や評価、不動産鑑定には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。
法律事務所リンクスは、複数の不動産会社と取引があり、数多くの査定を依頼してきました。
リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
ページトップに戻る