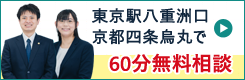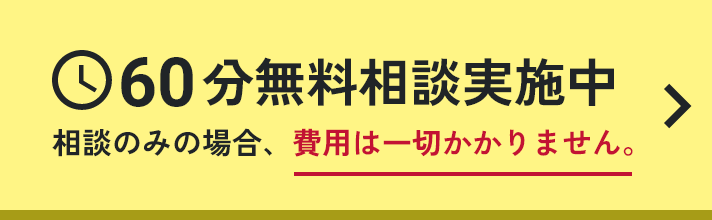遺言無効を主張したい方
遺言が有効か調査したい
必ず遺言に従わないといけない?
お亡くなりになられた被相続人が遺言書を残していた場合、原則として、その遺言書の内容に従って遺産相続することになりますが、どのような場合でも、遺言書に従わなければないわけではありません。
- まず、遺言書が無効である場合には、遺言書に従う必要はありません(遺言書が無効の場合)。
- また、遺言書が有効であっても、遺言書に書かれた遺産の分け方が、相続人の最低限の取り分である遺留分を侵害している場合には、遺留分を請求することができます(遺留分を請求できる場合)。
このページでは、どのような場合に遺言書が無効になるのかをご説明します。
遺留分の請求を検討されている方は「遺留分請求専門サイト」をご覧ください。
遺言書が無効な場合とは?
次のような場合には遺言書は無効です。
1 遺言書がパソコンで記載されている
民法968条1項は「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」としていますので、普通の遺言書は、すべて自筆でなければなりません。
2 遺言書の作成日付がない
民法968条1項は「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」としていますので、普通の遺言書は、日付の記載がない遺言書は無効です。
3 修正の仕方が間違っている
民法968条2項は「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない」としていますので、この方法で修正がなされていなければ無効です。
4 遺言書の内容が不明確で故人の意思が分からない
遺言書の内容はできる限り作成者の意思を読み取って解釈することになりますが、遺言書のある部分について2通りの解釈のどちらもありうるという場合には、遺言書の内容が特定できないので、その部分については無効になります。
5 遺言書を作成した時点で遺言書を作成する能力(遺言能力)がなかった
遺言書の効力が最も争われるパターンです。
遺言書を作成するには、遺言書の内容を理解して作成するだけの能力が必要ですし、遺言書の内容が複雑であればあるほど、その複雑な内容を理解して作成したかが問われることになります。
遺言書作成当時の遺言能力は、当時の診療録や日記、メモなどから判断することになります。
弁護士費用について
相続トラブル・遺産返還請求
| 取得額 | 着手金 | 成功報酬 |
| ~300万円に当たる部分 | 33万 | 22万 |
|
~3000万円に当たる部分 |
16.5% | |
| 3000万円を超える部分 | 11% |
※1 弁護士費用とは別に実費(各種資料取得費用、通信費等)がかかります。
※2 弁護士費用は消費税込です。
ページトップに戻る