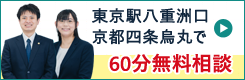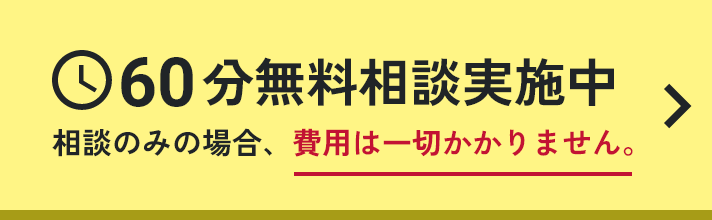遺言書の検認とは?申立書の必要書類と期限は?手続きの流れは?
自筆の遺言書で法務局で保管されていない場合には家庭裁判所の検認が必要
遺言書の検認とは、主に自筆で書かれた遺言書について、その内容や状態を家庭裁判所が確認し、偽造や変造を防ぐための手続きです 。この手続きは、相続人全員に対して遺言書の存在とその内容を公式に知らせる目的も担っています 。
ただし、ここで最も注意すべき点は、検認が遺言書の法的な有効性(有効か無効か)を判断するものではないということです 。裁判所はあくまで、検認日時点での遺言書の形状、日付、署名といった外形的な状態を確認・記録するにとどまります。したがって、検認手続きを経たからといって、その遺言書の内容が法的に確定するわけではありません。
このページでは、法律事務所リンクスの相続に強い弁護士が、遺言書の検認の申立てについてご説明します。
遺言書の検認申立てが必要な遺言書と不要な遺言書
遺言書にはいくつかの種類があり、検認が必要なものと不要なものに分かれます。
検認が必要な遺言書
- 自筆証書遺言: 遺言者が全文、日付、氏名を自筆で書き、押印して作成した遺言書です。自宅の金庫や貸金庫などで保管されている場合、相続手続きを進める前に必ず検認を受けなければなりません 。
- 秘密証書遺言: 遺言者が遺言内容を記して署名・押印した書面を封筒に入れ、同じ印鑑で封印し、公証人と証人の前で自己の遺言書であることを申述する方式の遺言書です。内容を秘密にできますが、検認は必要です 。
検認が不要な遺言書
 公正証書遺言: 公証役場で公証人と証人2名以上の立ち会いのもと作成される遺言書です。作成プロセスが厳格で、原本が公証役場に保管されるため、信頼性が高く検認は不要です 。
公正証書遺言: 公証役場で公証人と証人2名以上の立ち会いのもと作成される遺言書です。作成プロセスが厳格で、原本が公証役場に保管されるため、信頼性が高く検認は不要です 。- 法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言: 2020年7月10日から始まった制度で、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができます。この制度を利用した場合、遺言書の形式チェックがなされ、原本が公的に保管されるため、検認は不要となります 。
遺言書検認の申立ての流れは?期限はある?
遺言書を発見した相続人や保管者は、被相続人が亡くなったことを知った後、「遅滞なく」家庭裁判所に検認の申立てを行う必要があります 。手続きは大きく分けて5つのステップで進行します。詳しくは「裁判所の遺言書の検認のページ」をご覧ください。
ステップ1: 必要書類の収集
検認申立てにおいて最も時間と労力を要するのが、必要書類の収集です。特に、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本類や、相続人全員の戸籍謄本を集める作業は煩雑を極めます 。この作業は、法的に有効な相続人を一人残らず確定させるための重要な調査であり、数週間から数ヶ月かかることも珍しくありません。
ステップ2: 家庭裁判所への申立て
 必要書類が揃ったら、家庭裁判所に検認の申立てを行います。
必要書類が揃ったら、家庭裁判所に検認の申立てを行います。
- 申立人: 遺言書を保管している人、または発見した相続人です 。
- 申立先: 遺言者(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です 。最後の住所地は、住民票の除票や戸籍の附票で確認できます。管轄の裁判所は裁判所のウェブサイトで調べることができます。
- 費用: 申立てには、遺言書1通につき800円の収入印紙と、裁判所から各相続人へ通知を送るための郵便切手が必要です。郵便切手の金額は裁判所によって異なるため、事前に確認が必要です 。
- 期限:法律では「遅滞なく」申立てを行うよう定められていますが、戸籍収集には時間がかかるため、申立人は法的な義務と事務的な遅延との間で大きなストレスを抱えることになります。
ステップ3: 検認期日通知書の受領
申立書類に不備がなければ、申立てから1週間〜1ヶ月程度で、家庭裁判所から申立人および相続人全員宛に「検認期日通知書」が郵送されます 。この通知書には、検認が行われる日時と場所が記載されています。
ステップ4: 検認期日当日
指定された日時に家庭裁判所へ出頭します。申立人は必ず出席しなければなりませんが、他の相続人の出席は任意です 。しかし、遺言書の原本を直接確認できる貴重な機会であるため、可能な限り出席することが望ましいでしょう。
当日の持ち物リスト
申立人が持参すべきものは以下の通りです。事前に準備しておきましょう。
- 遺言書の原本(封印されている場合は絶対に開封しないこと)
- 裁判所から送られてきた「検認期日通知書」
- 申立人の印鑑(申立書に押印したもの)
- 申立人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 検認済証明書の発行に必要な収入印紙(遺言書1通につき150円)
当日の手続きの流れ
手続きは審判廷(または審判室)で、裁判官、申立人、出席した相続人が同席のもとで行われます。
- 裁判官が手続きの開始を宣言し、申立人から遺言書を提出させます 。
- 封印のある遺言書の場合、裁判官が相続人の目の前で開封します 。
- 裁判官が遺言書の形状、日付、署名、訂正箇所の状態などを確認し、その内容を読み上げます。
- 出席した相続人は、遺言書の原本を閲覧する機会が与えられます。
- 裁判官が確認した内容を「検認調書」という公的な記録として作成します。
手続き全体の所要時間は、通常5分から15分程度で終了することが多いです 。
検認期日における重要な注意点
- 議論の場ではない: 検認期日は、あくまで遺言書の現状を確認する手続きです。遺言の有効性や内容の是非について、その場で異議を申し立てたり、相続人間で議論したりすることはできません 。
- 弁護士の同席: 弁護士に依頼している場合、代理人として検認期日に同席することができます 。司法書士や行政書士は法律上同席できないため、これは弁護士ならではの大きなメリットです 。法的な観点から手続きを見守り、不測の事態にも対応できるため、大きな安心感が得られます。
ステップ5: 検認済証明書の取得と遺言執行
検認期日が終了したら、申立人は「検認済証明書」の交付を申請します。これには遺言書1通につき150円の収入印紙が必要です 。この証明書が添付された遺言書の原本が、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約といった、その後の具体的な相続手続きに必須の書類となります 。
遺言書検認の必要書類一覧【相続人の状況別】
遺言書検認の申立てに必要な戸籍謄本類は、誰が法定相続人になるかによって大きく異なります 。これは、法的に相続権を持つ可能性のある人物をすべて洗い出し、遺産分割協議から誰も漏れることがないようにするための厳格な手続きです。
この戸籍収集の過程は、単なる事務作業ではなく、法的な「相続人調査」そのものです。この調査を通じて、これまで知られていなかった相続人(例えば、前妻との間の子など)が判明することもあり、その場合、遺産の分配計画が根本から覆る可能性もあります。
全てのケースで共通して必要な書類
- 遺言書の検認申立書: 裁判所のウェブサイトから書式をダウンロードできます 。
- 遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本): これにより、遺言者の婚姻歴や子の有無などをすべて確認します 。
- 相続人全員の現在の戸籍謄本: 相続人が生存していることを証明するために必要です 。
相続人の構成別で必要となる追加の戸籍謄本
相続人の構成に応じて、上記に加えて以下の戸籍謄本類が必要になります。詳細は裁判所のウェブサイトでも確認できますが、ここでは代表的なケースをまとめます。
| 相続人の構成 | 必要な追加戸籍謄本 |
| 配偶者と子(第一順位) | ・死亡した子(またはその代襲者である孫など)がいる場合、その人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本類 |
| 配偶者と直系尊属(父母・祖父母)(第二順位) | ・死亡した子(またはその代襲者)がいる場合、その人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本類 ・死亡した直系尊属(父母など)がいる場合、その死亡の記載がある戸籍謄本類 |
| 配偶者と兄弟姉妹(甥・姪)(第三順位) | ・死亡した子(またはその代襲者)がいる場合、その人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本類 ・遺言者の父母の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本類 ・死亡した兄弟姉妹がいる場合、その人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本類 ・代襲者である甥・姪が死亡している場合、その死亡の記載がある戸籍謄本類 |
戸籍謄本類に関する補足
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書): 現在の戸籍の内容を証明するもの。手数料は1通450円程度 。
- 除籍謄本(除籍全部事項証明書): 婚姻や死亡などにより、戸籍に記載されていた全員が除かれたことを証明するもの。手数料は1通750円程度 。
- 改製原戸籍謄本: 法改正前の古い様式の戸籍謄本。相続人調査では、古い時代の家族関係を遡るために必須となることが多い。手数料は1通750円程度 。
これらの書類は、対象者の本籍地がある市区町村役場で取得します 。本籍地が遠方であったり、複数にまたがっていたりすると、収集には多大な手間がかかります。
遺言書の検認を弁護士に依頼することを検討した方がよい場合とメリット
遺言書検認の手続きは、自分で行うことも可能ですが、その手続きの煩雑さや潜在的なトラブルのリスクを考えると、弁護士に依頼する方がよい場合もあります。
弁護士に依頼することを検討した方がよい場合
遺言書をどのように執行したらよいか分からない場合
遺言書の作成者に相続人がいなかったり、相続人がいたとしても自分で執行することが難しい場合、内容が複雑で執行方法が分からない場合などには、弁護士への依頼をお勧めします。
弁護士に依頼すれば、遺言書の検認の申立てから遺言執行者に就任して遺言執行までしてもらうことができるからです。
遺言能力が疑われている場合(認知症など)
遺言書が作成された当時、遺言者が認知症などで遺言の内容を正しく理解し判断する能力(遺言能力)がなかった場合、遺言は無効となります。もっとも、認知症であれば必ず無効になるというわけではなく、その程度によって有効となる場合も多いです。
遺言能力の有無を証明するためには、当時の医療記録(カルテ)や介護認定の資料、看護記録などが重要な証拠となりますが、専門的な分析が必要です。他の相続人から遺言能力が疑われている場合には、弁護士に検認の申立てから他の相続人への対応まで依頼することを検討した方がよいでしょう。
遺留分を請求される可能性が高い場合
遺言書が他の相続人の遺留分を侵害していて遺留分を請求される可能性が高い場合、遺留分侵害額請求への対応に備えて、弁護士に検認の申立てから依頼することを検討した方がよいかもしれません。
弁護士に依頼する具体的なメリット
- 時間と手間の大幅な削減: 最も負担の大きい戸籍謄本類の収集から、申立書の作成、裁判所への提出、期日の調整まで、すべての手続きを代行してもらえます 。平日の日中に役所や裁判所へ行く時間がない方にとって、これは大きな利点です。
- 検認期日への同席: 司法書士や行政書士は書類作成の代行はできますが、代理人として検認期日の法廷に同席することは法律上認められていません。弁護士だけが、申立人と一緒に法廷に入り、法的な観点からサポートすることができます 。万が一、他の相続人から予期せぬ質問や主張がなされた場合でも、その場で適切に対応してもらえる安心感は計り知れません。
- 相続トラブルへのシームレスな対応: 検認は相続のスタートラインです。もし検認をきっかけに遺言の有効性や遺産分割をめぐる争いが発生した場合、司法書士では対応できず、改めて弁護士を探す必要があります。最初から弁護士に依頼していれば、そのまま代理人として交渉や調停、訴訟手続きに移行でき、スムーズな問題解決が期待できます。
- 精神的な負担の軽減: 他の相続人との関係が良好でない場合、手続きに関する連絡や質問が直接来るのは大きなストレスです。「弁護士に依頼しているので、詳細は弁護士に聞いてください」と対応することで、感情的な対立を避け、冷静に手続きを進めることができます 。
遺言書の検認に関するよくあるご質問(FAQ)
Q1: 検認前に封印のある遺言書を開封してしまったらどうなりますか?
A1: 遺言書そのものが無効になるわけではありませんが、過料として5万円以下の支払いを命じられる可能性があります 。家庭裁判所以外の場所で封印のある遺言書を開封することは法律で禁じられていますので、絶対に開封せず、そのままの状態で家庭裁判所に提出してください。
Q2: 検認手続きに期限はありますか?
A2: 法律上は「遅滞なく」と定められているだけで、「死後〇ヶ月以内」といった明確な期限はありません 。しかし、検認が終わらないと不動産の名義変更や預貯金の解約といった相続手続きを進めることができないため、遺言書を発見したら速やかに手続きに着手することが望ましいです。
Q3: 相続人の一人が海外に住んでいる場合、手続きはどうなりますか?
A3: 手続き自体は国内の家庭裁判所で行われます。海外在住の相続人にも、裁判所から国際郵便で検認期日の通知書が送付されます。そのため、通常よりも手続きに時間がかかる可能性があります。海外在住の相続人も期日への出席義務はありませんが、その後の遺産分割協議には参加してもらう必要があります。弁護士に依頼すれば、海外在住の相続人との連絡調整も代行してもらえます。
Q4: 遺言書が複数見つかった場合はどうすればよいですか?
A4: 検認が必要な形式の遺言書であれば、見つかったものすべてについて検認の申立てを行う必要があります。内容が互いに矛盾する遺言書がある場合、原則として日付が最も新しい遺言書の内容が優先されます 。ただし、解釈が複雑になるケースも多いため、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
Q5: 検認が終われば、すぐに遺産を分けられますか?
A5: 必ずしもそうとは限りません。検認は、あくまで遺言書を使って銀行や法務局での手続きを開始するための「許可証」のようなものです。検認後、遺言の内容に従って手続きを進めることになりますが、もし相続人の間で遺言の有効性や遺留分について争いが生じた場合は、まずその問題を解決しなければなりません。つまり、検認は相続手続きのゴールではなく、本格的なスタート地点なのです。
遺言書の検認申立てでお困りの方へ

このように、遺言書の検認には難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士による無料相談を受けられることをお勧めしております。
遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。
司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。
弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。
法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が遺言書に関する無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
ページトップに戻る