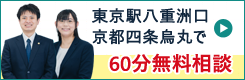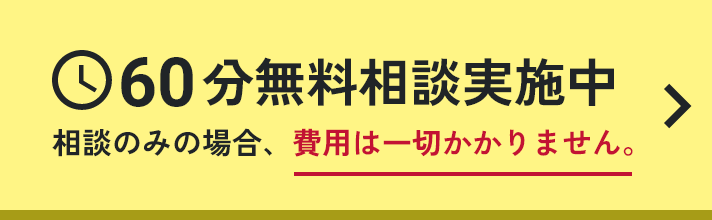遺言書の検認が終わったら?検認後異議申立てできる?
遺言書の検認後でも遺言無効や遺留分侵害額請求は可能
遺言書の検認が終わったら、遺言書の内容に従い、不動産の名義変更や預貯金の解約といった具体的な相続手続きが始まります。これらの手続きには、家庭裁判所が発行する「検認済証明書」が不可欠です。
また、遺言書の検認が終わった後でも、遺言書の内容に異議を申し立てることは可能です。検認は遺言書の有効性を判断する手続きではないため、「遺言無効確認訴訟」や「遺留分侵害額請求」といった法的手段を通じて、遺言書の内容を争うことができます。
このページでは、法律事務所リンクスの相続に強い弁護士が、遺言書の検認が終わった後の流れや異議申し立ての方法についてご説明します。
遺言書の検認が終わった後の手続きの全貌|7つの必須ステップで解説
遺言書の検認は、相続手続きのゴールではなく、あくまでスタートラインです。検認が無事に終わると、いよいよ遺言書の内容を実現するための具体的な手続きが始まります。ここでは、その全体像を7つのステップに分けて詳しく解説します。遺言書の内容に疑問を持つ方にとっても、相手方が今後どのような手続きを進めていくのかを理解することは、ご自身の対抗策を考える上で極めて重要になります。
ステップ1:家庭裁判所で「検認済証明書」を申請・取得する
 検認手続きが完了したら、まず家庭裁判所に対して「検認済証明書」の交付を申請します。これは、その遺言書が家庭裁判所による検認を経たことを公的に証明する書類です。
検認手続きが完了したら、まず家庭裁判所に対して「検認済証明書」の交付を申請します。これは、その遺言書が家庭裁判所による検認を経たことを公的に証明する書類です。
この証明書がなければ、法務局での不動産の名義変更(相続登記)や、金融機関での預貯金の解約・払い戻しといった、ほとんどの相続手続きを進めることができません。
申請には、遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要です 5。申請が受理されると、検認済証明書が遺言書の原本に合綴(ホチキス止めなどで一体化)された形で返還されます。
ステップ2:遺言書の内容を正確に確認する
検認済証明書付きの遺言書が手元に戻ったら、改めてその内容を隅々まで正確に確認します。誰がどの財産を相続するのか、記載されている財産は全てか、といった点を明確に把握することが目的です。
特に注意すべきは、遺言書に記載されていない財産(遺産)の存在です。例えば、「自宅不動産は長男に、A銀行の預金は長女に」と書かれていても、B銀行の預金や株式、自動車などが遺言書に記載されていないケースは少なくありません。このような記載漏れの財産については、遺言の効力が及ばないため、相続人全員による「遺産分割協議」で分け方を決める必要があります。この協議がまとまらないと、後々のトラブルの原因となります。
ステップ3:遺言執行者の有無を確認し、就任手続きを進める
次に、遺言書で「遺言執行者」が指定されているかを確認します。遺言執行者とは、遺言の内容をスムーズに実現するために、相続人に代わって財産管理や各種手続きを行う権限を与えられた人のことです。
遺言執行者がいる場合の手続き
遺言執行者が指定されていれば、その人が中心となって相続手続きを進めます。遺言執行者は、就任後すぐに相続財産の調査に着手し、財産目録を作成して相続人に提示する義務があります。不動産登記や預貯金の解約なども、基本的には遺言執行者が単独で行うことができるため、手続きは比較的スムーズに進みます。
遺言執行者がいない場合の手続きと注意点
遺言書に遺言執行者の指定がない場合、相続人全員が協力して手続きを進めることになります。しかし、これは実務上、多くの困難を伴います。例えば、金融機関での預貯金解約手続きでは、相続人全員の署名・捺印(実印)と印鑑証明書の提出を求められることがほとんどです。相続人のうち一人でも非協力的な人がいると、手続きが完全にストップしてしまいます。
このような事態を避けるため、相続人の間で協力が得られない場合や、手続きが複雑で手に負えない場合は、利害関係人(相続人など)が家庭裁判所に申し立てて、遺言執行者を選任してもらうことができます。
ステップ4:相続財産調査と財産目録の作成
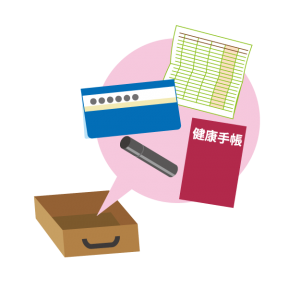 遺言執行者(または相続人)は、被相続人(亡くなった方)の財産を正確に把握するため、徹底した財産調査を行います。これには、預貯金、不動産、株式などのプラスの財産だけでなく、借金やローンといったマイナスの財産も含まれます。
遺言執行者(または相続人)は、被相続人(亡くなった方)の財産を正確に把握するため、徹底した財産調査を行います。これには、預貯金、不動産、株式などのプラスの財産だけでなく、借金やローンといったマイナスの財産も含まれます。
調査が完了したら、その結果を一覧にまとめた「財産目録」を作成します。この財産目録は、相続人全員が遺産の全体像を共有し、後の手続きを透明性をもって進めるための重要な書類です。
ステップ5:不動産の名義変更(相続登記)
遺言書によって不動産を相続した人は、法務局で所有権移転登記(相続登記)を行い、不動産の名義を自分に変更します。この手続きには、検認済証明書付きの遺言書、被相続人の戸籍謄本、相続人の住民票、固定資産評価証明書など、多くの書類が必要となります。
ステップ6:預貯金の解約・名義変更
金融機関での手続きも重要なステップです。遺言書に基づき預貯金を相続する人は、銀行や信用金庫などの窓口で、預金の解約・払い戻し、または名義変更の手続きを行います。ここでも、検認済証明書付きの遺言書が必須となります。金融機関ごとに独自の書式や必要書類があるため、事前に問い合わせて確認することが賢明です。
ステップ7:相続税の申告・納付(期限は10ヶ月)
 相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告と納付が必要です。この手続きの期限は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」と非常に厳格に定められています。期限を過ぎると延滞税などのペナルティが課されるため、注意が必要です。
相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告と納付が必要です。この手続きの期限は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」と非常に厳格に定められています。期限を過ぎると延滞税などのペナルティが課されるため、注意が必要です。
これらの手続きは、一見すると単なる事務作業の連続に見えるかもしれません。しかし、遺言書に異議を唱えようと考えている方にとっては、これら一つ一つのステップが「相手方が遺言の有効性を前提に権利を確定させていく過程」そのものです。相手方が財産目録を作成し、登記を移転していく中で、時間が経過すればするほど、後からそれを覆すのは困難になります。つまり、この期間は、相手方にとっては手続きを進める期間であると同時に、あなたにとっては情報収集と戦略立案のための貴重な時間なのです。行動をためらっている間に、既成事実が積み重ねられてしまうリスクを常に意識する必要があります。
検認後でも遅くない!遺言書に異議を申し立てる2つの法的手段
「検認が終わってしまったら、もう遺言書の内容を受け入れるしかないのか」と諦めてしまう必要は全くありません。検認後であっても、遺言書の内容に納得がいかない場合に、その効力を争うための法的な手段が明確に用意されています。
大前提:検認手続きは、遺言書の有効・無効を判断する場ではない
まず、最も重要な大前提を理解する必要があります。家庭裁判所が行う「検認」という手続きは、あくまでその時点での遺言書の形状や状態を確認し、後日の偽造や変造を防ぐために証拠を保全する目的で行われるものです。
裁判官は遺言書の内容を読み上げますが、その内容が法的に有効か、あるいは無効かを判断することはありません。したがって、「検認済」という証明は、遺言書が法的に有効であることのお墨付きでは全くないのです。この点を正しく理解することが、異議申立てへの第一歩となります。
方法1:遺言そのものの無効を主張する「遺言無効確認請求」
一つ目の方法は、遺言書そのものが法的な効力を持たないと主張し、遺言を「無かったこと」にするための手続きです。これが認められれば、遺言書は完全に無効となり、相続人全員で遺産分割協議を行って財産の分け方を決めることになります。
どのような場合に遺言は無効になるのか?(5つの具体例)
遺言が無効とされるケースには、主に以下のようなものがあります。
- 形式上の不備:自筆証書遺言で、全文が自筆でない、日付や署名、押印がないなど、法律で定められた形式を守っていない場合
- 遺言能力の欠如:遺言者が遺言を作成した当時、認知症や重度の精神疾患などにより、遺言の内容やその結果を理解する能力(遺言能力)がなかった場合
- 偽造・変造:遺言書が、相続人の誰かや第三者によって偽造・変造されたものである場合
- 共同遺言:夫婦など、2人以上の人が1通の書面で共同して作成した遺言は、法律で禁止されており無効です
- より新しい遺言書の存在:日付の異なる複数の遺言書が見つかった場合、最も新しい日付の遺言が有効となり、それ以前のものは撤回されたものとみなされます
遺言無効を主張するための手続きの流れ(交渉→調停→訴訟)
遺言の無効を主張する場合、一般的に以下のステップで進められます。
- 交渉:まずは、遺言によって利益を受ける他の相続人などに対し、遺言が無効である旨を伝え、話し合いによる解決(遺産分割協議の実施など)を目指します。
- 遺言無効確認調停:話し合いで合意に至らない場合、家庭裁判所に「遺言無効確認調停」を申し立てます。調停は、調停委員という中立的な第三者を交えて話し合いを進める手続きです。訴訟を起こす前に、まず調停を経ることが原則とされています(調停前置主義)が、話し合いの可能性がない場合には、最初から訴訟を起こすことが認められることもあります。
- 遺言無効確認訴訟:調停でも解決しない場合、最終手段として地方裁判所に「遺言無効確認訴訟」を提起します。これは本格的な裁判であり、裁判官が証拠に基づいて遺言の有効・無効について法的な判断を下します。
【最重要】無効を立証するための証拠集め
遺言無効確認訴訟において最も重要なのは「証拠」です。無効を主張する側が、その理由を客観的な証拠によって証明する責任(立証責任)を負います。
- 遺言能力の欠如を主張する場合:遺言作成当時の被相続人の医療記録(カルテ)や診断書、介護認定の記録、介護施設の連絡帳、長谷川式簡易知能評価スケールなどの認知機能テストの結果などが決定的な証拠となり得ます。
- 偽造を主張する場合:被相続人が生前に書いた他の書面(手紙、日記、契約書など)と遺言書の筆跡を比較する「筆跡鑑定」が不可欠です。
これらの証拠を個人で集めるのは非常に困難であり、専門的な知識と手続きが必要となります。
方法2:最低限の相続分を確保する「遺留分侵害額請求」
二つ目の方法は、遺言書の有効性自体は争わず、「遺言の内容は認めるが、それによって法律で保障された私の最低限の取り分が侵害されたので、その分を金銭で支払ってほしい」と請求するものです。
遺留分とは?誰に、どれくらいの権利があるのか
「遺留分」とは、被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、子、直系尊属)に対して、法律上、最低限保障されている遺産の取り分のことです。遺言によって、特定の相続人や第三者に全財産が渡され、他の相続人が全く財産を受け取れないといった事態を防ぐための制度です。
遺留分の割合は、相続人の構成によって以下のように定められています。
| 相続人の組み合わせ | 全体に対する遺留分 | 各相続人の遺留分割合 |
| 配偶者と子 | 遺産全体の 1/2 | 配偶者: 1/4, 子: 1/4 (子が複数なら按分) |
| 配偶者のみ | 遺産全体の 1/2 | 配偶者: 1/2 |
| 子のみ | 遺産全体の 1/2 | 子: 1/2 (子が複数なら按分) |
| 配偶者と直系尊属(父母など) | 遺産全体の 1/2 | 配偶者: 1/3, 直系尊属:1/6 |
| 直系尊属のみ | 遺産全体の 1/3 | 直系尊属: 1/3 |
| 兄弟姉妹 | なし | 兄弟姉妹には遺留分はありません |
【要注意】遺留分侵害額請求の厳格な期限(知った時から1年)
遺留分侵害額請求で最も注意すべきは、非常に短い時効期間です。この権利は「相続の開始と、遺留分を侵害する遺贈や贈与があったことを知った時から1年以内」に行使しなければ、時効によって消滅してしまいます。また、たとえ知らなかったとしても、相続開始から10年が経過すると権利は完全に失われます。
遺留分を請求するための手続きの流れ(内容証明郵便→交渉→調停→訴訟)
遺留分の請求手続きは、遺言無効主張とは異なる流れで進みます。
- 意思表示(内容証明郵便):まず、時効を中断させるために、遺留分を侵害している相手方(多くの財産を受け取った相続人など)に対し、「遺留分侵害額を請求します」という意思表示を明確に行う必要があります。口頭でも有効ですが、後々の証拠として残すため、「配達証明付き内容証明郵便」で通知を送付するのが最も確実で一般的な方法です。
- 交渉:意思表示の後、相手方と具体的な支払額や支払方法について話し合いを行います。
- 遺留分侵害額請求調停:交渉がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を介して話し合いを進めます。訴訟を起こす前に、まず調停を経ることが原則とされています(調停前置主義)が、交渉が十分なされた場合には、話し合いの余地がないとして、最初から訴訟を起こすことが認められることもあります。
- 遺留分侵害額請求訴訟:調停でも解決しない場合は、地方裁判所に訴訟を提起し、裁判官の判断を仰ぐことになります。
遺言の無効主張と遺留分請求、この2つの選択肢は、それぞれに異なる時間軸と戦略を要求します。
遺言無効の主張には明確な時効はありませんが、証拠集めには時間がかかります。一方で、遺留分請求の権利は、知ってからわずか1年で消滅します。もし、遺言無効の証拠集めに1年以上を費やし、結果的に無効が認められなかった場合、その時点ではもう遺留分を請求する権利すら失っている、という最悪の事態に陥りかねません。
このようなリスクを回避するための専門的な戦略は、まず1年という時効期間内に内容証明郵便を送付して遺留分侵害額請求権を行使した上で、じっくりと遺言無効を立証するための証拠集めを進めるという二段構えのアプローチです。この戦略的な判断と実行は、法律の専門家でなければ極めて困難と言えるでしょう。
法律事務所リンクスは遺留分侵害額請求の相談が60分無料!
 法律事務所リンクスでは、遺留分に強い弁護士による60分無料相談を実施しています。
法律事務所リンクスでは、遺留分に強い弁護士による60分無料相談を実施しています。
相談に当たっては、ご予約いただいた際にご事情を伺い、調査をした上で相談に臨みますので、無料相談の時間内で充実した情報を提供しております。
相談者様が聞き足りなかったということが起きないようにしておりますし、ホワイトボードを使うなどして分かりやすく説明していますので、お気軽にお問い合わせください。
相談者様が聞き足りなかったということが起きないようにしておりますし、ホワイトボードを使うなどして分かりやすく説明していますので、東京で相続に強い弁護士に相談されたい方は「東京で相続を弁護士に無料相談なら法律事務所リンクス」のサイトを、京都で相続に強い弁護士に相談されたい方は「京都で相続を弁護士に無料相談なら法律事務所リンクス」のサイトからお気軽にお問い合わせください。
遺留分請求の注意点について動画でご覧になりたい方はコチラ
こんな時はすぐ弁護士に相談を|手遅れになる前のチェックリスト
遺言書の検認通知を受け取り、内容に疑問や不満を感じたとき、一人で悩んでいても事態は好転しません。相続問題、特に遺言に関するトラブルは、時間が経てば経つほど不利になるケースがほとんどです。以下のような状況に一つでも当てはまる場合は、手遅れになる前に、すぐに弁護士へ相談することを強くお勧めします。
遺言書の内容に少しでも疑問を感じたら(具体的なお悩み別)
- 「故人の筆跡と違う気がする、使われている印鑑が見慣れないものだ」
- 「遺言書が作成された当時、故人は認知症を患っていた、または判断能力が著しく低下していたはずだ」
- 「特定の相続人や、全く知らない第三者に全財産が渡されており、あまりに不公平で納得できない」
- 「遺言書に書かれていない財産(預貯金、不動産、有価証券など)が他にもあるはずだ」
- 「遺言執行者や他の相続人が高圧的で、財産の内容を教えてくれないなど、話し合いが全くできない」
- 「自分の遺留分が侵害されていると思うが、相続が始まってからもうすぐ1年が経ちそうで焦っている」
弁護士に依頼する3つの大きなメリット
なぜ、早期に弁護士に相談すべきなのでしょうか。それには、金銭的な利益だけでなく、精神的な負担を軽減するという大きな理由があります。
メリット①:最適な法的手段(無効主張か遺留分請求か)を戦略的に判断してもらえる
遺言を争うには「遺言無効」と「遺留分請求」という二つの道がありますが、どちらを選択すべきかは、証拠の有無や時効、相続関係の複雑さなどを総合的に考慮した高度な専門的判断が必要です。弁護士は、あなたの状況を客観的に分析し、勝訴の可能性やリスクを勘案した上で、最も有利な解決策を提案します。前述した「1年の罠」に陥るリスクを回避できるのは、弁護士に依頼する最大のメリットの一つです。
メリット②:複雑な法的手続きと証拠収集をすべて代行してもらえる
遺言無効や遺留分請求の手続きには、家庭裁判所や地方裁判所への申立書の作成、膨大な戸籍謄本の収集、相手方との交渉、法廷での主張・立証など、専門知識がなければ対応できない作業が山積しています。特に、遺言能力を争う際の医療記録の取り寄せや、偽造を疑う場合の筆跡鑑定の手配など、証拠収集は極めて困難です。弁護士は、これらの煩雑で専門的な手続きをすべてあなたに代わって行います。
メリット③:他の相続人との交渉窓口となり、精神的負担を劇的に軽減できる
相続問題は、親族間の感情的な対立を伴うことが多く、当事者同士で話し合うことは精神的に大きなストレスとなります。弁護士が代理人として交渉の窓口に立つことで、あなたは相手方と直接顔を合わせる必要がなくなります。法的な根拠に基づき、冷静かつ論理的に交渉を進めることで、感情的な対立を避け、円満かつ迅速な解決を目指すことができます。
相続問題にかかる弁護士費用の相場と仕組み
弁護士への相談をためらう最大の理由の一つが「費用」への不安でしょう。しかし、多くの法律事務所では、明確な料金体系を用意しており、初回相談は無料の場合も少なくありません。費用の内訳と相場を理解しておくことで、安心して相談に臨むことができます。
- 相談料:弁護士に法律相談をする際の費用です。相場は30分5000円~1万円程度ですが、「初回相談無料」の事務所も多いです。
- 着手金:正式に依頼する際に支払う費用です。結果にかかわらず返金されないのが一般的で、相場は20万円~50万円程度です。事案の複雑さによって変動します。
- 報酬金:問題が解決した際に支払う成功報酬です。獲得できた経済的利益(遺産の額など)に応じて計算されることが多く、旧日本弁護士連合会の報酬基準を参考にしている事務所が現在でも多く見られます。
- 実費:収入印紙代、郵便切手代、戸籍謄本などの取得費用、交通費など、手続きに実際にかかった費用です。
- 日当:弁護士が裁判所への出廷などで遠方に出張した場合に発生する費用です。半日で3万円、1日で5万円程度が相場です。
費用は事務所によって異なりますので、必ず依頼前に見積もりを確認しましょう。
遺言書の検認後の手続きでお困りの方へ

このように、遺言書の検認には難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士による無料相談を受けられることをお勧めしております。
遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。
司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。
弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。
法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が遺言書に関する無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
ページトップに戻る