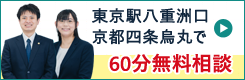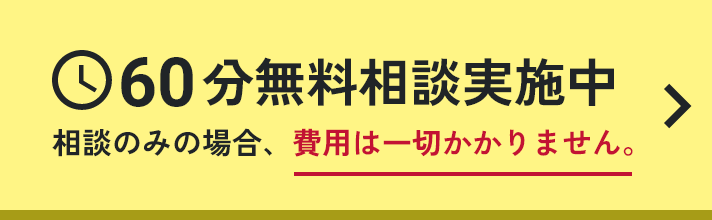遺言書の検認は欠席できる?検認期日通知書が届いたらどうすればよい?
遺言書の検認期日にはできる限り出席すべきだが欠席しても後から対応可能
遺言書の検認期日への出席は、申立人でなければ義務ではなく、欠席しても法的な罰則はありません。欠席者には後日、検認が完了した旨の通知が届きます。
検認が終わった後でも、遺言書の内容に異議を申し立てることは可能です。検認は遺言書の有効性を判断する手続きではないため、「遺言無効確認訴訟」や「遺留分侵害額請求」といった法的手段を通じて、遺言書の内容を争うことができます。
このページでは、法律事務所リンクスの相続に強い弁護士が、遺言書の検認を申し立てられた側が、検認期日に出席すべきか、欠席した場合の対処法、弁護士に相談した方がよい場合について、解説します。
遺言書検認期日の通知が届いた方はできる限り出席を
 ある日突然、家庭裁判所から「遺言書検認期日通知書」が届き、驚いている方もいるでしょう。これは、あなたが相続人の一人として法的に認められたことを意味します。ここでは、通知を受け取った方がどう対応すべきかを解説します。
ある日突然、家庭裁判所から「遺言書検認期日通知書」が届き、驚いている方もいるでしょう。これは、あなたが相続人の一人として法的に認められたことを意味します。ここでは、通知を受け取った方がどう対応すべきかを解説します。
結論:申立人でなければ欠席しても法的な問題はない
遺言書の検認を申し立てた「申立人」本人でなければ、検認期日に欠席しても法律上の問題は一切ありません。罰金や過料などのペナルティが科されることはなく、相続権を失うといった不利益もありません 。
多忙な場合や遠方に住んでいる場合など、やむを得ない事情で出席できないことは当然あり得ます。その際、事前に家庭裁判所に欠席の連絡を入れる必要もありません。
検認期日を欠席する2つの戦略的デメリット
法的な不利益はないものの、検認期日を欠席することには、戦略的な観点から見過ごせないデメリットが存在します。これらは罰則ではなく、「機会の損失」と考えるべきです。
デメリット①:遺言書の内容をその場で確認できない
 検認期日では、裁判官の立ち会いのもと、遺言書が開封され、その内容が出席した相続人たちに示されます。期日に出席すれば、誰よりも早く、そして正確に遺言書の内容を直接確認することができます。
検認期日では、裁判官の立ち会いのもと、遺言書が開封され、その内容が出席した相続人たちに示されます。期日に出席すれば、誰よりも早く、そして正確に遺言書の内容を直接確認することができます。
検認期日は、遺言書の「原本」を自身の目で直接確認できる最初の、そして非常に重要な機会です。写真やコピーではわからない筆跡の勢いやインクのにじみ、紙の質感などを確認することで、遺言書が作成された当時の状況を推し量る手がかりが得られるかもしれません。
一方、欠席した場合、遺言書の内容を知るタイミングは他の相続人よりも遅れます。後日、家庭裁判所から検認が済んだ旨の通知は届きますが、遺言書のコピーが同封されているわけではありません。内容を知るためには、申立人や他の出席した相続人に問い合わせる必要があり、情報が間接的になったり、正確性に欠けたりする可能性があります。
デメリット②:他の相続人の反応や裁判官からの質問事項が直接わからない
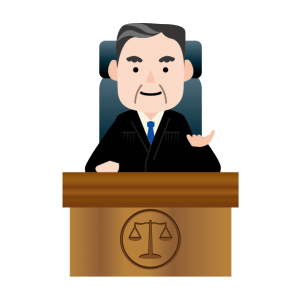 検認期日に出席するもう一つの重要な価値は、法廷の「空気」を肌で感じられる点にあります。遺言書が開封された瞬間の、他の相続人たちの表情や反応は、今後の紛争の可能性を探る上で貴重な情報となり得ます。
検認期日に出席するもう一つの重要な価値は、法廷の「空気」を肌で感じられる点にあります。遺言書が開封された瞬間の、他の相続人たちの表情や反応は、今後の紛争の可能性を探る上で貴重な情報となり得ます。
また、裁判官が遺言書の形状、封筒の状態、筆跡、印影などについて、申立人や出席者に質問をすることがあります。例えば、「この筆跡は故人のものに間違いありませんか?」といった質問に対する他の相続人の応答や態度を直接見聞きすることは、遺言書の信憑性を判断する上での一つの材料になります。欠席すると、こうした生の情報を得ることができません。
期日当日は何が行われるのか?
当日は、裁判官が遺言書の状態を確認し、その内容を読み上げ、検認調書に記録します。出席した相続人は、この手続きに立ち会うことになります。この場で遺言内容の有効性について議論したり、異議を申し立てたりすることはできません。あくまで、遺言書の現状を確認する手続きです 。
遺言書の内容に納得できない場合はどうするか?
検認の場で初めて見た遺言書の内容が、生前の被相続人の意向と大きく異なっていたり、特定の人に著しく有利で不公平だと感じたり、あるいは筆跡が本人のものと違うように見えたりした場合、遺言書の検認期日の終了後に、遺言書の無効を訴えたり、遺留分侵害額請求などの法的な対応を取ることが可能です。詳しくは後でご説明します。
遺言書の検認期日を欠席した場合の対処法
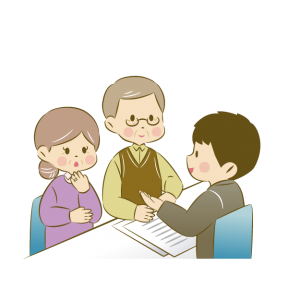 検認期日に欠席した相続人には、後日、家庭裁判所から「検認済通知書」が郵送されます。これは、指定された日時に検認手続きが完了したことを知らせるためのものです。
検認期日に欠席した相続人には、後日、家庭裁判所から「検認済通知書」が郵送されます。これは、指定された日時に検認手続きが完了したことを知らせるためのものです。
万が一、この通知書がいつまで経っても届かない場合は、郵便事故の可能性も考えられます。その際は、家庭裁判所に直接問い合わせ、発送状況を確認しましょう。必要であれば、検認手続きの結果が記録された「検認調書」の謄本(コピー)を取り寄せることで、遺言書の内容を含む手続きの詳細を確認することができます。
遺言書の検認手続きに欠席したとしても、遺言書の内容が疑わしかったり不公平であったりした場合、泣き寝入りして受け入れる必要は全くありません。検認が終わった後でも、遺言の無効を主張する権利や、最低限の相続分である遺留分を請求する権利が法律で認められています。
しかし、これらの権利を行使するには、専門的な知識と複雑な手続き、そして何よりも厳しい期限が伴います。特に、遺留分侵害額請求の「知った時から1年」という時効は、あっという間に過ぎてしまいます。
遺留分侵害額請求を検討している場合には、早めに弁護士に相談するようにしてください。
法律事務所リンクスは遺留分侵害額請求の相談が60分無料!
 法律事務所リンクスでは、遺留分に強い弁護士による60分無料相談を実施しています。
法律事務所リンクスでは、遺留分に強い弁護士による60分無料相談を実施しています。
相談に当たっては、ご予約いただいた際にご事情を伺い、調査をした上で相談に臨みますので、無料相談の時間内で充実した情報を提供しております。
相談者様が聞き足りなかったということが起きないようにしておりますし、ホワイトボードを使うなどして分かりやすく説明していますので、お気軽にお問い合わせください。
相談者様が聞き足りなかったということが起きないようにしておりますし、ホワイトボードを使うなどして分かりやすく説明していますので、東京で相続に強い弁護士に相談されたい方は「東京で相続を弁護士に無料相談なら法律事務所リンクス」のサイトを、京都で相続に強い弁護士に相談されたい方は「京都で相続を弁護士に無料相談なら法律事務所リンクス」のサイトからお気軽にお問い合わせください。
遺留分請求の注意点について動画でご覧になりたい方はコチラ
こんなときは弁護士へ相談を|遺言書をめぐるトラブル
遺言書の検認は、あくまで手続きの入り口です。検認の場で明らかになった遺言書の内容をめぐり、様々なトラブルが発生する可能性があります。以下のようなケースに当てはまる場合は、ご自身の正当な権利を守るため、早期に弁護士へ相談することをお勧めします。
遺言書の有効性に疑いがある場合
検認は遺言の有効性を判断しないため、内容に疑いがあれば法的に争うことが可能です。
遺言能力が疑われる(認知症など)
遺言書が作成された当時、遺言者が認知症などで、遺言の内容を正しく理解し判断する能力(遺言能力)がなかった可能性があります。この場合、遺言は無効となります。遺言能力の有無を証明するためには、当時の医療記録(カルテ)や介護認定の資料、看護記録などが重要な証拠となります 。
遺言書が偽造された可能性がある(筆跡が違うなど)
「どう見ても本人の筆跡ではない」「署名がいつもと違う」といった場合、第三者によって遺言書が偽造された疑いがあります。このようなケースでは、遺言者の生前の日記や手紙など、本人の筆跡がわかる他の資料と比較する筆跡鑑定が有効な証拠となります 。
法律で定められた形式を満たしていない
遺言書は、民法で厳格な形式が定められています。例えば、自筆証書遺言の場合、「全文、日付、氏名」がすべて自書でなければならず、一つでも欠けていたり、パソコンで作成されていたりすると無効になります。また、日付が「令和5年吉日」のように特定できない場合も無効となる可能性があります 。
遺言書の内容が著しく不公平な場合(遺留分侵害)
「全財産を長男に相続させる」「愛人にすべてを遺贈する」といった内容の遺言書も法的には有効です。しかし、配偶者、子、直系尊属(父母など)には、法律によって最低限保障された遺産の取り分である「遺留分」という権利があります。
遺言によってこの遺留分が侵害された場合、侵害された相続人は、財産を多く受け取った人に対して、侵害された分に相当する金銭を支払うよう請求することができます。これを「遺留分侵害額請求」と呼びます 。
他の相続人との関係が悪く、トラブルが予想される場合
遺言書の内容自体に法的な問題がなくても、相続人間の感情的な対立から、手続きが円滑に進まないケースは少なくありません。特定の相続人が遺産に関する情報の開示を拒んだり、話し合いに一切応じなかったりする場合、弁護士が代理人として間に入ることで、冷静かつ法的なルールに則った交渉を進めることが可能になります 。
【専門家が解説】遺言の無効を主張する法的手続き(遺言無効確認訴訟)
遺言書の有効性に疑いがある場合、「遺言無効確認」を求める法的手続きを進めることになります。これは専門的な知識と証拠収集が不可欠なため、弁護士のサポートが必須です。
ステップ1: 証拠収集
遺言の無効を主張する側が、その無効原因を立証する責任を負います。そのため、訴訟を起こす前の証拠収集が最も重要です 。
- 遺言能力が争点の場合: 遺言作成日時点での遺言者の心身の状態を示す客観的な証拠、例えば、医師の診断書、カルテ、介護記録、長谷川式認知症スケールなどの検査結果などを収集します 。
- 偽造が争点の場合: 筆跡鑑定を専門機関に依頼します。また、遺言書作成の経緯を知る可能性のある人物(介護士や親族など)からの聞き取りも重要になります。
ステップ2: 遺言無効確認調停
いきなり訴訟を提起することは原則としてできず、まずは家庭裁判所に「遺言無効確認調停」を申し立てる必要があります(調停前置主義) 。調停では、調停委員という中立な第三者を交えて、相続人間での話し合いによる解決を目指します。
ステップ3: 遺言無効確認訴訟
調停で話し合いがまとまらなかった場合、地方裁判所に「遺言無効確認訴訟」を提起します 。訴訟では、原告(無効を主張する側)と被告(有効を主張する側)が、それぞれ書面で主張を述べ、証拠を提出し合います。審理には通常1年〜2年程度の期間を要します 。
遺言無効が確定した場合
裁判所の判決により遺言の無効が確定すると、その遺言書は初めから存在しなかったものとして扱われます。その結果、相続人全員で、法律で定められた相続分(法定相続)に基づいて遺産をどう分けるかを話し合う「遺産分割協議」を行うことになります 。
【専門家が解説】最低限の相続分「遺留分」を請求する法的手続き
遺言によって最低限の相続分である「遺留分」を侵害された場合、その権利を回復するための手続きが「遺留分侵害額請求」です。この手続きには厳格な期間制限があるため、迅速な対応が求められます。
極めて重要な時効期間
遺留分侵害額請求権は、相続の開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと、時効によって消滅してしまいます 。また、それを知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過すると権利は消滅します。特に「知った時から1年」という期間は非常に短いため、注意が必要です。
ステップ1: 意思表示(内容証明郵便)
時効を中断させるため、まずは遺留分を侵害している相手方(財産を多く受け取った人)に対し、「遺留分侵害額を請求します」という意思表示を明確に行う必要があります。口頭でも有効ですが、後日の紛争を防ぐため、「いつ、誰が、誰に、どのような内容を伝えたか」を郵便局が証明してくれる配達証明付き内容証明郵便を利用するのが最も確実な方法です 。
ステップ2: 話し合い(交渉)
意思表示の後は、当事者間で支払うべき金額や支払い方法について話し合いを行います。遺産の評価(特に不動産)や生前贈与の有無などで計算が複雑になるため、弁護士に依頼して正確な請求額を算定し、代理人として交渉してもらうのが一般的です 。合意に至った場合は、その内容を「合意書」として書面に残します。
ステップ3: 遺留分侵害額請求調停
話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額請求調停」を申し立てます。これも調停前置主義の対象であり、訴訟の前に必ず経なければならない手続きです 。調停委員を介して、解決に向けた話し合いが進められます。
ステップ4: 訴訟
調停でも合意に至らない場合は、最終的に地方裁判所(または簡易裁判所)に訴訟を提起することになります 。訴訟では、裁判官が証拠に基づいて法的な判断を下します。
遺言書の検認期日通知書が来てお困りの方へ

このように、遺言書の検認には難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士による無料相談を受けられることをお勧めしております。
遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。
司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。
弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。
法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が遺言書に関する無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
ページトップに戻る