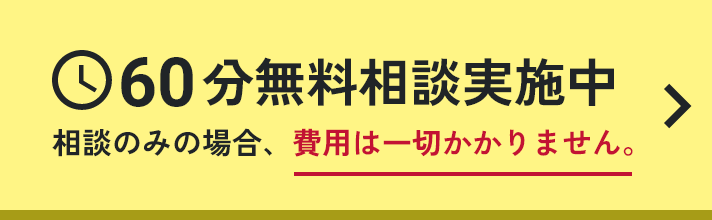共有名義の相続はトラブルだらけ?メリットは?不動産の持分売却は?
不動産を共有名義で相続してもよいですか?
共有名義での相続とは
共有名義での相続には厳密には2種類あります。
- 遺産分割前に法定相続分どおりの登記をすること(法定相続分による相続登記)
- 遺産分割によって決まった共有持分に従って登記すること(共有分割による相続登記)
①の共有名義は遺産分割が終了するまでの暫定的な共有(遺産共有)であるのに対し、②の共有名義は遺産分割によって決まった最終的な共有(物件共有)であるという違いがありますが、登記上はその違いは分かりません。
法律事務所リンクスは相続の相談が60分無料!
 法律事務所リンクスでは、遺産相続に強い弁護士による60分無料相談を実施しています。
法律事務所リンクスでは、遺産相続に強い弁護士による60分無料相談を実施しています。
相談に当たっては、ご予約いただいた際にご事情を伺い、調査をした上で相談に臨みますので、無料相談の時間内で充実した情報を提供しております。
相談者様が聞き足りなかったということが起きないようにしておりますし、ホワイトボードを使うなどして分かりやすく説明していますので、お気軽にお問い合わせください。
不動産の相続の進め方を動画でご覧になりたい方はコチラ
法定相続分による相続登記は単独申請可能
法定相続分による相続登記は、遺産分割が終了する前にする登記であり、相続人の誰かが遺産分割によって取得する予定の場合にはあまり行われません。取得する相続人が決まってから相続登記をすればよいからです。
これに対し、不動産を相続人全員が売主となって法定相続分に従って売却する場合には、共有名義で登記して売却することになります。
法定相続分による遺産共有登記は単独申請が可能ですので、次のようなトラブルが発生する可能性があります。
不動産の共有持分の売却トラブル
遺産分割前の遺産共有持分であっても持分譲渡することが可能です。
相続人の中には長引く遺産分割に辟易として、法定相続分による相続登記を単独申請して、自身の遺産共有持分を持分買取業者に売却して換金する人が出てこない限りません。
このようなことにならないよう速やかに遺産分割をする必要がありますし、遺産共有持分売却によって不利益が生じる場合には、審判前の保全処分などの対抗手段を取る必要があります。
共有名義での相続のデメリットとメリット
共有名義での相続のデメリット
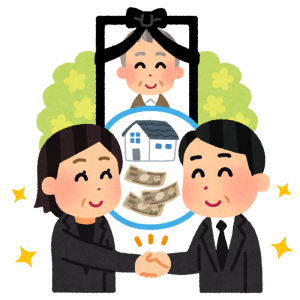 相続財産に賃貸マンションや賃貸アパート、駐車場などが含まれている場合に、賃料を分配するために共有名義で相続することがあります。しかし、共有名義での相続には、次のようなリスクがあります。
相続財産に賃貸マンションや賃貸アパート、駐車場などが含まれている場合に、賃料を分配するために共有名義で相続することがあります。しかし、共有名義での相続には、次のようなリスクがあります。
- 売却するのに共有者全員の同意が必要
- 賃貸するのに持分の過半数の同意が必要
- 共有から離脱するには買取が必要
売却するのに共有者全員の同意が必要
例えば賃貸アパートを単独相続をした場合、単独相続をした人はその土地や不動産を自由に売却することができますが、共有名義で相続した場合、賃貸アパートを売却するには、他の共有者全員の同意が必要になります。
賃貸するのに持分の過半数の同意が必要
賃貸アパートの一部屋を誰かに貸す場合、過半数の持分を持つ共有者の同意が必要であり、過半数の同意を得られなければ、賃貸借契約を締結することができません。
共有から離脱するには買取が必要
共有から離脱するには、誰かに買い取ってもらう必要があります。共有者が買い取ってくれなければ第三者に共有持分を売却することもできますが、共有持分を買い取ってくれる人が出てくるとは限りませんし、仮に買い取ってくれてもかなり安い額になる可能性が高いです。
共有名義での相続をしてしまうと…
共有名義での相続には上記のようなデメリットがあるので、安易に共有にすることはお勧めしません。
共有名義で相続してしまうと、共有状態で遺産分割は完了しますので、原則として遺産分割の手続は利用できなくなりますし、仮に遺産分割をやり直して誰かに持分を集中させることにしたとしても、税務上は相続ではなく売買や贈与として扱われ、別途消費税や贈与税が課税されてしまいますので、下記のような遺産分割方法も検討してみてください。
換価分割
不動産を売却して換価した上で、売却益等を遺産分割する方法です。
詳しくは「不動産を売却して現金で分けたい」をご覧ください。
代償分割
相続人の誰かが不動産を取得し、その代わりに、他の相続人に代償金を支払うことで遺産分割を成立させる方法です。
相続人の誰かに代償金を支払う資力がある場合に可能となります。
賃貸マンション・アパートの遺産分割
賃貸マンション・アパートの相続・遺産分割には様々な注意点があります。
詳しくは「賃貸マンション・アパートの相続・遺産分割」をご覧ください。
共有名義での相続のメリット
次のような場合には共有名義での相続にメリットがあるかもしれません。
- 実家しか相続財産がない場合
- 賃貸物件を共有名義で相続して賃料を分配する方が得な場合
- 不動産がもともと被相続人と相続人の共有であった場合
とはいえ、特定の誰かが不動産を占有し続けたり、賃料の分配がうまくいかなかったりした場合には、どうすればよいのでしょうか。
共有名義での相続のトラブルとその解決法
共有名義での相続の具体例① 実家しか相続財産がない場合
 Xは配偶者を亡くし、子供としてA、B、Cがいる。
Xは配偶者を亡くし、子供としてA、B、Cがいる。
Xは自宅を所有しているが、遺言を残さずに亡くなった。
次の場合にどうなるか。
- Xは生前にAと住んでいた。まだ遺産分割が終了していないが、B、Cとしては、Aに出て行ってもらいたいと考えている。
- BとCは、Aに言われるがまま、持分を3分の1ずつとする共有名義での相続に同意したが、Aばかり利益を得ているので、Aに出て行ってもらいたいと考えている。
- ②の場合で、Bは一旦、Aが住み続けるのに同意していた場合はどうか。
共有者の1人が不動産を占有している場合
遺産分割が終了していない場合
①のようにXがAを生前一緒に住まわせていた場合、遺産分割が終了するまでは、無償で使用させる旨の合意があったと推認されるという最高裁判例があるので、このままではB、Cが求めてもAに出て行ってもらうことはできません。A、B、Cで遺産分割協議を進めて、自宅不動産をどうするのかを決める必要があります。
共同名義での相続が終了している場合
②のように共有名義での相続が終了している場合、遺産分割は終了しています。
民法252条1項は「共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者(A)があるときも、同様とする。」としています。
BとCの持分を足すと3分の2になり過半数ですので、Aに出て行ってもらうことが可能になります。
これに対し、③のようにBが一旦はAが住み続けることに同意していた場合、AとBの持分を足すと3分の2になり過半数ですので、一旦はAが使用する権限を持ったことになります。
民法252条3項は、新たな過半数による決定があったとしても、過去に「共有者間の決定(ABの過半数による決定)に基づいて共有物を使用する共有者(A)に特別の影響を及ぼすべきときは、その(Aの)承諾を得なければならない。」としており、Aが承諾しなければ出て行ってもらうのは難しそうです。
もちろん、Aが住み続けることで、BとCの持分が活用できなくなりますので、無償で住み続けることに同意していたということでなければ、BとCは自身の持分に対応する使用の対価を支払ってもらうことは可能です(民法249条2項)。
最終手段は共有物分割訴訟
遺産分割が終了している場合、家庭裁判所の遺産分割調停や遺産分割審判は利用できませんので、共有関係を解消して金銭を取得するには、地方裁判所に共有物分割訴訟を提起する必要があります。
共有名義での相続の具体例② 賃貸物件を共有名義で相続した場合
 AとBが賃貸マンション1棟を持分2分の1ずつで相続した場合、次のようなことが起きたらどう対処すればよいでしょうか。
AとBが賃貸マンション1棟を持分2分の1ずつで相続した場合、次のようなことが起きたらどう対処すればよいでしょうか。
- Aはマンションの1室が空いたのでCに賃料10万円で貸したいが、Bは12万円以上でないとかしたくないと言い出した場合
- AがBに賃料から諸費用を差し引いて2分の1を支払おうとしたところ、Bはそんなに諸費用は掛からないと言い出した場合
- AがBに賃料を渡さないと言い出した場合
- Bが賃貸マンションを売却したいが、Aがこれに応じない場合
賃貸条件が一致しない場合
民法252条1項は「共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。」としていますが、双方の持分とも2分の1で過半数に達しませんので、現状維持となり、Cに賃すことはできないということになります。
費用の負担
民法253条1項は「各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。」としていますので、Bは管理の費用の2分の1を支払う義務があります。なお、同2項は、「共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。」としていますので、1年間費用を支払わなければ、Aは相応の賞金を支払ってBの持分を取得できます。
賃料の分配
賃料は持分に応じて分配しなければなりませんので、AはBに賃料の2分の1を支払わなければなりません。BはAが支払わない場合に、不当利得返還請求訴訟を提起することができます。
売却
賃貸マンション1棟を売却するには、他の共有者全員の同意が必要になります。自分の持分だけを売却するのは自由です。
最終手段は共有物分割訴訟
遺産分割が終了している場合、家庭裁判所の遺産分割調停や遺産分割審判は利用できませんので、共有関係を解消して金銭をするには、地方裁判所に共有物分割訴訟を提起する必要があります。
遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要

このように、共有名義での相続には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。
遺産分割はもちろんのこと、共有名義で相続した後の処理も弁護士であれば対応することが可能です。
弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。
法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
ページトップに戻る